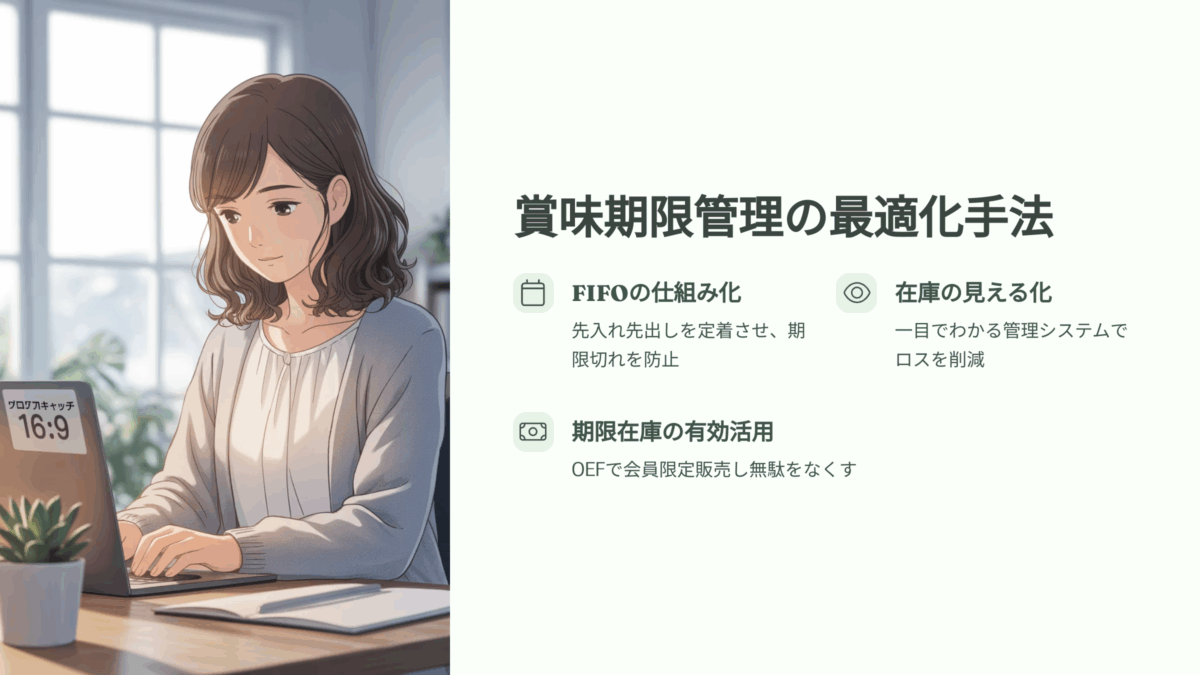賞味期限管理に悩む食品卸の現場で、在庫ロスや廃棄コストがじわじわ効いてきていませんか?
この記事では、FIFOの徹底と販路活用による在庫ロス削減法をご紹介します。
目次を見て必要なところから読んでみてください。
食品卸が直面する「賞味期限管理」のリアルな課題
なぜ在庫ロスが発生するのか?現場の盲点とは
賞味期限が過ぎてしまった食品を、ため息まじりに廃棄する――
そんな日常を「もったいない」と感じながらも、どうにもできずにいる現場の方は少なくありません。
✅ 実は、在庫ロスの原因は“気づかないうちに”起きていることが多いのです。
・急な納品スケジュールのズレ
・商品ごとに異なる賞味期限のばらつき
・パレットや棚の奥に“見えなくなる”在庫
こうした小さなズレや見落としが積み重なることで、気づけば売れ残りや期限切れが発生してしまいます。
「在庫管理してるつもりだったのに」という声は、どの現場でもよく聞かれます。
特に、扱っている品目が多ければ多いほど“管理しきれないリスク”は高まるのです。
日々の業務に追われる中で、完璧なチェック体制を保つのは、簡単なことではありませんよね。
紙・エクセル管理の限界と「見えない損失」
「うちはエクセルで管理してるから大丈夫」
そう思っていても、実際には更新が遅れたり、入力ミスが起きたり、誰がどのデータを見ているか分からなくなったり…そんな“あるある”が起きがちです。
✅ アナログ管理では、在庫の動きに“リアルタイムで追いつけない”という限界があります。
また、紙ベースで賞味期限を管理している現場では、現物との照合に手間がかかり、どうしても後手に回ってしまうという声も。
この「目に見えにくいムダ」が、知らないうちに大きな損失となって積み上がっていることもあるのです。
以下はよくある在庫管理の落とし穴をまとめた表です:
| 課題 | 見えにくい損失例 |
|---|---|
| 賞味期限の記録漏れ | 廃棄ロス、再発注ミス |
| エクセル管理の更新遅れ | 売れ残り増加、機会損失 |
| 在庫ロケーションの把握不足 | 古い商品が棚の奥に滞留 |
こういった積み重ねが、「食品ロス」「廃棄コスト」「利益圧迫」という形で現れてきます。
「わかってるけど徹底できない」FIFO運用の実情
先に入ったものを先に出す、というFIFO(First In, First Out)の考え方。
賞味期限管理の基本とも言えますが、「実際の現場で徹底できているか?」と聞かれると、多くの担当者が首をかしげるのが現実です。
✅ 「ルールはあるけど、実行がむずかしい」これが多くの現場の本音です。
たとえば、
・急ぎの出荷に追われて、つい“手前にある商品”から出してしまう
・入庫のたびに商品位置が変わって、どれが古いかわからなくなる
・パートさんや新人さんがルールを知らず、順番が崩れてしまう
こうした“ちょっとしたズレ”が、結果的にロスを生む原因になります。
「ルール化」だけでなく、「現場で迷わず動ける仕組み」にまで落とし込むことが、実はとても大切なのです。
FIFOの徹底は、在庫を効率よく回転させるための“土台”になります。
ですが、それを無理なく、自然に回るようにする仕組み化が、これからの賞味期限管理のカギだと私たちは考えています。
在庫ロスを減らす鍵は“仕組み化されたFIFO”にあり
FIFO(先入れ先出し)の基本と現場での落とし穴
食品卸の在庫管理では、「古いものから出す」というFIFO(先入れ先出し)が基本中の基本です。
でも、それが“ちゃんとできていれば”苦労はないんですよね。
✅ 実際には「やるべき」と「できること」の間にギャップがあるのが現実です。
たとえば、
・作業スタッフによって在庫の並び順がバラつく
・急ぎの納品でルールを無視せざるを得ない日がある
・賞味期限が商品によって微妙に異なり、判断が難しい
こうした“現場特有のゆらぎ”があると、マニュアル通りに動かすのは本当にむずかしいものです。
FIFOの運用が定着しない原因は、「ルールが守られない」ことではなく、ルールを“迷わず守れる環境”がないことだと感じます。
仕組みで迷いを減らす。ここがFIFO徹底のポイントです。
「賞味期限×入庫日」で回転を自動化する方法
賞味期限だけで管理すると、実は落とし穴があります。
なぜなら、同じ商品でも納品時期によってロットが分かれていることが多いからです。
✅ 「賞味期限」と「入庫日」、この2つを掛け合わせて管理することで、在庫回転が一気にスムーズになります。
たとえばこんな工夫ができます:
- 入庫日ごとに色付きラベルや棚番号を分けて保管
- 賞味期限の近い順にピッキングリストを自動で生成
- 「あと何日で期限を迎えるか」を一覧表示するシステムを使う
こうした工夫をすることで、「どれを先に出すべきか」がひと目でわかるようになり、現場での判断がグンと早く、正確になります。
しかも、人の勘や記憶に頼らなくていいので、新人スタッフでも迷わず動けるんです。
在庫の見える化が“判断スピード”を変える
「いま、どれくらい在庫があって、何が危ないのか」
これがパッと見てわかる状態、いわゆる“見える化”は、在庫ロス削減の最重要ポイントです。
✅ 在庫が見えることで、“判断”が早くなる。そして“行動”が変わるんです。
たとえば、
・今週中に賞味期限を迎える商品がひと目でわかれば、「まとめて販促に回す」という判断が即できる
・滞留しそうな商品を早めにOEFなどの販路に流せば、廃棄を防ぎながら現金化できる
・営業やMD担当が「今動くべき商品」を自分で把握できるので、社内連携がスムーズになる
これは、ただ管理がしやすくなるだけでなく、“会社全体の意思決定スピード”を上げてくれる仕組みでもあります。
在庫ロスを防ぐためには、「管理しやすい」「動きやすい」「判断しやすい」この3つの“やすい”が揃うことがカギ。
仕組み化されたFIFOは、まさにそれを叶える方法のひとつです。
すぐに実践できる在庫ロス削減の3つのステップ
在庫ロスを減らすために、大がかりなシステムを入れたり、特別な人員を増やしたりする必要はありません。
ちょっとした工夫と“気づける仕組み”をつくることで、毎日の現場は確実に変わっていきます。
ここでは、すぐに取り組める3つの具体的なステップをご紹介します。
1. 賞味期限の「危険ゾーン」を明確化する
まず最初にやるべきは、どの段階から在庫が“危ない状態”なのかを社内で定義することです。
✅ 「賞味期限○日前」を“危険ゾーン”としてルール化するのがポイントです。
たとえば、
- 賞味期限まで「30日以内」→注意喚起
- 「14日以内」→販促・値下げ対象
- 「7日以内」→優先出荷 or 特販ルートへ移動
このように“ゾーニング”しておくことで、誰でも「今すぐ動くべき在庫」が判断できるようになります。
特に、現場のスタッフ・営業担当・商品管理チームが共通のルールで動けるようになると、対応が一気に早くなります。
ちょっとのルールづくりが、結果的に“ロスゼロ”に近づく第一歩です。
2. 月次・週次でロス在庫を抽出&アラート化
ルールを決めたら、次に必要なのは「定期的にロス候補を洗い出す仕組み」です。
✅ ポイントは、“データで見る”ことと、“定期的にチェックする”こと。
たとえば、
- 毎週月曜に「賞味期限30日以内の商品リスト」を抽出
- 月初に「前月末までに出荷できなかった在庫」を洗い出し
- チェック結果をチームで共有して次のアクションへ
こんな流れがあるだけで、「なんとなく気づいたら期限が…」という事態を防ぐことができます。
アナログ管理でも、色付きマーカーでラベルを貼るだけでも十分効果はあります。
重要なのは、「気づける状態をつくること」です。
3. OEFなどクローズド販路で“期限付き商品”を現金化
ロスの危機が迫っている在庫は、ただ焦るだけではもったいない。
そんなときこそ、「売れる販路」にのせることが最後の一手になります。
✅ OEFのような“会員限定”の販路は、期限が迫った商品を“ちゃんと価値ある形で”届けることができます。
OEFは、価格表示はオープンですが、購入できるのはサブスクリプション会員だけ。
つまり、ブランド価値を守りながら、在庫を現金化できる販路なんです。
しかも、購入者は“エシカルに共感した人たち”。ただのアウトレット販売とは違い、「フードロス削減に参加している」という満足感を持って商品を受け取ってくれます。
現場で残念な気持ちになりがちな“期限間近の商品”が、ちゃんと喜ばれる未来に変わる。
それが、このクローズド販路の強みです。
販路連携で在庫が売れる仕組みに——OEFの活用法
「このままでは賞味期限が切れてしまう…」
そんな商品にも、本当はまだ“必要としてくれる人”がいます。
ただ、その人に届く道がないだけなんです。
OEF(アウトレット・エコロジー・フードロス)は、
そんな“もったいない”を“ありがとう”に変える販路のひとつです。
期限が近い商品を「サブスク会員限定」で販売
OEFでは、賞味期限が迫っている商品や規格外の在庫を、月額会員に向けて特別価格で提供しています。
✅ 「売れ残り」ではなく「レスキュー食品」として、共感とともに購入される仕組みです。
この仕組みが成り立つのは、購入者が「フードロスを減らしたい」という意識を持ったサブスク会員だから。
期限間近の商品も「価値ある選択肢」として受け止めてもらえるのです。
だからこそ、“値引きしても傷つかない”し、“買った人にも満足感がある”。
売り手にとっても買い手にとっても、やさしい流れができているんです。
価格表示はオープン、購買は会員限定の安心設計
OEFでは、商品情報や価格はすべて公開されています。
でも、実際に購入できるのは「有料会員だけ」という仕組みです。
✅ この「価格オープン/購買クローズド」という構造が、ブランド価値を守ります。
よくあるのが、「値引き販売しているのがバレてしまい、正規ルートの取引先に気まずい思いをした…」というお悩み。
でも、OEFならその心配はありません。
・商品情報は一般に公開されていて透明性がある
・でも、買えるのは“選ばれた人たち(=会員)”だけ
つまり、誰でも見られるけれど、誰でも買えるわけじゃないという“絶妙なバランス”が守られています。
このクローズド・バイイングモデルこそが、市場価格への影響を最小限に抑えながら、販路として活用できるポイントなのです。
食品ロス対策とブランド価値の両立ができる
在庫を処分したい。でも、ブランドは守りたい。
この二つの想いは、いつも背中合わせにあるものです。
✅ OEFは「売ること=ブランドを広めること」になる、新しい販路のかたちです。
・フードロス削減という社会的意義がある
・消費者もエシカルな行動に参加できる
・出品者の“ブランドストーリー”も丁寧に伝わる
売ることが「社会貢献」になり、買うことが「エシカルな選択」になる。
そんな循環の中で、期限付きの商品も、ブランドの一部として受け入れられるんです。
OEFのサブスクモデルは、ただの商品流通ではなく、“ブランドと顧客の関係性”を丁寧につなぐ場所でもあります。
エシカルに、でも現実的に。
在庫を無駄にしない販路を考えるとき、OEFという選択肢はきっと意味のある一歩になります。
✅在庫のムダを減らす販路戦略が気になる方はこちらからどうぞ
在庫のムダを減らす販路戦略が気になる方はこちらからどうぞ