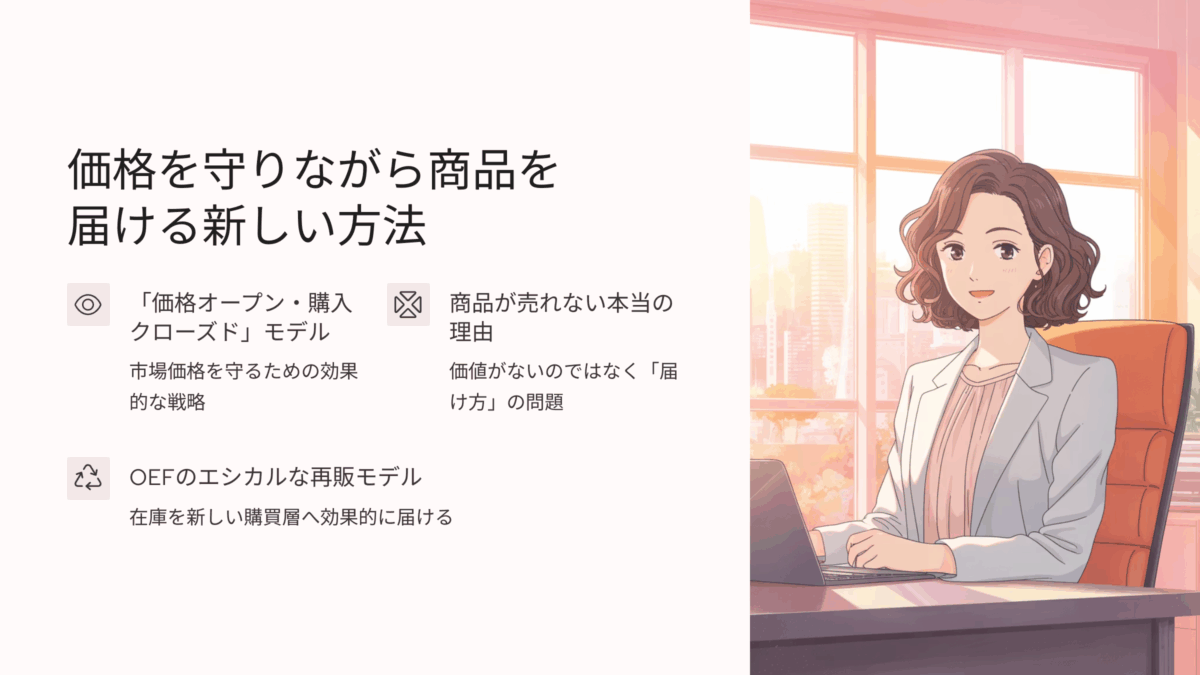売れ筋から外れてしまった商品、本当にそのまま手放してしまっていいのでしょうか?実は“売れなくなった”のではなく、“届け方を変えればまだ売れる”ことも多いんです。目次を見て必要なところから読んでみてください。
トレンド変化に左右される問屋のリスクと現実
どれだけ丁寧に仕入れた商品でも、トレンドが変われば急に売れ行きが落ちてしまう──そんな経験、ありませんか?とくに問屋さんや卸売業をされている方にとっては、「売れるはずだった商品が急に動かなくなる」ことは、避けて通れない課題かもしれません。今回は、売れ筋の変化にどう向き合い、在庫を無駄にしないための視点を一緒に考えていきたいと思います。
突然売れなくなる商品、背景にある3つの構造変化
商品が売れなくなる理由は「流行が去ったから」だけではありません。実は、もっと根本的な変化が静かに進んでいることも多いのです。ここでは、問屋や卸業が直面する“見えにくい構造変化”を3つに分けて整理してみます。
✅ 消費者の情報源が変化している
かつてはテレビや雑誌が主流だった情報も、今はSNSや口コミサイトが中心になっています。とくにZ世代は「誰が紹介しているか」で購買を決める傾向が強く、商品そのものよりも“語られ方”に価値を感じているようです。
✅ ライフスタイルの多様化と細分化
「みんなが同じものを欲しがる時代」は終わりつつあります。たとえば、健康志向の高まりで砂糖を控える人が増えたり、環境配慮の観点からパッケージの素材で選ばれたり。“売れる理由”が一つではなくなったことが、在庫の読みにくさにつながっています。
✅ コロナ以降の価値観シフト
一時的な混乱と思われたパンデミックは、長期的に消費者の選択基準を変えました。「必要なものしか買わない」「地元を応援したい」「エシカルな企業から買いたい」など、感情や社会的な視点が購買行動に影響するようになったのです。
こうした変化はじわじわと広がり、気づいたときには「これまで売れていた商品が動かない…」という事態につながります。
「人気が落ちた=価値がない」ではない理由
売れなくなった商品を見ると、つい「もう需要がないのかも」と思ってしまいますよね。でも、本当にそうでしょうか?実は、売れないのではなく“今の売り方では響かない”だけというケースも少なくありません。
たとえば、少しパッケージが古いだけ、名前の印象が流行から外れた、情報発信のチャネルが合っていない──そんな小さなズレで、本来の良さが伝わらなくなっていることもあります。
ここで大切なのは、「売れない=失敗」と決めつけないことです。むしろ、「まだ届けられていない人がいる」と考えることで、新しい販路や伝え方が見えてくるかもしれません。
実際、以前OEFで扱ったあるフェイスマスクも、当初は売れ行きが振るわなかった商品でした。でも、「ヒト幹細胞」や「高保湿」という機能面では非常に優れていたので、“ママ世代のセルフケア”という文脈で見せ方を変えたら、定期的に購入される人気商品に生まれ変わったんです。
商品の“賞味期限”は、市場の熱狂が過ぎた後でも終わりではありません。視点を変えるだけで、まったく新しい価値として蘇ることがあるのです。
次は、こうした“再価値化”をどのように実現できるか、具体的な提案をしていきたいと思います。
売れ筋から外れた商品を“再発掘”する視点

一度は人気があった商品も、売れ行きが落ちると「もう出番はないのかな…」と思ってしまいがちです。でも本当にそうでしょうか?実は、“売れなくなった商品”こそ、新しい価値をまとって再登場できるチャンスを秘めていることが多いのです。ここでは、その見つけ直し方=「再発掘」の視点について、一緒に考えてみたいと思います。
誰にとって価値があるのか?ターゲットの再定義
「この商品、もう売れない…」と感じたとき、まず立ち止まってほしいのが“誰に向けて売っていたか”という視点です。ターゲット設定が昔のままだと、今のニーズとズレてしまっていることもあります。
✅ 以前の購入層ではなく、これからの層に合う使い方や価値を見出す
✅ 若年層ではなく、ミドル世代にとっての「懐かしさ」や「安心感」として再提示
✅ 自宅用ではなく、ちょっとしたギフトや“人に贈る”用途として見せ方を変える
たとえば、地味なデザインのドレッシングが売れなくなっていたとしても、「離れて暮らす親への仕送り用」「栄養にこだわる一人暮らしの学生向け」として紹介すれば、まったく違う文脈で魅力が伝わることがあります。
“価値を感じる人”が変わっただけで、商品そのものの魅力が消えたわけではない。そのことを思い出すだけで、再提案のアイデアはぐっと広がっていきます。
「アウトレット×エシカル消費」という新たな切り口
もうひとつ注目したいのが、アウトレット商品とエシカル消費のかけ合わせです。
アウトレットと聞くと、「安い」「在庫処分」といったイメージが先に来るかもしれません。でも今は、それを“選ばれた人だけが手にできる賢い選択”として、ポジティブに捉える消費者が増えています。
特にOEFのようなプラットフォームでは、「価格はオープンでも、購入は会員限定」という仕組みで、ブランド価値や定価販売ルートを守りながら再販できるんです。これがまさに「クローズド・バイイングモデル」と呼ばれる考え方。
このモデルには、以下のようなメリットがあります:
| 特徴 | メリット |
|---|---|
| 誰でも商品情報は見られる | プロモーション効果がある |
| 購入できるのはサブスク会員のみ | 価格崩れの心配がない |
| “訳あり”ではなく“エシカルな選択”として提案 | ブランドのイメージを損なわない |
この仕組みによって、「売れ残り=恥ずかしいこと」ではなく、「ムダにしない=誇れる選択」として、問屋や卸売企業の商品が新たな価値を得られるのです。
小さな傷がついただけで店頭に並ばなかった商品、パッケージが変更された旧ロット品、数量が中途半端に残ってしまったセット商品…。そういった“もったいない”商品たちに、新しい居場所をつくるのが、この再発掘の発想です。
次回は、そんな商品の“再販ルート”をどうつくっていくか、一歩踏み込んで考えてみましょう。
問屋・卸が取れる3つの在庫再活用ルート

売れ筋から外れた商品や在庫をどう活かすか——それは、問屋・卸にとっていつの時代も頭を悩ませるテーマです。でも、だからこそ今、“再活用”の視点を持つことが、経営の安定にも、社会的価値にもつながっていきます。
ここでは、在庫をムダにしないための「3つの販路の選択肢」をご紹介します。
既存チャネルでの値下げ再販とその限界
まず一番オーソドックスなのが、「今ある取引先で値下げして再販する」方法です。確かに、すでにルートがある分、出荷まではスムーズですし、最短で現金化できる可能性もあります。
ただし、この方法にはいくつかの注意点もあります。
✅ 値下げが恒常化すると、ブランド価値が下がってしまう
✅ 他の小売店との価格バランスを崩し、取引関係に影響が出ることも
✅ 商品の価値ではなく「安さ」だけが印象に残ってしまう
つまり、短期的な在庫処分には有効でも、中長期的な戦略としては“限界がある”のです。とくに繰り返し使う商品ほど、価格に対する信頼感が大切です。
企業コラボによるプロモーション活用
次に注目したいのが、他社と組んでプロモーションの一部として商品を活用する方法です。たとえば、美容室の来店プレゼント、アプリ登録特典、サンプリング企画などと組み合わせることで、在庫を「PR用資産」に変えることができます。
ここでのポイントは、「捨てるくらいなら、知ってもらう機会に変えよう」という視点です。
こんな事例があります。
✅ 季節外れの入浴剤を、フィットネスジムの「冬向けキャンペーン特典」として再活用
✅ 消費期限が近い食品を、地元企業のファンイベントの参加者向けギフトに
“販売”ではなく“体験”に変えることで、商品に再び息を吹き込むことができる。そんな柔軟な使い方も、今の時代にはとても大切です。
購買層を絞ったEC販路の活用(会員限定モデル)
そして今、じわじわと注目を集めているのが、会員限定のECモデルです。とくにOEFのように「価格は見えるけど、買えるのは会員だけ」という仕組みは、ブランド価値を守りながら“売る場所”を切り替えたい問屋さんにぴったりの選択肢です。
✅ ブランド毀損を避けたい
✅ 通常ルートでは出しにくい商品を、エシカルな理由で見せられる
✅ 小ロットでも販売しやすく、定価とのバランスもとりやすい
しかも、「在庫が余ったから安く売る」のではなく、「フードロスを減らすため」「エシカルな消費を支援するため」という“共感されるストーリー”があることも大きな強みです。
こうしたクローズドな販路は、ただの商品処分ではなく、次につながる新しい出会いの場にもなります。
在庫を抱えることは、リスクであると同時に、新しい価値提案のチャンスでもある。そんな視点で、一緒に道を探していけたら嬉しいです。
市場価格に影響を与えずに在庫を販売する方法

「在庫を売りたいけど、取引先やブランドの価格維持が気になる」──そんなお悩み、問屋さんやメーカーの方からよく聞きます。確かに、市場価格を崩してしまうと、長年築いてきた信頼や取引関係に影響を与えてしまう可能性がありますよね。
でも、実は“値崩れを起こさずに売る”方法もちゃんとあるんです。ここではその具体的な仕組みと、販促の新しい考え方をご紹介します。
「価格オープン・購入クローズド」が可能にするブランド保護
一見矛盾しているように思えるかもしれませんが、「価格は公開するけど、購入は限定する」という仕組みは、ブランドを守るうえで非常に有効です。これがいわゆる「クローズド・バイイングモデル」という考え方です。
このモデルでは、
✅ 誰でも商品ページは見られる
✅ 価格も明記されているので“誠実な販売”として映る
✅ でも実際に購入できるのは、会員など限定された層のみ
という特徴があります。
たとえばOEFでは、登録制のサブスク会員しか購入ができません。つまり、不特定多数へのばらまきではなく、価値観に共感する人だけに届く仕組みなんです。
これによって、こんな安心感が得られます:
| 不安 | この仕組みでどう解消できる? |
|---|---|
| 「一般市場に安売りが出回ったらどうしよう」 | → 限定購入なので価格崩れを起こさない |
| 「取引先から“勝手に安売りした”と誤解されないか不安」 | → 誰に販売したか管理できるので、説明がしやすい |
| 「ブランド価値が損なわれないか心配」 | → エシカルな販売理由がセットになっているのでむしろ好印象 |
まさに、“売る”ことと“守る”ことを両立できるやさしいモデルなのです。
新規ターゲット層への“見せるだけ”で刺さる販促戦略
販売の場を「会員限定」にすることで、もう一つ面白い効果があります。それは、「見せるけど、簡単には買えない」ことで、逆に欲しくなる」という心理的効果です。
これは心理学でも「スノッブ効果(snob effect)」と呼ばれる現象で、「誰にでも買えるものより、限られた人しか手にできないもの」に価値を感じやすいという傾向のことです。
特に今の若い世代は、「あなただけに届く」「選ばれた人だけが知っている」というプレミア感に反応する傾向が強いと言われています。
たとえば、
✅ SNSで「OEFで出会った商品たち」と投稿される
✅ でもリンクを開いてみると、「会員限定」と表示される
✅ 「何これ、ちょっと気になる…」と自然にエンゲージメントが生まれる
このように、“見せるだけでファンを引き寄せる”販促スタイルが成立するのです。
ただ安く売るだけでは、今の時代には刺さらない。
でも、「この商品にはこんな価値があるんだ」と伝えながら、それを丁寧に届けるしくみがあれば、共感と信頼を得ながら在庫も動かせる。
OEFのような会員制ECは、そんな“見せ方の革命”を可能にしてくれる、これからの時代の販路だと私は思っています。
OEFという再販プラットフォームの選択肢

売れ残った商品をどうにかしたい。でも、既存の販路を傷つけるような売り方はしたくない。そんなジレンマに悩む問屋さんやメーカーさんにとって、OEFは「在庫を守りながら動かせる」新しい選択肢になります。
エシカルECという性質を活かしながら、フードロスや過剰在庫といった社会課題の解決にもつながる。そんなしくみが、ここにはあります。
問屋が安心して出品できる「クローズド・バイイングモデル」
OEFでは、「価格は公開しているけれど、購入できるのは会員だけ」というクローズド・バイイングモデルを採用しています。
この仕組みのメリットはとてもシンプルです。
✅ 商品情報は誰でも見られる → プロモーション効果あり
✅ 購入は会員限定 → 価格破壊が起こらない
✅ 会員は価値観でつながっている → ブランド毀損のリスクが低い
たとえば、「参考価格5,000円の商品を2,500円で出品したら、他社が怒るのでは?」と心配になる方も多いと思います。でもOEFでは購入の導線が“会員だけ”に閉じているので、市場価格への影響は最小限です。
さらに、会員は“安ければ何でもいい”という層ではありません。エシカル消費に共感してくれている人たちなので、「安くてラッキー」ではなく「フードロスを減らせてうれしい」と受け取ってくれます。
この信頼感が、問屋さんが安心して出品できる理由なのです。
「フードロス対策」と「販路拡張」を両立するEC設計
OEFは単なるアウトレットサイトではありません。“フードロス削減”という社会的意義を持ったECプラットフォームです。
そのため、出品された商品には「訳あり」や「B品」といったラベルをつけるのではなく、
✅ “レスキュー在庫”という前向きなネーミング
✅ なぜこの商品が出てきたのか、背景まで丁寧に説明
✅ 「買うことが社会貢献になる」というストーリーづくり
こういった工夫を通じて、「安く売っている」ではなく「価値ある選択を提案している」という文脈で伝えることができます。
これは単に在庫処分を目的とした販路ではなく、ブランド価値を守りながら販路を“拡張”する設計でもあるのです。
既存のB品・余剰品を価値ある選択肢に変える仕組み
たとえば、賞味期限が迫った調味料や、外箱にキズがついた化粧品。「商品としてはまったく問題がないけど、店頭には出せない」そんな在庫はどこの倉庫にも眠っているのではないでしょうか。
OEFでは、そういった商品たちを「もったいないBOX」や「特別セット」に再構成し、わくわく感をプラスした形で提案しています。
✅ セット販売にして“体験価値”を高める
✅ 「何が届くかわからない」楽しさを加える
✅ 利益よりも“使い切ること”に重きを置く
このような発想で、“あまりもの”が“選ばれるもの”に変わる。それがOEFの一番の強みです。
在庫は「余ったもの」ではなく、「まだ出番を待っているもの」。OEFなら、その商品にもう一度スポットライトを当てることができます。
あなたの倉庫に眠る“価値ある一品”、OEFで新しい場所に届けてみませんか?