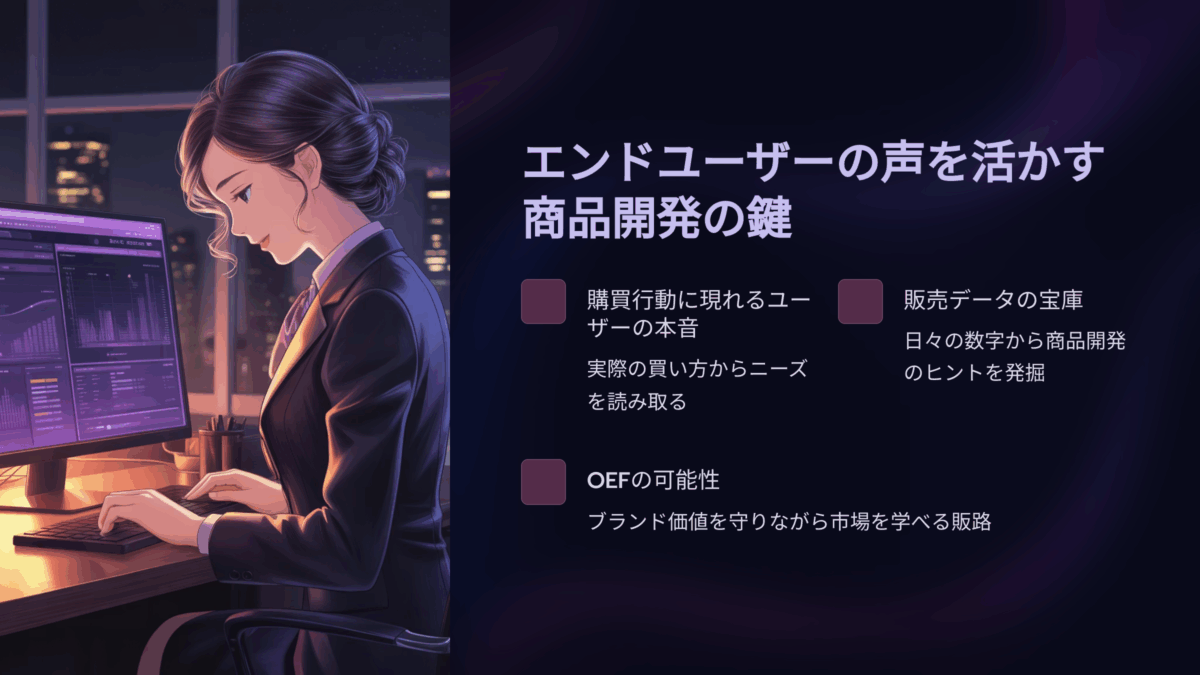問屋・卸として「なぜ売れないのか?」に悩んだことはありませんか?
OEFでの実例をもとに、消費者ニーズをどう可視化し、商品企画に活かせるかを解説します。
目次を見て必要なところから読んでみてください。
問屋が抱える「消費者ニーズが見えない問題」とは?
「問屋」として商品を扱っていると、どうしても“本当に求められているもの”が見えにくくなることがあります。日々の業務の中では数字や在庫の動きばかりが気になってしまって、その先にいるエンドユーザーの顔が見えなくなる。でも、今の時代、それではなかなか売れない…そんなもどかしさを感じている方も多いのではないでしょうか。
なぜ問屋には“エンドユーザーの声”が届きにくいのか
問屋さんは、基本的に「小売店への納品」が主なお仕事です。だから、お客様の声が直接入ってくる構造になっていないんですよね。たとえばスーパーやドラッグストアの売場で商品がどんな風に手に取られているか、誰がどんな気持ちで買っているのか。こうした購入の「理由」や「背景」までは、伝言ゲームのように途中で消えてしまいます。
さらに最近では、ネットショップやSNSの影響もあり、消費者の行動や価値観がどんどん変化しています。でも、そういったトレンドの変化が店舗経由ではキャッチしづらい。だからこそ、「この商品、売れるはずだったのに…」というすれ違いが生まれがちなんです。
「売れるはずの商品が売れない」ギャップの正体
せっかくこだわって作った商品や、過去に人気だったロングセラー。問屋さんとしては「これなら絶対売れる」と思って出したのに、思うように動かない——そんな経験、ありませんか?
その背景には、「使いたい人」の気持ちと、「売る側」の視点がズレてしまっていることが多いのです。たとえば、見た目は良くても「使い方がわかりにくい」「価格と価値が釣り合っていない」と思われていたり。あるいは、「もう似たような商品を持っているから、今は買わない」というパターンもあります。
つまり、売れるかどうかは“スペック”だけじゃなくて、“今の気分”や“暮らしの中でのリアルな悩み”とつながっているかどうかが大切なんです。
✅ こんなズレが起きていませんか?
| ギャップの例 | 見えない“本当の理由” |
|---|---|
| 想定より価格が安く設定されているのに売れない | 顧客が「安すぎて不安」「品質に疑問」と感じている |
| 他社と同じスペックで競合もいるのに売れない | 差別化ポイントが伝わっていない、または不要と判断されている |
| 長く売れていた定番商品が突然売れなくなった | 生活スタイルやニーズが変化している(例:コロナ後の価値観変化) |
このような“売れない理由”は、実はエンドユーザーのデータや声をしっかり見ていくことで見えてきます。ですが、それを得るための仕組みがないままでは、いつまでたっても「なぜ売れないのか?」に答えが出ないままになってしまいます。
そんなときこそ、「直接ユーザーとつながる場所」に出してみることが、ヒントになるかもしれません。次の章では、その具体的な方法についてお話ししますね。
販売データを活かせば、商品開発はもっと確実になる

商品の開発や改良をするとき、なんとなくの感覚や過去の売れ筋だけを頼りにしていませんか?
でも今の時代、それだけでは足りないことが増えてきました。本当に求められているものは、ユーザーの“リアルな行動”の中にあるからです。問屋さんが直接そのデータにふれることができれば、より精度の高い商品づくりができるようになります。
中間流通を飛び越えた“リアルな購買行動”の強み
小売店や中間業者を通して商品を流通させる仕組みは、もちろん必要なことです。ただ、そのぶん「誰が、どんな気持ちで買ったのか?」といった購入の背景が見えにくくなるというデメリットもあるんです。
一方で、OEFのような会員制・直接販売型のECプラットフォームでは、「どのタイミングで、どんなセットで、どんな人に選ばれたか」という“買う瞬間”のデータを、サプライヤー側でも確認することができます。
これは、問屋さんにとってとても貴重な情報です。たとえば、
✅ 売れ筋商品と一緒に買われた“意外な組み合わせ”
✅ 「子どもの栄養補助」を目的に買われたドリンクが、実は「高齢の親のため」というレビュー
✅ 平日よりも週末に圧倒的に売れるパターン など
こうした行動データからは、お客様が“どういう課題を感じていて、どんな文脈で商品を使おうとしているのか”まで見えてくることがあります。
「誰が・いつ・何と一緒に買ったか」が次のヒントになる
OEFでは、購入者の傾向をジャンルごとに見ることができます。たとえば「食品」「ビューティー」「日用品」などのカテゴリの中で、どんな商品が一緒にカートに入れられているか。これを見るだけでも、たくさんのヒントが隠れているんです。
✅ 購買データから見えることの一例
| データの種類 | 商品開発につながる視点 |
|---|---|
| 商品の同時購入パターン | 「次はこの2つをセットにして売ってみよう」 |
| 購入者のレビュー傾向 | 「“香りが良い”という声が多い → 次は香り別バリエ展開」 |
| 売れる曜日・時間帯 | 「土日に売れる → 家族利用が多いかも」 |
たとえば「レトルト雑炊」と「まつ毛美容液」が一緒に売れた、なんてケースもあります。いったいなぜ?と思うかもしれませんが、「自分へのちょっとしたご褒美」「手軽に栄養と美容ケアを済ませたい」というニーズが見えてくるかもしれません。
こうした「誰が、いつ、何を買ったか」の積み重ねが、次の一手を考えるための“リアルなヒント集”になります。単なる在庫処分ではなく、ユーザー理解のためのテストマーケティングとして活用することもできるんです。
このあとご紹介するのは、そんな「販売の現場」から得られるインサイトを、どうやって商品企画や改善に活かしていくのか。その具体的な活用法についてです。
OEFのような会員制ECが提供する、可視化されたニーズ

これまで「在庫処分」と聞くと、どうしても“赤字覚悟の最終手段”というイメージがありましたよね。でも今、その在庫処分の場が、マーケティングや商品改善に活かせるデータの宝庫になりつつあるんです。
OEFのような「会員制のエシカルEC」は、ただ売るだけでなく、“消費者の選び方”を見える化するプラットフォームとして進化しています。
在庫処分から“マーケティングデータ取得”へと進化
問屋さんやメーカーさんにとって、余った在庫をどこでどう売るかは大きな悩みのひとつ。でも、OEFではその“売れ残り”が「ユーザーの本音を探るフィールド」になるんです。
たとえば、OEFに出品すると、
✅ どの商品がどのくらいのスピードで売れたか
✅ サムネイル画像のどれがクリックされやすかったか
✅ 商品説明や割引率によって反応がどう変わるか
など、小売現場では得られにくい「ダイレクトな反応」が数字として見えてきます。しかも、ユーザーはエシカル消費に関心のある“価値観でつながった人たち”なので、本質的なニーズや感情が行動に現れやすいのが特徴です。
つまり、「売れるかどうか」の結果だけじゃなく、“どうして売れたのか” “どんな人が選んだのか”を深掘りできる。この時点で、すでに在庫は“マーケティングデータの入り口”になっているんです。
「買い方」に隠れたインサイトをどう読み解くか
ユーザーがどんな風に商品を選び、どんな文脈で購入しているのか。その「買い方」に注目することで、思わぬ発見があります。
たとえば、「野菜BOX」と一緒に「まつ毛美容液」が売れていたとします。いったいなぜ…?と思いますよね。でも、それは“週末の自分メンテナンス”という購買文脈が隠れていたりするんです。
このような“使われ方”や“シチュエーション”の情報は、レビューや購入タイミング、組み合わせ購買の傾向を見ていくことで見えてきます。
✅ OEFで読み解ける「買い方」インサイトの例:
| 購買行動 | 読み取れること |
|---|---|
| 朝に売れやすい | 通勤前・子育て前に使われる商品かも |
| 美容アイテムが週末に売れる | 自分時間の充実ニーズがある可能性 |
| 同梱されやすい商品がある | セット化やギフト展開のヒントになる |
こうしたインサイトを、次の仕入れや企画開発に役立てることができれば、「売れなかった在庫」ではなく、「次のヒットを生むヒント」に変わっていきます。
OEFは、“商品を捨てる”のではなく、“価値と声を拾い上げる”場所。そんな風に捉えていただけたら嬉しいです。次は、このインサイトをどう商品企画に落とし込むか、具体的な活用法を見ていきましょう。
売ることで“見える化”できる、新しい商品企画の形

商品を作るとき、「これなら売れるはず」と信じて世に出す。でも、実際に動かしてみないとわからないことも多いですよね。
特に問屋さんやメーカーさんは、実際のエンドユーザーの反応を“肌で感じる”機会が少ない分、商品改良の方向性に迷うことも多いのではないでしょうか。
でも、売ってみることで得られる情報は、改善のための答え合わせにもなります。今は、“売ること”がそのまま“テストマーケティング”になる時代なんです。
価格反応・セット購入・レビューから得られるヒント
OEFのような販売プラットフォームを使うと、ただの「売れた/売れなかった」だけでなく、そのプロセスに潜むさまざまなヒントが見えてきます。
たとえばこんな声や動き。
✅「この値段なら即買いだったけど、あと300円高ければ迷ってたかも」
✅「このセット内容、うちの家族にはちょうど良かった」
✅「見た目で選んだけど、実際に使ってリピ確定!」
これらは、売ってみないと見えてこない“生の声”です。レビューや購入傾向を分析すれば、「どの価格帯が最も反応がいいのか」や「セット内容にどんな価値が感じられているか」といったポイントがクリアになります。
OEFでは、セット購入率やレビュー投稿率、リピート率なども数字で確認できるため、感覚に頼らず、データで改善策を見つけることができるんです。
✅ 商品改善のヒントになる要素一覧
| 項目 | 見えるポイント |
|---|---|
| 購入価格帯 | 適正価格の見極めに役立つ |
| セット購入傾向 | お得感や使い勝手への評価 |
| レビュー内容 | 顧客満足度や使用シーンの把握 |
| リピート率 | “また買いたい”と思わせる要素の有無 |
数字だけでは読みきれない“ニュアンス”がレビューに表れるのも、エンドユーザーに近いECならではの魅力ですね。
消費者の“納得ポイント”を知れば無駄な改良が減る
多くの企業がやりがちなのが、「もっとよくしよう」と思って、実は必要ない部分まで手を加えてしまうこと。でも、消費者が感じる“納得感”がどこにあるのかを掴めば、不要な改良にかけるコストや手間を省けるようになります。
たとえば、パッケージを高級感のあるデザインに変えたら売上が落ちた…なんてこともあります。それは、ユーザーが「気軽に買える」ことに価値を感じていたからかもしれません。
つまり大事なのは、“企業側の正解”ではなく、“消費者の納得ポイント”を基準に商品を育てていくことなんです。
その納得ポイントは、データの中にちゃんとあります。OEFでの販売体験を通じて得た反応を丁寧に拾っていけば、“無駄な改良”をやめて、“本当に求められる改善”に集中できるようになります。
次は、そんな納得感を生み出すために、OEFがどんな価値を問屋さんやメーカーさんに提供しているのか。販路としてのポテンシャルに迫っていきます。
OEFという選択肢が、問屋・卸の未来を広げる

これからの問屋・卸にとって、「売れ残りをどうするか」はもちろんのこと、「どうブランドを守りながら売るか」も大きなテーマになってきています。
OEFは、そんな悩みを抱える企業にとって、在庫を活かしながら新しい販路を築ける“安心設計”の仕組みを提供しています。
単なる在庫処分ではなく、ブランド価値とサステナビリティを両立できる場所として、多くのサプライヤーさんに選ばれている理由が、ここにあるんです。
ブランドを守りつつ販売できる「クローズド・バイイングモデル」
OEFでは、「誰でも見られるけど、買えるのは会員だけ」というクローズド・バイイングモデルを採用しています。
これによって、市場価格への影響を最小限に抑えながら在庫を販売できるようになっているんです。
✅ このモデルの特徴
- 価格はオープン:参考価格・販売価格ともに表示され、透明性を確保
- 購入は会員限定:サブスク会員だけが購入できるため、販売先がコントロール可能
- ブランド毀損リスクの回避:一般市場ではなく、限定的な販路内での消費行動
この仕組みによって、「B品を売る=ブランド価値が下がる」というイメージを払拭しながら、安心して在庫を現金化できるんです。
実際に、メーカー様からも「得意先にバレる心配がないのが助かる」という声をよくいただいています。
廃棄コスト削減だけじゃない、価値創出の仕組みとは?
OEFの本質は、単に在庫を売る場ではありません。
“もったいない”在庫に、もう一度チャンスを与えることで、商品にも企業にも新しい価値を生み出す場所なんです。
たとえばこんなケースがありました。
✅ 出荷時期を逃して倉庫に眠っていた「冬限定のお菓子」
→ OEFで「レスキュー在庫」として販売したところ、1週間で完売。レビューも高評価。
→ 結果、翌年はOEF限定のパッケージを企画し、新たな定番商品に育ちました。
このように、在庫処分=終わりではなく、新しい始まりになる可能性があります。
商品はただ売られるのではなく、ストーリーや文脈とともに選ばれるようになってきている今、OEFのような場は“第二の販路”ではなく、“価値再発見のステージ”としても活用できます。
廃棄コストがゼロになるだけでなく、「ブランドの余白」を丁寧に拾っていくことができる。
それが、OEFという選択肢がこれからの卸・問屋ビジネスにおいて持つ、本当の強みなのかもしれません。
次は、そのデータや反応をどう商品づくりに活かしていけるのか。より実践的な視点で掘り下げていきますね。
OEFで得られるユーザーデータを、商品開発に活かすには?

商品を「売ること」は、ゴールではありません。それはむしろ、「次のヒントを得るための出発点」だと、私は思っています。
OEFでの販売は、単なる在庫消化ではなく、ユーザーのリアルな声や行動を集められる“小さな実験場”でもあるんです。
この実験で得られたデータを、次の商品開発や企画改善に活かしていくことが、問屋さんやメーカーさんの可能性を大きく広げてくれます。
出品後の購入動線・反応を分析して次の一手に
OEFで出品すると、その商品が「どんな動線で見られ、どう選ばれて、いつ買われたのか」が細かく追えます。
この購入動線こそ、次に打つべき手を見つけるためのヒントになります。
✅ たとえば、こんなデータが見えてきます:
- PVは多いのに購入が少ない → 商品名や写真、価格にギャップがあるかも
- 特定の曜日や時間帯に集中して売れている → ライフスタイルに合った商品かもしれない
- レビューが一部に集中している → ユーザーにとって印象的なポイントが偏っている可能性
これらの情報をしっかり読み取ることで、「なぜ売れたのか/売れなかったのか」を自分の中で整理できるようになります。
ただ出して終わりではなく、出したあとの行動を“言語化”することが次の商品改善につながる鍵なんです。
「売って終わり」ではなく「売って学ぶ」が成功の鍵
従来の在庫処分は「とにかく早く捌く」が目的でした。でも、OEFではそれを“学びの場”として使うことができるんです。
実際に、OEFでテスト販売したあとにパッケージを見直したり、サイズや組み合わせを調整して次回の生産に反映させる事例も増えています。
✅ OEFで得たユーザーデータを活かす流れ
| ステップ | 活用のポイント |
|---|---|
| 出品 → 反応の記録 | クリック数・購入数・レビュー内容のチェック |
| 購入者像の把握 | 購入時間帯・商品組み合わせ・使用シーンを分析 |
| 仮説を立てて改善 | 価格設定・パッケージ・訴求文言などの見直し |
| 再出品 or 新商品へ | 改善後に再検証するか、次の企画につなげる |
このサイクルを回すことで、「なんとなく作った商品」が、「理由のある商品」に変わっていきます。
そして何より、「売って学ぶ」姿勢があれば、どんな在庫も無駄になりません。商品に“次の命”を吹き込むことができるのです。
OEFは、ただの販売チャネルではなく、データとユーザーの声が集まる“リアルな研究所”。
これからの時代、こういった販路をどう使いこなすかが、問屋・メーカーの未来を左右していくのではないでしょうか。