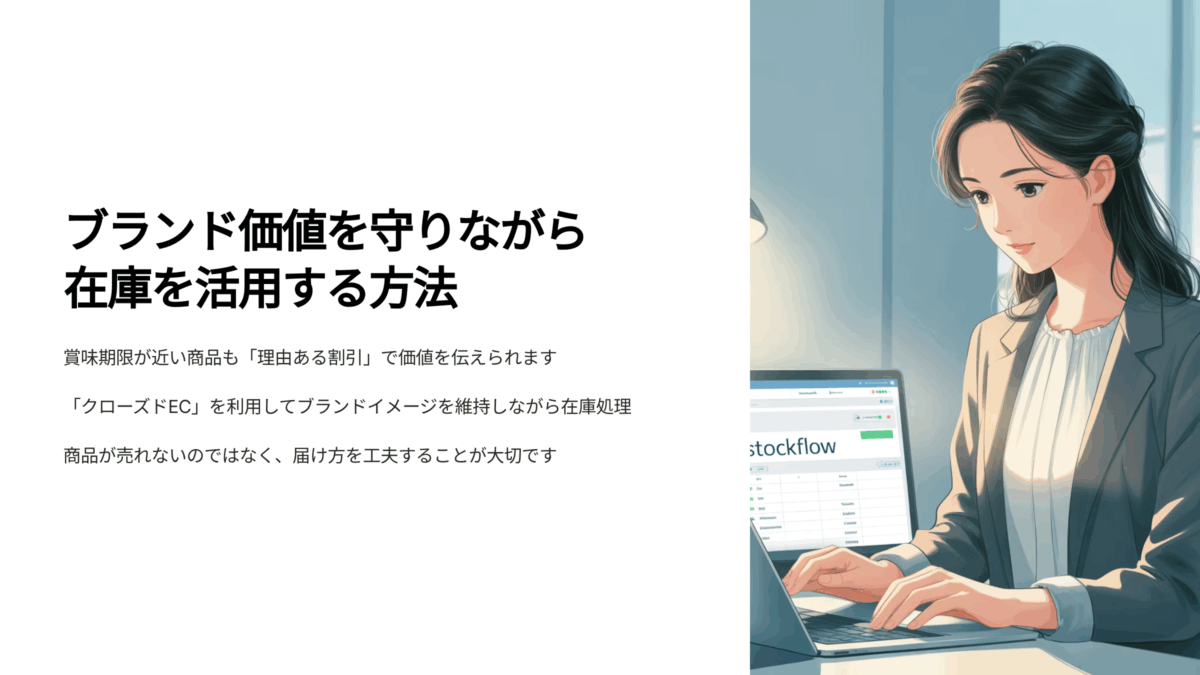販路が突然なくなったとき、在庫をどうするかで悩んでいませんか?この記事では、賞味期限の近い食品や訳あり商品を“売れる在庫”に変えるためのヒントをまとめました。目次を見て必要なところから読んでみてください。
食品の販路を失ったとき、まず考えるべき3つの選択肢
急な取引先の縮小や契約終了、想定外の需要減…そんなときに直面するのが、「食品の販路を失ってしまった」という現実です。
ですが、廃棄を選ぶ前にできることは意外とたくさんあります。ここでは、在庫をムダにしないための視点を3つにしぼってご紹介します。少しでもヒントになればうれしいです。
廃棄という最終手段をとる前にできること
賞味期限が迫ってきた食品を前に、「もう売れないかも」と感じたことはありませんか?
でも、そこで“捨てる”という判断を下すのは、まだ早いかもしれません。
✅ まず見直したいのは、「今すぐ売る必要があるのか?」という視点です。
数量限定のセット販売や、訳あり商品としてのリパッケージ、在庫を活かしたノベルティ活用など、“すぐ売る”以外の選択肢もあります。
例えば、あるメーカーさんは「セット組みにしたら売れた」という経験をされていました。バラバラだと見向きもされなかった商品が、セットにすることでお得感が伝わり、注文が増えたそうです。
「価値がない」のではなく、「価値が伝わっていない」だけかもしれない。そんな視点で、一度立ち止まって見てみるのも、大切な一歩です。
卸売に頼らずにBtoCで売るという視点
販路がなくなった=「次の卸先を探さなきゃ」と思いがちですが、必ずしも“卸す”ことが最善とは限りません。
✅ 今の時代、「卸す」から「直接届ける」へのシフトも選択肢の一つです。
特に、フードロス削減やエシカル消費に関心のあるお客さまは、訳あり商品でも“ストーリーのある食品”を選ぶ傾向があります。
BtoCの良いところは、商品の魅力を自分の言葉で届けられること。なぜこの商品が残っているのか、どんな想いでつくられたのか。伝え方ひとつで、買い手の受け取り方も変わります。
卸では埋もれていた価値が、消費者との直接の対話でよみがえることもあるんです。
「売る相手を変える」だけで販路が広がる可能性
販路がなくなったというとき、じつは「今までの売り方では売れなくなっただけ」ということも少なくありません。
ターゲットを変えるだけで、売れる可能性がひらけることもあるんです。
✅ たとえば「高級スーパーで売れなかった食品」が、サブスク型のエシカルECでは人気商品に変わったケースもあります。
それは、売る相手の価値観が違うから。見た目よりも「共感」や「ストーリー」で選ぶ人たちが、そこにはいます。
「どこで売るか」ではなく、「誰に届けるか」という発想の転換が、次の販路を広げる鍵になるかもしれません。
どんなに素晴らしい商品でも、伝える相手を間違えてしまえば、魅力が伝わりにくくなってしまいます。だからこそ、一度「売る相手」を見直してみること。これは、販路喪失に直面したときにこそ考えたい、大切な選択肢のひとつです。
賞味期限が近い食品を「売れる商品」に変える考え方

賞味期限が迫った商品を見ると、「もう値下げするしかない」と思ってしまうかもしれません。ですが、それだけではもったいないのです。ほんの少し視点を変えるだけで、“訳あり”が“選ばれる”理由に変わることもあります。ここでは、そうした再価値化のヒントをお伝えします。
安売りではなく「理由ある割引」に変換する
「売れ残ったから安くする」
そのままだと、どうしてもネガティブな印象が先行してしまいますよね。ですが、割引には“前向きな理由”を添えることができます。
✅ たとえば、「フードロス削減のための特別価格」
✅ 「〇月〇日までのレスキュー販売キャンペーン」
✅ 「数量限定・感謝価格セット」など
“値引き”ではなく“共感”が理由になると、価格が価値に変わります。
消費者も「理由がある割引」には納得感を持って選んでくれます。エシカルな選択をした自分を、少し誇らしく感じてくれるかもしれません。
パッケージの問題?賞味期限?原因別の価値再定義
なぜ“売れない”と判断してしまったのか。そこを丁寧に見直してみると、新しい価値の種が見つかることがあります。
下記は、よくある「売れづらい理由」と、その再定義のアイデアです。
| 問題の例 | 再定義のポイント |
|---|---|
| パッケージにキズ | 内容に問題なしなら「訳ありお得セット」で販売可能 |
| 賞味期限が近い | 保存性が高い食品なら「〇日以内に使い切れるレシピ付き」に |
| 季節外れの商品 | 「早めのストックで賢くエシカル消費」という打ち出し方 |
※このように、“欠点”と思える部分が、工夫次第で“選ばれる理由”になることもあるのです。
お客さまの目線に立って、「それでも欲しいと思える理由」をつくっていきましょう。
「おいしいのに売れない」食品に光を当てる方法
実際に味はおいしい、品質も良い。でも売れない。
そんなときこそ、ストーリーの力を活用してみてください。
✅ どこで、どんな人が、どんな思いで作ったのか
✅ なぜ今、手元にたくさん在庫があるのか
✅ どんな人に届けたいと思っているのか
こうした情報を添えることで、ただの商品が“想いのこもった食品”に変わります。
実際に、「規格外の野菜を使った焼き菓子を、ストーリーと一緒に紹介したら完売した」という例もあります。
「おいしい」は伝わらないけれど、「大切に育てた」が伝わると、心が動く人がいる。
“売る”というより、“気持ちごと届ける”くらいの気持ちで。
そうやって丁寧に光を当てることで、今ある在庫は、きっとまた誰かのもとで輝けるはずです。
卸販売をサブスク化すると何が起きるのか?

「売れればラッキー」「今月はゼロかも…」そんな不安定な卸販売の中で、“定期的に売れる仕組み”があったらいいのにと思ったことはありませんか?
その願いをかなえるのが、サブスクリプション型の販売モデルです。ここでは、卸販売をサブスク化することで得られる安心や柔軟性について、具体的にお伝えしていきます。
「毎月定期で買ってくれる人」がいるという安心
いちばんの違いは、やはり「先が読める」ことです。
毎月、あらかじめ決まったサブスク会員数に対して商品を届ける仕組みは、売上予測が立てやすくなるという大きなメリットがあります。
✅ 今月はどれくらいの売上が見込めるか
✅ どのタイミングでどれだけ出荷すればよいか
✅ 突然の在庫処分に追われる心配がない
この「安心感」があるからこそ、商品開発や仕入れにも余裕が持てるようになるのです。
あるメーカーさんは、「毎月の定期枠での出荷があるだけで、気持ちが全然違う」と話していました。売上が見込めるって、やっぱり心強いものですよね。
価格設定の自由度とブランド価値の両立
「アウトレット販売=ブランドが傷つく」と思われがちですが、それは販売先の設計次第です。
たとえば、クローズドなサブスク会員向けに限定販売するモデルなら、不特定多数ではなく価値を理解した人たちだけに届けることができます。
✅ 会員限定の価格設定が可能
✅ 市場全体の価格への影響が出にくい
✅ 「安売り」ではなく「理由ある価格」として提供できる
つまり、ブランドイメージを守りながら在庫をさばけるというのが、サブスク販売の強みです。
消費者も「訳あり」だから買うのではなく、「応援したい」「共感したい」から選ぶ。そんな関係性を築くことができるのが、サブスクならではの魅力なのです。
在庫数に合わせて出荷できる柔軟さ
もうひとつの大きなメリットが、「供給に合わせて販売を調整できること」です。
つまり、“たくさんある月だけ多めに”“少ないときはお休み”といった調整が可能なのです。
たとえば…
| 月 | 出荷可能数 | 販売設定 |
|---|---|---|
| 6月 | 500個 | 通常通りのサブスク出荷 |
| 7月 | 200個 | 一部商品のみ限定販売 |
| 8月 | 800個 | ボリュームセットで販売 |
※このように、在庫状況に合わせて柔軟に設計できるのが特徴です。
在庫があるときにだけ活用できる、負担の少ないサブスクモデルは、「出しすぎて赤字」「売れ残って困る」から自由になれる方法でもあります。
まとめると、サブスク化は「売上の安定」「ブランド維持」「在庫管理の柔軟性」という3つの安心をもたらしてくれる仕組み。
もし、今の販路で限界を感じているなら、“定期的に売れる仕組み”という新しい選択肢を、ぜひ検討してみてくださいね。
サステナブルな販売チャネルとしての新モデル

在庫を抱えたとき、「どう処分しようか」ではなく、「どう活かそうか」と考えられる販路があると、少し気持ちが軽くなりますよね。
サステナブルな社会が求められる今、売る側も、選ぶ側も“思いやり”でつながる販売チャネルが注目されています。ここでは、そんな“やさしい販路”の新しいカタチをご紹介します。
フードロス削減につながる販路の選び方
「まだ食べられるのに、捨てられてしまう食品」がある一方で、「そんな食品を探している人」も、実はたくさんいます。
✅ 少し賞味期限が近いだけ
✅ 規格外のため店舗では並べられない
✅ 季節商品の在庫が残ってしまった
これらの食品を、「おいしくムダなく食べたい」という思いを持つ消費者に届けるルートがあれば、廃棄の必要なんてなくなるかもしれません。
大切なのは、「お得だから買う」だけでなく、「共感して選んでもらう」こと。
そのためには、フードロス削減に関心のある人たちに届く場=販路を選ぶことがポイントです。
社会貢献と売上を両立する「クローズドEC」という発想
サステナブルな販路として注目されているのが、「クローズドEC」という仕組みです。
これは、商品情報はオープンだけど、購入は登録会員のみに限定されている販売モデルのこと。
この形なら…
✅ ブランド価値を守りながらアウトレット販売ができる
✅ 市場価格への影響を最小限に抑えられる
✅ 「訳あり商品を選ぶ=社会貢献」という価値提案がしやすい
特に、「安売りに見せたくない」「価格崩れが心配」という方にとっては、安心して取り組める形といえるでしょう。
「選ばれた会員だけに届ける」という仕組みは、信頼と共感で成り立つ販路でもあるのです。
安心して出品できる「会員限定販売」のしくみ
「誰でも買える」オープン販売とは違い、会員限定販売には“伝えたい相手にだけ届く”という安心感があります。
出品する側から見た安心ポイントは、こんな感じです。
✅ 購入者は、価値観に共感してくれる会員のみ
✅ 価格表示はあっても、実際の取引は限定的
✅ 社会貢献意識の高いユーザーとの継続的なつながりが生まれる
これにより、「出品したらどこかに拡散されそう」「得意先との兼ね合いが心配」といった不安もぐっと軽減されます。
「一度きりの在庫処分」ではなく、長く続けられるエシカルな販路として。
会員制という形は、ブランドと信頼を守りながら、販路を育てていける新しいスタイルなのです。
売る側も買う側も、やさしい気持ちでつながれる。
そんなサステナブルな販路の選択肢、これからもっと広がっていくといいですね。
【事例紹介】販路を失った食品が月間◯件売れた仕組み

「うちの商品、もう売れないかも…」そう感じたときって、本当に胸が苦しくなりますよね。でも、その商品に“価値がなくなった”わけではありません。届け方を変えるだけで、ふたたび選ばれるようになることだってあるんです。
ここでは、実際に販路を失ったあとに再起した食品たちの事例を通じて、どんな工夫で“売れる流れ”を作ったのかをご紹介します。
ある焼き菓子メーカーの復活ストーリー
ある地方の小さな焼き菓子メーカーさん。
観光地の売店が主要販路だったのですが、コロナ禍で観光客が激減し、突然、出荷先をすべて失ってしまいました。
「このままだと、焼いたお菓子が全部廃棄になる…」そんな危機的状況の中で選んだのは、“オンラインでの限定販売”という新しいチャレンジでした。
✅ 見た目に少し焼きムラのある“訳あり品”をセット化
✅ 製造者の想いを伝えるストーリーを添えて販売
✅ 「もったいないを救うお菓子セット」として展開
結果、初月で300セットが完売。以降も定期的なリピート購入につながり、今では毎月安定的に注文が入るようになったそうです。
「おいしさに変わりはないのに、店頭に出せないだけ」——そんなお菓子に、もう一度光が当たった瞬間でした。
農家直送のおまかせBOXが支持される理由
季節によって収穫量が読みにくい野菜や加工品。
ときに過剰にできすぎてしまったり、規格外で出荷できなかったり…。そんな課題を抱えた農家さんたちが力を合わせて生まれたのが、「もったいない おまかせBOX」です。
✅ 野菜・パン・加工品をミックスして“何が届くかお楽しみ”に
✅ 訳ありだけど、味も品質もばっちりのものばかり
✅ フードロス削減を応援したい人たちにぴったりの内容
このBOXは、「ワクワク感」「エシカル消費」「お得感」が揃っていることで、月間500件以上の注文を集める人気商品に成長しました。
受け取る側も、「何が入ってるかな?」と楽しみながら待ってくれる。そんな消費者とのあたたかい関係性が続いているのも、この商品の強みです。
ドレッシングメーカーが在庫をさばけたワケ
ギフト需要を見込んで大量に仕込んだドレッシングが、予想以上に動かず、倉庫に残ってしまった…。そんな悩みを抱えていた調味料メーカーさんがとった行動は、“セット販売による再パッケージ化”でした。
✅ 人気のラスクと組み合わせた“レスキューセット”として再構成
✅ 「賞味期限が近い」と明記しつつ、送料込みの特別価格で販売
✅ 販売ページでは、フードロス削減の背景ストーリーを丁寧に紹介
すると、「ちょっとお得だし、応援にもなるよね」と購入する人が続出。数週間で在庫800セットが完売し、口コミでも高評価が広がったそうです。
売れた理由は、“安さ”だけではありません。「共感できる理由」があったからこそ、選ばれたのです。
どの事例も、「捨てるしかない」から「届けたい」に発想を切り替えたことが、再起のきっかけになっています。
在庫には、想いが詰まっています。その想いを伝える方法さえあれば、また誰かのもとで活かされる。そう信じて、私たちはこれからも“もったいない”に寄り添い続けたいと思っています。
最後に:販路を失っても、価値を失ったわけじゃない

商品が売れなくなったとき、「うちの商品にもう価値はないのかもしれない…」と感じてしまうのは、とても自然なことです。
でも、販路がなくなった=価値がなくなった、ではありません。
大切なのは、「まだ知られていない」「伝えきれていない」可能性を、あきらめずに見つけていくこと。
ここでは、そんな“次の一歩”に背中をそっと押す視点をお届けします。
「売れない」は「伝わってない」だけかもしれない
どんなに味に自信があっても、
どんなに丁寧に作った商品でも、
その価値がきちんと伝わっていなければ、手に取ってもらえません。
✅ 「安いから」ではなく「選びたくなる理由」があるか
✅ 「誰に届けたいか」が明確になっているか
✅ 「どこで」「どう」伝えているかを見直せているか
もしかすると、「売れない」のではなく、ただ、まだ出会えていないだけかもしれません。
その商品が“待っている人”のところに届けば、また新しい価値が生まれる。
だからこそ、「伝え方」を見直すことには、まだまだ希望があるのです。
次の一歩を踏み出すなら、今がそのタイミング
販路を失ったという経験は、とてもつらいものです。
でも、それは「終わり」ではなく、「見直すきっかけ」だと私は思います。
✅ 今までの販売方法にこだわらず、
✅ 伝える言葉や売る場所を変えてみる
✅ 新しいパートナーや販売モデルとつながってみる
このタイミングだからこそできること、きっとあると思うんです。
勇気を出して、小さな一歩を踏み出す。
その一歩が、未来の安定につながっていくかもしれません。
エシカルECで在庫が資産に変わるという選択肢
「もったいない」を「ありがとう」に変える場所。
それが、エシカルECという新しい販路です。
✅ 賞味期限が近いだけ
✅ パッケージに少しキズがあるだけ
✅ 通常の販路では出しづらいB品
そんな商品でも、価値を理解して選んでくれる会員がいるからこそ、
“在庫”が“資産”として、もう一度輝きはじめます。
そして、そこには「安く仕入れる」だけではない、あたたかい消費の形があります。
社会貢献にもつながる販路で売れるという体験は、きっと事業者の自信にもつながるはずです。
「売れない在庫」なんて、ほんとうはどこにもありません。
ただ、出会えていないだけ。伝えられていないだけ。
もし、そう感じられたなら——
その商品は、まだまだ誰かの笑顔をつくる力を持っているということです。
私たちと一緒に、その力をもう一度、信じてみませんか?