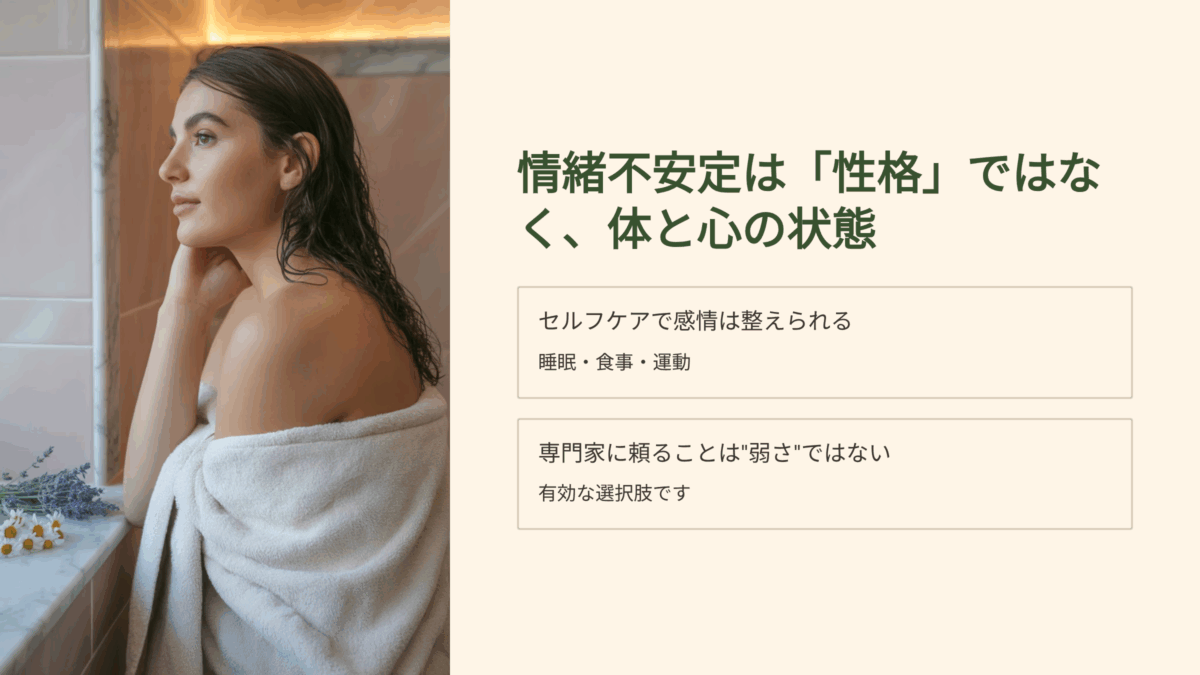情緒不安定に悩む20代女性に向けて、PMS・ホルモンバランス・自律神経の視点から対処法とセルフケアの方法を紹介。22歳の体験談をもとに、心との向き合い方や婦人科・カウンセリング活用のリアルな声も掲載。
22歳の私が直面した「情緒不安定」【その正体と背景】
なんだか気持ちが不安定、すぐ泣いてしまう、自分でも理由がわからない…。そんな状態が続くと、「私っておかしいのかな?」と感じてしまいますよね。でもそれ、実はよくあることなんです。ここでは、私が22歳のときに体験した「情緒不安定」という名のモヤモヤにどう気づき、どんな背景があったのかを振り返ってみます。
まずは“原因不明の感情の揺れ”に名前をつけることから始めましょう。
なぜか涙が止まらない…情緒不安定に気づいたきっかけ
あの頃の私は、とにかく情緒がぐらぐらで。仕事でちょっと注意されただけで、トイレで泣いたり。友達のちょっとした一言に過剰に反応してしまったり。寝不足かと思えば、たっぷり寝ても改善されず。「こんなに泣くなんて、私、どうかしてる…?」と、自分を責める日々が続いていました。
でもある日、ふと手帳にメモしていた生理周期と照らし合わせてみたら、「あれ?これ、毎月同じ時期に起きてる?」と気づいたんです。
その瞬間、自分の感情が“わけのわからない暴走”ではなく、体のサイクルと関係している可能性を感じて、少しだけ気持ちが楽になりました。
女性ホルモンと自律神経の乱れが心に与える影響
女性の体は、ホルモンバランスに影響を受けやすい仕組みになっています。特に排卵後から月経前にかけては、プロゲステロン(黄体ホルモン)の影響で心も体も不安定になりやすい時期です。
さらに自律神経が乱れると、以下のような不調が出やすくなります。
✅ イライラしやすい
✅ 涙もろくなる
✅ 集中できない
✅ 寝つきが悪くなる
✅ 食欲の変化がある
こうした変化は、ホルモン×自律神経×ライフスタイルの三拍子で起こることが多く、性格ではなく「体の反応」であることがほとんど。だからこそ、自分のせいにしすぎないことが本当に大切です。
情緒不安定は「性格」じゃなく「状態」だった
私はずっと、「私は感情の起伏が激しい性格なんだ」と思い込んでいました。でも後になって気づいたのは、それは“性格”ではなく“状態”だったということ。
たとえば、仕事が忙しすぎる、生活リズムが乱れている、夜遅くまでスマホを見てしまう、冷たいものばかり食べている…そんな日常の積み重ねが、自律神経を乱してホルモンバランスにも影響を与えます。
つまり、「情緒不安定」って、本人の気持ちだけではコントロールできない“心と体のSOS”なんです。
そして、この状態はケアすることで必ず軽くなっていきます。
私自身もそうでした。だから、まずは「こんな自分じゃダメだ」と責める前に、「これは私の体が出してくれたサインかも」と、ひと呼吸おいて見つめてみてください。
あなたの心が揺れるのは、弱いからじゃなく、ちゃんと感じているからです。
当時の私が試した情緒不安定の対処法【体験ベースで紹介】
「情緒不安定ってどうすればいいの?」と検索しても、正直ピンとこないことってありますよね。私もそうでした。だからここでは、22歳の私が実際に試してみて、効果を感じた“3つのセルフケア習慣”をご紹介します。難しいことではなく、今日から少しずつ取り入れられることばかり。自分の気持ちと体を、ゆっくりと整えるヒントになれば嬉しいです。
とにかく寝てみる:睡眠不足と情緒の関係
一番シンプルで、でも軽視されがちなのが「睡眠の質」です。
私が一番ひどく情緒が乱れていた時期、夜ふかしが当たり前になっていました。スマホを見ながらダラダラ夜を過ごし、寝るのは深夜2時過ぎ。朝はギリギリまで寝て、起きてもだるさが取れない…。このサイクルを見直して、22時以降はスマホを手放し、23時には布団に入るようにしてみたんです。
最初は少し辛かったけれど、1週間くらい続けると、朝起きたときの「重だるさ」が明らかに変わりました。そして不思議なことに、涙が出そうになる頻度も減ったんです。
それだけ、睡眠と感情は密接に関係しているということ。
✅ 睡眠が整うと、自律神経のバランスがとれやすくなる
✅ ホルモンの分泌リズムが安定しやすくなる
✅ 感情のブレーキが利きやすくなる
私にとって「ちゃんと眠ること」は、感情の土台を作る最初のステップでした。
食生活の見直しで気分が安定した話
忙しい日々の中で、食事をおろそかにしていませんか?
私は当時、食べる時間もバラバラで、菓子パンやカップ麺、甘いドリンクばかりの生活を送っていました。でもこれが、情緒の不安定さを加速させていた要因のひとつだったんです。
ある日ふと思い立って、「一日一食は、できるだけ温かくて栄養のあるものを食べよう」と決めました。味噌汁、玄米、納豆、煮物、たんぱく質をしっかり摂る…。ほんの少しの意識で、心のザワザワが少しずつ落ち着いていくのを実感しました。
特に意識したのはこの3つ:
| 栄養素 | 働き | 食材例 |
|---|---|---|
| ビタミンB群 | ストレス緩和、神経の働きをサポート | 豚肉、卵、納豆 |
| 鉄分 | イライラ・だるさの予防 | レバー、小松菜、ひじき |
| タンパク質 | ホルモンや神経伝達物質の材料 | 鶏むね肉、豆腐、魚 |
「ちゃんと食べること」は、自分を大切にすること。
そう気づいてから、私はごはんの時間を心のケア時間として大事にしています。
頭で考えるより、体を動かす:運動で感情が整うワケ
「気分が落ち込んだときは、まず動く」
今ではそんな風に言えるようになった私ですが、当時は動く気力すらなかったんです。でも、ある日30分だけウォーキングしてみたら、呼吸が深くなって、なぜか気分がちょっとだけ前向きになった。それがきっかけで、週に1〜2回は軽く体を動かすようにしました。
ここで大切なのは、「ちゃんと運動しなきゃ」ではなく、「ちょっと歩くだけでもOK」というマインドです。
✅ 太陽の光を浴びる
✅ 呼吸が整う
✅ セロトニン(幸せホルモン)の分泌が促される
感情がぐらついているときって、考えすぎて、頭ばかり疲れてしまうんですよね。そんなときこそ、体を動かすことで「今、ここ」に意識を戻すことができます。
私にとっての運動は、ジム通いでも筋トレでもなく、“感情のデトックス”としての散歩でした。
情緒不安定な時期って、自分のコントロールがきかないように感じて、本当に苦しい。でも、「これならできそう」と思えるケアを一つずつ積み重ねていくことで、ちゃんと抜け道は見つかるんです。
どれかひとつでも、「やってみようかな」と思ってもらえたら、それがもう第一歩です。
情緒不安定な自分とどう向き合った?【心の中の変化】
体のケアだけではカバーしきれないのが「心のゆらぎ」。特に、情緒不安定なときは、自分で自分を追い詰めてしまうこともあります。ここでは、私自身が感情の波と向き合いながら、少しずつ心の見方を変えていったプロセスをお話しします。「気合い」や「ポジティブ思考」では乗り越えられなかったからこそ、“ほどく”ことでラクになれた体験を共有したいと思います。
「ちゃんとしなきゃ」を手放す練習
22歳の私は、いつも「ちゃんとしなきゃ」と自分に言い聞かせていました。
✔ ミスしないように
✔ 笑顔でいなきゃ
✔ 人に迷惑かけちゃいけない
でも情緒が乱れているときほど、その“ちゃんと”が重荷になって、さらに自分を責めるループにはまっていきました。
そんなある日、信頼している年上の友人に「まさみちゃん、それ、ちゃんとしすぎじゃない?」と言われたんです。
その一言にハッとして、そこから少しずつ、「ちゃんとしなきゃ」に気づくたびに、「まぁ、いっか」って言ってみる練習を始めました。
たとえば、
・朝ごはんがコンビニでもOK
・仕事で疲れた日は早く寝てOK
・涙が出たら、無理に止めなくてOK
“手放すこと=甘え”ではなく、“自分に優しくする選択”なんだと、後になってようやく気づけました。
SNS断ちで得た“比べない”感覚
当時、私の情緒が大きく揺れていた原因のひとつが、SNSでの「他人との比較」でした。
キラキラして見える同世代の投稿を見ては、「私だけ遅れてる」「私ってつまらない人間かも」と落ち込む。投稿を見る→落ち込む→自己否定、の無限ループ。
それを断ち切るために、思い切って1週間だけSNSのアプリをスマホから消してみたんです。
最初の数日はそわそわしましたが、不思議と心が静かになっていって、「今、自分が感じてること」や「目の前のこと」に集中できるようになっていきました。
そして気づいたのは、“情報”より“感覚”を信じた方が、私は落ち着けるということ。
SNSって便利だし、つながりも生まれるけど、情緒が不安定なときは“自分の感情が他人の投稿に左右されすぎる”時期でもあるんですよね。
だから、「今は見ないほうがいいかも」と感じたら、それは逃げじゃなくて“自分を守る判断”なんです。
涙の日を責めないで:「そんな日もある」と思えるまで
私、情緒が揺れている時期って、ほんとうによく泣いてました。
仕事の帰り道でも、家でひとりになったときでも、なんなら電車の中でも。
そして泣くたびに、「なんでこんなことで泣くの?」「また感情に振り回されてる…」と自分を責めていました。
でもある日、いつものように泣いていたときに、ふと心の中で「泣いてもいいじゃん、つらかったんだもん」って言ってみたんです。
そしたら、なんだか涙の質が変わったというか、悲しみから“解放”に変わったような感覚になりました。
それ以来、私は泣いた日はカレンダーに小さく「🌧(雨マーク)」を書いて、「そういう日もある」って受け止めるようにしています。
感情を否定しないことは、自分を大切にすること。
涙が出るのは、あなたの心がちゃんと感じてる証拠です。
心の変化って、見えにくいし、成果が数字で出るわけじゃない。
でも、「ちょっと自分に優しくできた日」が積み重なることで、気づいたら前よりずっと生きやすくなっていた。それが私の実感です。
“治す”んじゃなく、“付き合い方を変える”こと。
それが情緒不安定との向き合い方の、いちばん優しいアプローチかもしれません。
専門家に頼ってよかったこと【病院・カウンセリング体験】
情緒不安定が続くと、「もう何をしてもよくならないかも」と感じてしまうこと、ありますよね。セルフケアだけではどうにもならなかった私は、思いきって専門家の力を借りてみることにしました。それは、「弱さ」じゃなく、「選択肢を増やすこと」だったと今では思います。この章では、婦人科とカウンセリングという2つのアプローチが、どう私の回復に影響したかをリアルにお伝えします。
婦人科受診でわかったホルモンバランスの乱れ
当時の私は、「情緒不安定=メンタルの問題」だと思い込んでいました。でも、ふと「もしかして体の問題かも?」と感じて婦人科を受診したのが転機でした。
問診と血液検査の結果、医師からは「黄体ホルモンの変動が強く出やすい体質かもしれませんね」と言われたんです。つまり、PMS(月経前症候群)の影響で、感情の浮き沈みが強く出ていた可能性があるということ。
そこで提案されたのは、
✅ 低用量ピルによるホルモン調整
✅ 睡眠と食事の見直し
✅ 自律神経を整えるサプリの活用
すべてを一度に実行するのではなく、できるところから少しずつ取り入れてみることにしました。
その結果、「生理前の涙が出る感じ」が少しずつ和らいでいったんです。
ホルモンの乱れは“気のせい”ではなく、ちゃんと根拠がある。
そう分かったことで、「私がおかしいんじゃない」と思えるようになったことが、一番の安心材料でした。
カウンセリングで「話す」ことの大切さに気づく
もうひとつ大きかったのが、カウンセリングに通ってみたことです。
最初はかなり勇気がいりました。「こんなことで相談していいのかな?」という不安も正直ありました。
でも、実際に話してみると、自分が思っていた以上にいろんなことを抱え込んでいたことに気づいたんです。
カウンセラーの方が、
「それって、ものすごくがんばってきた証拠だよ」
「一度、ちゃんと悲しんでもいいと思いますよ」
と声をかけてくれた瞬間、自然と涙があふれてきて…。
それからは、話すことで心の中の“つかえ”が少しずつ外れていく感覚を覚えました。
カウンセリングって、アドバイスをもらうというより、“自分の本音に気づくための場所”なんですよね。
感情がこじれているときほど、言葉にして誰かに聞いてもらうことの意味は本当に大きいと実感しました。
メンタル不調とPMSの境界線を知る
婦人科やカウンセリングを通じてわかったのは、「これはメンタルの問題なのか、ホルモンの影響なのか」を見極めることの大切さです。
PMS(月経前症候群)による情緒不安定は、排卵から生理前にかけて起きる一時的なもので、生理が始まると症状が軽くなることが特徴です。
一方、メンタル不調(うつ症状など)は周期に関係なく続くことが多く、放置すると慢性化するリスクも。
| 比較項目 | PMSの情緒不安定 | メンタル不調(うつ傾向) |
|---|---|---|
| 発生タイミング | 生理前のみ | 常に波がある |
| 期間 | 数日〜1週間程度 | 長期にわたり継続する |
| 改善傾向 | 生理が始まると軽くなる | 時期に関係なく継続 |
| 対処法 | ホルモン調整・生活改善 | 医療的支援が必要な場合も |
どちらにしても、「自分の状態を知る」ことがスタート地点です。ひとりで抱え込まず、専門家に頼る選択をしていいんです。
誰かに頼ることって、弱さじゃない。
むしろ、「私は大事にされていい存在なんだ」と自分で自分に教えてあげることだと私は思います。
情緒が不安定な自分を、まずは自分自身が受け入れてあげること。
そして必要なら、プロの手を借りてみる勇気も、立派なセルフケアなんです。
今、情緒不安定な20代に伝えたいこと
22歳の頃の私は、「こんなことでつらくなる自分は弱い」と思い込んでいました。でも、あの頃より少し年を重ねた今なら言えるんです。情緒が不安定になるのは、誰にでもある自然なこと。そしてそれは、ちゃんと向き合えば変えていけるということ。
ここでは、当時の私自身に、そして今まさにモヤモヤの中にいる20代のあなたに伝えたい3つのことをまとめました。どれも、フェムケアの視点から心と体を“ちゃんと大事にする”ヒントです。
自分の心と体を切り離さないで
心が揺れるとき、つい「メンタルが弱い」と思いがちですが、その背景には体の変化や不調が関わっていることがとても多いです。
✔ 生理前のホルモン変動
✔ 睡眠不足
✔ 栄養の偏り
✔ 自律神経の乱れ
こうした体の要因が、心に大きく影響していることを知っておくだけで、「なんでこんなに気分が落ちるの?」という問いが少し楽になります。
フェムケアの原点は、「心と体を切り離さずに捉えること」。
体を整えることで心が安定する。心を緩めることで体もラクになる。そんな循環が、少しずつあなたを支えてくれます。
ケアは“我慢”じゃなく“選択肢”であること
私たちは、つい「がまんすること=エライこと」と思いがちです。でも、本当のケアって、“何かを我慢すること”じゃない。
ケアは、“どうしたいか”を自分で選ぶための余白をつくること。
情緒が不安定なときこそ、自分にこう問いかけてみてください。
- 今、何をしてあげたら私の心は少しラクになる?
- 誰に助けを求めたら安心できる?
- 今日は何を手放していい?
そうやって、自分のケアの「選択肢」を持てることが、自立した大人の第一歩なんだと、私は実感しています。
情緒不安定は「ダメなこと」じゃない
声を大にして伝えたいのはこれです。
情緒不安定になること=ダメな自分ではない。
むしろ、それは「ちゃんと感じている」「ちゃんと反応できている」自分の強さかもしれません。
社会の中でがんばる私たちは、「安定している人」が正解のように見えてしまうけれど、感情の波があるからこそ、人に優しくなれるし、誰かの痛みに寄り添える。
私自身、情緒が不安定だった時期があったからこそ、今こうしてフェムケアという道にたどり着き、多くの人と共感を分かち合えるようになりました。
だから、どうか自分を責めないでください。
“不安定さ”は、あなたの個性のひとつ。
それに気づけたとき、きっとあなたは、もっと自分を好きになれるはずです。
情緒が揺れるのは、「ちゃんと生きてる証」だと私は思っています。
だからこそ、焦らず、責めず、自分の声を少しずつ拾っていくこと。
それが、フェムケアのはじまりです。
あなたがあなた自身に、やさしくなれる日がきますように。