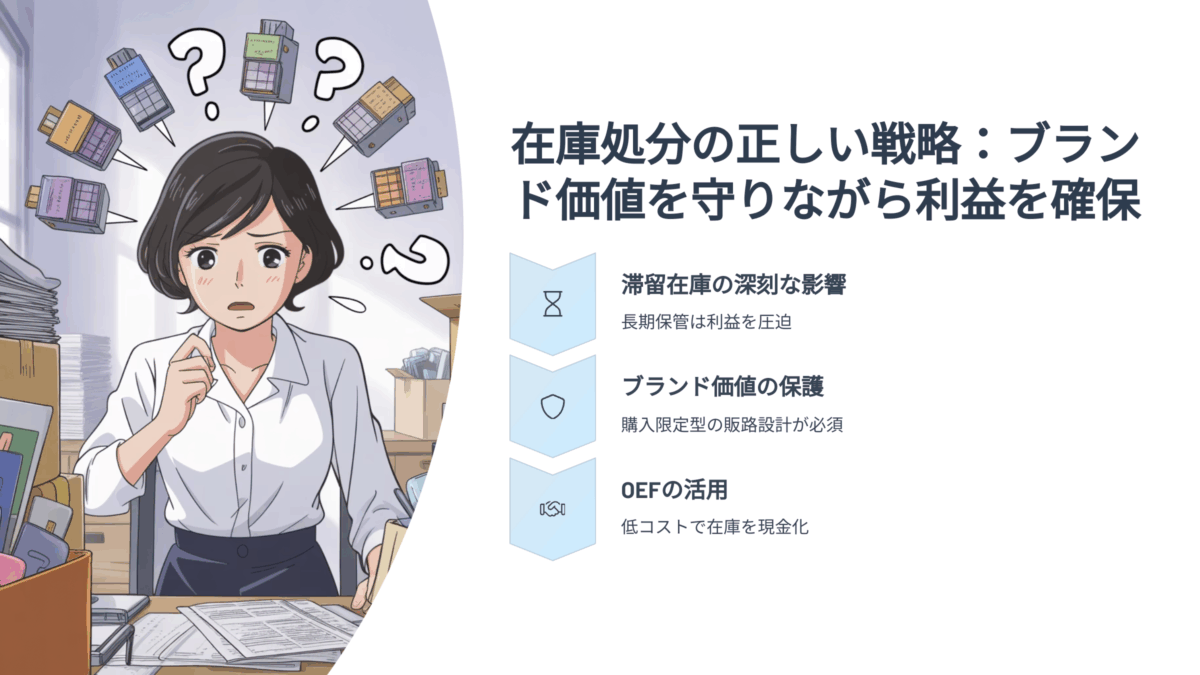滞留在庫の保管コスト、見えない損失になっていませんか?
ブランドを守りながら在庫を現金化する方法、実例とともに解説します。
目次を見て必要なところから読んでみてください。
問屋・卸業者を悩ませる「滞留在庫」と倉庫コストの現実
売れない在庫が「利益圧迫」の元凶になる
「倉庫に置いてあるだけでコストがかかる」。頭ではわかっていても、つい後回しになってしまうのが在庫管理のことかもしれません。でも、売れるはずだった商品が長く倉庫に眠っていると、それは静かに利益をむしばむ要因になってしまいます。
特に、季節商品やトレンド性の高いアイテムは、時間が経つほどに「売りにくくなるリスク」が高まります。
賞味期限がある食品はもちろん、日用品や雑貨でもパッケージ変更や製造ロットの都合で、「まだ使えるのに価値が下がってしまう」なんてことも少なくありません。
在庫が増えすぎてしまうと、必要な商品が見つけにくくなったり、ピッキングや出荷の手間も増えてしまいます。
つまり、売れない在庫を抱えているということは、目に見えないコストを日々積み重ねていることと同じなのです。
たとえば、こんなケースはありませんか?
✅ 売れると思って仕入れた商品が、思ったより動かずに残っている
✅ 少し前の販促キャンペーンで余った在庫が、棚の奥に眠っている
✅ 「いつか売れるかも」と思って処分を先延ばしにしている
その「ちょっとした放置」が、やがて大きなムダになってしまうこともあるのです。
「置いておくだけ」で発生する倉庫費・機会損失
在庫は「資産」として扱われがちですが、売れなければ“負債”になりかねないという事実も忘れてはいけません。
商品の保管には、スペースや管理の人件費、冷蔵・冷凍の設備コストなど、さまざまな間接的コストがかかっています。
以下のように、滞留在庫が抱える“見えにくいコスト”は意外と多いものです。
| 滞留在庫が生む主なコスト | 内容 |
|---|---|
| 保管コスト | 倉庫の賃料・棚のスペース使用料など |
| 管理工数 | 在庫チェック、ピッキング、棚卸しの手間 |
| 機会損失 | 本来売れたはずの商品のスペースを奪っている |
こうしたコストは、1つ1つは小さくても、積もれば毎月何万円、年間で何十万円というレベルに達することもあります。
また、在庫が長期滞留することで、商品そのものの価値が下がってしまうのも大きなリスクです。「新商品」や「今どき感」がなくなってしまうと、割引してもなかなか動かなくなる…。そうなると、泣く泣く処分という選択をせざるを得ないケースも。
在庫を持つことが当たり前の問屋や卸業者さんにとって、これは避けて通れないテーマです。
だからこそ、「売れない在庫をどう減らすか?」ではなく、「どう価値を見出して流通させるか?」に視点を変えていくことが大切なのではないでしょうか。
倉庫の片隅に眠っているその商品、もしかしたら「必要としている誰か」に届けば、もう一度輝けるかもしれません。
次回は、そんな在庫の“もったいない”を“売上”に変えるためのヒントをご紹介していきますね。
よくある在庫処分の落とし穴とは?

在庫が滞留していると、「とにかく早く処分しなきゃ」という気持ちになりがちです。ですが、その焦りのままに動いてしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。
いま、多くの問屋さんや卸業者さんが悩んでいるのは、「在庫を処分する方法はあっても、それが本当に正解なのか?」という問いではないでしょうか。
在庫処分は、ただ売り切ればいいというものではありません。ブランドや信頼を守りながら、納得できるかたちで価値を回収することがとても大切です。
安売り・叩き売りがブランドに与える影響
在庫を早く捌くために、つい「赤字でもいいから安く売ってしまおう」と考えてしまうことがあります。でも、その安売りが長い目で見て大きな代償を生むことも少なくありません。
たとえば、卸先の小売店で叩き売りが続くと、
「このブランドはよくセールになってるから、定価では買いたくない」
「品質に何か問題があるのでは?」
といった消費者の信頼低下につながることもあるのです。
また、既存の取引先からも「他で安売りしてるなら、うちも仕入れ価格を見直してほしい」といった交渉が入ってしまうことも…。
一度下がったブランドイメージを元に戻すのは、想像以上に大変です。
だからこそ、安売りには「ブランド毀損リスク」という目に見えないコストがあることを、忘れずにいたいですね。
寄付・廃棄にもコストがかかる現実
「寄付すれば社会貢献になるし、良いことじゃないか」
そう思われる方も多いと思います。もちろん、善意ある行動としてとても大切な選択肢です。
ただ、実際に寄付するとなると、梱包・配送・仕分けなどの物流コストや人件費がかかります。また、受け取る側の条件や品質基準もあり、すぐに引き取ってもらえるとは限らないケースもあります。
一方で廃棄となると、産業廃棄物として処理費用が発生するだけでなく、企業としての環境配慮への姿勢が問われる時代になっています。
つまり、寄付も廃棄も「コストゼロではない」どころか、実は目立たない経費がかさんでいる可能性があるのです。
処分コストと物流手間で“逆に赤字”になるケースも
「在庫は早く手放したほうがいい」
たしかにそれは一理あります。でも、処分=赤字の出口になってしまっては、本末転倒です。
とくに物流面での負担は見落とされがちです。
「バラで箱詰めし直す必要がある」
「混載便で送れず送料が割高になる」
「対応するスタッフの手が足りない」
こんな事態になってしまうと、在庫を動かすたびにコストが膨らむという悪循環に…。
一見すると“在庫処分成功”に見えても、
ふたを開ければ「利益ゼロ」「むしろ赤字」では意味がありません。
だからこそ、これからの在庫処分には「どれだけ安く売れるか」ではなく、「どんな販路で、どんな価値として届けるか」が問われる時代です。
もし、「この商品、まだ誰かに喜ばれるはず」と思えるものがあるのなら、価格ではなく想いと価値を伝えられる場所に届けていきたいですね。
次は、その“価値を守りながら在庫を減らす方法”について、一緒に考えてみましょう。
在庫を利益に変える「スペース効率化」戦略3選

「まだ売れる商品なのに、スペースばかり取ってしまう」
そんな在庫、倉庫のどこかに眠っていませんか?
売れ残りではなく、“売る場”を失っているだけの在庫はたくさんあります。
今回は、その在庫をスペースのムダから“利益”へ変える3つの戦略をご紹介します。
どれも難しいことではありません。少し視点を変えるだけで、倉庫にも気持ちにも、ゆとりが生まれるはずです。
アウトレット販売で保管コスト→現金化
最初の選択肢は、アウトレット販路への切り替えです。
賞味期限が迫っていたり、パッケージに少し傷がある商品など、店頭には並べづらいけれど品質に問題のないものを、「お得なアウトレット商品」として出品するという方法です。
この方法の良いところは、“今あるもの”をすぐにキャッシュに変えられること。
さらに、倉庫スペースも空くため、次の仕入れに向けて回転がよくなります。
アウトレット販売は、「値崩れを起こすのでは?」と心配されることもありますが、購入層を限定することでブランド価値を守ることも可能です。
たとえば、会員制で販売する仕組みにすれば、市場全体への影響を最小限に抑えることができます。
小ロット販売・詰め合わせセットで価値アップ
「ひとつひとつは地味だけど、まとめれば魅力的になる」
そんな商品があれば、セット商品として再構成するのがおすすめです。
たとえば、
・季節外れの在庫を“おまかせボックス”に詰める
・用途やテーマでセットにして、“選ぶ楽しさ”をプラスする
・試供品やB品をオマケとして活用する
こうした工夫をすることで、単品では売れにくかった在庫にも「体験価値」や「楽しさ」が加わり、売上アップが期待できます。
小ロットでの販売に切り替えることで、
「大口の取引がないと出せない…」という壁も乗り越えやすくなります。
実際に、セット販売をきっかけに定期購入につながったケースも少なくありません。
“少しだけ試せる・気軽に買える”というハードルの低さが、今の消費者ニーズにも合っているのです。
サブスク向け販路で定期的に出荷スペース確保
最後は、「スペース効率化」と相性の良いサブスクリプション型の販路です。
ポイントは、“定期的に在庫が動く仕組みを持つ”ということ。
いくら在庫があっても、「出荷の予定が立たない」と、結局スペースを圧迫してしまいますよね。でも、サブスク向けの販売チャネルであれば、
・毎月決まった数を出荷できる
・予定が組めるから人員配置も効率化できる
・出荷ベースで在庫が循環する
というメリットがあります。
さらに、サブスクユーザーは「商品との出会い」を楽しんでいる方が多く、
少し珍しいものや、普段手に取らない商品ほど喜ばれる傾向があります。
つまり、「売れ残り」ではなく「発見できる商品」として届くというわけです。
このように、「どうして売れない?」ではなく、
「どう届ければ喜ばれる?」という発想に切り替えることが、在庫を利益に変えるカギになります。
限られた倉庫スペースを、利益を生むスペースに。
その第一歩は、在庫に「新しい出口」を用意することかもしれません。
ブランドを守りながら在庫整理するための工夫

在庫整理というと、「値下げ」や「処分」という言葉が先に浮かんでしまうかもしれません。
でも、実際はもっと繊細で、ブランドの価値を守るための“設計力”が求められる作業でもあります。
どんなにお得でも、どんなに売上につながっても、ブランドイメージが下がってしまえば本末転倒。
ここでは、ブランドを守りながら、在庫を無理なく流通させるための工夫についてお伝えします。
「価格は見せて、購買は限定」の安心設計とは?
まずお伝えしたいのが、「誰でも見られるけど、誰でも買えるわけではない」という販売のかたち。
これを「クローズド・バイイングモデル」といいます。
たとえば、ECサイト上では商品名や価格は公開されていても、実際に購入できるのは登録会員だけという設計。
この仕組みのいいところは、価格が外に見えていても、それが「市場価格」として流通しないという点です。
価格がオープンになっていることで“透明性”は保ちつつ、
購買行動が制限されていることで、ブランドイメージや既存の取引関係を守ることができるんですね。
しかも、会員は“エシカル消費に関心のある人たち”に限られているため、
「安いから買う」のではなく、「意味のある買い物として選ばれる」傾向があります。
この限定性が、ブランドの安心感につながっているのです。
市場価格を壊さず販路を確保する方法
在庫処分でよくある不安が、「あちこちで安売りされたら、他の取引先に迷惑がかかるのでは?」というもの。
とくに、量販店や小売チェーンとの契約があるメーカーさんにとっては、死活問題ですよね。
そんなときに大切なのは、「誰に」「どう届けるか」を明確にする販路選定です。
たとえば、価格比較サイトや検索エンジンで拾われないように、
・販売ページをクローズドにする
・会員登録後のみカートが開く設計にする
・SEOで拾われにくい設計をあえて選ぶ
などの方法があります。
また、ユーザーを“お得に買いたい人”ではなく、“エシカル消費に共感する人”に絞ることで、
単なるディスカウントではなく「意味ある選択」として受け入れられる土壌を作ることができます。
この「価値ある売り場づくり」が、ブランドの未来を守る販路につながっていきます。
企業間の信頼を損なわない販売チャネルの条件
そして何よりも大切なのが、パートナー企業や取引先との信頼関係を守ることです。
「他社が知らないところで勝手に安売りしている」
そんなふうに思われてしまったら、次の取引どころか、長年の関係も揺らいでしまうかもしれません。
だからこそ、販売チャネルには“説明責任が果たせる明確なルール”があることが重要です。
信頼されるチャネルの条件は、たとえばこのようなものがあります。
✅ 会員制で、販売対象が限定されている
✅ プラットフォーム自体に「フードロス削減」などの社会的意義がある
✅ 商品の販売状況が把握でき、出品者がコントロールできる
こうした設計があれば、取引先にもきちんと説明できますし、何よりブランドの信頼性を損なわずに在庫整理が可能になります。
「売るか守るか」ではなく、「売りながら守る」。
今の時代は、そんな販路設計ができるかどうかが、企業価値にもつながっていくのではないでしょうか。
フード・日用品問屋が活用する「新たな販路」の実例

「このままだと在庫が期限切れになってしまう…」
「少し古いパッケージだけど、中身は変わらないのに…」
そんな悩みを抱えるフード・日用品の問屋さんは少なくありません。
ですが、今では在庫を“処分”ではなく“再価値化”して売り切る販路が広がってきています。
ここでは、実際に成果を上げた3つの事例を通して、「在庫が売れる場所」のリアルをお伝えします。
食品業者が成功した“詰め合わせ販売”の裏側
ある食品問屋さんは、賞味期限が1か月〜3か月程度残った商品を多く抱えていました。
個別に売るには物流コストが見合わず、悩んだ末に選んだのが「おまかせ詰め合わせBOX」という形式でした。
詰め合わせる内容は、パン、ドレッシング、レトルト、乾物など多岐にわたり、「何が届くかわからない楽しさ」が人気を呼びました。
結果的にこのBOXは完売し、
✅ 通常では売り切れなかった在庫が一気に動いた
✅「届くのが楽しみ!」という声とともにSNSで拡散
✅ 単品ではなく“体験”として購入され、価格へのネガティブ印象が生まれなかった
という嬉しい結果に。
この事例のポイントは、“在庫処分”ではなく“福袋的な価値提供”に切り替えたこと。
お客様にとっての“ワクワク”が、売上につながったのです。
日用品卸が在庫を減らしながらブランド認知を広げた事例
とある日用品卸さんは、長期滞留していたスキンケア商品や入浴剤を、アウトレット販売で出品しました。
もちろん、価格オープン/購入クローズドの販売モデルを採用。
これにより、ブランドの通常ルートには影響を与えることなく、在庫を動かすことができました。
さらに注目すべきは、購入後にブランド名を検索し、公式通販やドラッグストアでの購入につながったケースが増えたという点。
つまりこの取り組みは、
✅ 在庫の現金化
✅ ブランド認知の拡大
✅ 新規ファンの獲得
という三拍子そろった好事例となったのです。
特別価格で出会った商品が、「次は定価でも買いたい」につながる。
それはまさに、「在庫を未来のファンづくりに活かした」好例でした。
ローカル問屋が全国のエシカル消費者とつながった理由
ある地方の食品問屋さんは、地元で出荷先が限られていたため、一定量の在庫が定期的に余ってしまっていました。
そこで、「エシカル消費に関心のある全国の人たちに届けたい」と考え、エシカル購買層が集まる会員制ECプラットフォームに出品。
ここで重要だったのは、“価格の安さ”ではなく“価値の共感”で商品が選ばれたことです。
例えば、
「パッケージに少し汚れがあるけど、味や品質には問題なし」
「地方で作られた、こだわりの無添加お菓子」
といった商品が、都市部の購入者に「こういうのが欲しかった!」と好評を得ました。
この事例から見えるのは、
✅ 「規模の壁」ではなく「価値観の近さ」でつながる販路
✅ 地方でも、全国に“理解ある購買者”がいる時代
✅ エシカルという“共通言語”が販路を広げるカギになる
という事実です。
物流が全国に対応できるようになった今、“都会の棚”を狙わなくても、買ってくれる人と出会える時代になりました。
だからこそ、在庫に困ったときにこそ「誰に届けたいか」を見直すことが、販路開拓の第一歩なのかもしれません。
OEFが選ばれる理由と出品のメリットとは?

「在庫は動かしたい、でもブランドは守りたい」
そんな問屋さん・卸業者さんの声に応える新しい販路として、注目を集めているのがOEF(Outlet, Ecology, Foodloss)です。
フードや日用品を扱う事業者にとって、「売れなかった」ではなく「まだ売れる」商品を、価値ある形で届けられる場所。それがOEFの目指す世界です。
ここでは、OEFが支持されている理由と、実際に出品することのメリットをご紹介します。
購入は会員限定=ブランド価値を守る設計
OEFの大きな特長のひとつが、「価格はオープン」「購入は会員限定」という仕組みです。
誰でも商品情報や価格は見ることができますが、実際に購入できるのは月額会員として登録しているユーザーのみ。
これにより、次のような効果が生まれます。
✅ 市場価格を壊す心配がない
✅ 値崩れによる既存取引先とのトラブルを防げる
✅ エシカルに共感する“選ばれた消費者”に届く
つまり、「安く見せたくない」「ブランド価値を守りたい」という企業にとっても、安心して販売できる仕組みなんですね。
実際、多くのサプライヤーさんから「これなら安心して在庫を出せる」と評価をいただいています。
初期費用を抑えて即日出品OK
OEFは、はじめやすさも大きな魅力のひとつです。
出品には審査がありますが、承認後はシンプルな登録ステップだけで、最短即日から販売がスタートできます。
費用も明確で、以下のようなシンプルな料金体系です。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 初回登録費 | 15,400円(税込)※初回のみ |
| 月額出品費 | 2,980円(税込) |
| 販売手数料 | 10%(決済手数料込み) |
このように、大きな広告費やシステム投資をせずにスタートできるのが特徴です。
特に、小ロットやスポット販売をしたい業者さんにとっては、「お試しで始めやすい」「コストリスクが少ない」と好評です。
「売れた時だけ手数料」で低リスクの販路拡大
OEFでは、売れたときだけ販売手数料が発生する仕組みです。
つまり、「売れなければ、コストが発生しない」。この明快さが、多くの卸事業者から支持されています。
さらに、OEFのユーザー層は、安さだけで動く購買層とは異なり、「エシカル消費」に高い関心を持つ人たちです。
だからこそ、商品が“処分品”としてではなく、
✅「まだ使えるのに廃棄されそうだったものを救う」
✅「サステナブルな選択肢として価値を感じてくれる」
という形で受け入れられます。
このように、売上・信頼・ブランド価値の“すべてを守れる”新しい販路として、OEFは日々注目を集めています。
もし今、「在庫はあるけど動かせない」「ブランドを壊さず販路を広げたい」と感じているなら、
OEFでの出品は、きっとそのひとつの答えになるはずです。