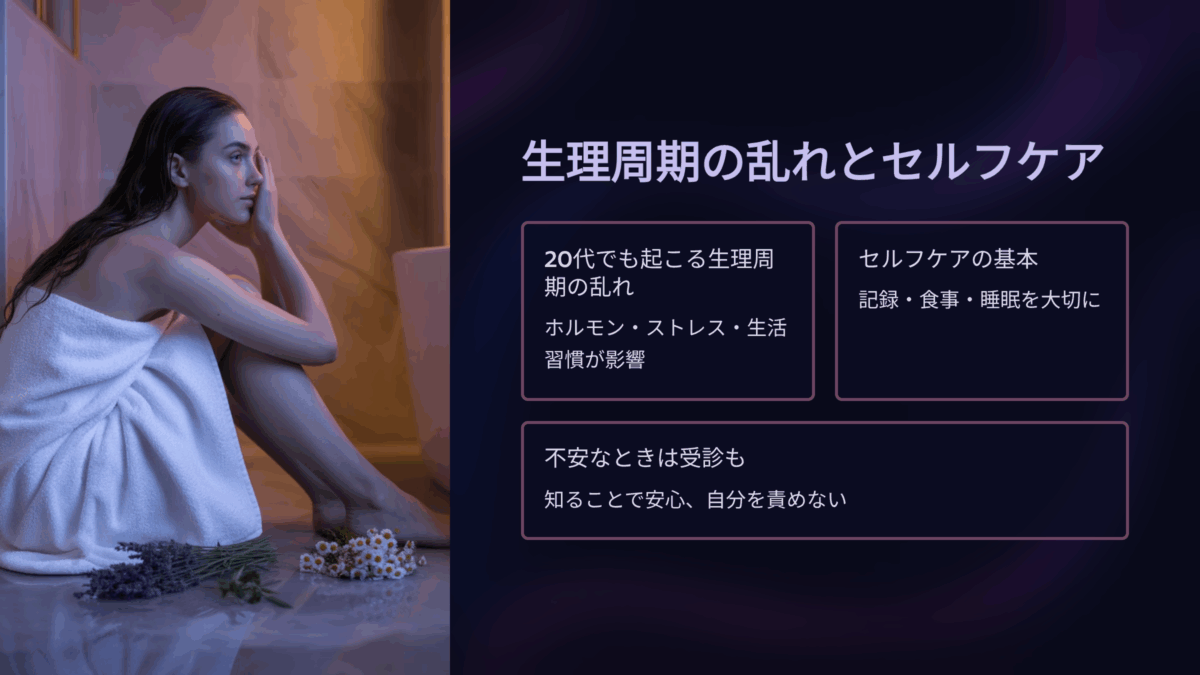生理周期が乱れる原因は、ホルモンバランスの変化やストレス、睡眠不足、栄養不足などさまざま。この記事では、22歳で生理不順を経験した私の体験談をもとに、セルフケア方法や婦人科受診の目安まで詳しく解説します。女性ホルモン・生理不順・20代・周期の乱れに不安を感じる方におすすめです。
生理周期が乱れた22歳の私が感じたこと【共感ベースの体験談】
生理周期が急に乱れたとき、「えっ、なんで? 私、何かおかしいのかな…?」と戸惑った経験はありませんか?この章では、実際に22歳のときに生理周期が崩れた私自身の体験をベースに、感じた不安や、誰にも言えなかったモヤモヤとの向き合い方をお話しします。同じように悩んでいる人が、「自分だけじゃない」と少しでも安心できるように、心の内側までリアルに綴ります。
周期の乱れに気づいたきっかけ
最初に「なんか変だな」と感じたのは、予定日を過ぎても生理が来なかったときでした。私はもともと28〜30日周期で比較的安定していたので、少しのズレなら気にしないタイプ。でも、その月はいつまで経っても来なくて、「あれ?」という違和感がじわじわと広がっていきました。
次の生理が来たのは、なんと前回から43日後。それでも「たまたまかな」と思っていたら、今度は19日で来て、量も少なく、色も薄い…。そのあたりから「これはさすがにおかしいかも」と思い始めたんです。
周期が乱れる=体のサイン。当時の私は、それに気づいているようで、気づかないふりをしていたかもしれません。
病気?ストレス?「原因がわからない不安」との向き合い
生理周期が乱れる理由って、本当に人それぞれです。ホルモンバランスの乱れやストレス、寝不足、ダイエット、生活環境の変化。思い当たる節はいくつもありました。
私の場合は、ちょうど就職活動と卒業制作が重なった時期。知らず知らずのうちに、体にも心にも無理がかかっていたのだと思います。
でも、厄介だったのは「明確な原因がわからないこと」への不安でした。
- まさか病気?
- 将来、妊娠に影響する?
- 婦人科に行くべき?
- 周りに相談していいことなの?
いろんな思いが頭の中をぐるぐるして、「わからない」ことが何より不安でした。そして同時に、「こんなことで不安になる自分が弱いのかな」と自分を責めてもいました。
でも今なら、はっきり言えます。不安になるのは当たり前。それに向き合おうとするだけで、すでにすごいことなんです。
誰にも言えなかったモヤモヤと、心の葛藤
正直な話、当時は誰にも言えませんでした。
友達との話題は、恋バナや就活の愚痴が中心。生理の話なんて、重たすぎる気がして。「周期が乱れててさ…」なんて切り出す勇気はなかったです。
親に言うのも気が引けて、「また余計な心配かけるかな」と遠慮してしまった。結果、私はひとりでググって、悩んで、自己診断して、また不安になって…を繰り返していました。
今でこそ、「フェムケアはもっとオープンでいい」と思えるようになりましたが、あのときは本当に孤独でした。生理のことを話題にするだけで、どこか“恥ずかしい”とか、“重い”って思われるような、そんな空気があったんですよね。
でも実際は、体のことをきちんと話せることが、自分を大切にする第一歩。モヤモヤを抱え込んだままだと、心までどんよりしてきます。
だからこそ、この記事では声を大にして伝えたいんです。
✅周期が乱れることは、決して珍しいことじゃない
✅不安になるのは、体がちゃんとサインを出している証拠
✅話していい。頼っていい。自分を責めなくていい
「誰にも言えなかった」私の体験が、今まさに悩んでいるあなたの安心材料になれたら、とても嬉しいです。
生理周期が乱れる主な原因とは【知識としての整理】
生理周期が乱れたとき、「とにかく不安」「原因がわからないのがつらい」という声をよく聞きます。でも、理由がわかるだけで、心って少し落ち着くんですよね。この章では、生理不順の主な原因やメカニズムを、20代前半にも当てはまる視点でわかりやすく整理していきます。「知っておくこと」=「自分のケアに役立てられること」。そう信じて、一緒に学んでいきましょう。
ホルモンバランスの乱れ:20代前半にも起こる理由
「ホルモンバランスの乱れ」と聞くと、更年期や30代以降のイメージがあるかもしれません。でも実は、20代前半でも普通に起こります。
私たちの体は、視床下部・脳下垂体・卵巣という三つの司令塔が連携して、女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)を分泌しています。このバランスが少し崩れるだけで、生理周期にズレが出るのです。
しかも、10代後半〜20代前半は、「ホルモンが安定しきっていない」時期。社会的な変化(進学・就職・人間関係)も重なるので、ホルモンバランスはとても揺れやすい。
✅ポイントまとめ
- 20代でもホルモンバランスは乱れる
- 規則的な周期=正常、とは限らない
- 体がリズムを探っている最中かもしれない
「まだ若いのにおかしい?」と自分を疑わなくて大丈夫。体はちゃんと調整しようとしてくれているのです。
ストレス・睡眠不足・ダイエットが影響するしくみ
生理は、ただの月1イベントではありません。心身の状態を反映するバロメーターです。とくに、現代の女性を悩ませがちな「ストレス・睡眠不足・過度なダイエット」は、周期の乱れに直結します。
| 原因 | 生理周期への影響 | 補足ポイント |
|---|---|---|
| ストレス | 視床下部の働きが低下し、ホルモン指令が乱れる | 精神的ストレス・環境変化の両方が影響 |
| 睡眠不足 | メラトニンやホルモン分泌が不安定になる | 夜型生活は要注意 |
| 無理なダイエット | 脂肪が減りすぎると、排卵が止まることも | エストロゲンは「脂肪組織」からも作られる |
つまり、「体にとっての安心感」があるかどうかがカギなんです。どこかで無理していたら、ちゃんと体が「ちょっと休んで」と教えてくれているのかもしれません。
「頑張りすぎ」が周期のズレを生むって、切ないけど、本当にあるあるなんですよね…。
重大な疾患が隠れていることも?受診の目安
多くの場合、生理周期の乱れは一時的な体の反応ですが、なかには婦人科系の疾患が原因の場合もあります。たとえば、以下のような症状がある場合は、婦人科への受診をおすすめします。
✅受診を検討したいサイン
- 生理が3か月以上来ていない
- 毎回の周期が極端に短い(21日未満) or 長い(35日以上)
- 生理の量が極端に多い/少ない
- 排卵障害を起こすような疾患(多嚢胞性卵巣症候群など)の疑いがある
- 下腹部痛や発熱など、他の体調不良を伴う
もちろん「怖いから行かない」気持ちもわかります。でも、診てもらうことで安心できることも多いんです。
「何もなかった」と言われたら、それはそれでひと安心。“不安を抱えたまま放置”のほうが、体にも心にもストレスです。
一歩踏み出すことが、セルフケアの第一歩。ちゃんと知ることは、自分を大切にすることにつながります。
周期が乱れたとき、私が実践したセルフケア【リアルな対処法】
生理周期が乱れたとき、ただ「戻ってくれればいいのに」と願うだけでは、不安は消えてくれませんでした。だからこそ私は、自分なりにできることをひとつずつ試してみました。この章では、実際に私が取り入れて効果を感じたセルフケアをご紹介します。難しいことはしていません。「気づく」「整える」「休ませる」——その3つを軸に、やさしく体と向き合うことから始めました。
アプリでの記録と「自分のパターン」を知ること
まず取り入れたのが、生理管理アプリです。正直、以前は「記録なんて面倒」と思っていたのですが、生理周期が乱れたことで「まずは現状を知ろう」と思い直しました。
記録を始めると、気づきがたくさんありました。
- いつもより遅れているのか、そもそも不規則なのか
- 生理前に情緒が乱れることが多い時期
- 頭痛や眠気、ニキビなどの体調変化
これって、ホルモンバランスがどんな波を描いているかを“見える化”する行為なんですよね。
✅私が記録していたこと
- 生理の開始日と終了日
- 経血量(多い/少ない)
- お腹の張り・気分の変化
- 睡眠時間と質
- 食欲や便通の変化
自分のパターンが少しずつ見えてくると、「次も同じかも」と予測できて、不安が減りました。“知る”って、こんなに心強いんだと気づかされたケアでした。
食生活の見直しと栄養のバランスを整える工夫
周期の乱れを経験してから、私は食生活にも目を向けるようになりました。それまでの私は、朝食を抜いたり、コンビニ飯や菓子パンで済ませることも多く、正直“栄養バランス”は意識できていませんでした。
でも調べてみると、女性ホルモンの分泌や代謝に深く関わる栄養素がいくつもあるんですよね。
| 栄養素 | 期待できる働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| 鉄分 | 経血による鉄の喪失を補う | レバー・赤身肉・ひじき |
| ビタミンB6 | ホルモンの代謝をサポート | バナナ・玄米・鶏むね肉 |
| マグネシウム | 自律神経を整える | ナッツ類・豆類・海藻 |
| イソフラボン | エストロゲンに似た働き | 納豆・豆乳・豆腐 |
食事を完璧にするのは難しいけど、「ちょっとだけ意識する」ことでも変化は起きます。私は、朝食にヨーグルト+ナッツ+バナナを加えることから始めました。
あと、水分をしっかり摂ることも意識しました。体が潤うと、巡りも整ってくる感じがして。無理な制限をやめて、「体にやさしいものを選ぶ」ように切り替えたことが、結果的に心の安定にもつながりました。
心と体をつなげる:睡眠・リラックスの時間を大切に
最後に一番大きかったのが、「ちゃんと休む」こと。
就活やSNS、将来への不安で、私の頭の中はいつもフル回転。布団に入っても、心はずっと働きっぱなしで、浅い眠りが続いていました。
でも、私たちの体は眠っている間にホルモンバランスを整えてくれているんですよね。だから、睡眠の質は思っていた以上に大切でした。
私がやったことは、ほんの小さな工夫ばかりです。
✅やってよかったリラックス習慣
- 寝る1時間前はスマホを手放す
- 白湯を飲んで、体を内側から温める
- 深呼吸して「今日はこれでOK」と自分に声をかける
- アロマや間接照明で、安心できる空間をつくる
特に「自分をねぎらう言葉」を習慣にしたことで、心がゆるみ、体のこわばりも和らいでいきました。
「頑張らなきゃ」じゃなくて、「今日もよくやったね」。そんな風に自分と会話することが、ケアのいちばんの基本なのかもしれません。
周期が乱れたときにできることは、実はたくさんあります。「ちゃんとケアしよう」と思えた瞬間から、体との関係性は少しずつ変わっていく。私の体験が、あなたの一歩につながりますように。
受診・相談するという選択肢【不安を軽くするために】
生理周期の乱れが続くと、どうしても「病院に行ったほうがいいのかな…?」と考える瞬間が出てきます。でも同時に、「婦人科ってなんかこわい」「恥ずかしい」と感じる人も多いのではないでしょうか。この章では、実際に私が婦人科を受診した体験をもとに、ハードルの下げ方や受診の流れ、不安を軽くする考え方をまとめました。行くかどうかを決めるためにも、まずは“知ること”から始めてみてください。
婦人科に行くまでのハードルと、実際の流れ
婦人科って、どこか「特別な場所」という空気感がありますよね。私も最初は、病院の名前を検索するだけでドキドキしていました。
「内診されるのかな?」「服脱ぐの?」
そんな疑問と不安が頭を占めて、なかなか予約のボタンが押せなかったんです。
でも実際に行ってみて思ったのは、“行くまでは不安、行ったらホッとする”ということ。
私が受診したときの流れはこんな感じでした。
✅初めての婦人科受診の流れ(例)
- ネット予約または電話予約
- 問診票の記入(生理周期・体調・不安なことなど)
- 医師との面談(必要に応じて血液検査・内診)
- 結果説明と今後のアドバイス
ちなみに私は、このとき内診はありませんでした(問診と血液検査のみ)。何をするかは体の状態によるので、無理に何かされるわけではありません。その点も安心材料のひとつでした。
医師に聞かれたこと・伝えてよかったこと
受診のとき、医師にどう話したらいいのかも不安のひとつですよね。私も、うまく伝えられるか不安で、ちょっとしたメモを持っていきました。
実際に聞かれたのは、こんな内容でした。
✅医師に聞かれたこと
- 最終生理の開始日
- 普段の周期と変化のタイミング
- 痛みや不快感の有無
- 妊娠の可能性(聞かれてびっくりする人も多いですが、一般的です)
- ストレスや生活の変化があったかどうか
ここで感じたのは、曖昧でもいいから「自分の言葉で話す」ことが大事だということ。
「多分○月くらいに来た気がして…」でもOK。先生たちはそれをヒントに、必要な検査やアドバイスをくれます。
そして、私が伝えてよかったと思ったのはこんなこと。
- 最近忙しくて、かなり寝不足だったこと
- 体重が少し減っていたこと
- 生理以外の変化(肌荒れやイライラなど)
こうした情報が、「これは一時的な乱れかもしれませんね」と医師の判断につながったのです。話してみると、「あ、これも言ってよかったんだ」と思えることがたくさんありました。
「異常なし」と言われても安心できた理由
検査結果を聞く瞬間って、本当に緊張しますよね。私は、「何かあったらどうしよう」とドキドキしていました。でも、先生から言われたのは、
「今のところ、特に大きな問題はなさそうですね」
という一言でした。
異常がなかった。もちろん嬉しかったです。でも、それ以上に感じたのは、
「ちゃんと診てもらった」という事実が、不安をぐっと軽くしてくれたということ。
それまで、「自分で検索して」「自己判断して」「モヤモヤして」いた状態から、「医師の目でチェックされた」「何かあっても次は相談できる」という安心感に変わったんです。
これって、実はすごく大きな変化でした。
婦人科に行く=何か問題があるから、ではありません。
「今の自分を知るため」に行く場所。
そして、「自分の体の味方を増やすため」に行く場所でもあると思っています。
怖い気持ちがあるのも自然です。でも、その一歩の先には、もっとラクに体と向き合える未来が待っているかもしれません。私の経験が、そんな一歩の背中をそっと押せたら嬉しいです。
体と向き合うということ【自分を責めないケア習慣】
生理周期の乱れを通して感じたのは、「自分の体とどう向き合うか」がすべての起点になるということでした。誰かと同じじゃなくていいし、完璧を目指す必要もありません。この章では、私が実践してきた“自分を責めない”ための考え方や習慣をまとめました。セルフケアは、情報よりも先に「心の土台」が必要です。あなた自身のペースで、丁寧に読んでもらえたら嬉しいです。
「ちゃんと知ること」で不安はやわらぐ
私たちは、不調を感じたときにまず「どうしよう」と不安になります。でも、その多くは“知らないこと”から生まれる不安だと気づきました。
例えば、生理周期が30日から40日に延びただけで、「これって病気?」と焦ったことがあります。でも、女性の正常な周期は25〜38日が目安と言われていて、多少のズレは生理的な範囲内だということを後から知りました。
つまり、不安って「何も知らない状態」だと何倍にも膨らむんです。
でも逆に、少しでも情報を知っていれば、「これは様子見でいい」「これは相談しよう」と判断できるようになる。
✅不安を減らす「知る」のアプローチ
- 信頼できる情報を、1日1つだけ読む
- 生理日や体調を記録し、変化を見える化する
- 「なぜ不安なのか」を紙に書き出して整理する
大切なのは、「情報を詰め込むこと」じゃなくて、今の自分に必要なことだけを、丁寧に知ることです。
周囲と比べない:自分のペースで向き合う大切さ
私が周期の乱れに悩んでいたとき、一番しんどかったのが、周りと比べてしまうことでした。
「○○ちゃんはいつもピッタリ周期で来てるらしい」
「私だけ変なんじゃないか」
「なんで私の体はコントロールできないの?」
そんな風に自分を責めてしまう瞬間が、何度もありました。
でもあるとき、ふと気づいたんです。人と体のつくりが違うのに、生理だけ同じになるわけがないって。生活リズムも、ストレスの感じ方も、体質も違うのに、同じサイクルで動く方が不自然なんですよね。
だから私は、自分にこう言うようにしました。
「私の体には、私のリズムがある」って。
それだけで、気持ちがすごくラクになったんです。
✅“比べない習慣”のために心がけたこと
- SNSで「理想的な体調管理」系の投稿を無理に見ない
- 友達との会話で「比べる話題」になったらそっと引く
- 「私の体のことは、私がいちばん知ってる」と思うようにする
自分を守るのは、自分の役割。自分だけのペースで向き合うことが、いちばんやさしいケアのかたちだと信じています。
小さな違和感を無視しないためのマインドセット
周期が乱れる前、私の体は実は、小さなサインを何度も出していました。
- 急にニキビが増えた
- いつもより眠りが浅くなった
- お腹の張りがずっと続いていた
でも当時の私は、「疲れてるだけ」「そのうち治る」と見て見ぬふりをしてしまったんです。
結果として、体の不調は大きくなっていきました。
だから今は、小さな違和感にこそ、ちゃんと目を向けるようにしています。それは「心配しすぎ」じゃなくて、「自分を大事にする習慣」だと思うんです。
✅違和感に気づくためのマインドセット
- 「今日はどうだった?」と1日1回、自分に問いかける
- 不調が出たときは、「どうしてだろう?」と興味を持つ
- 「こんなことで受診していいのかな?」と思ったら、行ってみる
ケアって、何かを“する”ことだけじゃなくて、自分の体にちゃんと耳を傾けることでもあると思います。
「違和感を無視しない」。それだけで、体との信頼関係はぐっと深まります。
“フェムケア”は、特別な人だけのものじゃない。
「なんか変かも」に気づいたあなたの中に、すでにその意識は芽生えている。
誰かに言えなかった気持ちも、今日ここまで読んでくれたことも、ぜんぶちゃんと意味があること。
自分の体を、もっと味方にしていきましょう。それは、誰よりもあなたが生きやすくなるための選択です。