
中小企業の滞留在庫問題を解決する「在庫管理の見える化」と「販路多角化」の方法をやさしく解説。在庫管理ツールの活用法やOEFなどエシカルECの活用法も紹介しています。無理なく始められる実践型の在庫対策アイデアが満載です。
なぜ中小企業にとって滞留在庫が経営リスクなのか?
在庫が余ってしまうのは、どの企業にも起こりうることです。でも、それが「滞留在庫」として長期間残ってしまうと、思っている以上に経営に影響を与えてしまいます。
「まだ売れるかもしれない」「もったいないから置いておこう」――そんな気持ち、よくわかります。けれど、その在庫がいつの間にか経営の足かせになっていることに、気づきにくいのです。
ここでは、滞留在庫がなぜリスクになるのかを、日常の感覚に近い視点で見つめ直してみたいと思います。
キャッシュフローを圧迫する“棚卸資産”の罠
売れ残った商品は、「いつか売れるから大丈夫」と思われがちですが、実はお金が“物”のカタチになって止まってしまっている状態なんです。つまり、仕入れに使った分の現金が、倉庫の奥でじっと眠っているようなもの。
その間にも、家賃や人件費、仕入れコストなどの支払いは続いていきますよね。在庫が動かなければ、お金が回らなくなって、経営の体力がどんどん削られてしまうのです。
とくに中小企業の場合は、資金繰りの余裕があまりないケースが多く、「ちょっとした在庫過多」が命取りになってしまうこともあります。
✅ 在庫は資産でもあるけれど、同時に“負債”になるリスクもあるということを、常に意識しておきたいですね。
「まだ売れるかも」が生む心理的バイアスとは
在庫を見つめながら、「これはまだ売れる」「今はタイミングじゃないだけ」と思ってしまうこと、ありませんか?
実はこれ、「サンクコスト効果」と呼ばれる心理的バイアスが関係しています。すでにお金や労力をかけたモノほど、手放すのが惜しく感じるという心のはたらきです。
でも、時間が経てば経つほど、商品は劣化したり価値が下がったりしてしまいます。「もったいない」と思って残した在庫が、結局もっともったいない結末を迎える――そんなことも少なくありません。
だからこそ、「売るか、捨てるか」ではなく、“第三の道”として在庫を活かす新しい選択肢を持っておくことが、これからの時代、とても大切になると感じています。
たとえば、賞味期限が近い食品や、パッケージに少しだけ傷がある日用品。それらを“エシカル商品”として、共感してくれる人に届ける仕組みがあれば、在庫は価値に変わります。
そんな考え方のもとで、OEFのような仕組みが生まれてきているのだと思います。
✅ 「もったいない」を、誰かの「うれしい」に変えること。
それが、これからの在庫管理に求められる視点ではないでしょうか。
在庫の見える化が経営改善につながる理由

「在庫管理」と聞くと、どうしても“地味な作業”というイメージを持たれるかもしれません。でも実は、在庫の“見える化”が、会社の元気を取り戻す第一歩になること、あまり知られていないんです。
売上を増やすことばかりに目が向きがちな日々の中で、「今、何が、どれくらいあるのか?」という足元の情報が整うと、驚くほど経営の流れがスムーズになります。
ここでは、在庫の見える化がどうして大切なのか、その理由をわかりやすくお伝えしますね。
数字で可視化すると「動き」が見えてくる
在庫を感覚で把握していると、「なんとなく足りている気がする」「まだあるから大丈夫」と思ってしまうこと、ありますよね。でも、実際の数字で見ると、意外な偏りや滞留に気づけることが多いんです。
たとえば、以下のような表を定期的にチェックしてみると、在庫の流れが“見える”ようになります。
| 商品カテゴリ | 在庫数 | 入出庫の変化(前月比) |
|---|---|---|
| 加工食品 | 120 | +15%(増加) |
| 日用品 | 80 | -10%(減少) |
| ギフト用品 | 30 | ±0(変化なし) |
※このように数字で整理すると、「この商品は増えてきているな」「あまり動いていないな」といった判断が感覚でなく客観的にできるようになります。
✅ 見える化すると、売れ筋や不良在庫の傾向が把握できるようになり、次のアクションがとりやすくなります。
たとえば、増えてきた在庫はプロモーションに回す、動かない商品は在庫圧縮の候補にする、といった判断もできるようになりますね。
社員間の連携が強化される副次効果も
もうひとつ、見逃せないのが社内コミュニケーションが自然とよくなること。
在庫の数字が見えるようになると、「どれを優先的に売ろうか」「この商品、最近どう動いてる?」といった会話が社内で生まれやすくなります。これって、実はとても大きな変化なんです。
今まで属人的だった在庫管理が、みんなで共有・判断できる“チームの情報”になることで、現場の連携力もぐっとアップします。
✅ 「情報を共有することで、人の動きも変わる」
それが、見える化のもうひとつの価値だと思っています。
業務改善の第一歩として、まずは在庫の棚卸しから始めてみませんか?
エクセルでも手書きでもOK。大切なのは、「数字で見てみる」こと。
ほんの小さな一歩が、経営全体の風通しを変えるきっかけになりますよ。
すぐに導入できる在庫管理ツール3選
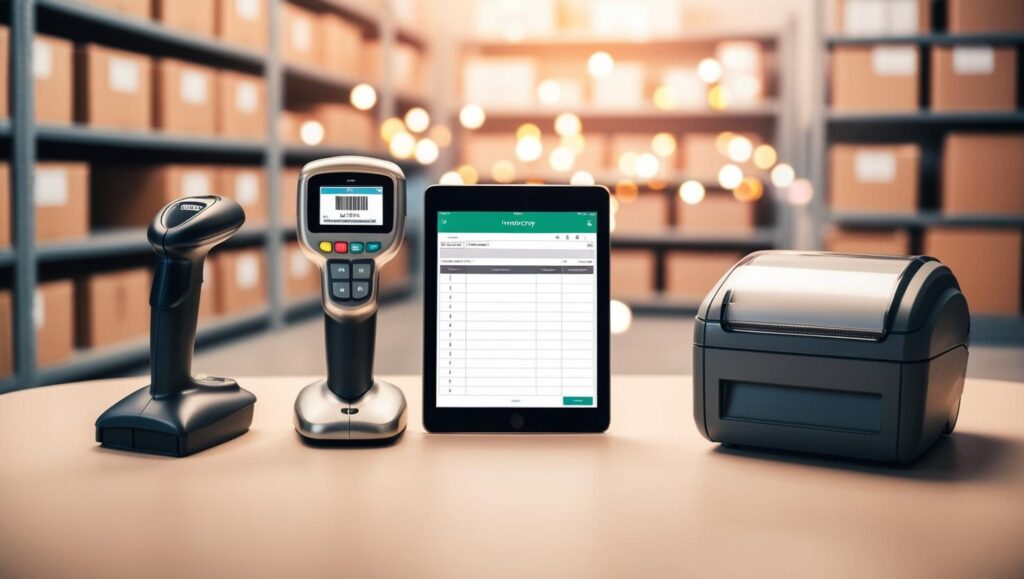
「在庫の見える化が大切なのはわかるけれど、実際にどうやって始めればいいのか分からない…」そんな声をよく耳にします。
特に中小企業では、大がかりなシステムは難しいと感じる方も多いですよね。
でも大丈夫です。今の現場にすぐ取り入れられる在庫管理ツールは、意外と身近なところにあるんです。
ここでは、「すぐに使えて効果も実感しやすい」3つのツールをご紹介します。
それぞれ特徴が違うので、ご自身の環境に合った方法を選んでみてくださいね。
スマートマットクラウド|重量センサーで在庫を自動検知
物の重さを感知するマットの上に商品を置くだけで、自動的に在庫数を記録してくれるスマートマットクラウド。
在庫が減ってきたらスマホに通知が来るので、「気づいたら在庫ゼロ!」なんてことも防げます。
たとえば、調味料や衛生用品など、「減っていくけれど数えづらいモノ」の管理にぴったり。
倉庫だけでなく、厨房やバックヤードにも導入できるのが魅力です。
✅ 人の手を介さず、在庫管理が“習慣化”されるのが一番のポイントです。
「在庫管理にかける時間をぐっと減らしたい」「ミスをなくしたい」という方におすすめです。
WMS(倉庫管理システム)|複数拠点の在庫を一元化
WMSとは「Warehouse Management System(倉庫管理システム)」の略で、
複数の倉庫や店舗を持つ企業に向いている本格的な在庫管理ツールです。
入出庫の履歴やロケーション(どこに何があるか)まで細かく把握できるので、人的ミスが減るだけでなく、出荷作業も効率化されます。
たとえば、こんな場面で活躍します。
| 課題 | WMSでできること |
|---|---|
| 倉庫AとBの在庫バランスがわからない | 各拠点の在庫状況をリアルタイムで確認可能 |
| どの商品がどこにあるか不明 | 棚番ごとに登録してロケーション管理 |
| ピッキング作業に時間がかかる | リスト化して効率的な作業手順を提示 |
※WMSは最初の設定に少し手間がかかりますが、中長期で見ると大きな時短と正確さの向上につながります。
導入サポートを行っているサービスも多いので、「そろそろ本格的に整理したい」と感じている方におすすめです。
スプレッドシート×Googleフォーム連携|最も手軽なスタート方法
「いきなりツールを導入するのは不安…」という方には、スプレッドシートとGoogleフォームの連携がおすすめです。
実際に、私のまわりでも小規模な事業者さんがこの方法で在庫管理を始めて成果を出していました。
やり方はとてもシンプルで、商品ごとの入力フォームをGoogleフォームで作り、
入力内容をスプレッドシートに自動で集計するだけ。
✅ スマホやタブレットからも入力できるので、現場のスタッフも参加しやすいのが魅力です。
紙の在庫表から卒業したい方や、「まずは無料で試してみたい」という方に、最初の一歩としてぴったりです。
在庫管理=大がかりな仕組みと思われがちですが、今ある課題に合わせて、できるところから始めることが何より大切です。
無理なく続けられる方法から、ぜひ一緒に探してみましょうね。
あなたの在庫が、ちゃんと「動く資産」に変わる日がすぐそこまで来ているかもしれません。

滞留在庫について、定義やリスク、対処法まで全体像を整理したい方はこちらも参考になります。
👉 滞留在庫の定義や経営リスク、具体的な対策までまとめて知りたい方はこちら
滞留在庫を「売れる資産」に変える3つの方法


「この在庫、もう売れないのかな…?」と悩んでしまう前に、まず滞留在庫の定義や見極め方を知っておくと、判断がスムーズになります。
▶滞留在庫とは?デッドストック・余剰在庫との違いと対策をわかりやすく解説
「どうしても売れ残ってしまう在庫がある」
「値引き販売ばかりで利益が出ない」
そんな風に感じたことはありませんか?
でも、その“滞留在庫”は、見方を変えればまだまだ価値ある資産。
ただ売る場所や方法を変えるだけで、在庫が再び動き出すことがあります。
ここでは、中小企業でもすぐ実践できる“在庫の再活用法”を3つご紹介します。
小さな工夫からでも、在庫の命を吹き返すことができるんです。
割引販売のその前に、「販路の最適化」が先
在庫を減らしたいと思ったとき、つい「値下げして売ろう」と考えてしまいがちです。
けれど、割引は最後の手段。まず考えてみてほしいのは、「この商品、どこで売るのがベストなんだろう?」という視点です。
✅ 売れない理由は「価格」ではなく「届ける場所」かもしれません。
たとえば、ネットショップでは売れなかった商品が、実店舗ではあっという間に売れることもあります。
逆に、地元では反応が薄かった商品が、SNSで紹介した途端に完売することも。
まずは今ある販路を見直してみましょう。
- 顧客層と商品の相性は合っているか?
- その販路、まだ本当に機能している?
- 新しいチャネル(モール・EC・ポップアップ)を試せないか?
ほんの少し視点を変えるだけで、売れ残りが「新しい売上」に変わることもあるんです。
OEF(エシカルEC)で“期限が近い商品”を価値に変える
もし、「賞味期限が近くてもう売りづらい…」「外装にちょっと傷がある」
そんな理由で行き場を失っている商品があるなら、OEFのような“エシカルな販路”を活用するのもひとつの方法です。
OEFでは、「もったいないけど、まだちゃんと使える」商品を
サブスク会員限定でお得に販売しています。
✅ 一般流通に出せない在庫でも、エシカル消費に共感する人たちが「それ、欲しかった!」と受け取ってくれる。
この仕組みは、単なる“在庫処分”ではなく、「商品の命をちゃんと使いきる」ことにつながる販売方法です。
企業としての社会的なイメージアップにもつながりますし、
在庫を“責任を持って売る”という姿勢は、いま本当に求められている考え方ではないでしょうか。
社員や既存顧客向けの「B品セール」で関係強化も
もし「販売用には難しいけど、品質には問題ない」という商品があるなら、社内販売やB品セールも検討してみてください。
たとえば、
- 社員向けの特別販売会(福利厚生としても好評)
- メルマガ読者限定の「ちょっと訳あり市」
- 会員顧客向けに“お楽しみBOX”として福袋販売
こんな形で展開すれば、「ちょっと訳あり」な商品が喜ばれる特別な体験に変わります。
✅ 「売れ残り」ではなく、「選ばれし特価品」として伝える工夫も大切です。
また、こうした販売方法は「ありがとう」の声がダイレクトに返ってきやすいので、スタッフのモチベーションアップにもつながりますよ。
在庫は、ただ“減らす”だけではなく、“活かし方”を工夫することで、新しいつながりや価値を生むチャンスになります。
大切なのは、「どうすれば捨てずに済むか?」をあきらめずに考えること。
その姿勢こそが、これからのエシカルな時代に求められる経営のあり方だと、私は思っています。
まとめ|見える化+販路多角化が中小企業を救う
滞留在庫に悩んでいる企業にとって、「在庫管理の見える化」と「販路の見直し」は、もっとも効果的で現実的な改善策だと感じています。
私たちが向き合っているのは、ただの商品ではありません。
誰かの想いが込められた“まだ価値あるモノたち”なんです。
売れ残りではなく、まだ出会うべき人に届いていないだけ。
そう考えると、在庫をどう動かしていくかは、もっと前向きなチャレンジになれるはずです。
まずは社内の“在庫を見に行く文化”から始めよう
日々の業務が忙しい中で、在庫はどうしても“あとまわし”になりがちです。
でも本当は、一番身近にある経営資源なんですよね。
「今、うちに何があるのか?」
「どうしてこの商品は動かないのか?」
そんな問いかけを、まずはスタッフみんなで共有する時間をつくってみてください。
✅ “見に行く文化”が根づくと、現場の意識が自然と変わります。
現物を見て、話して、アイデアを出し合う。たったそれだけでも、在庫が“眠ったまま”になるリスクはぐっと減ります。
そして、そこから新しい販路への可能性も生まれてくるかもしれません。
OEF出品でフードロス削減と売上確保を同時に叶える
在庫をどう減らすか?という視点だけでなく、どう活かせるか?という視点で考えたとき、OEFのようなエシカルECはとても有効です。
賞味期限が迫っている食品や、ちょっとした傷がある雑貨でも、「もったいない」と感じる消費者にとっては“買いたい理由”になることもあります。
OEFではサブスクリプション会員向けに販売を行っているため、価格が一般流通に影響を与えずに済むというメリットも。
これは、ブランドを大切にしたい企業にとって、安心して出品できる仕組みです。
✅ 売れなかったモノが「社会に役立つ」商品に生まれ変わる
そんな体験は、企業にとっても働く人にとっても、大きな意味を持つはずです。
今あるものを、無駄にしない。
それは「地球にやさしい選択」であると同時に、中小企業の経営を健やかに保つ力強い戦略でもあります。
在庫に目を向けることは、未来への目線を整えること。
まずは、ひとつ、棚を開けてみるところから一緒に始めませんか?


