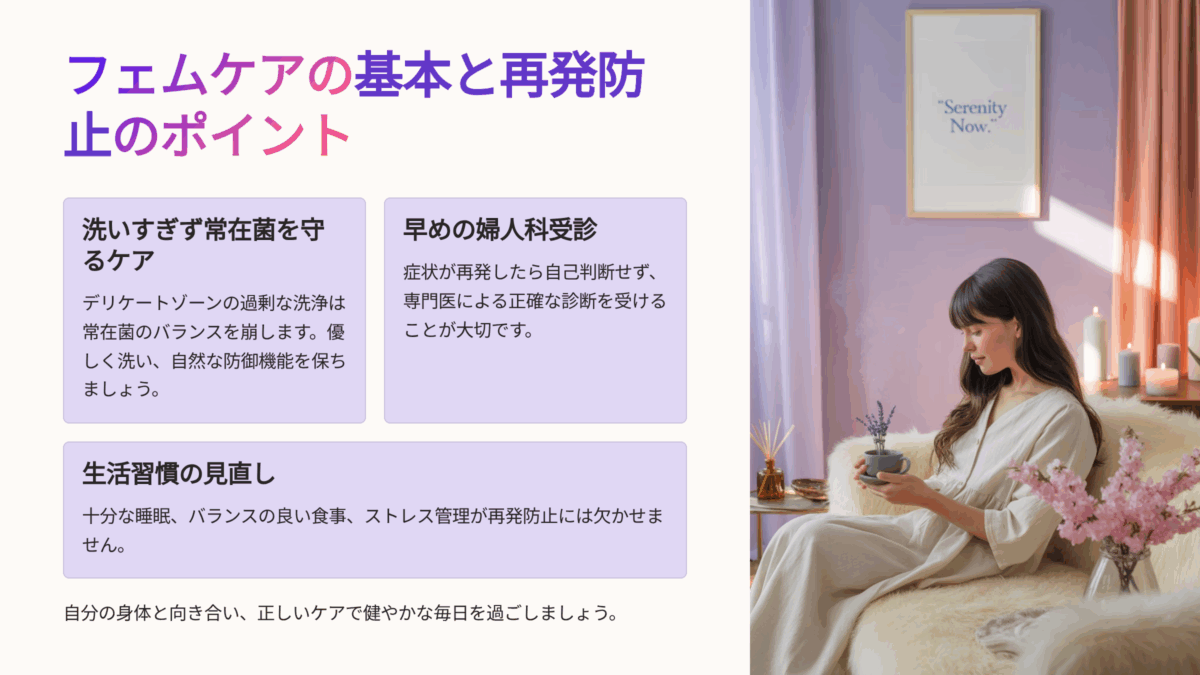何度もくり返すカンジダに、「もう治らないのかも」と感じていませんか?
実は、私もそう思っていた一人です。
再発を止めた体験をもとに、本質的な対策をまとめました。目次を見て必要なところから読んでみてください。
「カンジダが治らない」と感じるのはなぜ?
カンジダが繰り返し再発すると、「もう一生治らないのかも…」と感じる方は少なくありません。実際、私自身もそうでした。病院で治療しても、数ヶ月後にはまたかゆくなる。そんな体験の繰り返しに、心まで疲れてしまうんですよね。
この章では、なぜカンジダが“治ったと思ったのに再発する”のかを、3つの視点から分解してみていきます。
再発を繰り返す女性が抱える不安とは
「また来たかも」って思うたびに、落ち込むんです。誰にも言えないし、気分も沈むし、仕事にも集中できない。
私が初めて膣カンジダになったのは20代の頃。正直、最初は「ただのかゆみかな?」と思って放置していました。
でも、何度も繰り返すうちに、自分の身体がどこか壊れてしまったんじゃないかと思うほど、不安になっていきました。
カンジダは、身体の中に元からいる「常在菌」のバランスが崩れて増殖することで起こる感染症です。
一度の治療でスッキリ治る人もいれば、何度もぶり返す人もいる。その違いの多くは、治療だけでなく生活環境や体質、ケア方法までを含めた「見直し」にあります。
だからこそ、「なんで私だけ…」と思わなくて大丈夫。
大切なのは、再発の原因にちゃんと目を向けることなんです。
自然治癒に頼るのが危険な理由
「薬を使うのに抵抗がある」「市販の洗浄剤で様子を見たい」
そう思う気持ちも、すごくわかります。私もそうでした。
でも、カンジダは自然治癒するケースが少ない感染症です。
特に症状が強いときや、くり返し出る場合、自己判断でケアし続けると、かえって悪化することもあります。
さらに怖いのは、カンジダだと思っていたら、実は別の感染症だったというケース。
かゆみやおりものの変化だけでは、素人判断は難しいものです。
市販薬でいったん楽になっても、原因菌が完全にいなくなっていないことも多く、それが再発の原因になることも。
だからこそ、「様子を見る」より「専門家に相談する」ことが早道なんです。
実は“治っていない”ケースも多い
再発じゃなくて、そもそも前回のカンジダが完全には治っていなかった。そんな場合も少なくありません。
特に市販薬での対処では、正確な診断がないまま自己流で治療することになります。
それによって、症状が一時的におさまっても、菌自体が残っていて、しばらくするとまた増殖することがあります。
また、膣内環境はとても繊細です。
抗生物質やピル、疲労、ストレス、食生活、通気性の悪い下着など、さまざまな要因が常在菌のバランスを乱してしまうことも。
その状態が続くと、一度治療してもすぐに再発する体質になってしまう。これが、多くの女性が「もう治らないのかも」と感じる理由のひとつです。
✅まとめ:この章のポイント
- カンジダは自然に治りにくく、自己判断では見落としがち
- 「また再発した」は、「まだ治っていなかった」可能性もある
- くり返す背景には、生活習慣や体質の影響もある
カンジダが再発しなくなった理由とは
「もう一生このかゆみと付き合うのかな…」とあきらめかけていた私が、カンジダを再発させなくなったのには、明確な理由があります。
それは、「たまたま治った」わけではなく、根本から見直したから。
この章では、私が実践して効果を感じた3つの視点から、再発しない身体づくりについてお話しします。
常在菌のバランスを整えた生活習慣
まず見直したのは、デリケートゾーンを“洗いすぎない”ことでした。
市販のボディソープでゴシゴシ洗う習慣があった私。
でも、それが逆効果だったんです。膣内や外陰部には、善玉菌(ラクトバチルス)を中心とした常在菌がいて、外部からの刺激や菌の繁殖を防いでくれています。
それを毎日、洗浄力の強いもので根こそぎ洗っていたら…防御力がゼロになって当然ですよね。
私がやめたこと(NG習慣)と、始めたこと(GOOD習慣)は以下の通りです。
- やめたこと
- デリケートゾーンの過剰洗浄
- ナイロンタオルでの摩擦
- 通気性の悪い下着の長時間着用
- 始めたこと
- 専用ソープでのやさしい洗浄(1日1回)
- コットン素材の下着への切り替え
- おりものシートをこまめに交換
たったこれだけでも、かゆみの頻度がグッと減ったのを実感しました。
膣の自浄作用はとても賢くて、外からのケアは“引き算”でいいと気づいたんです。
自己判断をやめて医師の診断を受けた
もうひとつ、大きな転機だったのが、「ちゃんと婦人科に行く」と決めたこと。
最初は正直、少し怖かったです。
でも、自己判断で市販薬を何度も使っても治らなかったのに、たった一度の検査と治療で、症状がしっかり落ち着いたんです。
カンジダは、他の性感染症と症状が似ていることも多く、自己診断では不十分なこともあります。
私が婦人科で受けたことはこんな流れでした:
- 診察・問診
- おりもの検査(菌の種類を特定)
- 抗真菌薬の処方(必要に応じて内服 or 膣錠)
このプロセスを経て、「自分の症状を正しく理解する」ことができたのは、精神的にもすごく大きかったです。
「婦人科って、もっと早く行けばよかった」
これが、正直な感想です。
免疫力を見直して体質改善につなげた
最後に取り組んだのが、体全体のコンディションを整えること。
カンジダがくり返す背景には、免疫力の低下があると言われています。
私の場合、仕事のストレス、睡眠不足、偏った食生活などが重なり、「治りにくい身体」になっていたことに気づきました。
そこから少しずつ意識したことは、シンプルなことばかりです。
- 1日7時間以上の睡眠をとる
- 白砂糖やアルコールの摂取を減らす
- 食物繊維や乳酸菌を意識してとる
- 湯船につかる・深呼吸する習慣をもつ
特別なサプリや高価なグッズは使っていません。
ただ、「わたし、疲れてるな」と気づいたときに、ちゃんと休むようにした。
それだけでも、身体の変化を感じるようになりました。
そしてなにより、「私はちゃんとケアできてる」という自信が、再発への不安を手放す力になったと感じています。
✅ まとめ:この章のポイント
- 常在菌を守るケアが再発予防の第一歩
- 自己判断をやめて、きちんと診断を受けることが根本解決につながる
- 食事・睡眠・ストレス管理で“カンジダに負けない身体”をつくる
生活習慣でカンジダを防ぐには?
再発をくり返すカンジダに終止符を打つには、“その場しのぎの対処”だけでは足りません。
ここからは、カンジダの再発を防ぐために、私自身が日々意識しているケアの習慣や生活全体の整え方をシェアします。
特別な知識がなくても、今日からできることばかりです。
デリケートゾーンのケアと注意点
デリケートゾーンは“特別扱いするべき場所”というより、「正しい知識でやさしく扱う場所」だと私は思っています。
清潔に保ちたいあまり、やりすぎてしまう人ほど、常在菌バランスを崩してしまいがちなんです。
私が見直したポイントはこの3つです。
- 洗いすぎない:1日1回、専用ソープで指の腹でやさしく洗うだけ
- ふき取りすぎない:タオルでゴシゴシはNG。やわらかい素材で“おさえるように”
- 湿らせない:おりものシートは長時間使いっぱなしにしない。通気性重視
また、生理中も気をつけています。
ナプキンを頻繁に変える、ムレない素材を選ぶなど、肌への負担を減らすことが大切です。
洗いすぎも、香り付きケアも、実は不要。
必要なのは、「守るケア」だけなんです。
食生活・睡眠・ストレス管理の基本
意外と見落とされがちですが、腸内環境と膣内環境は密接に関係しています。
腸にいる善玉菌(乳酸菌)が減ると、膣の自浄作用にも影響が出て、カンジダが増えやすくなることも。
私が日々意識しているのは、以下のようなことです。
- 発酵食品(納豆・味噌・ヨーグルトなど)を毎日少しでもとる
- 食物繊維を多くとって、腸の動きをよくする
- お菓子や砂糖をとりすぎない(糖分はカンジダ菌のエサになります)
加えて、睡眠の質とストレスマネジメントもすごく重要。
睡眠不足や精神的ストレスは、免疫力を大きく下げてしまいます。
湯船に浸かって、スマホを手放して、呼吸に意識を向けるだけでも、自律神経が整って、身体の中が静かになっていく感覚があります。
完璧じゃなくても、「今日はちょっと気をつけようかな」からで大丈夫。
自分のために選ぶ食事と睡眠が、未来の体調をつくります。
避けたほうがよいNG習慣とは
カンジダを防ぐうえで、「これはやめたほうがよかった」と私が実感した習慣を最後にまとめます。
- ナプキンやおりものシートをつけっぱなしにする
→ムレ・雑菌の繁殖につながる - きつめのパンツやレギンスを長時間はく
→通気性が悪く、湿度が高くなりやすい - 抗生物質をむやみに使う(風邪などで)
→善玉菌まで殺してしまうことがある - 過度なダイエットや不規則な生活
→ホルモンバランスや免疫力の乱れにつながる
一つひとつは小さなことですが、毎日の積み重ねが、再発を防ぐ大きな力になります。
「またなったらどうしよう」ではなく、「今、整えているから大丈夫」と思える自分に出会えるよう、習慣を味方にしていきましょう。
✅ まとめ:この章のポイント
- デリケートゾーンは「守るケア」が基本。洗いすぎない
- 腸内環境・睡眠・ストレス管理が膣の健康に直結する
- NG習慣を減らすだけでも、再発リスクは大きく下がる
受診の目安と市販薬との違い
「これって婦人科に行くべき? それとも様子見でいい?」
カンジダの再発時に、多くの人がいちばん迷うのがここかもしれません。
私自身も、最初は恥ずかしさや不安で、なかなか一歩を踏み出せませんでした。
でも、「行くべきとき」に受診することで、ムダに悩まなくてすむことも本当に多いんです。
ここでは、受診の目安や市販薬との違い、病院での検査の流れまで、整理してお伝えします。
どんなときに婦人科を受診すべき?
以下のようなケースは、迷わず早めの受診をおすすめします。
- はじめての症状で、自己判断が難しいとき
- 市販薬を使っても1週間以上改善しないとき
- 再発をくり返していて、体質が不安なとき
- おりものの色・におい・量に明らかな変化があるとき
- 外陰部の腫れ・強い痛み・排尿時の違和感があるとき
特に、「またカンジダかな?」と思っても、実はトリコモナス膣炎や細菌性膣炎、性感染症だったというケースもあります。
症状だけでは見分けがつかないからこそ、“カン”ではなく“検査”で判断することが安心への近道です。
また、何度も再発する場合は、一度専門家に体質的な傾向や生活習慣を相談しておくのもおすすめです。
婦人科は、「具合が悪くなってから行く場所」ではなく、未然に防ぐために使っていい場所なんですよ。
市販薬で対応してよいケース・ダメなケース
薬局で買えるカンジダ用の膣錠やクリーム、市販薬にも役割があります。
ただし、すべての人が自己判断で使ってよいわけではありません。
以下のようなときには、市販薬での対応も可能とされています。
- 以前、医師から「カンジダ」と診断されたことがある
- 同じような症状が再び出たが、軽度で日常生活に支障がない
- 妊娠していない/基礎疾患がない など
一方で、以下のケースでは市販薬の使用を避け、受診することが推奨されます。
- はじめての症状(原因がはっきりしない)
- 症状が重い、または長引いている
- 妊娠中・授乳中
- 市販薬で何度も再発している
市販薬は「すぐに病院に行けないときの応急処置」にはなるけれど、根本治療ではないと考えるのが大切です。
とくに再発が続いている方は、一度きちんと医師の診断を受けることが、結果的に早く治る近道になります。
病院での検査と治療の流れ
初めて婦人科に行くときって、どうしても緊張しますよね。
私も最初は「どんな検査をされるのか不安」で、なかなか足が向きませんでした。
でも実際には、あっけないほどシンプルな流れでした。以下のようなプロセスです。
- 問診(症状の時期・経過・性状など)
- 内診とおりものの採取(膣内の状態をチェック)
- 顕微鏡検査・培養検査で菌の種類を特定
- 診断と薬の処方(膣錠・クリーム・内服薬など)
※病院によっては、結果が出るまで数日かかることもあります。
婦人科の先生は、カンジダの患者さんを日常的にたくさん診ています。
こちらが思っているほど特別でも恥ずかしくもありません。
私は、「もっと早く行けばよかった」と何度思ったかわかりません。
症状が出ているときはもちろんですが、落ち着いているときに“予防のため”に相談するのもアリですよ。
✅ まとめ:この章のポイント
- 「いつ病院に行くか」は、症状の強さと頻度が判断のカギ
- 市販薬は自己判断に頼りすぎず、使いどきを見極める
- 婦人科での診察はシンプル。診断をつけてもらうだけで安心につながる
よくある質問と誤解の解消
カンジダの話って、なかなか人には聞けないですよね。
だからこそ、ネットで調べては不安になって…の繰り返しという方も多いのではないでしょうか?
私自身も、初めてなったときは「何が本当で何が誤解なのか」すらわからず、すごく混乱しました。
この章では、そんな声に多い3つの代表的な誤解や疑問を、できるだけフラットにお答えしていきます。
カンジダはパートナーにうつる?
まずよくあるのが、「カンジダって性病なの?うつるの?」」という不安。
結論から言うと、カンジダは基本的に性感染症(STD)ではありません。
膣カンジダの原因菌である「カンジダ・アルビカンス」は、もともと多くの人の身体(腸や口、膣など)に存在している常在菌です。
ただし、以下のようなケースでは注意が必要です。
- パートナーに症状がある(かゆみ、赤みなど)
- オーラルセックスで口腔カンジダが移る可能性がある
- 性交による摩擦で膣内環境が乱れ、再発しやすくなる
つまり、“感染する”というより、“環境の乱れで発症しやすくなる”という考え方のほうが近いんです。
再発をくり返す場合、パートナーと一緒にケアを見直すのもひとつの選択肢かもしれませんね。
責めたり責められたりするものではなく、身体の状態として捉えることが大切です。
おりものが白い=カンジダ?
「おりものが白くてポロポロしてる。これってカンジダ?」
これはカンジダを経験したことのある方なら、一度は感じたことのある疑問だと思います。
確かに、カンジダの典型的な症状のひとつに“白くてヨーグルト状のおりもの”があります。
ただし、それだけで「絶対カンジダ」とは言い切れません。
おりものの変化には、以下のような原因もあります。
| おりものの状態 | 考えられる原因(例) |
|---|---|
| 白くポロポロ | カンジダ、排卵後の変化など |
| 黄色や緑っぽい | 細菌性膣炎、トリコモナスなど |
| 灰色・悪臭 | 細菌性膣炎の可能性大 |
つまり、見た目やにおいだけで自己判断するのはリスクがあるということ。
「いつもと違うかも」と思ったら、早めに受診して確かめるのが一番確実です。
私自身も、「あれ?これはカンジダ?」と感じて婦人科を受診した結果、実はまったく別の原因だった…ということがありました。
繰り返すのは自分だけ?
「なんで私だけ…?」「また再発?こんなに何度もなる人いるのかな?」
そう感じると、落ち込んだり、どこか自分を責めてしまったりしますよね。
でも、大丈夫。カンジダは珍しいものではありません。
実際、女性の約75%が一度はカンジダ膣炎を経験すると言われており、そのうち半数近くが再発を経験しているという報告もあります。
私のもとにも、「月に一度は再発していたけど、生活を見直したら落ち着いてきた」という声がたくさん届いています。
つまり、「再発する=特別な体質」「重症」とは限らないんです。
大切なのは、自分を責めることではなく、
「私の身体、ちょっとがんばりすぎてるのかも」と気づいて、整えてあげること。
誰かと比べず、自分の身体と向き合う選択をしていきましょう。
✅ まとめ:この章のポイント
- カンジダは性感染症ではないが、パートナーの影響もゼロではない
- おりものの変化だけでカンジダと断定せず、他の病気の可能性も考慮を
- 再発は珍しくない。自分だけだと思わなくて大丈夫
まとめ:カンジダを「再発させない」ために
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
カンジダは、一度の治療で終わる人もいれば、何度もくり返してつらい思いをする人もいます。
でもそれは、「治療が足りない」のではなく、日常の積み重ねがカギを握っているからなんです。
私自身、何度も再発をくり返しながら、「これを機に、もっと自分の身体とちゃんと向き合おう」と思えるようになりました。
このまとめでは、再発を防ぐためにとくに大切だと感じたことを、3つの視点から整理してお伝えします。
本質的な改善のポイント3つ
再発を止めるには、ただ薬を使うだけでは足りません。
私が実際に変化を感じた「本質的な改善」のポイントは、この3つです。
- 膣まわりを守るケア
洗いすぎない・乾燥させすぎない・通気性を意識する - 生活習慣の見直し
睡眠・食事・ストレスケアを通じて、免疫力を取り戻す - 「私には効く方法」を探る姿勢
体質は人それぞれ。人の真似ではなく、自分に合うケアを選ぶ
症状に向き合うだけでなく、“自分のために選ぶ”ケアをしてあげることが、再発しない身体をつくっていきます。
受診と記録で自己管理を習慣に
もうひとつ、見落とされがちだけど大切なのが、「記録」と「相談すること」。
再発がある人ほど、
「前はいつ症状が出たのか」「そのとき何をしていたのか」
これをメモしておくだけでも、自分の傾向やリズムに気づけることがあります。
また、婦人科は決して“病気になったときだけ行く場所”ではありません。
「再発しやすくて不安」「正しいケアがわからない」そんなときにこそ、予防的に相談することが大切です。
少し勇気がいるかもしれませんが、その一歩が自分を守る力になります。
✅カンジダ対策セルフチェックリストつき
今のあなたの状態を確認できるように、シンプルなセルフチェックを用意しました。
気になる項目が多い場合は、生活習慣や受診の見直しを考えてみてもいいかもしれません。
- デリケートゾーンをボディソープで洗っている
- 毎日おりものシートを長時間つけっぱなし
- 睡眠は6時間未満が続いている
- 甘いもの・お酒をよくとる
- ストレスを感じていて、リラックスする時間がない
- 再発しても「また市販薬でいいや」と思っている
- 婦人科に行ったのは1年以上前
✅3つ以上当てはまる方は、一度セルフケアを見直すきっかけにしてみましょう。
一つずつでいいんです。小さな見直しが、確かな変化をつくっていきます。
カンジダに悩むことは、決して恥ずかしいことではありません。
それよりも、悩みに気づいて、ケアを選べる自分でいることが、いちばんすてきなことだと私は思います。
もっとやさしく、もっと自分らしく。
あなたが、あなた自身の身体と仲良くなれますように。
✅「もっと具体的に聞いてみたい」「セルフケアって何から始めればいいの?」という方へ
わたし谷澤まさみが運営する「フェムケアの部屋」では、LINEで最新情報やセルフケアのヒントをお届けしています。
【公式LINEはこちらから】
👉 https://lin.ee/oFb3xWZ
一人で抱えず、あなたらしいケアを一緒に選んでいきましょう。