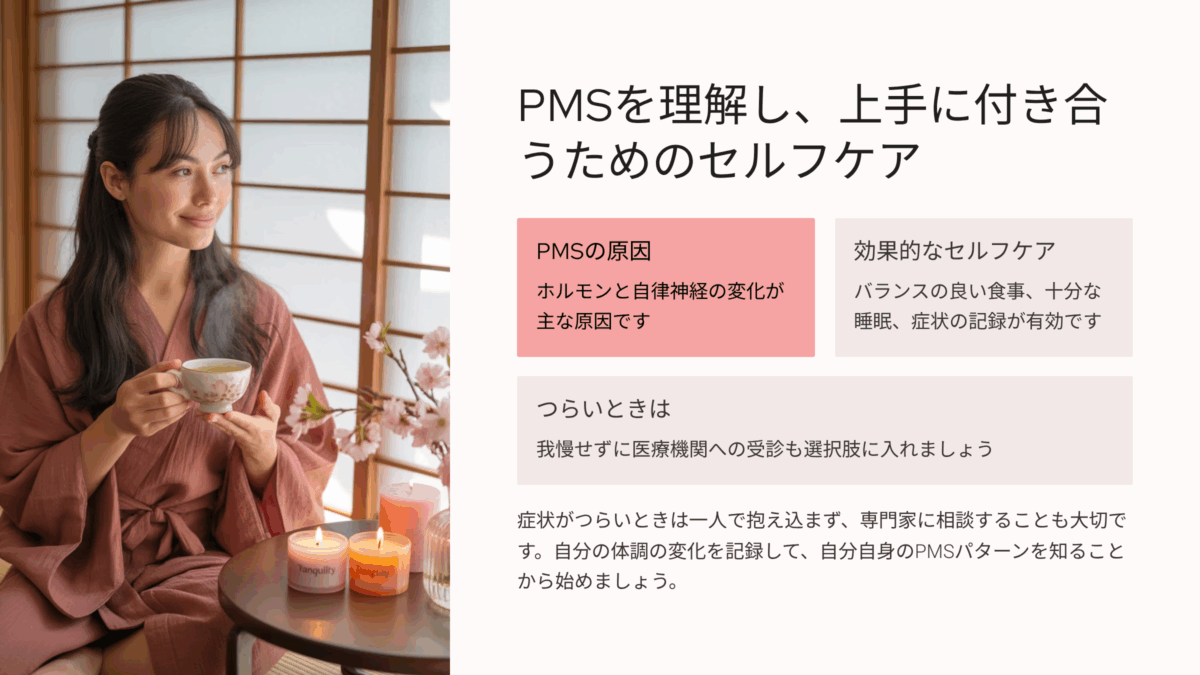PMSのつらさに悩み、どうにかしたいけれど何をすればいいかわからない。そんな私が実践してきたセルフケアと、その効果を等身大でまとめました。目次を見て必要なところから読んでみてください。
PMSのつらさ、なぜ起こる?(体験ベースの問題提起と原因理解)
PMSがしんどい、でも誰にもちゃんと話せない。そんな日々を、私もずっと抱えていました。
「毎月やってくるこの不調、いつまで続くの?」と、ふとした瞬間に涙が出そうになることも。
でも、なぜこの不調が起こるのかを知ったことで、私は少しずつ向き合い方を変えられるようになりました。
ここでは、私自身の実体験とともに、PMSの基本的なメカニズムと、その裏にあるホルモンや自律神経の変化をやさしく整理していきます。
PMSとは何か?主な症状とその仕組み
PMSとは「月経前症候群」のこと。
生理が始まる3〜10日ほど前から、心や体にさまざまな不調があらわれる症状の総称です。
✅ 私がよく感じていた症状はこんなものでした:
- ちょっとしたことでイライラする
- なぜか急に悲しくなる、涙が出る
- 下腹部が重くて動きたくない
- 便秘や肌荒れがひどくなる
- 人と話すのがしんどくなる
人によって、出る症状も重さも違いますが、生活に支障が出るレベルでつらいのに「気のせい」にされがちなのがPMSのしんどさです。
医学的には、女性ホルモンの変動によって脳や神経系、内臓に影響が出ることが原因とされています。
特に排卵後から月経開始までの間に、プロゲステロン(黄体ホルモン)とエストロゲン(卵胞ホルモン)が急激に変動することで、体と心のバランスが崩れやすくなるのです。
このホルモン変化は避けられないもので、「性格が弱いから」とか「甘えている」なんて全く関係ありません。
まずはここを、自分自身がちゃんと知ってあげることが本当に大切だと感じています。
なぜ毎月つらい?ホルモンと自律神経の関係
PMSのつらさを知るうえで欠かせないのが、ホルモンと自律神経の関係です。
実はこの2つ、私たちの体の中でしっかり連動しています。
月経周期の後半(黄体期)に入ると、プロゲステロンが増えて、交感神経が優位になる傾向があります。
この状態では、以下のような変化が起こりやすくなります:
- 体温が上がる(寝つきが悪くなる)
- 心拍や血圧が上がる(ドキドキしやすい)
- イライラ・不安・落ち込みなどのメンタル症状が出る
- 胃腸の働きが鈍くなる(便秘・むくみ)
つまり、ホルモンのゆらぎが、自律神経を通じて私たちの「生活のしやすさ」に直結しているんですね。
私も、毎月このタイミングになると睡眠が浅くなり、心がギスギスしがちでした。
「なぜ昨日まで大丈夫だったことに、今日は耐えられないんだろう?」と自己嫌悪する日も…。
でもこの仕組みを知ってから、「あ、これは“私が悪い”んじゃなくて“体の反応”なんだ」と思えるようになりました。
その理解があったからこそ、自分に合ったセルフケアを探すモチベーションにもつながったのだと思います。
PMSに向き合う第一歩は、「自分を責めないこと」。
そして、「体のしくみを正しく知ること」。
ここを押さえるだけで、次に取る行動がきっと変わっていきます。
私がPMS改善を目指した理由(行動のきっかけと挫折体験)
PMSのことをきちんと理解し始めた私は、「じゃあ、これからどうすればいいの?」という問いに直面しました。
すぐに病院に行くという選択肢もありましたが、正直それが難しい状況もありますよね。
ここでは、私がPMSを自分で改善したいと思ったきっかけや、そこに至るまでに経験した“うまくいかなかった方法たち”を、リアルにお伝えします。
病院に頼らずどうにかしたい…日常生活の支障
PMSの症状が重くなってきたのは、30代に入ってからでした。
仕事も責任あるポジションを任されるようになり、ちょっとした体調の波が、大きなミスにつながることも。
例えば、生理前の一週間はこんな感じでした。
- 通勤中に涙が出そうになる
- 同僚にきつく当たってしまって自己嫌悪
- 夕方には思考が止まるほどの疲労感
- 予定していた仕事が進まない
周囲に「PMSで…」なんて正直に言える空気もなくて、ずっとひとりで抱えていました。
でも、毎月こんな状態が続くのはあまりにも苦しい。
薬に頼るのはなんとなく抵抗があって、「自分の力でどうにかしたい」という思いが強くなっていったんです。
私は医療従事者ではないし、専門的なことは正直よくわかりませんでした。
でも、自分の体は自分で守るしかないという直感のような気持ちが、行動のきっかけになりました。
試してダメだった方法とその理由
とはいえ、最初からうまくいったわけではありません。
むしろ、「これで改善するかも」と思って始めたことが、まったく効果を感じられなかったり、むしろ悪化したりすることもありました。
特に挫折感が大きかったのが、以下のような方法です。
- 市販のサプリメントを飲んでみたけど変化なし
→「女性にやさしい」「ハーブが効く」と書いてあったけど、私には合わなかったようで、1ヶ月続けても体感なし。 - カフェイン断ちを試みたけどストレス増
→イライラが和らぐという話を聞いてコーヒーをやめたけど、逆に頭がぼんやりして、仕事に集中できずに挫折。 - 「気分転換が大事」として外出を増やした結果、疲れが悪化
→無理して外に出ようとして、かえって疲れて余計に落ち込む…の悪循環。
こうした経験を経て感じたのは、どんなセルフケアも「自分の体質や性格に合うか」がすべてだということ。
ネットで見た方法をそのまま取り入れても、うまくいかないことの方が多い。
大事なのは、「合わないと感じたら一度立ち止まる」ことと、「記録を取って、振り返る」ことでした。
この失敗の積み重ねが、次にご紹介する「自分に本当に合ったセルフケア」を見つける土台になったのです。
本当に効果を感じたセルフケア(体験に基づく具体策)
たくさんの失敗を経て、ようやく「これは私に合っているかも」と感じられるセルフケアに出会えました。
どれも劇的に改善するような即効性はありませんが、「ちょっと楽になったかも」と思える感覚の積み重ねが、月経前のつらさを軽くしてくれたんです。
ここでは、私が実際に取り入れてPMSの改善に役立った3つの習慣を、具体的にご紹介します。
食事を見直した:避けた食品・取り入れた栄養
私にとって最も効果を感じたのは、毎日の食事を見直すことでした。
これまで「体にいいはず」と思っていたものが、実はPMSを悪化させていた可能性もあると知って、ハッとしたんです。
✅ 私が避けるようにした食品
- カフェイン(コーヒー・紅茶)
- 精製された砂糖(お菓子・ジュース)
- 添加物の多い加工食品(コンビニ惣菜など)
- 塩分の多いスナック菓子やインスタント食品
これらは血糖値やホルモンバランスを乱しやすく、イライラやむくみの原因になりやすいことが知られています。
代わりに意識して摂るようにしたのが、以下の栄養素でした。
✅ PMSに役立った栄養素と食品例
| 栄養素 | 効果 | 食品例 |
|---|---|---|
| ビタミンB6 | 神経伝達物質の合成を助け、気分の安定に役立つ | さつまいも、まぐろ、バナナ |
| マグネシウム | 筋肉のけいれんや頭痛の軽減に | アーモンド、ほうれん草、玄米 |
| 鉄分 | 疲労感や集中力の低下を予防 | レバー、ひじき、赤身肉 |
| 良質な脂質 | ホルモンの材料として必要 | アボカド、ナッツ、亜麻仁油 |
特別なダイエットをしたわけではありません。
でも、「お昼はできるだけ自炊にしてみよう」とか「夜のおやつをナッツに変えてみよう」といった小さな選択が、数ヶ月後には明らかな心身の安定につながっていたと感じます。
睡眠と運動:生活リズムの整え方
PMSが重いときは、どうしても夜更かしやだらだら過ごす時間が増えてしまいがちでした。
でもその生活が、さらに自律神経を乱して悪循環になっていたことに気づきました。
そこでまず取り組んだのが、「毎日同じ時間に寝て、起きる」こと。
夜10時以降はスマホを触らないようにして、23時には布団に入ることを意識しました。
体温が高くなる黄体期には寝つきが悪くなるので、就寝前に白湯を飲んだり、足湯を取り入れるなど、副交感神経を優位にする工夫も効果的でした。
運動に関しては、「激しい筋トレ」ではなく、「ゆるい有酸素運動」が自分には合っていました。
- 朝10分のストレッチ
- 生理前は散歩を中心にする
- 無理せず「気持ちいい」と思える範囲で動く
この生活リズムを少し整えただけで、日中の気分の落ち込みやイライラが和らいだように感じました。
やっぱり、自律神経って生活の土台なんだなと実感しました。
メンタルケア:アプリでの記録とセルフモニタリング
最後にご紹介したいのが、心の状態を「見える化」するというセルフケアです。
私はPMSの時期、自分の気分の波に翻弄されて、「昨日まで元気だったのに、なんで今日はこんなにダメなんだろう…」と落ち込むことがよくありました。
でも、PMS専用の記録アプリを使って、体調や気分の変化を毎日数秒でメモするようにしてから、少しずつ考え方が変わってきました。
✅ 私が記録していた項目
- 気分(落ち込み/怒り/焦りなど)
- 体調(頭痛/腹痛/眠気)
- 睡眠時間・質
- 食事内容(甘いもの・カフェインなど)
- ストレス度(主観で1〜5)
この記録を3ヶ月くらい続けてみたら、「生理前になると必ず○日くらいからイライラする」などの自分なりのパターンが見えてきたんです。
そうすると、「これはPMSのせいだから、自分のせいじゃない」と切り替えることができるようになり、メンタルのダメージを最小限にできるようになりました。
このセルフモニタリングは、婦人科を受診する際の情報整理にも役立つので、ぜひおすすめしたい習慣です。
セルフケアのメリットと限界(客観視と注意喚起)
ここまでご紹介してきたように、私はPMSの改善に向けてセルフケアを試行錯誤してきました。
その結果、確かに症状が軽くなったり、自分を責めなくなったりする大きな変化を感じています。
でも同時に、「セルフケアだけですべてが解決するわけではない」という現実にも、ちゃんと目を向ける必要があると感じています。
この章では、セルフケアの良さと限界をフェムケアの現場での気づきとともに、フラットにお伝えします。
続けやすさ・副作用の少なさ
まず、セルフケアのいちばんの魅力は、日常の中で無理なく取り組めることだと思います。
病院に行く時間が取れない日も、薬に頼ることに抵抗がある人も、自分のペースで続けられるというのは大きなメリットです。
たとえば、
- 甘いものを控えてみる
- 夜更かしをやめてみる
- メモアプリで気分を記録してみる
こうした小さな行動でも、PMSの予防や悪化の防止につながる可能性があります。
そして何より、セルフケアは基本的に副作用がほとんどないという点でも安心感があります。
ただし、ここで忘れてはいけないのが、効果には個人差があるということ。
体質やホルモンの分泌バランス、ストレスの度合いなどによって、「効いた」と感じるまでのスピードも違いますし、そもそもセルフケアの範囲では届かない不調もあります。
だからこそ、「これをやれば絶対よくなる」と思い込まずに、「やってみて、合わなかったら見直す」くらいの柔軟さを持つことが、セルフケアを続けるコツだと思います。
改善しないときは?受診をためらわないで
PMSの症状には、セルフケアで十分コントロールできるケースもあります。
でも、もしあなたがこう感じているなら、一度医療機関を頼ってみることをおすすめします。
✅ こんなときは、受診をためらわないで:
- 気分の落ち込みが2週間以上続いている
- 日常生活に支障が出るほどイライラや不安が強い
- 周囲との関係に深刻な影響が出ている
- 毎月、生理が近づくのが怖いと感じる
これらは、月経前不快気分障害(PMDD)の可能性もあります。
PMSの重い症状が、単なる「気分の波」ではないこともあるんです。
私自身、婦人科を受診することにためらいがあった時期もありました。
「こんなことで病院に行っていいのかな」「何て説明すればいいんだろう」と、不安ばかりが先に立ってしまって。
でも、あるとき勇気を出して相談してみたら、医師はとても淡々と、そして丁寧に対応してくれました。
「もっと早く来てよかったのに」という言葉に、涙が出そうになったことを覚えています。
病院に行くことは、「負け」でも「甘え」でもありません。
今の自分に必要なサポートを選ぶという、立派な自己ケアの一環です。
そして、受診することで、ホルモンバランスの乱れや貧血など、隠れた体の問題に気づけることもあります。
セルフケアと医療ケアをうまく使い分けることこそ、これからのフェムケアに必要な視点だと、私は実感しています。
PMSと向き合う日々:心と体を守るために(読者への提案)
PMSの悩みは、症状が出ているときだけでなく、「また来るかも」という予期不安も含めて、とても消耗するものです。
しかも、それを誰にも見せずに抱え込んでいる人がほとんど。
私もそうでした。毎月繰り返される不調のなかで、「これが普通なんだろうか」「ずっとこのまま?」と、自分の気持ちにふたをしながら生活していた時期があります。
でもあるとき、ふと気づいたんです。
「このつらさに意味なんてない」と思っていたけど、自分の体とちゃんと向き合うきっかけをくれているのかもしれないって。
この章では、PMSと向き合う上で私が意識している「心と体を守るヒント」を、読者のみなさんと共有したいと思います。
自分を責めない・ひとりで抱えない
PMSがしんどいとき、つい「なんで私はこんなに不安定なんだろう」とか、「また人にきつくあたってしまった…」と、自分を責めてしまうことってありませんか?
でもそれって、症状の一部であって、あなたの本質ではありません。
体と心が不調なときは、誰だっていつものようには振る舞えません。
それは、「我慢が足りない」とか「意志が弱い」といった話ではなく、生理学的にそういう時期があるというだけです。
だからまずは、こう思ってみてください。
- 「今日はそういう日なんだ」
- 「体がサインを出してくれているんだ」
- 「この気分は一生続くわけじゃない」
そして、可能であれば身近な人に少しだけ気持ちを伝えてみてください。
「生理前でちょっとしんどくて…」と一言添えるだけでも、関係が少し柔らかくなることがあります。
もちろん、それすら難しい日もあるかもしれません。そんなときは、ノートやアプリに気持ちを吐き出すだけでも、頭の中が整理されて少し楽になります。
自分を責めず、少しずつでも誰かと分かち合えるようになること。
それがPMSと向き合ううえでの土台になると、私は思っています。
小さな変化を記録し、振り返る習慣を
PMSは、毎月やってくるからこそ「よくなる兆し」や「悪化のきっかけ」に気づきにくいもの。
だから私は、「気づくための習慣」として記録を続けています。
といっても、難しいことはしていません。
アプリや紙の手帳に、こんなことをほんの一言メモするだけです。
- 「今日は眠くてやる気が出ない」
- 「甘いものを食べすぎたらイライラが増した」
- 「夜しっかり寝たら少し元気になった」
この小さな記録が、数週間後、数ヶ月後には「あ、ここが私のパターンなんだ」と気づくきっかけになってくれます。
体も心も、機械じゃないから日によって違う。でも、そこにはリズムや傾向があります。
それを他人ではなく、自分が一番知っておくことが、何よりのセルフケアになると感じています。
また、記録は「改善した実感」を持つことにもつながります。
変化はゆっくりだけど、ちゃんと前に進んでいると可視化できることで、自己効力感も高まるんです。
「完璧に管理する」ことが目的じゃありません。
むしろ、自分に優しくなれる時間をつくるという意味で、記録や振り返りはとても価値ある時間です。
PMSは、自分の体の声を無視しないための、ひとつのサインかもしれません。
向き合い方を変えたとき、少しずつ世界の見え方も変わっていく。
私の体験が、あなたがご自身のリズムを見つけるヒントになれば嬉しいです。
よくある質問:PMSセルフケアQ&A
ここでは、私がフェムケアの発信をするなかで、実際に多くの方から寄せられたPMSセルフケアに関する質問をまとめてみました。
「ネットには情報が多すぎて、何が本当なのかわからない」そんな悩みに、等身大の視点からお答えしていきます。
サプリや漢方は試すべき?
これはよく聞かれる質問ですが、結論から言うと、「自分の体質や生活スタイルに合わせて選ぶなら、試してみる価値はある」と私は思っています。
私自身も、PMSがひどかったときにいくつかのサプリや漢方薬を試したことがあります。
結果としては、「効果があったものもあれば、まったく体に合わなかったものもあった」というのが正直なところです。
✅ 試す前に意識したいポイント:
- 「何を改善したいか」を明確にする(例:イライラ?頭痛?むくみ?)
- 1つずつ取り入れて、効果を比較する
- 数週間は継続してみる(少なくとも2〜3周期)
- 副作用や相互作用に注意する(持病がある方は特に)
また、漢方は“体質”に合わせて処方されるものなので、自己判断で市販薬を選ぶのではなく、一度相談してみるのがおすすめです。
漢方薬局や婦人科で体質チェックをしてもらうと、より納得感を持って使えます。
つまり、サプリや漢方は「とにかく飲めば効く」ものではなく、“自分を知る”きっかけとして活用するのがポイントだと私は感じています。
どれくらいで効果が出る?
「どれくらいで楽になるの?」と焦る気持ち、すごくよくわかります。
でも、PMSのセルフケアはすぐに結果が見えるものではないことが多いです。
実感としては、生活習慣の見直しに関しては、最低でも1〜2ヶ月、体調の波を見ながらの経過観察が必要でした。
サプリや食事改善なども、ホルモンバランスの影響を受けるため、月単位での変化を追うのが現実的です。
私の場合:
- 食事改善は → 2ヶ月後に「前より穏やかかも」と感じた
- 睡眠リズムの調整は → 1週間でも違いを実感
- 記録習慣は → 3ヶ月後に「自分の傾向」がわかってきた
大切なのは、「効果があるか」よりも、「変化に気づける自分でいられるか」。
そう思えるようになると、セルフケアそのものがストレスではなく、自分の味方になってくれる時間に変わっていきます。
他の人はどうしてる?
これも気になりますよね。
「私だけがこんなにつらいのかな?」と感じると、より孤独感が深まってしまうものです。
私のSNSやイベントに寄せられる声では、みなさん本当にさまざまな工夫をして、なんとか日常を整えていることがわかります。
✅ よくあるPMSセルフケアの声(実例)
- 「通勤をやめて在宅ワークに変えてから、だいぶラクになった」
- 「ルーティンで朝に白湯とストレッチを取り入れたら、イライラが減った」
- 「パートナーに“PMSカレンダー”を共有したら、関係が楽になった」
- 「婦人科で低用量ピルを処方されて、毎月が劇的に変わった」
みんな完璧にやっているわけじゃありません。
「今日は無理しない」と決めて休む日もあるし、「やっぱりつらい」と泣く日だってある。
でも、「自分にできる範囲で何かをしている」こと自体が、ものすごく意味のあることだと思うんです。
だからこそ、「他の人と違うからダメ」ではなく、「私には何が合うかな?」という視点で、自分の選択を大切にしてみてくださいね。
まとめ:PMS改善セルフケアの要点と最初の一歩
PMSのつらさに悩んでいた私が、セルフケアを通してようやく感じられるようになったこと。
それは、「私の体は、わたしが守っていい」ということでした。
特別な知識も資格もなくても、自分の体調に目を向けるだけで、確かに何かが変わっていく。
この記事では、そんな日常の中でできるPMSセルフケアの選び方と続け方を、体験ベースでお伝えしてきました。
ここで一度、「私が実感した変化」と「読者の方が今日からできること」を整理しておきましょう。
実感できた3つの変化
私がセルフケアを継続する中で、特に「これは変わった」と感じたのは以下の3点です。
- 感情の波に気づけるようになった
→ アプリでの記録や生活リズムの見直しで、「なんでこんなに不安?」という混乱が減少。 - 生理前に“準備”ができるようになった
→ 食事や睡眠の調整を前もって意識することで、月経前の落ち込みや焦燥感が軽く。 - 人に伝える言葉が持てるようになった
→ 自分のリズムがわかることで、「今はちょっとつらい」と言える安心感が生まれた。
これらは、「治った」というより、「コントロール感が戻ってきた」という感覚です。
PMSのつらさがゼロになったわけではありません。でも、自分の体を他人事にしないことで、心の持ち方が変わった。それが何より大きな一歩でした。
今日からできることチェックリスト
では、読者のあなたがこれから始めるとしたら、どんな一歩からがいいのでしょうか?
無理なく始められることを、セルフチェックリスト形式でご紹介します。
✅ 気になる症状をメモに書き出してみる
✅ 生理周期を把握するアプリをインストールしてみる
✅ コンビニのお菓子を1回分だけナッツに置き換えてみる
✅ 夜スマホを置く時間を30分だけ早めてみる
✅ 「今、ちょっと不安定かも」と自分に声をかけてみる
✅ 「相談してみたい」と思える婦人科の情報を調べてみる
どれも、完璧じゃなくていいし、毎日じゃなくてもいいんです。
大切なのは、「私は私の体を気にかけている」という意識そのもの。
その気持ちが、フェムケアの原点だと私は思っています。
PMSは、自分をいたわる練習のようなもの。
つらさをひとりで抱えず、「選べるケア」で体と心に余白をつくること。
そのために、これからも生活のなかにフェムケアを取り入れていきませんか?
✅ LINEで最新情報・体験談をチェックしたい方はこちら
フェムケアの部屋 公式LINEに友だち追加する
関連記事:PMSに良い栄養素と悪い食品
参考情報・出典
本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。
- 日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」
https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4 - 厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html - MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms - 日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」
https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/ - 順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html