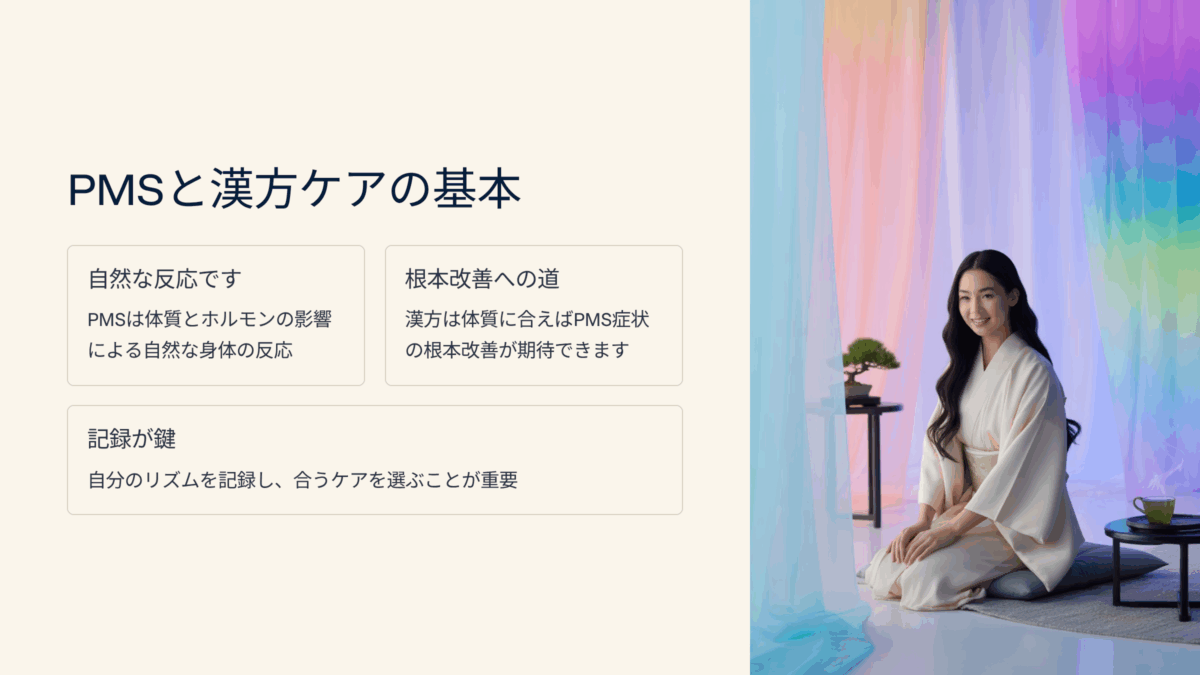毎月のPMS症状に悩みながらも、何を試してもピンとこなかった私が“漢方”に出会って気づいた、本当のセルフケアの意味とは?目次を見て必要なところから読んでみてください。
PMSと漢方の関係とは?(なぜ漢方が注目されるのか)
PMS(月経前症候群)に悩む女性たちの間で、最近「漢方」という選択肢がじわじわ注目を集めています。市販薬やサプリだけでは改善しきれない精神的・身体的な不調に対して、「体質から整える」アプローチが支持されているのです。私自身、数ある対処法の中から“漢方”を選んだ一人として、その背景や理由を生活者目線でお伝えします。
PMSの主な症状と原因
PMSの症状は、実にさまざまです。ある人にとっては「いつものこと」でも、他の人にとっては生活に支障をきたすほどの辛さになることもあります。
代表的な症状を挙げると、以下のようなものがあります。
- イライラ・怒りっぽさ・落ち込みなどの精神的な不安定さ
- 頭痛・腹痛・腰痛などの身体的不快感
- 眠気・集中力の低下・過食傾向などの行動の変化
これらの原因とされているのが、排卵後に変化する女性ホルモン(エストロゲンとプロゲステロン)のバランスです。特に月経の直前になると、急激なホルモンの低下によって、自律神経や脳内の神経伝達物質に影響が出やすくなります。
とはいえ、ホルモンの変動は“誰にでも起こる自然な生理現象”です。では、なぜ人によってこんなに差があるのでしょうか?
そのカギを握るのが、「体質」や「生活習慣」といった個人差です。
漢方がPMSに効果的とされる理由
漢方は、現代医学とは違った角度から私たちの不調にアプローチします。特にPMSのように、複数の症状が重なり合い、原因も一つではない不調に対しては、むしろ漢方の方が得意とする領域なのです。
たとえば、同じ「イライラしやすい」という悩みでも、
- ストレスによって気が滞っているのか
- 血の巡りが悪いことで頭にのぼせているのか
- 冷えや貧血傾向から気持ちが不安定なのか
など、体の状態によって原因の捉え方が変わります。
このように、漢方は「この症状=この薬」とは決めつけず、その人の体質・体力・生活環境に合わせて処方されるのが特徴です。
だからこそ、PMSのように症状が幅広く、かつ毎月のように繰り返す不調に対して、根本的なケアができる方法として注目されているのです。
実際に私も、いくつかの市販薬やハーブサプリを試しましたが、
「一時的には楽になるけど、また次の月には同じことの繰り返し…」
そんな時に、体質改善の視点から提案されたのが漢方でした。
ホルモンバランスと“体質”へのアプローチ
ここで少しだけ、「体質とは何か?」について触れておきたいと思います。
漢方でいう体質とは、以下のような要素を総合的に見たものです。
- 冷えやすいか、ほてりやすいか
- 疲れやすいか、睡眠の質はどうか
- お腹の調子や排便リズム
- 感情の揺れやすさ
つまり、月経だけでなく日常生活すべてのコンディションが関係してくるんですね。
そして、ホルモンバランスの乱れもまた、「冷え」「気の巡りの悪さ」「血の不足」などの体質的な偏りから影響を受けるとされています。
漢方の良いところは、「ホルモン」という目に見えないものに対して、自分の体感からアプローチできるところです。
✅ 生理前になると、なぜか気分が落ち込む
✅ 下腹部がずっと重だるくて、頭もボーっとする
✅ 人との会話すらおっくうになってしまう
そんな「いつものこと」に、名前がついた瞬間、私は少しだけホッとしました。
でも、そこから抜け出すためには、“自分の体を知ること”が最初の一歩だったんです。
だからこそ、「なんとなく調子が悪い」を見過ごさず、自分の体質と向き合う視点を持つこと。
それが、PMSと向き合うための大きなヒントになると、私は感じています。
実際に私が悩んだPMS症状とは(体験ベース)
「PMSって、こんなにしんどいものなんだ…」
そう気づいたのは、会社員として忙しく働いていた20代後半の頃でした。
頭ではわかっていても、心と体がついてこない。そんな日々の中で、「自分のせいじゃない」と思えるようになるまでには、時間がかかりました。
ここでは、私自身がどんな症状に悩み、どんな対処法を試し、なぜ“漢方”にたどり着いたのかを、体験ベースでお話しします。
精神的に不安定になった日々
一番つらかったのは、「自分が自分でなくなる感じ」でした。
普段は冷静で人ともうまくやっていけるタイプなのに、排卵期を過ぎる頃からイライラが止まらなくなって。
何気ない一言に過剰に反応したり、大切な打ち合わせの前に涙が出そうになったり。
そして、生理が始まるとケロッと元に戻る。
✅ なんであんなに怒ったんだろう
✅ あの態度、絶対おかしかったよね…
✅ 迷惑かけてばっかりじゃない?
そんなふうに自分を責める夜が、毎月やってきました。
当時は「PMS」という言葉も知っていたけれど、まさか自分がそうだとは思っていませんでした。
「生理前なんて、みんなちょっとは不安定になるものだよね」って。
でもそれは、“ちょっと”どころじゃなかったんです。
精神的な波が日常に影響を与えはじめたとき、「これはもう我慢して乗り越えるレベルじゃない」と感じました。
市販薬やサプリでは限界を感じた
最初に手に取ったのは、ドラッグストアで見かけたPMS向けの市販薬やハーブサプリでした。
- 「女性ホルモンのバランスを整える」と書かれたサプリメント
- 「気分を落ち着ける」とされるハーブティーやアロマ
- 鎮痛剤や鎮静系の漢方薬(市販)
最初の数日は、「なんとなくいいかも」と思えることもありました。
でも結局は、その月だけ。翌月にはまた振り出しに戻るような感覚。
続けても効いているのか実感できず、飲み忘れや不信感からだんだんフェードアウトしてしまいました。
「PMSって、根本的に治す方法ってないのかな?」
「ずっとこのまま波に飲まれて生きていくのかな?」
そんなふうに感じていたとき、信頼している人に言われた言葉がありました。
「体質ごと整えるなら、漢方のほうが合うかもしれないよ」
正直、それまでの私は「漢方=年配の人が飲むもの」「効果がゆっくりすぎて続かない」と思い込んでいました。
でも、この一言がきっかけで、視野が少しだけ広がったんです。
“漢方”という選択肢に出会うまで
そこからは、半信半疑ながらもいろいろ調べてみました。
“PMS 漢方 効果” “当帰芍薬散 PMS” “加味逍遙散 飲み方”など、検索履歴が漢方だらけになっていた時期も。
決定打になったのは、漢方相談を受けられる薬局に行ってみたことでした。
初めての漢方相談では、自分でも驚くほど話しました。
「いつから、どんな症状が出てるか」
「どんな食事をしているか」
「冷えやすいか、眠れているか」など…
その時すすめられたのが、加味逍遙散(かみしょうようさん)という漢方薬。
イライラ・不安・のぼせにアプローチし、気の巡りを整えるというものでした。
最初は正直、「本当にこんなので変わるの?」という疑いもありました。
でも、3ヶ月くらいかけて少しずつ変化を感じるようになりました。
✅ 気分の波が緩やかになった
✅ 生理前でも大きく落ち込むことが減った
✅ なにより「自分で対策している」実感が持てた
完璧に症状が消えたわけではないですが、“振り回されている感覚”から、“向き合えている感覚”に変わったことが、私にとってはとても大きな変化でした。
PMSは、目に見える病気ではありません。
だからこそ、自分でも気づかないまま「気のせい」にしてしまいがちです。
でも、わたしは声を大にして言いたい。
「気のせい」じゃない。ちゃんと“理由”がある不調です。
そして、それに対する“選択肢”があることを、もっと多くの人に知ってほしい。
次の章では、実際にPMSに用いられる代表的な漢方薬について、それぞれの特徴や向いている症状を具体的に紹介していきます。
「何を選べばいいかわからない」そんな方のヒントになればうれしいです。
PMSに使われる代表的な漢方薬とは?(何があるか)
「漢方っていろいろあるけど、どれがPMSに効くの?」
私自身も最初にぶつかったのがこの疑問でした。
漢方薬は症状に合わせて選ぶだけでなく、“体質”との相性もとても大事。ここでは、PMSのケアに使われることが多い代表的な3種類をご紹介します。それぞれに向いている症状や特徴があるので、自分の状態と照らし合わせながら参考にしてみてください。
加味逍遙散:イライラ・抑うつに
心のバランスが乱れやすい人向けの定番といえば、加味逍遙散(かみしょうようさん)です。
私は、初めて漢方相談を受けたときにこの処方をすすめられました。
特徴は、ストレスによって気が滞る=「気滞(きたい)」状態を整える働きがあること。
こんな人に向いています:
- 生理前にイライラや不安が強くなる
- 気分の浮き沈みが激しい
- 肩こりやのぼせ、ほてりを感じやすい
- 精神的な緊張やプレッシャーに弱い
加味逍遙散は、ホルモンバランスの変化で起こる情緒不安定やメンタルの揺れに対して、緩やかに働きかけてくれる処方です。
実際に私もこの漢方で「怒りっぽさ」や「涙もろさ」が和らぎ、仕事や人間関係での不安が少しずつマイルドになっていきました。
✅ 注意点:即効性はなく、2〜3ヶ月ほど継続して体質にアプローチしていく処方です。
当帰芍薬散:冷え・むくみに
「PMSの時期、なぜか足がパンパンになる」
「生理前はお腹も足も氷のように冷える」
そんな方には当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)が向いているかもしれません。
この処方の特徴は、「血(けつ)」を補って巡らせ、「水(すい)」の代謝を整えること。体の中の“冷え”“湿り”に働きかけてくれます。
こんな人におすすめ:
- 生理前に足がむくんだり、だるくなる
- 貧血傾向がある、立ちくらみしやすい
- 冷え性でお腹や腰が特に冷える
- 疲れやすく、気力が湧かない
当帰芍薬散は、特に体力があまりない“虚証(きょしょう)”タイプの女性に向いています。
私の知人でも、体が細くて血の気が少ないタイプの女性が、これでかなり症状が改善したと言っていました。
✅ むくみ・冷えといった“体の重さ”を感じる方に選ばれやすい漢方です。
桂枝茯苓丸:血行改善・頭痛に
「PMSになると頭がズキズキ…」「生理前になると顔色が悪くなる」
そんな「瘀血(おけつ)」と呼ばれる“血の巡りの悪さ”が原因の症状には、桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)が使われます。
特徴としては、血流を良くして、体にこもった熱や痛みをとる作用があります。
こんな人におすすめ:
- 月経前に頭痛・肩こり・ニキビが悪化する
- 生理前にお腹が張る、塊のような経血が出る
- のぼせやすく、顔が赤くなりやすい
- 手足は冷えるのに上半身が熱い
桂枝茯苓丸は、体の中に“停滞”や“詰まり”を感じるタイプに向いていて、特に「巡らせる」ことを重視した処方です。
✅ 比較的体力がある人や、“実証(じっしょう)”タイプの人向けとされています。
自分に合う漢方の選び方(どう選ぶか)
PMS対策として「漢方を試してみたい」と思ったとき、最初に迷うのが「何をどう選べばいいのか?」という部分。
私自身も、ネットで調べれば調べるほど「選択肢が多すぎてわからない…」と感じた時期がありました。
ここでは、市販漢方と処方漢方の違い、相談するときのポイント、注意すべきリスクまで、失敗しないための基礎知識をまとめます。納得して選びたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
市販と処方の違い
漢方薬は、大きく分けて以下の2種類があります。
| 漢方の種類 | 主な特徴 | 価格帯 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 市販漢方 | ドラッグストアや通販で購入可能。パッケージに「PMSに」と書かれていることも多い。 | 比較的安価 | 自由購入 |
| 処方漢方 | 医療機関で医師が症状に応じて処方。保険適用の場合もあり。 | 保険適用で安くなる場合あり | 婦人科・内科など |
市販の漢方は手軽で始めやすい反面、成分量が少なめだったり、自分の体質に完全には合わない可能性もあります。
一方、処方漢方は医師の判断に基づくため、体質や他の症状を含めて処方内容が決まることが多く、よりパーソナライズされたアプローチができます。
✅ 私の場合は、最初に市販の漢方で効果を実感できず、後から処方に切り替えて症状が改善しました。
漢方薬局・婦人科での相談ポイント
「いきなり病院に行くのはちょっとハードルが高い」
そんな方には、漢方専門薬局での相談という選択肢もあります。
初回はやや長めのカウンセリングが必要になりますが、その分自分の体質や不調の全体像を丁寧に見てくれるのが特徴です。
相談時にチェックされやすい項目:
- PMSの症状の出る時期と内容(いつ・どこに・どんな不調があるか)
- 月経周期の乱れ、経血の量や色、塊の有無
- 睡眠・排便・冷え・食欲などの日常の状態
- 性格傾向(緊張しやすい、疲れやすいなど)
漢方では、「部分」ではなく「全体」を見るのが基本。
婦人科で処方を希望する場合も、こうした情報を整理しておくとスムーズです。
✅ あらかじめ簡単なメモを用意しておくと、相談時に伝えやすくなります。
副作用や体質に合わないリスク
漢方薬=自然=安全、と思われがちですが、体質に合わないと逆に不調が出ることもあるので注意が必要です。
よくある副作用・注意点:
- 胃もたれ、下痢、便秘などの消化器症状
- アレルギー反応(発疹など)
- 体が熱っぽくなる、逆に冷えを感じる
特に、複数の漢方を自己流で併用してしまうと、相性が悪くて逆効果になることもあります。
また、持病がある方・妊娠中や授乳中の方は、自己判断での使用は避け、必ず医師または薬剤師に相談してください。
私も最初は「とにかく試してみよう」という気持ちで市販漢方を購入しましたが、2週間ほどで胃の不快感が出て中止した経験があります。その後、体質に合った処方に切り替えることで症状も安定しました。
漢方でPMSがどう変わったか?(ビフォーアフター)
「漢方って本当に効くの?」
「続ければ変わるの?」
そんなふうに感じている方も多いと思います。私自身、最初は疑い半分でした。だけど、試行錯誤しながら続けていくうちに、確かな変化がありました。
ここでは、漢方を飲み始めてからの変化、うまくいかなかった経験、そして継続して気づいたことを、リアルなビフォーアフターとしてお伝えします。
飲みはじめてからの変化
私が最初に処方されたのは「加味逍遙散」でした。
漢方薬局での丁寧なカウンセリングの末、「イライラや情緒の波が目立つ」「のぼせやすく、肩こりもある」などの特徴から、この処方が選ばれました。
正直、最初の1週間は「何も変わらないな」と思っていました。
でも、3週間ほど経った頃から、気づいたら“揺れ幅”が小さくなっていたんです。
- 前ならキレていた場面で、深呼吸できるようになった
- 生理前の涙もろさが少しマシになった
- 頭が“モヤモヤ”しない日が増えた
もちろん劇的な変化ではありません。
でも、「少しラクになったかも」と思える日が増えたことが、続けるモチベーションになりました。
✅ 自分の状態を記録しておくと、小さな変化にも気づきやすくなります。
合わない漢方でつまずいた経験
すべてが順調だったわけではありません。
実は、最初に試した市販の漢方薬(当帰芍薬散)は、私には合わなかったんです。
「冷えにもむくみにも良い」と聞いて購入したのですが、1週間ほど飲み続けると、逆に体が重だるく感じて…。
便通も乱れてしまい、服用をやめることに。
このとき、「自然なものでも体に合わないことがあるんだ」と痛感しました。
その後、薬局で体質を見直してもらったところ、私のタイプは“気の巡り”の問題が中心で、“血”を補うタイプの漢方では重すぎたと説明されて、すごく納得しました。
✅ 漢方=安心・安全とは限らない。合わないときは早めに見直すことが大切です。
継続する中で気づいたこと
漢方を3ヶ月、半年と継続するなかで、私がいちばん大きく変わったのは、「自分の体と丁寧に向き合う習慣がついたこと」かもしれません。
- 生理前の気分変化を記録するようになった
- 食べもの・睡眠・体調の関係に敏感になった
- 「またPMSか…」とただ落ち込むのではなく、「今この時期だからこう感じてるんだ」と受け止められるようになった
つまり、漢方がただ症状を抑えるだけでなく、「わたし自身を知るツール」になっていったんです。
実際、PMSだけでなく、季節の変わり目の不調や肌荒れまで起こりにくくなってきて、「体ってつながってるんだな」と感じる場面も増えました。
✅ ケアとは、「効いた・効かない」だけで判断しない視点も大事。
「漢方を飲んだらPMSが完全になくなった」
そんな都合のいい話ではないけれど、確実に“付き合い方”は変わったと感じています。
次の章では、漢方を取り入れるうえで気をつけたいこと、知っておきたい“限界”や“注意点”についてお伝えします。
「始めてみたいけど不安」「安全に続けるにはどうすれば?」と感じている方は、ぜひ読んでみてください。
You have not enough Humanizer words left. Upgrade your Surfer plan.
PMS×漢方で気をつけたいこと(注意点と限界)
ここまで、PMSに対する漢方の考え方や、実際に使われる処方についてお話ししてきました。でも、どんなに「体にやさしい」とされる選択肢でも、注意すべきポイントや限界があることを理解しておくことが大切です。
この章では、漢方を取り入れるうえで知っておきたい3つの視点をお伝えします。納得して続けるためにも、ぜひ確認しておいてください。
即効性はないことの理解
まず、最も大事なのが“即効性を期待しすぎないこと”です。
漢方は、症状の「今」を抑えるのではなく、体質の「根っこ」を少しずつ整えていくもの。そのぶん、効果を実感するまでに時間がかかるのが一般的です。
私の場合、加味逍遙散を飲み始めて実感が出るまでに、3週間〜1ヶ月ほどかかりました。もちろん個人差はありますが、「3日飲んでも変わらないからやめよう」と判断してしまうのは早すぎるかもしれません。
✅ 漢方の効果は“じわじわ”が基本。最低でも1〜2ヶ月は様子を見る姿勢が大切です。
また、生活習慣やストレスの状態も影響するため、「飲めば治る」ではなく、“体調を支えるひとつの土台”として捉えることが現実的です。
妊娠中・持病がある人の注意点
「自然なものだから安心」と思われがちな漢方ですが、妊娠中や持病のある方にとっては注意が必要です。
たとえば以下のようなリスクが考えられます:
- 子宮収縮を促す成分が入っている→妊娠中は避けた方がよい漢方も
- 利尿作用や血流促進が強い→心臓・腎臓・肝臓に負担をかける可能性
- 他の薬と成分が重複・干渉する→副作用や過剰摂取のリスク
特に、市販漢方を自己判断で飲む場合は、医師に相談する機会がないまま体調に影響が出るケースも少なくありません。
✅ 妊娠・授乳・持病がある方は、必ず医師・薬剤師・専門の漢方相談員に相談してから使用しましょう。
医師との併用・相談のすすめ
「漢方に頼りたいけど、今すでに婦人科で薬を処方されている」
そんな方にこそ伝えたいのが、漢方と西洋薬は併用できるケースも多いということです。
たとえば、
- ピルなどのホルモン治療と並行して漢方を取り入れる
- 鎮痛剤を補助するかたちで、体質改善の目的で漢方を服用する
このように、目的や作用の重なりを避けながら使い分けることが可能な場合があります。
ただし、ここでも大切なのは「自己判断をしない」こと。
処方薬がある場合は、必ず主治医に「漢方を併用したい」と伝えてください。必要であれば、漢方に理解のある婦人科や内科を探すことも視野に入れてみてください。
✅ 医師との信頼関係の中でケアを進めることで、安心して継続できる選択肢になります。
漢方は、PMSのつらさにやさしく寄り添ってくれる可能性のあるケアのひとつです。
でもその前提として、「正しく知る」「体と対話する」「必要な時は相談する」という姿勢が欠かせません。
次の章では、これまでの体験と学びをもとに、「わたしにとっての漢方とは何だったのか?」をまとめながら、PMSに悩む方へのメッセージをお届けします。
選択肢に迷っている方が、一歩を踏み出せるきっかけになれば嬉しいです。
なぜ私は毎月PMSに振り回されていたのか(体験の導入)
PMSに初めて本気で悩んだのは、働きはじめて3年目の頃でした。
忙しさもプレッシャーも慣れてきたはずなのに、なぜか月に一度、心も体もガタガタに崩れてしまう。その理由がわからず、毎月“嵐が過ぎるのを待つ”ように過ごす日々でした。
私の中では「生理前のちょっとした不調」のはずが、いつしか自分の性格や能力すら疑ってしまうほどの苦しさになっていたんです。
PMSってこんなに苦しいもの?私の月経前症状
月経前になると、さまざまな症状が現れました。
それはもう、“一言で言えないほどのグラデーション”です。
- 突然、何もかも嫌になる
- 些細なことで涙が止まらなくなる
- 眠れない、あるいは過眠になる
- お腹が張って重い、腰が痛い
- 肌荒れ、むくみ、食欲の暴走…
まるで自分の中に別人格が住んでいるような感覚。
「これ、私なの?」「いつまで続くの?」と、出口のないトンネルをさまよっているようでした。
しかも厄介なのは、生理が始まるとスッと消えること。
だからこそ、「あれは気のせいだったのかも」と思い込もうとしてしまい、本当のケアが後回しになっていったのです。
気分の浮き沈み・体調不良・人間関係への影響
一番つらかったのは、仕事や人間関係にまで影響が出ていたことです。
- 大事な会議の日に感情がコントロールできない
- パートナーに対して、なぜか過剰に攻撃的になる
- 周囲に「不安定な人」と思われている気がして、さらに落ち込む
そんな日々が続くと、だんだん「自分には問題があるんじゃないか」と思い込むようになりました。
本当は、ホルモンの変動と体質のバランスで起きている自然な反応だったのに、当時はそれに気づく余裕すらなかったのです。
そしてある日、「もしかしてPMSなのかもしれない」と自分の症状に名前をつけられたとき、私は初めて、“自分を責めなくていい理由”が見つかったような気がしました。
まとめ:PMSに悩む人に“漢方”という選択肢を
PMSという言葉が少しずつ広まりつつある今、それでもなお、多くの人が「ただの我慢」で乗り切ろうとしている現実があります。
でも、私は声を大にして伝えたい。
PMSは、「わたしのせい」じゃない。
そして、そこから抜け出すための選択肢は、確かに存在します。
私にとって“漢方”は、単なる薬ではなく、自分の体と向き合うきっかけになった存在でした。
効き目が穏やかである分、自分の内側の変化に目を向ける時間も自然と増えていきました。
もちろん、全ての人に漢方が合うとは限りません。
でも、「症状を抑えるだけじゃない、根本から整えるアプローチ」を探しているなら、漢方という選択肢を一度考えてみる価値はあると、私は実感しています。
✅ 「今月もまた同じかも」と感じている方へ
✅ 「自分に合う方法が見つからない」と悩んでいる方へ
✅ 「もうがまんしたくない」と思った方へ
まずは、あなたの不調に“名前”をつけることから始めてみませんか?
そしてそのうえで、無理なく続けられるケアをひとつずつ選んでいきましょう。
参考情報・出典
本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。
日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」
https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4
厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html
MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms
日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」
https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/
順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html
✅ フェムケアの最新情報を受け取りたい方へ
LINEで「フェムケアの部屋」のお友達登録をしていただくと、セルフケアに役立つ情報やコラムをいち早くお届けしています。
関連記事:PMSに良い栄養素と悪い食品
PMSの正体を知った瞬間、私の見方が変わった
「なんで私はこんなに感情が不安定なんだろう」
「周りはちゃんとやれてるのに、自分だけ…?」
そう感じていた私にとって、“PMS”という言葉を自分の症状に結びつけられた瞬間は、自分を責める日々から抜け出す第一歩でした。
症状の背景に「理由」があるとわかっただけで、ほんの少し心が軽くなったんです。
ここでは、PMSの仕組みと、より重度なPMDDとの違いについて触れながら、自分の状態を“感情”ではなく“知識”で見つめ直す視点をお伝えします。
PMSとホルモンの関係:なぜ心と体が乱れるのか
PMS(月経前症候群)は、排卵後から月経開始までのあいだに起こる、ホルモンバランスの急激な変化によって生じる症状です。
この時期、女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンが大きく上下し、それに伴って、
- セロトニン(幸福ホルモン)の分泌が減少
- 自律神経が乱れやすくなる
- 血行不良・むくみ・冷えが強くなる
といった変化が起こります。
つまり、PMSとは「心の問題」ではなく「ホルモンの波に伴う生理的な反応」。
ここを理解するだけでも、「わたしが弱いからじゃない」と気づける方がきっといると思います。
実際、私も知識を得る前は「感情の起伏が激しいのは性格のせい」と思っていたし、他人に言うのが恥ずかしくて隠してばかりでした。
でも、「脳内の神経伝達物質まで影響を受けてるんだ」と知ってからは、“気合い”や“根性”で乗り切るものじゃないんだと納得できるようになりました。
✅ PMSはホルモンの波によって引き起こされる、“見えにくい身体反応”です。
PMDDとの違いを知って、自分の状態を客観視
もうひとつ、私がPMSを正しく理解するうえで大きなヒントになったのが、PMDD(月経前不快気分障害)との違いです。
| PMS | PMDD | |
|---|---|---|
| 主な症状 | 情緒不安定、頭痛、むくみ、眠気など幅広い | 強い抑うつ・怒り・絶望感・対人関係の困難など精神症状が中心 |
| 発症頻度 | 女性の約70〜80%が何らかのPMS症状を経験 | 約3〜8%とされる |
| 社会生活への影響 | 日常生活に支障は出るが一時的 | 社会生活が困難になるほど深刻なケースも |
| 医療的対応 | 漢方・生活改善・低用量ピルなど | 精神科的アプローチ・抗うつ薬などの治療も含まれることがある |
私がPMSについて調べていく中で、「これはPMSを超えてるかも?」と感じる瞬間もありました。
たとえば、生理前になると何もかもが絶望的に感じて、誰とも話したくない、外にも出たくない。そんな日が何日も続いたこともあります。
でもPMDDとの違いを知ることで、「あ、これは重いPMSなんだ」と自分の状態を客観視できるようになったんです。
その結果、「病院に相談してもいいかも」「今の対処法は合ってる?」と、自分にとって最適なケアを選び取る視点が持てるようになりました。
✅ PMSとPMDDを線引きすることで、自分に合う対策が見えてきます。
試行錯誤のセルフケア、その失敗と気づき
PMSに悩みはじめた頃、私はとにかく“なんでもいいから効果がありそうなもの”を探し続けていました。
インスタ、note、YouTube…SNSで紹介されているセルフケア法は、ほとんど試したかもしれません。
でも今振り返ると、その時の私は「他人の方法」を借りているだけで、自分の体とちゃんと向き合えていなかったように思います。
ここでは、私が実際に経験した「効果が出なかったセルフケア」と、そこから得た“自分のリズム”への気づきをお話しします。
SNSで見た対処法を試すも…効果なし
PMSに効くと言われるセルフケアは、ネット上にたくさんあります。
- ヨガやストレッチで自律神経を整える
- ハーブティーやアロマでリラックス
- サプリメントでホルモンバランスを補う
- グルテン・カフェイン断ちで症状改善
これらを見かけるたびに、「これならできそう」「今度こそ効くかも」と期待して試してみました。
でも結局、どれも長くは続かず、目に見える効果も実感できないまま。
その理由は今ならわかります。
どれも“一時的な対処”であって、“自分の状態を知る”ことが置き去りになっていたから。
「〇〇がPMSに効くらしい」という情報は、あくまで一般論。
私自身のリズムや体質に合っているのかまでは、誰にもわかりません。
例えば、よくPMSに良いとされるカモミールティーも、私にはあまり合いませんでした。飲むと逆にお腹が張ることが多く、リラックスどころではなかったんです。
✅ 情報の“正しさ”よりも、“自分に合うかどうか”が一番大事。
自分のリズムを知ることの大切さに気づいた瞬間
そんな試行錯誤のなかで、転機になったのが「月経日記」をつけ始めたことでした。
アプリやノートに、毎日の体調や気分、食事、睡眠などを簡単に記録するだけ。
最初は「面倒かも」と思っていましたが、2〜3ヶ月続けてみて気づいたんです。
- この時期は毎月、肌荒れ+イライラがセットで出る
- 排卵期あたりに不安感が強くなる
- 生理前のむくみは食事内容と連動してるかも?
つまり、PMSは「毎月ランダムにやってくるもの」じゃなくて、自分の体内にある“リズム”に沿って起こっている現象だったんです。
この気づきがあってからは、「何が悪いの?どうすれば治るの?」というモヤモヤが、「今はこういう時期なんだ」と受け止める安心感に変わっていきました。
そのうえで、漢方のように体質にアプローチする選択肢を取り入れたことで、少しずつPMSとの“距離のとり方”がうまくなっていった気がします。
私に合ったPMSセルフケアとの出会い
「これをやれば必ずよくなる」という決定打がないからこそ、PMSのセルフケアは迷子になりやすい。
私もそうでした。でも、いろんな方法を試し、挫折しながら、ようやく「これなら続けられるかも」と思えるケアに出会えたんです。
ここでは、そんな私が見つけた「自分に合ったセルフケア」をご紹介します。
ポイントは、“特別なこと”よりも、“毎日の中にある選択”を少しずつ変えていくことでした。
生活改善で効果を感じた3つの習慣
まず、生活の中で取り入れてPMSが軽くなったと感じた習慣を3つ挙げます。
- 就寝時間を毎日30分早めた
→生理前は特に眠りが浅くなりやすい私にとって、「夜更かししない」はかなり効果的でした。 - カフェインを“完全に断たない”代わりに、午後以降は控える
→朝のコーヒーを楽しみながらも、午後はハーブティーなどに切り替え。イライラや動悸が軽減されました。 - タンパク質+鉄を意識した食事を意識
→貧血傾向があるため、PMS期にふらつきがあったのですが、朝にたんぱく質を摂るようにしてから明らかに改善。
どれも「簡単そうだけど意外と続かない」ことばかり。でも、“ちゃんとできた日”を意識するだけでも、体の反応が変わってくると感じました。
✅ コツは、“完璧”を目指さないこと。7割できれば上出来。
記録をつけて初めて分かった「私のパターン」
PMSとの向き合い方が変わった最大の理由は、毎月の記録をつけるようになったことでした。
といっても、難しいことではありません。
私がしていたのは、以下のようなシンプルなメモです:
- 今日の気分(例:落ち込み気味/元気/やる気なし)
- 体の状態(例:むくみ/頭痛/冷え/便通)
- 食事や睡眠(例:カフェイン摂取/就寝時間)
- 生理日と排卵予測日
これを1〜2ヶ月続けるだけで、自分の中に明確な「パターン」が見えてきました。
- 排卵後から気分が下がる
- 生理2日前がピークで、そこから回復
- 睡眠不足とカフェイン摂取でイライラが悪化
この“傾向”を知ることが、対策を立てるヒントになったんです。
「今こう感じてるのは、生理前だからか」
「今日は無理せずに、タスクを1つ減らそう」
そんなふうに、“自分をコントロールする”のではなく、“自分のリズムに合わせて調整する”というスタンスに変わっていきました。
やめてよかった習慣・取り入れてよかった工夫
いろんな情報に振り回された末に、「これは手放してよかった」と思ったこともいくつかあります。
やめてよかった習慣:
- 朝イチのスマホチェック(気分が乱される)
- 寝る前のダラダラSNS(睡眠の質が悪化)
- 「毎日続けなきゃ」という完璧主義な考え方
一方で、取り入れてよかった工夫はこちら:
- PMS期に「やることを減らす日」をあらかじめ決める
- パートナーにPMSの時期と症状を共有しておく
- 不調を「記録に残す」ことで、自分を責めない仕組みを作る
特に、「やることを減らす」という選択は、ケアの中でも一番効果的だったと思います。
無理をしないこと。自分を甘やかすのではなく、「必要な手加減」を知ること。
これも立派なセルフケアなんですよね。
PMS対策に“万能薬”はありません。
でも、自分に合った方法は、ちゃんと見つけられる。
そのためには、焦らず、比べず、少しずつ“わたしのリズム”に目を向けていくことが大切です。
✅ 自分の体と心に「何が起きているのか?」を知ること
✅ 小さな変化を記録して、「合う・合わない」を判断すること
✅ 「また不調になった」と責めるより、「どう対応しようか」と選ぶこと
これが、私が見つけた“自分に合ったPMSケア”の本質でした。
あなたにも、あなたのリズムに合ったケアが、きっとあります。