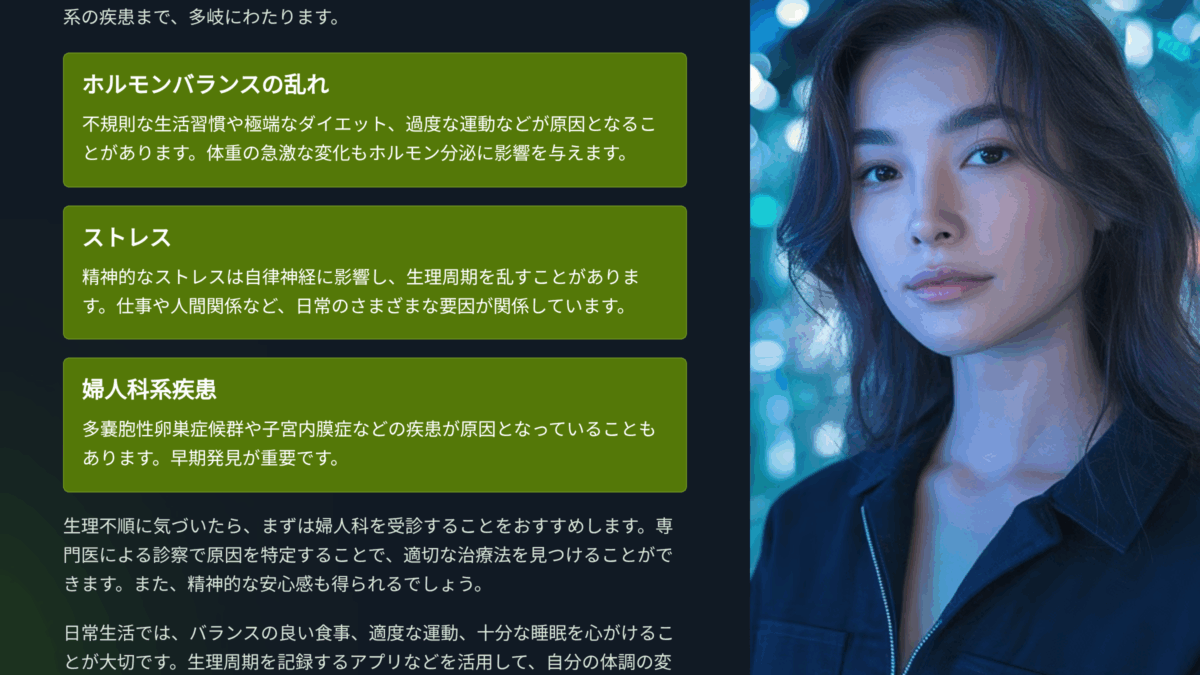突然生理が来なくなったら、不安と戸惑いでいっぱいになります。私の実体験をもとに、原因や受診の流れ、セルフケアまで詳しくまとめました。目次を見て必要なところから読んでみてください。
28歳、突然生理が来なくなった日【私の体験談】
「生理が来ない」という変化は、体からの大事なサインです。でも、頭では分かっていても、忙しさや不安で動けないこともあります。ここでは、私が28歳で突然生理が来なくなったときの気づきと、その時感じた迷いや葛藤を、等身大でお話しします。
気づきは「今月まだ来てない」から始まった
あれ、カレンダーがスカスカだな。ふとアプリを開いて、生理予定日を確認した瞬間、「え、もう2週間も過ぎてる?」と血の気が引きました。今までは数日のズレはあっても、こんなに遅れるのは初めて。体は確かに何かを訴えているのに、すぐには動けませんでした。
仕事とストレスで後回しにしてしまった理由
当時は、納期や会議に追われる毎日。夜は遅く、朝はコーヒーだけで出社。休みの日もPCを開くのが当たり前になっていました。「疲れてるだけだろう」と、自分に言い聞かせて異変を“なかったこと”にしようとしていたんです。心の奥底では、婦人科に行くのが怖かったのも本音でした。
誰にも相談できず、モヤモヤを抱えたまま過ごす日々
友達にも、同僚にも、家族にも言えず、ただスマホで「生理遅れ」「妊娠じゃない場合」などと検索する日々。夜ベッドに入ると、不安が頭をぐるぐる回って眠れなくなる。「こんなことで病院なんて…」という自己否定と、「いや、このままじゃだめ」という焦りが交互に押し寄せていました。
婦人科受診までの2週間に感じた体と心の変化
生理が来ない日が続くと、体も心も小さな変化を積み重ねていきます。放っておけば自然に戻るかもしれない。でも、もしかしたら何かのサインかもしれない。その間に起こった私の体調と感情の揺れを、リアルにお伝えします。
体のサイン:軽い下腹部痛と微妙な体調の変化
最初は鈍い下腹部の重さだけでした。生理前のような感覚なのに、出血はなし。数日経つと、肌が荒れやすくなったり、いつもより冷えを感じたり。小さな違和感が積み重なるほど、「あれ、やっぱりおかしいかも」と思う瞬間が増えていきました。
✅ 眠りが浅くなる
✅ お腹が張りやすい
✅ 体温の変動が大きい
メンタルの揺れ:不安と自己否定のループ
「病気だったらどうしよう」という不安と、「きっと私の生活がだらしないせい」という自己否定が、交互にやってきました。仕事中も、ふと頭の片隅でそのことが気になって集中できない。本当は早く解決したいのに、動き出せない自分にモヤモヤしていました。
「このままでいいの?」と思い始めた瞬間
ある夜、お風呂上がりに鏡を見て、肌のくすみや顔の疲れ具合にハッとしました。「このまま放っておいたら、もっと悪くなるんじゃない?」。そこで初めて、自分の体を“後回しにしてきたツケ”を払う時期かもしれないと感じたんです。この瞬間が、婦人科に行く決意の小さな種になりました。
生理が来ない原因は何?婦人科で聞いた主な可能性
婦人科に行くと、まず医師から「生理が来ない背景には複数の可能性がある」と説明を受けました。ここでは、実際に私が聞いた代表的な原因と、その背後にある仕組みをまとめます。自己判断で放置せず、早めに原因を知ることが大切だと痛感した瞬間でもあります。
ホルモンバランスの乱れとその背景
生理周期は、脳(視床下部・下垂体)と卵巣の連携で成り立っています。このどこかがうまく働かなくなると、排卵が止まったり、生理が遅れたりします。
背景としては、急な体重変化・過度なダイエット・夜型生活などが多いとのこと。医師からは「体は無理をしていると、まず“生殖機能”を休ませようとする」という話があり、妙に納得しました。
ストレスや生活習慣の影響
仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、睡眠不足…これらはすべてホルモンの分泌に影響します。特にストレスは、脳が危機状態と判断して排卵をストップさせることも。
✅ 睡眠時間が6時間未満
✅ 食事の時間がバラバラ
✅ 運動不足または過度な運動
こうした生活リズムの乱れは、生理不順の温床になりやすいと教わりました。
妊娠や婦人科系疾患の可能性
当然ですが、まず確認されるのは妊娠の有無。そのほか、子宮や卵巣に関わる疾患(子宮内膜症、卵巣嚢腫、多嚢胞性卵巣症候群など)も、生理が来ない原因になることがあります。医師は「症状が軽くても、検査で初めて見つかるケースが多い」と強調していました。
「大丈夫だろう」と思い込むのが一番危険—この言葉が今も心に残っています。
婦人科での診察と検査の流れ
「婦人科って何をされるんだろう…」という不安で、受診前はずっと落ち着きませんでした。でも実際には、自分の体を知るための情報を丁寧に集めるプロセスでした。ここでは、私が受けた初診から検査までの流れをまとめます。
初診時のヒアリング内容
診察室に入ると、まずは医師や看護師が時間をかけて質問してくれました。主に聞かれたのは以下のような内容です。
✅ 最終月経の時期と周期の変化
✅ 普段の生理の量や期間
✅ 体重変化や生活リズム
✅ 妊娠の可能性や避妊状況
「細かく聞かれるのは不安を減らすため」と後から気づきました。生活背景まで把握してくれるのは、症状の原因を見極める大事な手がかりになるからです。
行われた主な検査(血液検査・エコーなど)
ヒアリングの後は、必要に応じて検査が行われます。私の場合は、
- 血液検査(ホルモン値や貧血の有無をチェック)
- 経膣エコー(子宮や卵巣の状態を確認)
- 必要に応じて妊娠反応検査
エコーは緊張しましたが、痛みはほとんどなく、モニターで自分の子宮を初めて見たときの感覚は不思議でした。
検査を受けて感じた安心感と戸惑い
結果がすぐに分かるものもあれば、数日かかるものもあります。検査を受けた直後は、「ちゃんと調べてもらえた」という安心感と、「もし悪い結果が出たら…」という戸惑いが入り混じっていました。
でも、自分の体を“知る”ことが一歩目。これは受診して初めて実感できたことです。
婦人科受診後に変わった私のセルフケア習慣
診察を受けたことで、原因や体の状態が分かり、ようやく「じゃあこれからどうするか」に意識が向きました。そこで始めたのが、日常生活の小さな改善です。無理なく続けられるセルフケアこそ、長い目で見て体を守ってくれると感じています。
睡眠・食事・運動の見直し
受診をきっかけに、まずは睡眠を優先しました。
✅ 夜はスマホを早めに手放し、23時までに就寝
✅ 朝はたんぱく質を含む朝食を摂る
✅ 軽いストレッチや散歩で血流促進
医師から「生活リズムがホルモン分泌を整える土台になる」と言われ、生活習慣を整えることが“治療の一部”になると理解しました。
生理周期を記録する習慣のスタート
アプリで生理の開始日や体調、気分の変化を記録するようになりました。これにより、微妙なズレや傾向が見えるようになり、受診時にも役立ちます。「記録は未来の自分へのプレゼント」だと、今は思えます。
相談できる場所・人を持つことの大切さ
以前は、月経や体調のことを話すのが恥ずかしいと感じていました。でも、婦人科の先生や同じ経験を持つ友人に話すことで、心が軽くなる瞬間が何度もありました。
体の悩みはひとりで抱え込むほど重くなる。だからこそ、安心して話せる人や場所を持つことは、セルフケアの一部だと実感しています。
生理が来ないときに押さえておきたいポイント
「あと少し様子を見よう」が続いてしまうのが、生理が来ないときの怖いところです。ここでは、迷っているときに行動の判断材料になるポイントをまとめます。受診するかどうか迷ったときの参考にしてください。
受診の目安とタイミング
一般的には、生理が予定日から2週間以上遅れている場合は受診を検討すべきと言われます。さらに、次のような症状がある場合も早めの受診が安心です。
✅ 強い腹痛や出血が続く
✅ 発熱や体重の急な変化
✅ 過去にも同じ遅れが何度もある
自宅でできるセルフチェック項目
受診前に自分の状態を整理しておくと、診察がスムーズになります。
- 最終月経の開始日と終了日
- 最近の睡眠時間と食事の傾向
- 妊娠の可能性(避妊の有無)
- ストレスの有無や大きな生活変化
紙やスマホにメモしておくだけでも、診察時の不安が軽くなります。
受診前に準備しておくと良いことリスト
- 健康保険証
- 生理周期の記録(アプリや手帳)
- 飲んでいる薬やサプリの情報
- 過去の病歴やアレルギー情報
これらを揃えておくことで、医師がより正確に判断できますし、自分の体の情報を“見える化”するきっかけにもなります。
関係悪化を防ぐためのルール作り
PMSの影響で感情が揺れる時期は、どうしてもパートナーとの距離感が難しくなります。ここで大事なのは「ケンカを避ける」ことよりも、お互いが安心できる関係を保つためのルールを決めておくことです。小さな工夫で、衝突の芽をぐっと減らせます。
イライラ期の距離感と安心のサイン
感情が爆発しやすい時期は、距離をとることも愛情の一つです。私は、生理前の数日は「一人時間を増やす」ことをルールにしました。
ただ、完全にシャットアウトするのではなく、✅ 「今日は一人で過ごすけど、あなたのことが嫌いなわけじゃない」と事前に伝えます。
こうすると相手は不安にならず、お互いの時間を大事にできます。
事前に合図を決めておくメリット
「今、生理前だから少し敏感になってる」と毎回口で言うのは、正直面倒なときもあります。そんな時のために、合図を決めておくと便利です。
例えば、LINEのスタンプ、特定の絵文字、短いメッセージ(例:「低気圧きた」)など。これなら長い説明なしで、相手が状況を察して行動を調整できます。
私の場合は、🌙マーク(※ここでは文章説明)を送ると「今は静かにしておこう」というサインになっています。
お互いが安心できる会話フレーズ集
会話の中で、相手を安心させる一言を加えるだけで、関係はずっと穏やかになります。私が実際に使っている例はこんな感じです。
- 「今ちょっとしんどいけど、あなたが嫌なわけじゃない」
- 「少し距離を置きたいけど、終わったらまた話そう」
- 「手伝ってくれると助かる」
✅ これらは感情的にならず、自分の状態をシンプルに伝える言葉です。相手もどう行動すればいいか分かるので、余計な誤解や不安を減らせます。
このルール作りをしてから、私とパートナーのケンカは目に見えて減りました。次は「パートナーとの関係が変わった瞬間」で、その実感をお話しします。