
在庫が売れずに眠っている…。そんな悩みは多くのサプライヤーさんが抱えています。実はその在庫、ムダにせず“価値”として活かす方法があるんです。
目次を見て必要なところから読んでみてください。
なぜ滞留在庫がキャッシュフローを圧迫するのか?
「在庫が増えると、なんだか安心する」——そんな風に感じたことはありませんか?
売れそうな商品がたくさんあると、未来の売上が約束されているようで、気持ちが少しラクになる。
でも実は、その在庫たちが、あなたのお金の流れ=キャッシュフローを静かに止めてしまっているかもしれません。
「滞留在庫(たいりゅうざいこ)」という言葉は、少し耳慣れないかもしれません。
でもこれは、長期間売れ残ってしまっている在庫のことを指します。
在庫は商品であり、資産ではありますが、現金ではありません。つまり、「持っていても使えないお金」なんです。
ここでは、そんな滞留在庫が、どうしてキャッシュフローを圧迫してしまうのか。
そして、なぜ早めの対策が必要なのか、一緒に考えていきたいと思います。
在庫が「お金のブロック」になる仕組み
在庫というのは、そもそも仕入れや製造の段階で「お金に変わるはず」と期待して投資したものです。
ところが、思ったよりも売れなかったり、季節を外してしまったりすると、商品は倉庫の中に残り続けます。
ここで大事なポイントは、
✅ 在庫になった時点で、あなたのお金は「動かせなくなる」こと
✅ 売れるまでの間は、利益どころか「経費」を生み出し続けてしまうこと
です。
例えば、10万円分の商品を仕入れたとします。
もしその商品がすぐに売れれば、売上になってお金が戻ってきますよね。
でも半年以上売れなければ、その10万円は「使えないお金」のまま、あなたの中に滞留し続けるのです。
お金のブロックが1つ、2つと増えるほど、経営はじわじわと重たくなる——それが、滞留在庫の怖いところです。
倉庫費用・劣化リスク・保管コストの増大
そして、在庫が「動かない」ことの副作用は、それだけにとどまりません。
売れない在庫を持ち続けることで、実際にお金が出ていくリスクが増えていくんです。
たとえば……
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 倉庫費用 | 保管スペースを借りるコストがかさむ |
| 劣化・品質低下 | 賞味期限やトレンドの変化で価値が下がる |
| 管理コスト | 棚卸しや在庫確認の手間が増える |
| 廃棄コスト | 最終的に売れずに処分する際の負担 |
こうして見ると、「持っているだけでお金が出ていく」という現実が見えてきます。
特に食品や化粧品のように“時間とともに価値が下がるもの”は、スピードが命です。
「そのうち売れるかも」と考えるのは自然なことですし、私も過去にそう思っていた時期がありました。
でも実際には、在庫は“待てば待つほど損をする”存在でもあるのです。
だからこそ、早めに「新しい売り方」「新しい販路」を見つけることが、キャッシュフローを守る第一歩になります。
次の章では、そんな“出口のない在庫”を、「価値」に変える考え方について、お話ししていきますね。
キャッシュフローが悪化すると企業に何が起きる?
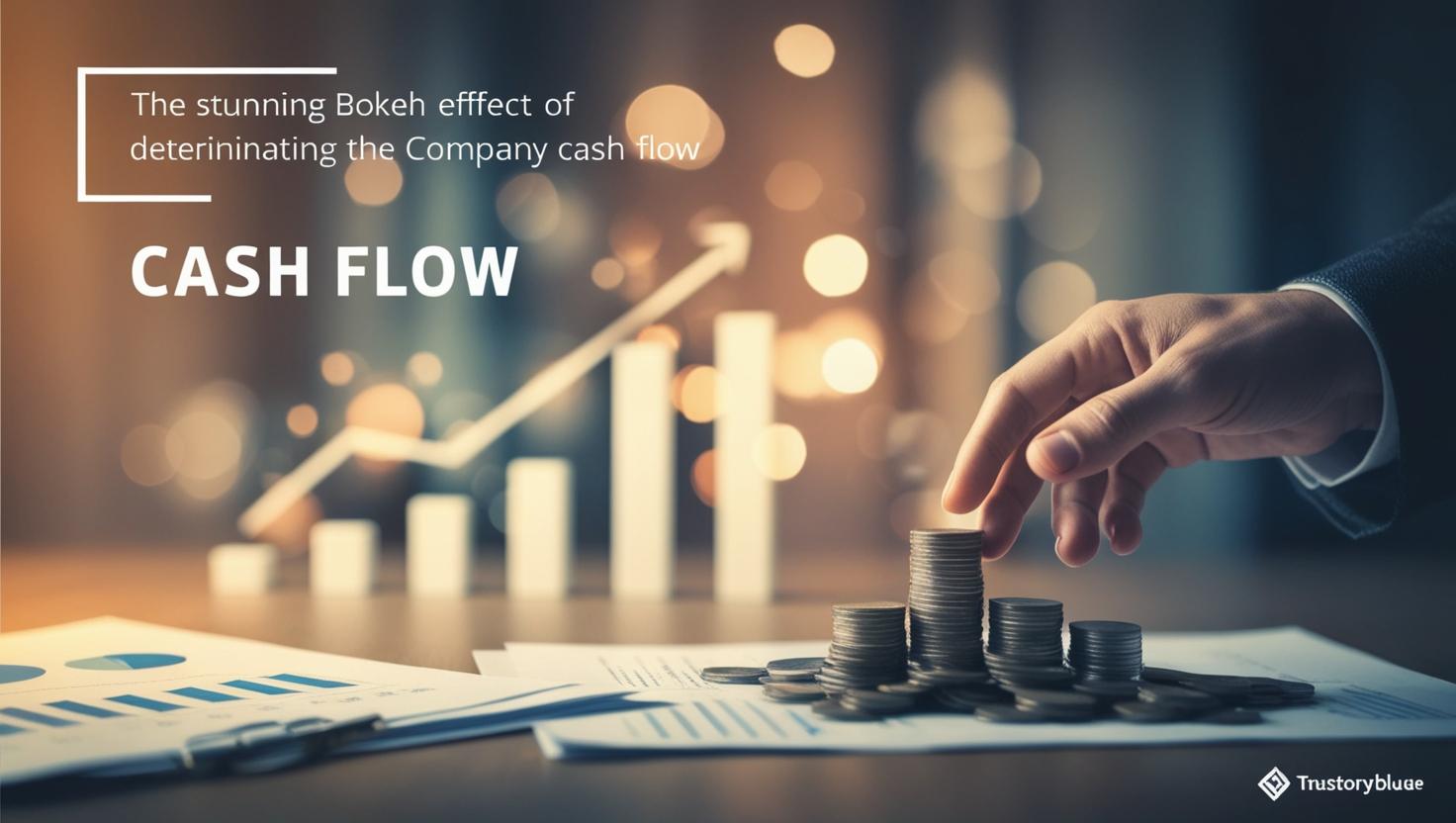
売上は出ているのに、なぜか会社のお金が足りない。
そんな状況に直面したことはありませんか?
これ、実はキャッシュフローの悪化が原因かもしれません。
会社にとって、キャッシュ(現金)は血液のようなものです。売上や利益といった「帳簿上の数字」だけでは、日々の仕入れや支払いはできません。
お金が回らなくなると、健全な経営はあっという間に傾いてしまうのです。
特に、「売れるはずだった在庫」が滞留し続けてしまうと、そのダメージは想像以上に大きくなります。
ここでは、キャッシュフローが悪化することで、どんな悪循環が生まれるのか、一緒に見ていきましょう。
仕入れ・販促・新規投資が止まる悪循環
お金が滞ると、まず直撃するのは「次の仕入れ」や「広告費」など、未来に向けた出費です。
たとえば…
✅ 人気の商品を追加発注したくても、資金が足りずチャンスを逃してしまう
✅ SNS広告やキャンペーンに回す予算が確保できず、集客力が落ちてしまう
✅ 設備投資や商品開発ができず、事業の成長が止まってしまう
こんなふうに、お金が足りないことで「売れるチャンス」や「育てる力」まで止まってしまう。
それが、キャッシュフロー悪化の連鎖です。
私のまわりにも、「資金繰りのために安売りを繰り返した結果、ブランドイメージが崩れてしまった…」という声を何度も聞いてきました。
一度お金の流れが止まってしまうと、そこからの立て直しには、思った以上の時間と労力がかかることも忘れてはいけません。
黒字倒産の原因にもなる「在庫過多」
数字上は黒字なのに、会社が潰れてしまう——これは決して珍しい話ではありません。
実際に、「黒字倒産」の大きな要因として挙げられるのが、在庫過多なんです。
これはどういうことかというと…
売れていない在庫がたくさんある=その分、現金が動かせないという状態。
売上に計上されていても、代金が未回収だったり、在庫として滞っていたりすると、実際には使えるお金がほとんど残っていないということが起こり得ます。
例えばこんなケースも。
| 状況 | リスク |
|---|---|
| 売上があるが入金が遅い | 支払いに間に合わず信用が落ちる |
| 商品はあるが売れない | お金が回らず事業が縮小 |
| 資金不足で仕入れができない | 売れる商品がなくなり、さらに売上減 |
表を見てわかる通り、キャッシュがなければ、ビジネスは前に進めないんです。
だからこそ、滞留在庫が増えてきたときには、ただ「安く売って処分する」ではなく、新しい販路や視点で「価値に変える」工夫が必要になってきます。
それが、OEFが提案している「エシカルなレスキュー販売」という選択肢でもあります。
ただモノを減らすのではなく、誰かにとっての“もったいない”を“ありがたい”に変えていく。
そんなサイクルが回る仕組みが、今こそ求められているのかもしれません。
滞留在庫を“価値”に変える3つの視点

売れ残った商品、賞味期限が近づいた食品、ちょっとパッケージにキズがあるだけの化粧品。
どれも本来の品質には問題がないのに、「売りづらい」というだけで眠ってしまっている在庫たち。
でもその在庫、もしかしたら新しい“価値”に生まれ変わるチャンスがあるかもしれません。
OEFでは、そうした滞留在庫を「もったいない」ではなく「ありがとう」に変える取り組みをしています。
今回は、その考え方を支える3つの視点をご紹介します。
「値引きではなく、共感で売る」OEFのエシカル文脈
在庫を売り切るために、ただ「安くする」だけでは、商品やブランドの価値が下がってしまうこともあります。
でも、OEFではちょっと違う方法でお届けしています。
それは、共感を軸にした「エシカル消費の文脈」にのせて売るということ。
✅ 賞味期限が近いけれど、まだおいしく食べられる
✅ B品だけど、使い心地には何の問題もない
✅ 生産者さんの想いがつまっている
こうした背景をしっかりと伝えることで、購入者の方に「安いから買う」ではなく、「この選択が誰かの力になるから買う」という気持ちで選んでもらえるのです。
だから、“お得なのに、あたたかい”買い物体験が生まれる。
それが、OEFが大切にしているスタイルです。
会員限定販売によるブランド毀損の回避策
「安売りするとブランド価値が下がってしまうのでは?」
そんなふうに感じるメーカーさんも多いと思います。とても大切な視点ですよね。
そこでOEFでは、「サブスク会員限定で販売」という仕組みを採用しています。
✅ 商品ページは誰でも見られるけれど、実際に購入できるのは会員だけ
✅ 一般流通価格と混同されないよう、価格を限定空間で運用
✅ 商品情報はオープンでも、取引はクローズド
このようにすることで、広くは見せつつ、深くは限定する。
ブランドを守りながら、新しい販路として活用していただける設計にしています。
「値崩れが心配で…」という方も、安心してチャレンジしていただける工夫です。
B品・賞味期限間近品を“レスキュー商品”として再定義
OEFでは、売れ残りや訳あり品を「ワケアリ在庫」とは呼びません。
私たちはそれを“レスキュー商品”と呼んでいます。
✅ まだ使える、食べられる
✅ けれどこのままだと廃棄されてしまう
✅ だから、必要としている誰かのもとへ届けたい
この考え方は、「フードロス削減」や「環境負荷の軽減」にもつながりますし、サステナブルな社会づくりの一歩でもあります。
さらに、OEFのユーザーさんの中には、「こういう商品をあえて選びたい」「無駄にしたくないから」と積極的にレスキュー商品を選んでくださる方もたくさんいらっしゃいます。
一度は行き場を失いかけた商品たちが、「こんな形でまた喜ばれているなんて」と感動したという声も、出品者さんからよくいただきます。
“もったいない”を“ありがとう”に変える場所——
OEFが目指しているのは、まさにそんなやさしい経済の循環です。

滞留在庫について、定義やリスク、対処法まで全体像を整理したい方はこちらも参考になります。
👉 滞留在庫の定義や経営リスク、具体的な対策までまとめて知りたい方はこちら
滞留在庫に悩むサプライヤーへOEFからの提案

倉庫の片隅で出番を待つ在庫たち——それが、いつのまにか“悩みの種”になっていませんか?
「まだ売れるはずなのに」「捨てるのはもったいない」
そんな商品たちに、もう一度活躍のチャンスをあげたい。それが、OEFの願いです。
ここでは、滞留在庫をムダにせず、無理なく売るためのOEFの仕組みと3つの提案をお伝えします。
「出品手数料無料+販売時だけ手数料」だから始めやすい
まずお伝えしたいのが、OEFは出品するだけなら、コストがかからないという点です。
✅ 初期費用や月額費用の負担が軽く、スタートしやすい
✅ 売れたときにだけ手数料(10%)が発生する、成果報酬型
在庫処分をしようとすると、広告費をかけたり、イベント出店したり、どうしても前払いのコストが発生しがちです。
でもOEFなら、リスクを最小限にしながら「まずは出してみる」という一歩が踏み出せます。
そして、商品の魅力や背景をしっかり伝えるページづくりもお手伝い。
「ただのセール品」ではなく、“ストーリーのある商品”として伝えることができるのも、OEFならではの強みです。
販路を確保しつつキャッシュを回すOEFモデル
「売れない間も、保管コストや資金の不安は続いてしまう」
そんな声もよく聞きます。
OEFのモデルは、サブスク会員限定販売というスタイルを取り入れており、
会員制ならではの「買いたい理由」を持つユーザーが集まっています。
✅ エシカル消費に共感し、「理由がある買い物」をしたい人
✅ フードロスや在庫ロスに関心を持っている人
✅ 限定セールやタイムセールに反応するお得好きな人
このようなユーザーに向けて販売できるから、通常の販路では届かない層にもリーチが可能です。
また、OEFでは売上金は翌月末には指定口座にお振込み。
キャッシュの回転がしっかり設計されているから、在庫→現金化のスピードも確保できます。
「捨てずに売る」ための新しいECとの付き合い方
いま、多くのサプライヤーさんが感じているのは、
「どこに出しても値崩れしそう」「自社サイトじゃ売れない」「もう在庫処分しかない…」という閉塞感かもしれません。
そんなとき、OEFのような“エシカルな目的を持ったEC”との出会いが、新しい選択肢になると考えています。
✅ 「もったいない商品に“新しい価値”をつけて届ける」
✅ 「エシカルな買い物に共感してくれる層と出会える」
✅ 「ブランドを傷つけずに、在庫を減らすことができる」
このように、単なる販売サイトではなく、“想い”でつながる場所としてOEFを活用していただけたら、とても嬉しいです。
捨てるのではなく、届ける。
売れ残りではなく、レスキュー商品。
在庫の中にある“価値”を、いま必要としている誰かに届けるために。
OEFは、あなたと共に、その一歩をつくります。
評価損とは何か?税務上の取り扱いと注意点

「この在庫、もう売れないかもしれない…」そんな時、ふと気になるのが税務上の処理ですよね。とくに期末を控えたタイミングでは、処分や棚卸しに頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、評価損(ひょうかそん)の基本と、処分前に押さえておきたい税務の注意点についてやさしくお伝えします。大切なのは、「なんとなく処分」ではなく、根拠のある判断と記録を残すことです。
小さなことのようでいて、後から大きな安心につながっていきますよ。
評価損を計上できる条件とは?
評価損とは、在庫の価値が下がったときに、帳簿上でその価値を減らすことができる会計処理のことです。たとえば、賞味期限が近づいた食品や、型落ちで市場価値が大きく下がった商品などが該当します。
ただし、「売れそうにないから評価損!」という気持ちだけでは認められません。税務上の評価損には、いくつか明確な条件があります。
✅ 商品の価値が著しく下がっていること
✅ 価格が下がった理由に、客観的な事実やデータがあること
✅ その下がった価値に基づいて、合理的に評価額を見積もっていること
つまり、「なんとなく値下げ」ではなく、ちゃんと説明できる根拠が必要なんですね。評価損は、会計処理だけでなく、税金の計算にも影響する重要な項目です。だからこそ、慎重に、でも丁寧に対応していきたいところです。
処分前に必要な「証拠資料」とは
評価損を認めてもらうためには、処分前の段階で「証拠」を残すことがとても大切です。「あのとき、確かに価値が下がっていた」ということを後から説明できるようにしておきましょう。
代表的な証拠資料には、次のようなものがあります。
| 証拠資料の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 写真記録 | 商品の状態(キズ・パッケージ破損・使用期限など) |
| 相場や価格変動の資料 | 類似商品の価格推移、市場での値崩れデータ |
| 在庫一覧と棚卸し表 | 該当商品の数量、評価減額、理由の記録 |
| 営業レポートや販売履歴 | 長期間売れていない記録、販促活動の結果など |
こうした資料を、定期的に残しておくことがポイントです。税務調査が入ったときも、これがあるだけで説得力がぐっと高まります。「なぜ評価損にしたのか」が明確になっていれば、トラブルも避けられますよ。
評価損と廃棄損の違いを理解する
よく混同されがちなのが、評価損と廃棄損のちがいです。似ているようで、扱いはまったく別物です。
✅ 評価損:商品はまだ手元にある状態で、価値が下がったことを帳簿に反映する
✅ 廃棄損:実際に商品を処分して、廃棄した時点で損失を計上する
つまり、「まだ持っているけど、価値がない」なら評価損、「もう捨てました」は廃棄損。
そして重要なのは、評価損は“事前準備”が必要な損失処理だということです。
廃棄してしまってから「損失として落としたい」と言っても、税務的には手遅れになることも…。だからこそ、処分前に在庫の見直しをしておくことがとても大切です。
売れ残った商品を見ると、少し気持ちが沈んでしまうこともあります。でも、事前に評価損として処理しておけば、税務的にも損を最小限に抑えられるんです。
そしてなにより、「まだ売れる可能性がある」なら、エシカルな販路で価値を活かす選択肢もあります。
税務処理と販路開拓、どちらも視野に入れながら、「もったいない」をなくしていけたら素敵ですね。


