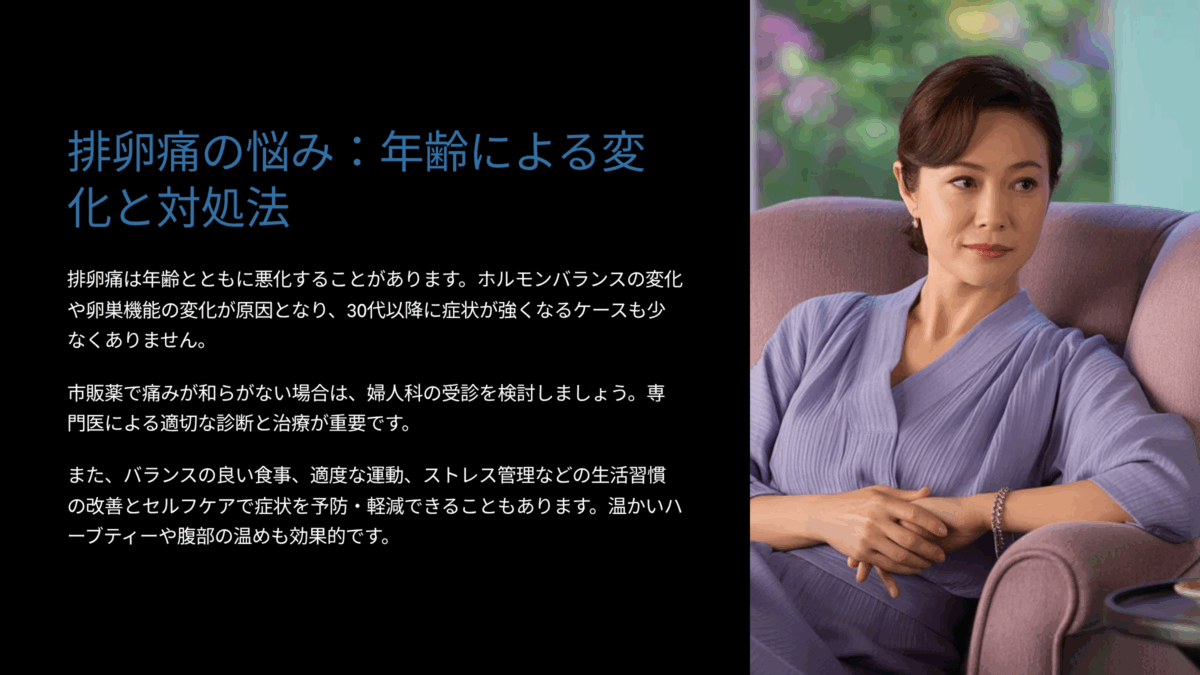市販薬が効かないほどの排卵痛に、35歳を過ぎてから悩まされる人が増えています。
その痛み、本当に「よくあること」で片付けていいのでしょうか?
目次を見て必要なところから読んでみてください。
排卵痛で寝込むほどの痛み、何が起きているのか(原因と仕組み)
「生理じゃないのにお腹が痛い…」そんな違和感、感じたことはありませんか?私もかつて、排卵日前にズキッと響くような下腹部の痛みに動けなくなった経験があります。とくに35歳を過ぎたあたりから、「ただの周期の一部」とは言い切れないつらさに変わってきました。
ここでは、排卵痛が起きるメカニズムと、PMSや月経痛との違いを明らかにしながら、「どうして市販薬が効かないような痛みに変わっていくのか?」という疑問にもつなげていきます。
排卵痛とは何か?PMSや月経痛との違い
まず「排卵痛」とは何か。簡単に言うと、排卵が起こるときの卵巣の動きに伴って感じる痛みのことです。月経のちょうど中間、次の生理の約14日前に起こります。
排卵時には、成熟した卵子が卵巣から排出されるのですが、その際に卵巣の表面が破れ、少量の出血や体液が腹腔内に漏れ出ることがあります。これが周囲の神経を刺激し、痛みとして感じられるのが排卵痛です。
この排卵痛は、
- 周期のど真ん中に突然ズキンとくる
- 片側(左右どちらかの卵巣)だけが痛むことが多い
- だいたい数時間〜数日で落ち着く
といった特徴があります。
ここで混同しやすいのが、月経痛やPMS(月経前症候群)です。
| 症状 | 発生時期 | 主な原因 | 痛みの性質 |
|---|---|---|---|
| 排卵痛 | 月経の約14日前 | 排卵時の卵巣からの出血・刺激 | 片側の下腹部が急に痛む |
| 月経痛 | 月経中 | 子宮収縮による痛み | 下腹部全体がズーンと重い |
| PMS | 月経の1週間前〜直前 | ホルモンバランスの変化 | 腹痛に加え、気分変動やむくみも |
排卵痛が強いと、「これ、生理の始まり?」と混乱することもあるんですが、タイミングと痛みの質で見分けることがポイントです。
35歳以降に強くなる排卵痛の背景とホルモンの関係
私自身もそうだったのですが、「昔はもっと軽かったのに…」と感じる人が増えるのが、30代半ば以降。特に35歳前後から「排卵痛が寝込むレベルに変わった」と話す方が増えてきます。
その背景には、ホルモンバランスの微妙な変化があります。
- 卵巣機能のゆるやかな低下
- 黄体ホルモン(プロゲステロン)の不安定化
- 排卵がスムーズにいかなくなることによる炎症反応の増加
こういった変化が、排卵そのものに“負荷”がかかる状態を生みやすくなります。たとえば、卵子がうまく飛び出せず、卵巣にとどまってしまうこともあり、これが強い痛みの原因になるケースも。
さらに、黄体期のプロゲステロンが不安定になることで、神経の過敏さや体全体のだるさも加わり、排卵痛が「痛み+倦怠感」という形で表れることもあります。
✅排卵痛が重くなる一因として、加齢だけでなくストレスや睡眠不足、冷えなども関与しているとされています。
だからこそ、「昔と違う」「何かおかしい」と感じたら、それを無視しないことが大切なんです。
年齢による変化を自分の体からの“サイン”として受け取れるかどうか。そこが、今後のケアを選ぶうえでの分かれ道になります。
市販薬が効かない排卵痛はなぜ?(対処と限界)
「とりあえず痛み止めを飲んでおけば、そのうち治まると思ってた」──私自身、そうやってやり過ごしてきた時期がありました。でもある日、それではどうにもならないくらい動けなくなって。「いつもの薬、効かない?」と感じたあの瞬間が、私のフェムケアとの向き合い方を変えたきっかけです。
ここでは、市販薬が効くケース・効かないケースの違いと、根本的な見直しが必要になるサインについて、生活者目線で整理していきます。
一般的な市販薬とその効果の限界
市販の鎮痛剤でよく使われているのは、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)と呼ばれる成分です。たとえば、イブプロフェンやロキソプロフェンなどが代表的ですね。これらは、炎症を抑えて痛みの物質(プロスタグランジン)の生成をブロックする働きがあります。
排卵痛にこれらがある程度効く理由は、卵巣の炎症や体液の漏れによって発生する痛みに関与しているためです。初期の頃や、症状が軽いうちは、市販薬で一時的に楽になることもあります。
でも、ここに落とし穴があります。
✅ 市販薬は“痛みのサイン”を一時的にマスクするだけで、原因を取り除くわけではない
✅ 成分量が限られており、体質や痛みの強さによっては十分な効果が得られない
✅ 複数回飲んでも効かないときは、そもそもの原因が複雑化している可能性がある
私のところに届く声の中にも、「毎回飲んでるのに効かなくなった」「2錠飲んでも寝込むくらい痛い」という相談がよくあります。これって、体からの「ちゃんと向き合って」というサインなのかもしれません。
鎮痛剤が効かないときにすべきこと
では、もしも市販薬が効かなかったとき、どうするのがベストなのか。いくつかのステップに分けて、現実的な選択肢を整理してみます。
1. 服用タイミングの見直し
痛みが出てから飲むのではなく、「排卵日が近いな」と感じた時点で先回りして飲む方が効きやすいと言われています。ただし、連用はNG。周期の予測と使い方に注意が必要です。
2. 他のアプローチを取り入れる
- 下腹部を温める(使い捨てカイロや腹巻など)
- ゆるやかなストレッチで血流を促す
- カフェインや冷たい飲み物を控える
- 睡眠をしっかり取る
これらはすぐに痛みを止めるわけではないですが、「痛みが強くなる流れ」を断ち切るうえで重要なセルフケアです。
3. 専門的な相談を検討する
✅ 「市販薬が毎回効かない」状態が続くときは、婦人科での相談が必要です。
婦人科では、市販薬よりも作用が強く持続時間の長い処方薬や、ホルモンバランスを整える薬などを提案してくれる場合があります。また、痛みの正体が本当に排卵痛なのか、それとも他の疾患(子宮内膜症や卵巣のう腫など)なのかを見極めるためにも、受診は大事なステップです。
私自身、婦人科で処方された薬を使ってみたら、「この痛み、やっぱり“普通じゃなかったんだ”」と気づけました。
「こんなことで病院行ってもいいのかな?」と迷う気持ち、すごくよくわかります。でも、市販薬が効かないほどの痛みって、もう“日常の一部”にはしなくていいサインなんです。
がまんではなく、見直す勇気を持つこと。それが、自分を守る一歩目だと思っています。
病院に行くべき排卵痛とは?(受診目安と診療内容)
「排卵痛くらいで病院なんて…」「どうせ検査しても何も出ないんでしょ?」──そうやって、がまんを選び続けてきた方も多いのではないでしょうか。私自身も「市販薬が効かない」ことをきっかけに初めて婦人科を受診したとき、何を聞かれるのか、どんなことをされるのか、不安でいっぱいでした。
ここでは、病院に行くべき排卵痛のサインと、実際に婦人科で受けられる検査や処方の内容を、初診の不安を取り除く目線でお伝えしていきます。
受診を検討すべき症状・頻度の目安
排卵痛があるからといって、すべての場合で受診が必要というわけではありません。とはいえ、「これって普通なのかな…」と迷いながら放置するよりは、一定の基準を知っておくことで、判断がしやすくなります。
✅ 次のような症状や頻度がある場合は、一度婦人科で相談してみましょう。
- 月に一度、寝込むほどの強い痛みが出る
- 市販薬を飲んでも改善しない
- 排卵期のたびに発熱や吐き気を伴う
- 左右どちらか一方の下腹部に鋭い痛みが毎回出る
- 排卵痛が悪化してきていると感じる
- 排卵期以外にも不正出血がある
- 妊娠を希望しているが、なかなか授からない
これらの中で1つでも当てはまるものがあるなら、「原因を調べる」こと自体がケアの一環です。
「こんなことで病院に行っても大丈夫かな?」と思う気持ちはすごくわかります。でも、受診して何もなければ安心ですし、何かあったときも早期に対応できることがたくさんあります。
婦人科で行われる検査と処方内容の例
実際に婦人科を受診すると、どんな流れになるのか。初めての方にもわかりやすいよう、一般的な診療のステップをご紹介します。
1. 問診
- いつから、どんな痛みがあるか
- 痛みの場所や強さ、周期との関係
- 月経の状態(周期・量・痛みの有無)
- 妊娠希望の有無や避妊方法
これらをもとに、症状の傾向を把握します。
2. 超音波(エコー)検査
お腹の上から、または内診を通して子宮や卵巣の状態を確認します。排卵のタイミング、卵巣の腫れ、子宮内膜症やのう腫の有無などがわかります。
3. 必要に応じて行う検査
- ホルモン検査(血液検査)
- 感染症の有無(クラミジアなど)
- 子宮がん検診(年齢やリスクに応じて)
4. 処方されるお薬の例
- 鎮痛剤(処方薬):市販薬よりも効果の高いもの
- 低用量ピル:排卵そのものをコントロールすることで、痛みを根本的に抑える
- 漢方薬:体質や自律神経に合わせた調整
こういった選択肢が出てくるのも、市販薬では限界がある排卵痛に対して「攻めのケア」ができるようになるからなんです。
私が初めて低用量ピルを勧められたとき、「こんなにラクになるの?」と驚いたのを今でも覚えています。もちろんすべての人に合うとは限りませんが、選べるケアがあること自体が安心につながると思うんです。
だからこそ、「体が教えてくれる違和感」に対して、“相談する”という選択を持っておくこと。それが、がまんを“自分で選ばない”フェムケアの第一歩だと思っています。
排卵痛との付き合い方を見直す(セルフケアと再発防止)
「また今月もこの痛みが来るのかな…」そんな不安に、毎月おびえたくないですよね。排卵痛が起きる根本的な原因は、自分の意志ではどうにもできない部分もあります。でも、セルフケア次第で“痛みの重さ”や“頻度”をやわらげることは十分にできると、私は自分の体で実感してきました。
ここでは、「予防できる部分」にフォーカスしながら、排卵痛と上手につき合うための生活習慣と、ホルモンバランスを整える食事・睡眠のコツをお伝えしていきます。
体を冷やさない/生活習慣の改善ポイント
排卵痛が重くなる大きな要因のひとつに、血流の悪さがあります。特に、体の冷えやストレスが続くと、骨盤内の血行が悪くなり、卵巣まわりの炎症や痛みが強まりやすくなります。
まずは「冷やさない」「ためこまない」生活を意識してみてください。
✅ 冷え対策の基本
- 夏でも足首・お腹まわりは冷やさない(レッグウォーマー・腹巻き活用)
- 冷たい飲み物は控えて、常温か温かいものを中心に
- お風呂はシャワーで済まさず、湯船に浸かる
✅ 血流を整える軽い運動
- 朝のストレッチ、足首回し、骨盤まわし
- エレベーターではなく階段を使う習慣
- 骨盤底筋をゆるめるヨガや深呼吸
✅ ストレス・自律神経ケア
- 深呼吸を意識した入浴時間
- 週に1〜2回、スマホを見ない夜を作る
- カフェイン・アルコールの摂りすぎを避ける
生活の中で「ついやってしまう冷え習慣」って、案外たくさんあるんですよね。でも、こうした小さな見直しが“次の排卵痛を少しでも軽くする”下地作りになると思っています。
ホルモンバランスを整える食事と睡眠の工夫
排卵痛の背景にあるホルモンの乱れには、日々の食事と睡眠も深く関わっています。「何を食べるか」「どんなふうに休むか」を少し意識するだけで、ホルモンが穏やかに働く環境づくりができるんです。
✅ おすすめの栄養素と食材
| 栄養素 | 役割 | 含まれる食材の例 |
|---|---|---|
| ビタミンB6 | 女性ホルモンの代謝をサポート | まぐろ、バナナ、さつまいも |
| ビタミンE | 血流を良くして生理機能を整える | アーモンド、かぼちゃ、アボカド |
| マグネシウム | 筋肉の緊張をやわらげる | 豆類、玄米、海藻 |
| 鉄分 | 貧血予防、ホルモン合成の材料 | レバー、ほうれん草、赤身肉 |
食事は「完璧じゃなきゃ意味がない」と思いがちですが、できる日の朝食に卵を足す、夜に味噌汁をつけるだけでも、体はちゃんと反応してくれます。
✅ 睡眠の質を上げるヒント
- 寝る2時間前にはスマホやPCを見ない
- 寝室は少し涼しめ&暗めに(22〜25℃、照明は暖色)
- 寝る直前にお腹を温める(湯たんぽ・カイロ)
とくに排卵期は、自律神経が乱れやすい時期。眠りが浅くなる方も多いのですが、「長く寝る」よりも「深く眠る」ことを意識してあげるだけでも、ホルモンの回復力はぐっと変わります。
よくある質問と迷いへのヒント(Q&A形式)
ここまで読んでくださった方の中には、「それでもやっぱり迷いがある」「もっと具体的に知りたい」という方もいるかもしれません。私もそうでした。誰かに聞きたいけど聞けない…そんなときに寄せられた質問の中から、特に多い3つを取り上げてお答えしていきます。
自分の体を大事にしながらも、無理せず選べる視点をもっていただけたらうれしいです。
「病気じゃないのに病院に行ってもいいの?」
✅ 結論から言うと、「もちろん、行っていい」です。
排卵痛は、病気と診断されることもあれば、そうでないこともあります。
でも、「生活に支障が出ている」時点で、それはもう“受診の理由”として十分なんです。
たとえば頭痛でも、軽いものなら市販薬で済ませるけれど、繰り返すようなら病院で診てもらいますよね。それと同じで、痛みの強さや頻度が日常生活に影響を及ぼしているなら、病名がつくかどうかにかかわらず相談していいんです。
婦人科では「何も異常が見つからなくてもいい」という前提で、話を聞いてくれる医師もいます。
「原因を突き止める」というよりも、今の自分の状態を一緒に把握してもらうこと。それが、医療との上手なつきあい方だと思っています。
「市販薬と処方薬、どう違う?」
これは本当に多い質問です。市販薬と処方薬、見た目は似ていても、中身には大きな違いがあります。
✅ 違いを一言で言えば、「効果の強さと持続時間、そして処方の根拠」です。
| 比較項目 | 市販薬 | 処方薬 |
|---|---|---|
| 成分の濃度 | 低め(安全性重視) | 症状に応じて調整可能 |
| 持続時間 | 短め | 長時間作用するものも多い |
| 医師の判断 | 不要(自己判断) | 医師の診断に基づく処方 |
| 適応症 | 一般的な痛み | 特定の症状に合わせて選ばれる |
処方薬は、あなたの体質や症状に合わせてカスタマイズされたケアのようなもの。
だからこそ、「自分に合った対策を知る」ために一度受診するのは、とても有効です。
ちなみに私は、婦人科で処方された鎮痛剤を使ってみて、「効き方がぜんぜん違う」とびっくりしたタイプです(笑)。
毎月のつらさをがまんするより、一度専門家の手を借りて選ぶ方が、ずっとラクでした。
「仕事を休むほどの痛み、どう説明すれば?」
これも、よく聞かれる悩みのひとつです。「排卵痛」と言っても、まだまだ職場では伝わりにくいし、理解されないことも少なくありません。
✅ 私がおすすめするのは、“状態”で伝えること。
たとえば、
- 「体調不良で横になって休みたい」
- 「下腹部の強い痛みで集中ができない」
- 「婦人科で相談して経過を見ているところです」
など、具体的すぎず、でも真剣さが伝わる言い方を心がけると、角が立たずに伝えられます。
職場に理解のある人がいれば、「排卵痛がひどい日がある」ということ自体を共有しておくのもひとつの選択肢。
私もチームで働いていたとき、「月1だけは自分に優しくする日がある」と話したことが、逆に信頼につながった経験があります。
もちろん、すべての職場でそれが通じるわけではありません。でも、「ちゃんと伝えていいことなんだ」という意識があるだけでも、心の重さは軽くなりますよ。
まとめ:排卵痛を軽く見ないで、自分の体を守る選択を
「ただの排卵痛でしょ」と、誰かに言われた言葉が今でも心に残っています。でも、“ただ”じゃないから、毎月寝込むくらい苦しい。それなのに、自分でも「我慢しなきゃ」と思っていたあの頃の私に、この記事が届いていたら──。そう思いながら、ここまで書いてきました。
今回お伝えしたかったことは、排卵痛を軽視しないということ自体が、立派なセルフケアだということです。
✅ 市販薬が効かないときは、体のサインに耳を傾けること
✅ 婦人科は「病気かどうか」だけを判断する場ではなく、対処法を一緒に探してくれる場所
✅ セルフケアの積み重ねで、“毎月のつらさ”はやわらげることができる
排卵痛に限らず、女性の体って年齢やライフステージとともに本当に変わっていきます。
「前は大丈夫だったから」じゃなく、今の自分に合ったケアを選ぶ視点を持てるかどうか。
それが、自分の体と信頼関係を築く一歩なんだと思います。
そして、あなたがこの痛みを誰にも言えずにいた時間も、がまんしてきた日々も、ぜんぶ無駄じゃない。
その経験が、きっと次の“選べるケア”につながっていきます。
もしこの記事が、誰かの「声にできなかった痛み」に寄り添えていたなら、それが何よりの喜びです。
💬 もっとフェムケアのこと、わかりやすく知りたい方へ
谷澤まさみのLINE公式アカウントでは、排卵痛・PMS・デリケートゾーンケアなど、
“誰にも聞けなかった”フェムケアの話を定期的にお届けしています。
✅ LINEで気軽に受け取れるセルフケアのヒント
✅ イベント情報や限定コンテンツも配信中
✅ 「私だけじゃなかった」と思える場所
よかったら、こちらからお友達になってくださいね。