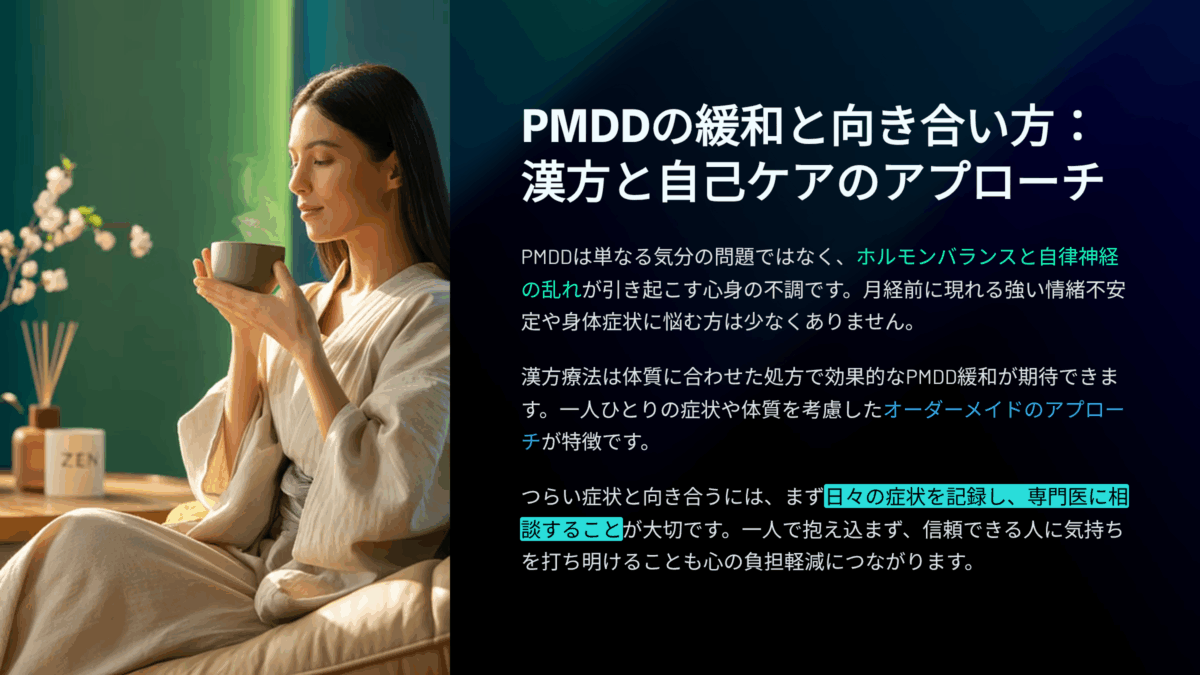PMDD(月経前不快気分障害)の原因がわからず苦しんだ私が、漢方との出会いで体と心のバランスを取り戻した体験を紹介します。症状の特徴や自分に合う漢方の選び方、受診のポイントも解説。PMSとの違いやセルフケアのヒントも満載です。
PMDDとは?つらさの原因をあらためて見つめる
「PMSはよく聞くけど、PMDDって何が違うの?」。そんな疑問を持ちながら、理由のわからないつらさに耐えている人は少なくありません。私自身も、最初は“気の持ちよう”だと思い込んでいた一人。でも、それは自分を見失う一歩手前でした。この章では、PMDDという状態の本質に迫りながら、自分を責めない視点を一緒に探っていきます。
PMSとの違いとは?PMDDの特徴
「生理前になるとイライラするのは当たり前」。そう思っていた頃、私は自分の感情の波を過小評価していました。でも、ある時ふと気づいたんです。「これはただのPMSじゃないかもしれない」と。
PMS(月経前症候群)は、生理の3〜10日前にあらわれる身体的・精神的な不調のことを指します。むくみや乳房の張り、便秘、軽い気分の落ち込みなどが典型的な症状です。
一方でPMDD(月経前不快気分障害)は、PMSの中でも特に精神的な症状が重い状態を指します。主に下記のような特徴があります。
- 怒りやイライラが爆発してしまう
- 自分が自分でなくなるような感覚
- 些細なことで涙が止まらなくなる
- 希死念慮(死にたくなる気持ち)が出てくる
- 社会生活・人間関係に深刻な支障が出る
症状のピークは排卵後から生理直前にかけてで、生理が始まると少しずつ軽くなるのが一般的です。
私自身も、日常の中で突然スイッチが入ったように落ち込み、人に会うのが怖くなったり、過食と絶食を繰り返したりしていました。あとになって、「これがPMDDだったのか」と名前がついた時、ようやく“自分のせいじゃなかった”と思えたのを覚えています。
なぜここまでつらくなる?ホルモンと自律神経の関係
PMDDの症状は「気持ちの問題」ではありません。女性ホルモンの変動と、それに伴う自律神経や脳内物質のバランスの崩れが深く関わっていると言われています。
まず、生理周期の中で排卵後に増加する「プロゲステロン(黄体ホルモン)」は、体を妊娠に備える働きをします。けれども、精神的には不安定になりやすく、脳内のセロトニン(幸せホルモン)の働きを抑える作用があると考えられています。
この時期に、
- 睡眠の質が下がる
- 食欲が乱れる
- ストレスに過敏になる
といった状態が起きやすくなり、結果的にPMDDとして症状が出てくるわけです。
また、自律神経も大きな影響を受けます。体温や血圧、内臓の働きを調整するこの神経が乱れると、倦怠感・動悸・吐き気・頭痛など、さまざまな身体症状も伴います。
私自身も、PMDDの症状がピークだった頃は「こんなに具合が悪いのに、検査では“異常なし”」。その事実が一番つらかったです。
見た目ではわからない不調だからこそ、「気にしすぎ」「甘え」と言われてしまうことも多い。でも、体の中ではちゃんとホルモンや神経がSOSを出しているんですよね。
✅ PMDDは「心の弱さ」ではなく、体の仕組みによるもの。自分を責めないことが、第一歩です。
病院では「異常なし」…原因不明に悩んだ私の体験
「しんどいのに、どこに行っても“異常なし”。じゃあ、私はどうすればいいの?」。病院を転々としても正体がわからない、そんな“行き止まり感”に飲み込まれていたあの頃の私のように、いま迷子になっている人へ。この章では、PMDDに気づくまでの“見えない戦い”をお話しします。
心療内科も婦人科も「様子見」…出口が見えなかった日々
一番最初に異変を感じたのは、30代に入ってからでした。
生理前になると気分が沈むことは昔からあったけれど、いつの間にか「ただのブルー」では済まされないレベルになっていって。
泣いた翌日に笑っていたり、その逆だったり、自分の感情がジェットコースターみたいに制御不能になる日々。
ある朝、布団から起き上がれなくなったんです。頭では「今日は仕事だ」とわかっているのに、体も心も完全にブレーキがかかったようで動けない。
そのとき初めて、「これはもう私ひとりではどうにもできない」と思い、心療内科に足を運びました。
でも、最初の診察で返ってきたのは「様子を見ましょう」「ストレスがたまっているのかもしれませんね」のひと言。
婦人科にも相談しましたが、ホルモン検査でも異常は出ず、「まあ、生理前はそういうこともあるよね」と軽く流されてしまって。
病名がつかない不調って、誰にも説明できないし、自分でも整理できないから、一番つらい。
“じゃあ私はこのままずっと、原因のわからないまま苦しむの?”という思いで、途方に暮れていました。
情緒不安定・過眠・絶望感…日常生活に支障が出た私の症状
正直に言うと、「PMDDです」とはっきり診断されたわけではありません。
ただ、自分で記録をとるようになって、生理の約10日前から毎回決まって心身の調子が崩れることに気づいたんです。
具体的には、
- 夜になると涙が止まらない
- 「なんのために生きてるんだろう」と思う日が続く
- 昼まで寝ても眠くて、起きられない
- 仕事の人間関係に耐えられなくなる
- 食べたくないのに暴食しては自己嫌悪
といった状態が毎月、必ず訪れました。
ある月、生理が始まった途端にふっと霧が晴れるように心が軽くなって、「あ、これがPMDDかもしれない」と思いました。
不調のピークが生理開始とともにパタッと終わるのが、PMDDの典型的な特徴なんですよね。
この頃には、もうメイクをする気力もなく、出かける前に玄関で立ちすくんでしまうような日々が続いていました。
周囲には言えなかった。理解されないのが怖くて。
だからこそ、今この記事を読んでくれているあなたに伝えたいんです。
✅ 「なんとなくつらい」を記録するだけでも、あなたの見えない不調に“輪郭”が生まれます。
診断が出なくても、自分の体を理解することはできます。
そして、その気づきこそが、次の選択肢を広げてくれると、私は実感しています。
きっかけは友人の一言「漢方って試してみた?」
「もう限界かも」と思っていた頃、友人にふと声をかけられた言葉が、私にとっての転機でした。『漢方って、試したことある?』。正直、それまでまったく選択肢に入っていなかった“漢方”という言葉。けれど、あのときの私は何かにすがりたかった。ここでは、私が“漢方”と出会ったきっかけと、その後の変化についてリアルにお話しします。
はじめは半信半疑だった…でも気持ちが軽くなった理由
PMDDのつらさが続く中で、婦人科も心療内科もあまり効果が出なかった私は、ある日、友人との何気ない会話で「漢方、合う人もいるらしいよ」と言われました。
正直、「漢方ってお年寄りが飲むものじゃないの?」くらいのイメージしかなかったんです。
それに、病院でもらえる薬じゃないと効かないと思い込んでいた私は、「気休めじゃないの?」とどこか疑ってもいました。
でも、毎月繰り返す“自分が壊れるような感覚”に、もう手立てがないと感じていた私は、ものは試しだ、と軽い気持ちで相談に行ったんです。
そのとき対応してくれた薬剤師さんが、じっくり時間をかけて私の話を聞いてくれたのが印象的でした。
食生活や睡眠、冷えの感じ方やストレスの感じやすさなど、かなり細かく聞かれました。
「えっ、そこまで聞くの?」と驚いたけれど、それだけ“私の体に合わせて”考えてくれるアプローチが新鮮だったんです。
処方されたのは、ホルモンや自律神経にやさしく働きかけると言われている漢方薬。
数日で劇的な変化があるわけではありません。でも、1〜2か月たつ頃には、
✅ 朝の気分が落ち込まなくなっていた
✅ 生理前でも人に会うのが怖くなくなっていた
✅ 睡眠の質がほんの少しだけ良くなっていた
という、小さな変化が積み重なっているのを感じたんです。
「なんとなく軽い」。この“なんとなく”が、私にとってはとても大きな前進でした。
私が選んだ漢方と、意外な「自分の体質」の発見
相談の中で驚いたのは、「あなたは“気滞(きたい)”タイプかも」と言われたこと。
これは、気の巡りが悪くなって、イライラや不安が強く出やすい体質を意味するそうです。
実際に私が処方されたのは、気の巡りを整える作用のある漢方でした(例:加味逍遙散などがよく使われるようです)。
体の冷えや、肩こり、生理不順にもつながるタイプだそうで、「あ、全部当てはまってる…」と妙に納得したのを覚えています。
ここで私が学んだのは、「自分の不調を“体質”として捉える」という視点。
病名ではなく、“今の体の状態”として理解することで、気持ちが少し楽になったんです。
- 不安になりやすいのも
- 眠れないのも
- イライラしてしまうのも
「私のせい」じゃなくて、「今の体のバランス」のせい。
そう思えるようになっただけで、自分を責める回数が減った気がします。
もちろん、すべての人に漢方が合うわけではないと思います。
でも、“体をまるごと見る”という考え方に触れたこと自体が、私にとっては大きな癒しになりました。
✅ PMDDを「治す」ではなく、「整える」。そんな視点が、私を日常に戻してくれた気がします。
PMDDに効くとされる漢方はどう選ぶ?
「漢方が良いって聞いたけど、何を選べばいいの?」。そう思って調べ始めたものの、名前も難しいし、自分の症状に合っているのか不安になる方も多いと思います。漢方は“今のあなたの体質”に合わせて選ぶのが基本。ここでは、PMDDのケアによく使われる代表的な漢方と、選ぶ際の注意点についてお伝えします。
よく使われる代表的な漢方薬とその特徴
PMDDのケアに用いられる漢方薬には、いくつかの定番処方があります。
ただし大切なのは、「これを飲めば誰でも改善する」という“万能薬”ではないこと。今の体と心の状態、体質、生活環境によって合う処方が異なります。
代表的な処方は以下の通りです。
| 漢方薬名 | 主な働き | 特徴的な体質・状態 |
|---|---|---|
| 加味逍遙散(かみしょうようさん) | 気の巡りを整え、情緒を安定させる | イライラ・不安・肩こり・冷え性 |
| 抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ) | 神経の興奮を鎮め、ストレスを和らげる | 怒りっぽさ・不眠・胃腸の不快感 |
| 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん) | 血の巡りを良くし、冷えやのぼせを改善 | 下腹部の張り・月経不順・冷えのぼせ |
| 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん) | 血を補い、水分代謝を整える | むくみ・貧血傾向・疲れやすさ |
私が処方されたのは加味逍遙散でしたが、「なんとなくイライラするけど、落ち込みもあるし…」というように、症状が複雑な方も多いはず。
そのため、複数の処方を組み合わせたり、調整を重ねながら合うものを見つけていくケースもあります。
✅ 漢方は「合うかどうか」がすべて。人と同じ処方が自分に合うとは限らないという視点がとても大切です。
体質に合わないと逆効果?漢方の注意点と受診のすすめ
「漢方は自然だから安心」と思われがちですが、実は体質に合わないと逆に不調を引き起こすこともあります。
たとえば、胃腸が弱い方に合わない処方を飲み続けると、食欲不振や下痢などの副作用が出る場合もあります。
また、市販薬で自己判断してしまうと、本来の体質とズレた処方を選んでしまうリスクもあります。
実際に私も、自己判断でドラッグストアの漢方を飲んでみたことがありますが、まったく効果を感じられず…最終的に専門家のカウンセリングを受けてようやく合う処方に出会えました。
漢方を安心して取り入れるには、以下のような視点が大切です。
- 専門の漢方薬局や漢方外来で体質を見てもらう
- 1か月単位で体調の変化を記録する
- 気になる症状をメモして相談する
- 副作用や違和感があればすぐに中止・相談する
特にPMDDのように、心と体の両面に関わる症状の場合は、「話をちゃんと聞いてくれる」専門家との出会いが重要だと私は感じました。
✅ 自分の不調に名前をつけることが目的ではなく、「自分の体を取り戻すための選択肢」として漢方がある。
そんな風に考えると、少し心が軽くなるかもしれません。
西洋薬と漢方のちがいとは?併用の可能性も
PMDDと向き合う中で、「西洋薬と漢方、どちらがいいの?」という問いに何度もぶつかりました。答えは人それぞれ。でも、違いをきちんと知ることで、自分に合った選択がしやすくなります。この章では、西洋薬と漢方それぞれの特徴、向いている人・いない人の傾向、併用の可能性について解説します。
向いている人・向いていない人のちがい
私自身、西洋薬(抗不安薬や低用量ピルなど)も、漢方も、どちらも試した経験があります。
そして感じたのは、「どちらが正解」ではなく、「その人の状況と体質で合うものが違う」ということでした。
ここでは、それぞれの特徴と、向いているタイプの例を簡単にまとめます。
| 比較項目 | 西洋薬 | 漢方 |
|---|---|---|
| 作用の速さ | 比較的速い(即効性あり) | 穏やかに効く(体質改善型) |
| アプローチ | 症状そのものを抑える | 体のバランスを整える |
| 副作用 | 出ることもある(例:眠気、だるさ) | 体質に合えば少ないが、合わないと不調の原因に |
| 向いている人 | 今すぐ症状を抑えたい/日常生活に支障がある | 長期的に体を整えたい/複数の不調がある |
たとえば、「仕事を休めない」「感情の波で人間関係に影響が出る」など、即効性を重視するなら西洋薬が選ばれやすいです。
一方で、「何年も続く体の不調がある」「薬に抵抗がある」「冷えや疲労感なども同時に気になる」場合は、漢方のアプローチが合うケースも多いと感じます。
✅ どちらを選ぶかは、“症状の強さ”と“自分が大事にしたい価値観”のバランス次第。
無理にどちらかに絞らなくてもよいのです。
医師に相談すべきポイントと受診時のチェックリスト
「西洋薬と漢方、併用しても大丈夫?」という不安を持つ方も多いと思います。
結論から言うと、医師や薬剤師にきちんと相談すれば、併用は可能なケースもあります。
ただし注意したいのは、「自己判断で飲み合わせを決めないこと」。
特に以下のような場合には、専門家への相談が必須です。
- すでに精神科や婦人科で薬を処方されている
- サプリメントや市販薬も複数飲んでいる
- 持病があり、定期的に薬を服用している
受診の際にスムーズに相談するためには、以下のようなチェックリストを準備しておくのがオススメです。
受診時のチェックリスト:
- 生理周期と気分の変化を記録したメモ(最低2〜3周期分)
- 現在飲んでいる薬・サプリの一覧(商品名も)
- 不調の内容と程度(いつ・どんな時・どれくらい困っているか)
- 日常生活で支障が出ていること(仕事・家事・人間関係など)
- 漢方に興味がある理由や不安な点
こうした情報があれば、医師も「この人にはどの方法が合いそうか」を判断しやすくなります。
私自身も、「気になることを遠慮せず、すべて話すこと」ができた時に、初めて腑に落ちるケアにたどり着きました。
✅ 医療の専門家は、“あなたの話を聞くためにいる”存在。
だからこそ、気になることは全部伝えてみてください。
まとめ:つらさに振り回されない私になるために
「毎月、生理前になると別人みたいになってしまう」。そんな自分に悩んで、責めて、答えが見つからなかった日々。けれど私は、PMDDという存在を知り、自分の体と向き合うことを始めてから、少しずつ世界の見え方が変わりました。ここでは、これまでの話をふり返りながら、“私自身を取り戻すためにできること”を一緒に整理してみましょう。
自分の体に目を向けることが第一歩
PMDDは、「見えない不調」です。検査をしても異常が見つからないことが多く、人に説明するのも難しい。
だからこそ、まずできることはひとつ――「自分の状態を、自分で知る」こと。
最初の一歩は、とてもシンプルでした。
- 気分が沈んだ日をカレンダーに〇をつける
- 「なんとなく調子が悪い」と思ったらメモに書く
- 生理周期と気分の関係を見直してみる
たったそれだけのことでも、「あ、毎月この時期がつらいんだ」と気づけたとき、自分の不調に“理由”があるとわかった安心感がありました。
感情の波に振り回されるのではなく、波の“パターン”をつかむ。それが、PMDDと付き合う上での大事な知恵だと、今では思っています。
✅ 自分を知ることは、自分を守ること。
それが、PMDDのケアの出発点です。
記録・受診・相談…ひとりで抱えないためにできること
PMDDの症状は、時に仕事や家庭、人間関係にも影響を与えるほど深刻です。
でも、“ひとりでがまんする”ことが正解じゃないということを、私は経験を通じて学びました。
今、もしあなたができそうなことを、いくつか挙げてみます。
- ✅ 記録する:感情・体調・睡眠・食欲などをメモに残す
- ✅ 受診する:婦人科、心療内科、漢方外来など、合う場所を探す
- ✅ 相談する:信頼できる友人、パートナー、専門家に話す
- ✅ 比べない:他人の症状と比較せず、自分の感じ方を大切にする
- ✅ ケアを選ぶ:薬・漢方・サプリ・セルフケアなどを主体的に選ぶ
何よりも大切なのは、「私には選ぶ力がある」と思い出すこと。
それだけで、少しだけ視界がひらけるような気がします。
私もまだ、波の中にいます。
でも、その波に“名前”がついたことで、自分を見失わずにすむようになりました。
✅ あなたの中にも、ちゃんと「わかろうとしている自分」がいるはず。
その気持ちを、大切にしてくださいね。
わたしの不快感から始まった、フェムケアの未来。
誰にも言えなかったモヤモヤが、誰かに届く言葉になりますように。
💬もっと自分の体と向き合いたいあなたへ
「フェムケアの部屋」では、月経やPMS・PMDDに関するセルフケア情報をお届けしています。
気軽に話せる相手がほしい時、自分のケアを見直したい時、まずはLINEでつながってみてくださいね。