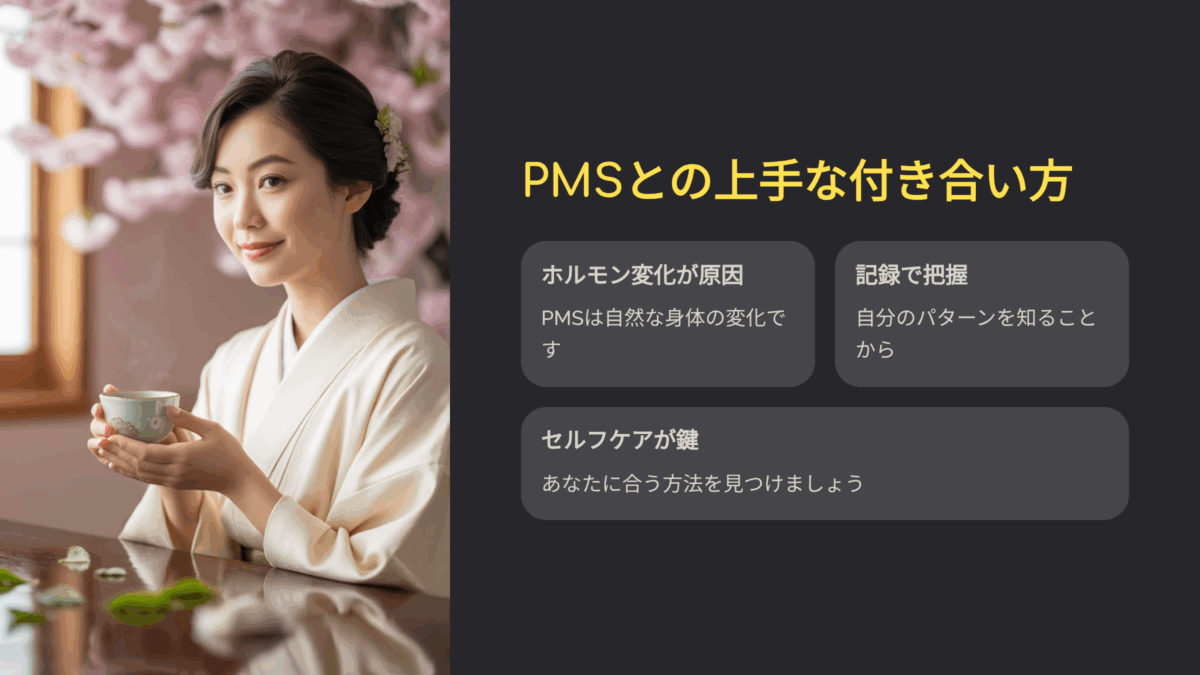PMSで毎月のように心も体も振り回されていた私。でも、自分のリズムと向き合うことで少しずつ変わっていきました。
目次を見て必要なところから読んでみてください。
なぜ私は毎月PMSに振り回されていたのか(体験の導入)
PMS(月経前症候群)は「月に一度の不調」では片づけられないほど、日常を左右します。 私自身も長い間「これは私の性格の問題なのか」と自分を責め続けてきました。でも、違ったんです。この章では、フェムケアの原点となった、私のPMSとの出会いとそのリアルをお伝えします。
PMSってこんなに苦しいもの?私の月経前症状
「また、今月も来た」
そう気づくのは、イライラが先か、涙が先か。
私にとってPMSは、自分ではどうにもできない波に毎月さらわれるような感覚でした。25歳を過ぎたあたりから、月経前になると急に感情が不安定になったり、無気力で何も手につかなくなったり。それまでもなんとなく「生理前は気分が落ち込むな」とは思っていましたが、年齢を重ねるにつれて症状が重くなっていくように感じたんです。
特に多かったのが、以下のような症状です。
- 朝起きるのがつらく、出勤がギリギリになる
- 家族やパートナーに対して妙にトゲトゲした言い方をしてしまう
- 小さなことで涙が止まらなくなる
- 胸が張って痛い、下腹部が重い
- 甘いものや脂っこい食べ物を異常に欲する
- 「この先どうせうまくいかない」という悲観的な思考ループ
体だけじゃなくて、心も支配されていく感覚があって。「私、このままじゃまずいかもしれない」と感じながらも、なぜこうなるのかはわかりませんでした。
検索すれば「PMS」とすぐに出てくるのに、それが自分のことだとは認めたくなかった。
だって、そんな言葉に頼った瞬間、自分が「弱い存在」になる気がしたからです。
でも、実はそこからが“私のフェムケア”の始まりでした。
気分の浮き沈み・体調不良・人間関係への影響
PMSのつらさは、自分の中だけにとどまりません。生活全体に静かに、でも確実に影響を及ぼします。
ある月のこと。職場で同僚に軽く指摘された一言にカッとなって、その場を離れてトイレで号泣してしまいました。後から冷静になると「なんであんなことで」と思うのに、感情のスイッチは自分でも止められない。しかも、そんな自分に対して自己嫌悪が重なり、「またやってしまった」「人間関係を壊したかも」と不安ばかりが膨らんでいくんです。
家族にも、「どうしたの?」「最近ピリピリしてない?」と距離を取られることもありました。月に数日間とはいえ、積もり積もれば信頼や関係性にも影を落とします。
そして一番つらかったのは、「この状態がいつ終わるのか分からない」不安でした。
仕事も、恋愛も、体調も、すべてがPMSの“機嫌”に左右されているような感覚。これはもう、単なる体調不良ではなく、“生活を揺さぶる存在”だったんです。
私が本気で「このままじゃまずい」と向き合うようになったのは、PMSによって自分の可能性が削られていると感じた瞬間でした。
PMSは、たかがホルモンのせい――そう思われることも多いかもしれません。
でも、実際には人生の質を大きく左右する“見えない負担”です。
次の章では、そんなPMSの正体を知ったことで、私の見え方がどう変わっていったかをお話しします。
✅ PMS症状があるのは「あなたのせい」ではありません。
それを知ることが、第一歩でした。
PMSの正体を知った瞬間、私の見方が変わった
PMSは、ただの気分の問題でも性格のせいでもありません。その背景には、女性ホルモンの繊細な変化があります。 ここでは「なぜPMSが起こるのか」「PMDDとの違いとは何か」を、専門用語をなるべく使わずに、生活者の目線で解説します。自分の状態を正しく知ることで、見えてくることがあるはずです。
PMSとホルモンの関係:なぜ心と体が乱れるのか
PMS(月経前症候群)という言葉は知っていても、「どうして起こるのか?」を詳しく説明できる人は、案外少ないかもしれません。私もかつてはそうでした。けれど、PMSの背景には“ホルモンの波”という生理的な現象があると知ったとき、なんだか少しホッとしたんです。
月経周期において、女性の体の中ではエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)という2つのホルモンがバランスを取りながら変動しています。
特に、生理の10日〜1週間前にはプロゲステロンが急激に増え、その後ガクンと減少します。
この変化に脳や神経が敏感に反応することで、以下のような症状が引き起こされやすくなるのです。
- 情緒不安定(涙もろさ、怒りっぽさ)
- 不眠、疲労感
- 食欲の変化
- 集中力の低下
- むくみ、胸の張り、頭痛などの身体症状
特に、セロトニン(幸せホルモン)の分泌が不安定になることが、心の症状に深く関係していると言われています。
この仕組みを知ったとき、「私、ただ感情的なんじゃなくて、ちゃんと理由があったんだ」と少し涙が出ました。
PMSの症状は100人いれば100通り。重さや出方もさまざまです。でも共通して言えるのは、「意志ではどうにもできない変化が、体の中で起きている」ということ。
それを知っているだけで、無理に気合で乗り切ろうとしなくなりました。
✅ ホルモンのせいにしていいんです。
それは「逃げ」ではなく、自分を守るための知識です。
PMDDとの違いを知って、自分の状態を客観視
PMSと混同されやすいのが、「PMDD(月経前不快気分障害)」という状態です。私自身も、この違いを知ったことで、「自分のPMSはどこまでが“普通”で、どこからが“専門的なケアが必要なレベル”なのか」を見極めるきっかけになりました。
簡単にまとめると、次のような違いがあります。
| 項目 | PMS | PMDD |
|---|---|---|
| 主な症状 | 身体症状・情緒の不安定さ | 主に精神的症状が重い |
| 日常生活への影響 | ある程度対応可能 | 仕事や人間関係に深刻な影響 |
| 感情のコントロール | 乱れるが意識できることも | 自傷衝動・絶望感を伴うことも |
| 対応 | 生活改善・セルフケア | 医療的な治療が推奨される場合あり |
私は自分の症状を、数ヶ月にわたって日記のように記録してみることで、「やっぱりPMSではあるけれど、PMDDの基準まではいかないな」と客観的に判断できました。
一方で、「もしかしてこれはPMDDかも」と気づいて病院に行った友人もいます。
大事なのは、“自分を他人と比べない”こと。 自分の感じているつらさが、自分にとっての事実であるなら、それを信じてあげてほしいんです。
そしてもし、仕事や人間関係が続けられないほどつらいなら、専門の医療機関に相談することをためらわないでください。
✅ つらさに名前がつくと、それだけで少し心が軽くなります。
試行錯誤のセルフケア、その失敗と気づき
PMSに悩まされる日々のなかで、「どうにかして軽くしたい」と思うのは当然のこと。私もいろいろな方法を試してきました。でも、効果が出なかったり、むしろ逆効果だったことも。この章では、そんな“遠回り”の経験から気づいた「正しい向き合い方」についてお話しします。
SNSで見た対処法を試すも…効果なし
正直に言うと、PMSに本気で向き合い始めた当初の私は、手当たり次第にネットの情報を漁っていました。
「チョコがいいらしいよ」
「運動が効くらしい」
「ピルを飲んだら楽になるって」
SNSやYouTubeで見かけた“いいらしいこと”を、そのまま自分にも当てはめて、期待して、落ち込んで……の繰り返し。
例えば、
- 話題のハーブティーを飲んでみたけれど、胃がもたれてしまった
- 「毎朝走るとスッキリする」と聞いて始めたら、むしろフラフラして仕事がつらくなった
- とりあえずピルをもらいに行ったけど、副作用がつらくてすぐ中断
周りが「効いた」と言っているものが自分には合わないとき、「私って本当に面倒な体だな」とまた自己嫌悪になりました。
でも今思えば、それらはすべて「自分のことをよく知らないまま選んでいた」結果だったんですよね。
症状の出方も、生活リズムも、体質も、人によって本当にバラバラなのに。
誰かの正解が、自分の正解とは限らない。
当たり前のことなのに、切羽詰まっているときって、それすら見えなくなっていました。
✅ セルフケアは、“選ぶ”より先に、“知る”が必要なんです。
自分のリズムを知ることの大切さに気づいた瞬間
迷走から抜け出すきっかけになったのは、あるとき試しに始めた「PMS記録ノート」でした。
きっかけは、「とにかく整理したい」という気持ち。毎月のモヤモヤをどうにか見える化できないかと思って、簡単な表を作ってみたんです。
- 日付と症状(気分、体の痛み、食欲など)
- そのときの仕事や予定
- 睡眠時間や食事内容
- 天気や気圧(地味に影響することも)
これを1〜2ヶ月続けてみたら、驚くほどはっきりと“パターン”が見えてきました。
「私は生理の5日前から落ち込みが始まり、2日前にピークがくる」
「睡眠時間が少ない日は、イライラが倍増する」
「排卵日頃に頭痛とむくみが出やすい」などなど。
このリズムがわかった瞬間、世界の見え方が変わったんです。
「あ、そろそろ気分が落ちてくる時期だから、予定は詰めすぎないでおこう」とか、
「今日は頑張れない日ってわかってるから、自分を責めるのはやめよう」とか。
つまり、先回りして自分をいたわることができるようになった。
それって、すごく大きな変化でした。
セルフケアって、特別な道具や知識が必要なわけじゃないんですよね。
「自分のリズムを把握する」ことが、最強のセルフケアになることもあると知ってからは、情報に振り回されなくなりました。
✅ “なんとなく”ではなく、“わかっているから対応できる”状態を目指す。
それが、私にとってのセルフケアの原点です。
私に合ったPMSセルフケアとの出会い
たくさんの情報に振り回された時期を経て、ようやくたどり着いたのが「自分に合ったセルフケア」でした。ここでは、私が実際に試して「効果を実感した習慣」、「気づきにつながった記録の方法」、そして「やめてよかったこと/続けてよかったこと」をリアルにお伝えします。
生活改善で効果を感じた3つの習慣
SNSや口コミに頼るのをやめて、自分の体と向き合いながら選んだセルフケア。なかでも「これは続けてよかった」と思える3つの習慣をご紹介します。
- 朝の光を浴びて、自律神経を整える
毎朝、5分だけベランダでコーヒーを飲むことにしました。
光を浴びることで、セロトニン(幸せホルモン)の分泌が促され、気分が安定しやすくなると言われています。朝からどんよりしていた気分が、少しずつ落ち着くようになりました。 - カフェインと甘いものを控えるタイミングを見直す
PMS期になると甘いものが欲しくなって、ついチョコやスイーツに手が伸びがち。でも、食べた後に余計イライラしたり、眠れなくなったりして逆効果でした。
なので私は「欲しくなる数日前から“減らす”ようにしておく」という形に変えました。 - PMS専用の“ゆるい日”を予定に組み込む
月に1〜2日、「何もしない日」をスケジュールに書き込んでいます。PMSのピークを見越して、なるべく予定を詰めない、考えごとも減らす。
この“バッファ”があるだけで、「休むことへの罪悪感」が消えました。
✅ 無理に変えなくていい。ただ、少し整えるだけでも体はちゃんと反応してくれる。
記録をつけて初めて分かった「私のパターン」
前章でも触れたPMS記録ですが、ここではもう少し具体的にご紹介します。
私が使っていたのは、スマホのメモアプリと、A5サイズの手帳。特別なアプリは使っていません。
以下のような項目を、毎日簡単にメモするだけです。
- 朝の気分(晴れ・モヤモヤ・涙など)
- 体調(頭痛・むくみ・眠気・便秘など)
- 睡眠時間/就寝時間
- 食事内容(特に甘いもの・カフェイン)
- 生理予定日からのカウント(D1が生理初日)
これを3ヶ月続けただけで、
「気分の落ち込みはD22〜D26あたりに集中する」
「寝不足の日は翌日の集中力が著しく下がる」
「外食が続いた週はむくみと下腹部痛が出やすい」
など、明確な“私だけのパターン”が浮かび上がってきました。
PMSって、「なんとなく不調」だからこそ、気づかないまま過ぎてしまう。でも、記録をすることで「予測できる不調」に変わります。それってすごく心強いんです。
✅ “見える化”は、自分を理解するための最大の武器。
やめてよかった習慣・取り入れてよかった工夫
セルフケアって、何かを「始める」だけじゃなく、何かを「やめる」ことも大事でした。
私がやめてよかったと実感しているのは、こんな習慣です。
- SNSで「理想のセルフケア像」を追いすぎること
モデルのような生活ができる人ばかり見て、勝手に落ち込んでいました。
今は、「今の私にできる範囲でいい」と決めています。 - 頑張って予定を詰め込むクセ
予定があると頑張ってしまう。だから、生理前の1週間は「余白」を残すように意識。 - 「気合いでなんとかする」精神
気合いでは、ホルモンバランスは整わないと気づきました。笑
一方で、「これは自分に合ってた」と思えた工夫はこちらです。
- PMS期だけ使うアロマや入浴剤を決める(香りの切り替えで気分が落ち着く)
- 「今日の体調メモ」だけでも手帳に書く(日記じゃなくてOK)
- 温めグッズ(腹巻・湯たんぽ)をあえて常備する(冬だけでなく年中活躍)
どれも特別なことではないけれど、“今の私”に寄り添ってくれる道具たちです。
セルフケアは、誰かの正解を真似するものではなく、「自分の快適さ」を知っていくプロセスそのもの。
それに気づけたことが、私にとって一番の転機でした。
✅ 自分を観察し、理解し、労わる。それが私にとってのPMS対策です。
今、PMSとどう付き合っているか
セルフケアを模索し、自分のリズムを知ることで、PMSとの向き合い方は大きく変わりました。症状が“完全になくなる”ことはなくても、「予測できる」「対処できる」だけで、心の余裕は生まれます。
ここでは、そんな今の私なりの付き合い方と、周囲との関係の変化についてお話しします。
完全にはなくならなくても「予測できる」安心感
今でも、生理前になると不安定になることはあります。
それでも、かつてのように「なぜこんなにしんどいのか分からない」「突然怒りや悲しみが襲ってくる」という状態ではありません。
一番大きいのは、自分で“予測できるようになった”こと。
- 生理予定日の10日前から「そろそろPMS期だから」と意識を切り替える
- 食事や予定、会う人を調整して、刺激を減らす
- 気持ちが揺れる日には「これはホルモンの波だから」と一歩引いて見守る
このように、“ただ振り回される存在”だったPMSが、“前もって準備できる相手”に変わった感覚があります。
もちろん、「なんで分かってたのに、また落ち込んでるんだろう」と思う日もゼロではありません。でも、その回数は確実に減りました。
PMSの症状は、完治するものではないかもしれません。
でも、「自分の味方でいられる日を1日でも増やす」ことは、確実にできる。
それが、私がセルフケアを通して得た一番の収穫です。
✅ コントロールできなくても、受け入れて寄り添うことはできる。
パートナーや職場との関係も変わった
セルフケアが自分の内側にとどまらず、人間関係にもプラスの変化をもたらしてくれたのは予想外でした。
以前の私は、PMSのことを誰にも言えませんでした。
言ったところで、「それって甘えなんじゃないの?」「生理のせいにしてるだけじゃない?」と思われそうで、怖かったんです。
でも、自分の状態を記録し、理解できるようになったことで、言葉にしやすくなった。
あるときパートナーに、「この週は気分が落ちやすいから、ちょっと優しめでいてくれると助かる」と伝えたんです。すると、「そうなんだ、じゃあ今週はデリバリーでいいよ」と軽やかに受け入れてくれて。
職場でも、無理に根性で乗り切るより、「この週は在宅にしてもいいですか?」と先に相談するようにしました。
もちろん全てがスムーズではないけれど、相手は“PMSを知らない”だけで、“理解できない”わけではないと気づきました。
そして何より、自分がちゃんと説明できるようになったことで、人に頼ることへの罪悪感も減ったんです。
✅ PMSと付き合うとは、「自分だけで抱え込まない」ことでもある。
PMSに悩むすべての人へ伝えたいこと
PMSに悩む人の多くが、「誰にも相談できないまま、自分の中だけで抱えている」という現実に直面しています。私もそうでした。だからこそ、これまでの体験を通して、いま苦しんでいるあなたに伝えたいことがあります。
この章では、「責めるのではなく、理解すること」、そして「受診すべきタイミング」について、生活者の視点からお話しします。
自分を責めないで。体と心に向き合うことから始めよう
PMSで気分が沈むとき、体が重たいとき、うまくできない自分にイライラしてしまうことってありますよね。
でもどうか、そのイライラを「自分のせい」にしないでください。
あなたの中で起きているのは、ホルモンの変化という「生理現象」です。コントロールできなくて当然なんです。
たとえば、風邪を引いたときに「気合で治せ」とは誰も言わないのに、なぜPMSだと自分を責めてしまうのでしょう。
私は、自分を責めることをやめたときから、セルフケアが機能し始めました。
- つらい日は、つらいと認める
- 涙が出る日は、無理に止めない
- うまくいかない日には、ひとつでもできたことを見つける
こうした小さな自己肯定の積み重ねが、自分自身への信頼を取り戻す第一歩になりました。
PMSは、心と体の声を聞くきっかけでもあります。
「自分をもっと大切にしよう」と思えるようになったのも、PMSがあったからこそ。
✅ “どうしてこんなにしんどいの?”という疑問を、“どうすればラクに過ごせるかな”という問いに変えてみてください。
きっと少しずつ、見え方が変わってくるはずです。
病院を受診すべきタイミングとは?
とはいえ、「つらいけど、どこまでが普通なのか分からない」と悩む方も多いと思います。
そんなときの判断基準として、私が意識していたのは以下のような点です。
- 仕事や学校に行けないほど気分が落ち込む
- 怒りや絶望感が強く、自己嫌悪や自傷的な思考にまで及ぶ
- 生理が始まっても気分の不調が改善しない
- 体の痛み(頭痛・腹痛・吐き気など)が市販薬ではおさまらない
- 生活や人間関係に深刻な支障が出ている
これらに当てはまる場合、「気のせい」では済ませないで、婦人科やメンタルヘルスの専門機関に相談することをおすすめします。
実際、私の友人のひとりは「PMSのせいで人と話すのも怖い」と感じるようになり、婦人科で相談したところ、PMDDの可能性があると診断されました。
そこから、漢方薬やカウンセリングなどを取り入れながら、少しずつ回復しています。
PMSやPMDDは、れっきとした「不調」であり、治療や支援の対象になる状態です。
「病院に行くほどじゃないかも」と我慢せず、“安心材料を得に行く”くらいの気持ちで受診してみてください。
✅ あなたが抱えている不調には、名前も理由も、そして解決の道もあります。
以上で本文パートは完結です。最後に、読者の行動を自然に促すまとめ+内部リンク+LINE友達追加の導線を出力いたします。
まとめ:PMSに振り回されない、自分軸のセルフケアを
この記事では、私自身がPMSに悩み、試行錯誤の末にたどり着いたセルフケアについてお話ししてきました。最後に、大切なポイントを3つにまとめます。
- ✅ PMSは「気のせい」でも「わがまま」でもない。ホルモンによる体と心の変化
- ✅ 情報に振り回されず、「自分のリズム」を知ることがケアの第一歩
- ✅ 完全に症状をなくすのではなく、「予測と対処」で日々をラクにしていく
PMSと共にある日々は、決して楽ではありません。
でも、自分の体と向き合い、選択肢を持てるようになれば、“振り回される側”から“付き合っていける側”へと変わることができます。
自分に合ったケアのかたちを見つけるきっかけになれば、嬉しいです。
関連記事:PMS症状を改善する食べ物と栄養素
\あなたに合ったセルフケア情報をもっと知りたい方へ/
LINEでフェムケアのヒントをお届け中。限定記事やチェックリストも配信しています。
参考情報・出典
本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。
- 日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」
https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4 - 厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html - MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms - 日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」
https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/ - 順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html