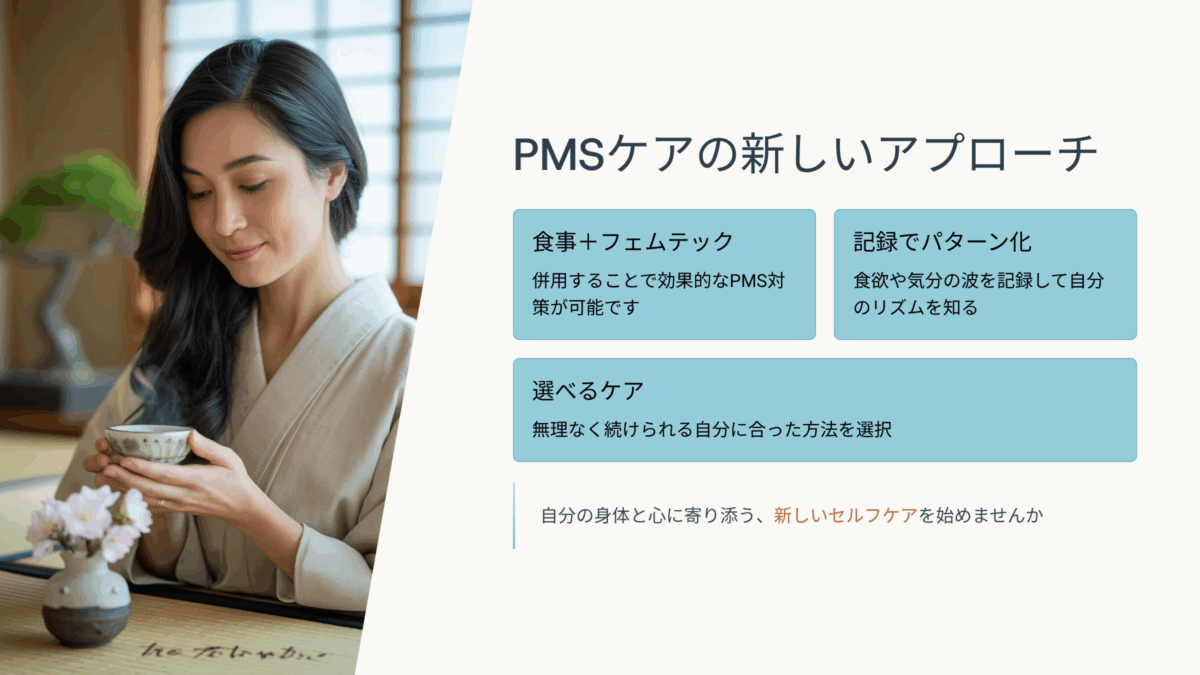PMSでつらくなる食欲や気分の波。「何を食べれば?」「フェムテックって効果あるの?」と悩む方へ。セルフケアとテクノロジーの併用で、無理なく整える方法を解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
PMS 食べ物の基礎知識(まず何が起きているのか)
- PMSとPMDDの違いと症状の範囲
- ホルモン変動と血糖値・セロトニンの関係
- 「食べると悪化しやすい」「助けになりやすい」の考え方
- まとめ
- PMS 食べ物で避けたいもの・取りたいもの(実例と根拠)
- 避けたい頻出食材とシーン(砂糖・カフェイン・アルコール・塩分)
- 取りたい栄養素(マグネシウム・ビタミンB6・オメガ3・鉄・食物繊維)
- コンビニ・外食での選び方(低GI・たんぱく質・間食リスト)
- まとめ
- フェムテックグッズで食事管理をラクにする(なぜ有効か)
- トラッキングアプリで周期×食欲パターンを見える化
- ウェアラブル・体温計で基礎体温と睡眠の連動を把握
- 温活・リラクゼーション系グッズで過食トリガーを下げる
- まとめ
- フェムテックグッズの選び方(意思決定フロー)
- 目的別マトリクス(記録・予測/体調把握/ケア体感)
- チェック項目(通知の柔らかさ・データ出力・プライバシー・コスト)
- 向いている人/向かない人の見極め
- まとめ
- 1週間の食事記録テンプレートとタグ付け
- PMS期の買い置きリストと置換ルール(甘いもの→果物+ナッツ等)
- 就寝前ルーティン(温活+ノンカフェイン+軽ストレッチ)
- まとめ
- 比較と事例(フェムテック活用のビフォーアフター)
- トラッキング中心/温活中心/併用のメリデメ比較
- 3パターンのシミュレーション(在宅勤務・外勤・子育て中)
- まとめ
- 受診の目安とセルフケアの限界(安全性の担保)
- 「生活支障度」「期間」「重症度」チェック
- 薬物療法や専門外来に相談すべきサイン
- 自己判断でやりがちなNG
- まとめ
- Q&A(よくある質問)
- まとめ
- まとめ(PMS 食べ物とフェムテックの併走で続ける)
- 要点の振り返りと次の一歩
- 1か月後に見直す評価指標
- 最後に:フェムケアは、“がんばり”ではなく“選びなおし”の連続
PMSとPMDDの違いと症状の範囲
「生理前、なんか気分が落ちる」「甘いものばかり食べたくなる」——それって、もしかしたらPMSかもしれません。でも、人によってはそれどころじゃない辛さを感じていることもあります。この章では、PMSとPMDDの違いを正しく知ることで、自分の状態を客観的に見つめ直すきっかけになります。
PMS(月経前症候群)とは、生理が始まる3〜10日前から現れる心身の不調のこと。症状には以下のようなものがあります。
- イライラ・落ち込み・情緒不安定
- 乳房の張り・むくみ・便秘
- 異常な食欲・集中力の低下
これに対してPMDD(月経前不快気分障害)は、PMSの中でも精神的な症状が特に強く出る状態です。抑うつ、不安、怒り、無気力など、日常生活や人間関係に支障が出るほどの重さが特徴です。
✅ PMDDは心の問題ではなく、ホルモンの影響による身体的な反応として捉える必要があります。
PMS・PMDDに共通するのは、「一時的なものだから我慢すべき」とされがちなこと。でも、不調の背景には明確な生理学的変化があるという事実を、まず知ることが大切です。
ホルモン変動と血糖値・セロトニンの関係
食欲が止まらない、急に甘いものが欲しくなる、なんだかずっと眠い…。そう感じたこと、ありませんか?それ、ホルモンのゆらぎと血糖値、セロトニンの関係が絡んでいる可能性が高いです。
生理前になると、体内のエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)のバランスが急激に変わります。このホルモン変動が、私たちの脳内物質「セロトニン」の分泌量を低下させる原因に。
セロトニンが不足すると…
- 気分が落ち込む
- イライラしやすくなる
- 衝動的に食べてしまう
という流れにつながります。
一方で、セロトニンの材料となる「トリプトファン」は、炭水化物と一緒に摂ることで脳に届きやすくなるため、無意識に甘いものやパンを欲する行動が起きやすくなるのです。
さらに、ホルモンの影響でインスリン感受性が低下し、血糖値が乱れやすくなるため、血糖の急上昇・急降下が起こりやすくなります。
その結果…
✅ エネルギー不足→疲労感
✅ 血糖急降下→怒りっぽくなる
✅ 脳が糖を求める→過食や中毒性の高い食べ物への依存
といった悪循環が生まれてしまうのです。
大切なのは、「意思が弱いから」ではないということ。ホルモンと血糖と神経伝達物質という、体内のシステムの連動で起きている現象だと知っておくと、必要以上に自分を責めずにすみます。
「食べると悪化しやすい」「助けになりやすい」の考え方
PMSがつらいとき、「何を食べたらいい?」という問いに答える前に、まず大切なのは「何を避けたほうがいいか」も知っておくことです。
食べると悪化しやすい食品
以下のような食品は、ホルモンバランスや血糖の乱れを助長しやすく、PMS症状の悪化につながる可能性があります。
- 精製された糖質(白砂糖・菓子パン・スイーツ)
- カフェイン(コーヒー・エナジードリンク)
- アルコール(特に糖分の多いカクテルなど)
- トランス脂肪酸(スナック菓子・ファストフード)
- 塩分の多い加工食品(ハム・ソーセージ・カップ麺)
これらは、血糖値の急激な変動や水分貯留、炎症反応を引き起こしやすく、PMS症状を長引かせる要因になります。
「やめなきゃ」と思うのではなく、「あえて避ける選択肢を持つ」くらいの距離感でOKです。
助けになりやすい食品
では、どんな食べ物がPMSのサポートになるのでしょうか?代表的な栄養素と食品を以下にまとめました。
| 栄養素 | 期待できる効果 | 食品例 |
|---|---|---|
| ビタミンB6 | セロトニン生成を助ける | バナナ、マグロ、さつまいも |
| マグネシウム | イライラ・頭痛・便秘の緩和 | アーモンド、ひじき、ほうれん草 |
| カルシウム | 情緒の安定、筋肉のけいれん緩和 | ヨーグルト、小松菜、チーズ |
| 食物繊維 | 血糖の安定、腸内環境の改善 | オートミール、雑穀、野菜全般 |
| 鉄分 | 倦怠感・貧血予防 | レバー、あさり、納豆 |
✅ 特に「ビタミンB6+マグネシウム」の組み合わせは、セロトニン生成の鍵とも言われており、PMS対策のベースになります。
「完璧な食事」ではなく、たとえば朝食にオートミールを足してみる、間食にナッツを選ぶ、といった“1つの選択肢”を増やすことから始めてみてください。
まとめ
PMSは、ただの「気のせい」や「甘え」ではありません。ホルモンの波に体も心も影響されているからこそ、食べ物という日常的な選択が、その波を穏やかにする力を持っています。
今日からできることは…
- 「体のせい」と知ることで、自分を責めない
- 食べ物でセロトニンや血糖のバランスをサポートする
- まずは“避けるもの”を知り、“選べるもの”を1つ持つ
不調と向き合うって、本当はとても勇気のいることです。でも、自分の体を「選べるもの」として捉えられるとき、フェムケアはもっと身近な存在になります。
✅ もし迷ったり、悩んだりしていたら、ひとりで抱えず、信頼できる医療機関や専門家にも相談してくださいね。
参考情報・出典
本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。
日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」
https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4
厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html
MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms
日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」
https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/
順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html
関連記事:PMS症状を改善する食べ物と栄養素
✅ 「フェムケアの部屋」では、LINEで日々のケアのヒントを配信中。心と体を整える小さな習慣、始めてみませんか?
公式LINEはこちらから登録
PMS 食べ物で避けたいもの・取りたいもの(実例と根拠)
避けたい頻出食材とシーン(砂糖・カフェイン・アルコール・塩分)
「なんだかイライラして、無性に甘いものを食べたくなる」
「眠気覚ましにコーヒーをがぶ飲みしてしまう」
PMS中のこうした行動、実はよくあることです。でもその選択が、不調をさらに悪化させている可能性があるとしたら——?
この章では、なぜそれらの食品がPMSの症状を悪化させやすいのか、その根拠とともに解説します。
1. 砂糖(スイーツ・菓子パン・甘い飲料)
生理前になると、血糖値が不安定になりやすくなります。砂糖の多い食品は血糖を急上昇させたあと、急降下させる「ジェットコースター血糖」を起こしやすく、以下のような影響が。
- イライラや気分の落ち込みを助長する
- 満腹感が得られにくく過食につながる
- 炎症反応を高め、肌荒れやむくみの原因に
✅ 生理前に「甘いもの依存」になるのは、ホルモンと血糖の連携による自然な反応。でも、代わりに果物やドライフルーツ、ナッツなどに切り替えるだけでも、かなり穏やかに過ごせます。
2. カフェイン(コーヒー・エナジードリンク・濃いお茶)
カフェインは交感神経を刺激し、眠気を吹き飛ばす一方で、神経過敏・不安感を強める作用があります。生理前は自律神経が乱れやすいため、その影響を受けやすいタイミング。
さらに、カフェインにはマグネシウムの排出を促進する作用も。PMS中に必要な栄養素が知らず知らずのうちに減ってしまうことにもつながります。
3. アルコール(ビール・ワイン・カクテルなど)
「飲んだらちょっと楽になるかも」と思う夜もあるかもしれません。でも、生理前のアルコールは要注意。
- 睡眠の質を下げ、疲労感や情緒不安定を助長
- 肝機能が落ちることで、ホルモン代謝がさらに乱れる
- セロトニンの分泌を阻害し、落ち込みやすくなる
特に、糖分の多いお酒やおつまみとのセットは、PMSの悪循環を深めやすい組み合わせです。
4. 塩分(加工食品・インスタント食品)
ホルモンの影響で「水分をためこみやすい」生理前に、塩分の多い食事を取ると…
- むくみやすくなる
- 頭痛・だるさが増す
- 血圧の変動が不安定になる
✅ 「つい食べがち」なスナックやコンビニ食品も、実はPMSには逆効果。成分表示を見る習慣をつけるだけでも、選択が変わってきます。
取りたい栄養素(マグネシウム・ビタミンB6・オメガ3・鉄・食物繊維)
食べ物でPMSを整えるとき、「何を控えるか」だけでなく「何をしっかり摂るか」がとても大切です。ここでは、症状の緩和に効果が期待されている栄養素とその理由、食品例をまとめました。
| 栄養素 | 主な働き | 食品例 |
|---|---|---|
| マグネシウム | 神経の興奮を抑え、イライラや頭痛を軽減 | ひじき、ほうれん草、アーモンド、納豆 |
| ビタミンB6 | セロトニンの生成を助け、情緒安定に寄与 | バナナ、さつまいも、鶏むね肉、玄米 |
| オメガ3脂肪酸 | 炎症を抑える作用があり、気分の落ち込みを軽減 | サバ、イワシ、亜麻仁油、くるみ |
| 鉄分 | 貧血・疲労感の予防。集中力維持にも関与 | あさり、レバー、小松菜、豆類 |
| 食物繊維 | 血糖値の安定・便秘の改善・腸内環境を整える | オートミール、きのこ、海藻、玄米 |
✅ この中でも、「マグネシウム+ビタミンB6」の組み合わせは、海外でもPMSサポートとして推奨される組み合わせ。サプリに頼らず、食材から取り入れることが理想です。
ポイントは、「特別な食材」よりも「日々の食卓で無理なく続けられること」。味噌汁の具を海藻に変える、間食にくるみを加えるなど、小さな選択の積み重ねが体調を整えてくれます。
コンビニ・外食での選び方(低GI・たんぱく質・間食リスト)
「忙しくて、自炊ができない日もある」
「外回り中のコンビニ飯、何を選べばいいの?」
そんなリアルなシーンでも、少しの工夫でPMSにやさしい選択はできます。この章では、私自身も実践している「避けずに選ぶ」外食・コンビニ術をご紹介します。
選ぶポイントはこの3つ
- 低GI食品(血糖値の急上昇を防ぐ)
- たんぱく質を含む食品(セロトニン材料)
- 過度に加工されていないもの(栄養素をキープ)
コンビニで選ぶなら?
- おにぎり(雑穀米・鮭など)+サラダチキン or ゆで卵
- オートミールカップ or ナッツ入りグラノーラバー
- 無糖ヨーグルト+冷凍ブルーベリー
- 豆乳 or 無調整アーモンドミルク
✅ 甘いカフェラテを選ぶ前に、無糖の温かい飲み物+たんぱく質の組み合わせを選んでみると、食欲が自然と落ち着くことも。
外食ならどうする?
- 和定食(焼き魚+小鉢)を基本に
- パスタよりは蕎麦、パンよりは玄米
- 油の少ない蒸し料理や煮物を選ぶ
- 居酒屋では「枝豆+冷奴+焼き魚」がおすすめ
外食では「完璧」を目指さないことが大事です。ひとつだけでも、意識的に栄養のあるものを足すというスタンスで。
PMS時のおすすめ間食リスト
| シーン | おすすめ間食 | 効果の理由 |
|---|---|---|
| 午前中に眠い | バナナ+無糖ヨーグルト | セロトニン材料+腸内環境サポート |
| 甘いものが欲しい | ドライいちじく+アーモンド | 食物繊維+マグネシウム |
| 夜の口さみしさ | くるみ+豆乳ホットドリンク | オメガ3+たんぱく質+温活効果 |
✅「我慢する」より「選べる」ことが、心身のコントロール感を育ててくれます。
まとめ
PMSは「一時的だから」と軽く扱われがちですが、食の選択が心と体に与える影響はとても大きいものです。
今回のポイントをまとめると…
- 避けたい食材(砂糖・カフェイン・アルコール・塩分)には、明確な悪化リスクがある
- マグネシウムやビタミンB6、鉄などの栄養素は、症状を整えるサポートになる
- 外食やコンビニでも、「少し意識する」だけで体にやさしい選択ができる
フェムケアは、“特別なこと”ではなく日々の選択の積み重ね。
どこかで聞いたアドバイスではなく、自分の体で感じて「納得できる」食習慣を、少しずつ作っていきましょう。
参考情報・出典
本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。
日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」
https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4
厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html
MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms
日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」
https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/
順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html
関連記事:PMS食事療法の完全ガイド
✅ 「フェムケアの部屋」では、LINEで体と心に寄り添うセルフケア情報をお届け中。
日々のちょっとした違和感に気づける感覚を、一緒に育てていきませんか?
公式LINEはこちらから登録
フェムテックグッズで食事管理をラクにする(なぜ有効か)
「食事でPMSを整えたい」そう思っても、実際には続かない。
その理由の多くは、「体の状態が分からないまま、無理にがんばっている」からです。
この章では、フェムテックグッズを使うことで、PMS期の体調と食欲の“クセ”が見えるようになる仕組みをお伝えします。食事管理がラクになる理由を、3つの視点から解説します。
トラッキングアプリで周期×食欲パターンを見える化
PMS中の過食や食欲の暴走って、自分では「コントロールできない」と思いがちです。
でも実は、「いつ、どんな食欲になるか」は毎月ほぼパターン化しています。
たとえば…
- 排卵後から生理直前にかけて、甘いものが異様に欲しくなる
- 生理直後は食欲が自然と落ち着き、さっぱりしたものを好む
- ストレスや睡眠不足の日はジャンクに手が伸びがち
これらの周期×食欲のクセを記録し、見える化できるのが、PMSや月経トラッキングアプリの強みです。
なぜアプリでの記録が効くの?
- 客観的に「自分のパターン」を知れることで、自分を責めずに済む
- 「あ、そろそろ暴食ゾーンかも」と事前に心構えができる
- 生理前にマグネシウムを意識しよう、間食リストを準備しようなどの具体的対策に落とし込める
✅ 食欲の波が「ランダムな敵」ではなく「周期的なパターン」として見えてくると、対応が“感情”ではなく“選択”になる。これはとても大きな変化です。
ウェアラブル・体温計で基礎体温と睡眠の連動を把握
「睡眠不足の日ほど甘いものがやめられない」
「なんだか寝ても疲れが取れない」
こうした実感、実は多くの人が感じています。そしてこれは基礎体温・自律神経・食欲ホルモンの関係性によるものです。
生理周期に伴って、私たちの基礎体温は以下のように変化します。
- 低温期(生理〜排卵):代謝が落ち着いていて、食欲も比較的安定
- 高温期(排卵後〜生理前):体温が上がり、眠りが浅くなる、イライラしやすい、甘いものが欲しくなる
ここで、睡眠の質がさらに下がると、食欲をコントロールする「レプチン・グレリン」というホルモンのバランスが崩れ、過食を誘発します。
ウェアラブルや体温計の役割とは?
- 毎日の体温を記録することで、「今は高温期だから過食しやすい」と自覚できる
- 睡眠スコアを確認することで、「今日は栄養重視の昼食にしよう」と調整できる
- 無理のない運動や休息のタイミングを見極めやすくなる
✅ たとえばスマートウォッチや婦人体温計のデータがあると、感覚ではなく数値で判断できるようになる。だから、「今日はあえて無理しない」を選びやすくなります。
温活・リラクゼーション系グッズで過食トリガーを下げる
意外かもしれませんが、PMS期の「食欲」は、実は「不安感」や「冷え」から来ていることも多いんです。
たとえば、こんな経験はありませんか?
- イライラして「何か食べないと落ち着かない」と感じる
- ずっと手足が冷えていて、甘いものがやめられない
- 無性にこってりしたものを欲するとき、心も疲れていた
このように、“満たされなさ”を食べもので埋めようとする心と体のサインは、温活やリラクゼーショングッズで緩和できるケースがあります。
どういったグッズが役立つのか?
- 温熱パッド・湯たんぽ:下腹部や仙骨を温めることで、自律神経の安定&食欲抑制に
- アロマディフューザー:ラベンダーやゼラニウムなど、ホルモンバランスに寄り添う香りでリラックス
- マッサージローラー・温感入浴剤:筋肉の緊張をほぐすことで、過緊張による衝動的な食欲を落ち着ける
✅ 体が温まっていると、「満たされ感」が自然と生まれ、脳が“食べなくても落ち着ける”と判断するようになります。
「食べる」以外のセルフケア手段を持つことで、“食欲一択”という選択肢から解放されるのです。
まとめ
フェムテックグッズは、「体を計る」「見える化する」「整える」ための道具。
でも本質は、「自分の不調に気づいて、納得して選べるようになる」ためのサポートです。
この記事でお伝えしたのは以下の3点です。
- トラッキングアプリは、周期と食欲の関係を“自分のこと”として理解するための鍵
- ウェアラブルや体温計は、感覚ではなく客観データから調整できる力をくれる
- 温活やリラックスグッズは、「食べる」以外のセルフケア習慣を育てるツール
フェムケアの本質は、“がまん”ではなく“選べること”。
デバイスに頼るのではなく、それを通して「自分の体と対話する」感覚を手に入れていけたら素敵だなと思います。
参考情報・出典
本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。
日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」
https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4
厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html
順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html
関連記事:PMS症状記録ダイアリーの使い方
✅ 「フェムケアの部屋」では、LINEで月経周期や食事・セルフケアのヒントをお届け中。
一緒に、自分の体とやさしく付き合う感覚を育てていきませんか?
公式LINEはこちらから登録
フェムテックグッズの選び方(意思決定フロー)
「PMSや生理の不調をラクにしたい」
「でも、フェムテックって何を選べばいいのか分からない」
そんな声をよく聞きます。
便利そうだから、SNSでバズっていたから。そうやって選んだグッズが自分に合わずにタンスの奥にしまわれてしまう——そんな“あるある”を減らすために、自分に合った選び方のフローをまとめました。
買う前に立ち止まって、「何のために使うのか?」を一緒に整理してみましょう。
目的別マトリクス(記録・予測/体調把握/ケア体感)
フェムテックグッズを「機能」で見る前に、まずは「目的」で整理するのが失敗しないコツです。
大きく分けて、以下の3つの目的に分類できます。
| 目的 | 主な効果 | 代表的なグッズ |
|---|---|---|
| ① 記録・予測したい | 生理周期やPMSの傾向を見える化し、対策につなげたい | トラッキングアプリ、スマート基礎体温計 |
| ② 体調を把握したい | 体温や睡眠の質を数値で管理したい/セルフケアのタイミングを見極めたい | ウェアラブル端末、スマートリング、連携アプリ |
| ③ ケアを体感したい | 体の不快感を緩和したい/癒しや安心感を得たい | 温活グッズ、リラクゼーショングッズ、セルフケアデバイス |
たとえば…
- 「いつも生理前に暴食してしまう」→①の予測・記録が向いている
- 「朝起きたときの疲労感を減らしたい」→②の体調モニタリングが活きる
- 「とにかくこの不快感を和らげたい」→③の体感ケアが効果的
✅ 機能ありきではなく、「何に困っているか」から逆算することが、長く使えるグッズとの出会い方です。
チェック項目(通知の柔らかさ・データ出力・プライバシー・コスト)
「よさそう!」と思っても、実際に使ってみるとストレスになる機能もあります。
たとえば通知がしつこいとか、デザインが好みじゃないとか。
ここでは、選ぶときにチェックしておきたい項目をまとめました。
1. 通知の柔らかさ・頻度
- 「今日の体調、ちょっと不調かも」と教えてくれるのはありがたい
- でも、「そろそろ生理ですね、気をつけて」みたいな通知が毎日届くと、気分が落ち込むことも
✅ 通知のON/OFF設定ができるか、言葉のトーンが自分に合っているかも大切なポイントです。
2. データの出力と連携のしやすさ
- 体温や睡眠のデータをあとから見返したい
- 他のアプリと連携して、月経と運動・食事ログを統合したい
✅ CSVでの出力可否や、連携できるアプリの種類は、継続利用の満足度に直結します。
3. プライバシー設定
- センシティブな体調データを扱うからこそ、外部への送信・広告利用の有無は確認したい
- 利用規約の中に、「第三者提供あり」の文言がないかをチェック
✅ 信頼できる開発元かどうかは、レビューだけでなく運営元の公式情報からも判断しましょう。
4. コスト・ランニング費用
- アプリ自体は無料でも、有料機能がないと使い物にならないことも
- 月額課金型か、一括購入かも含めて比較したい
✅ 価格だけでなく、「何にお金を払っているのか」が明確かどうかを見極めるのがポイントです。
向いている人/向かない人の見極め
フェムテックグッズは、魔法の道具ではありません。だからこそ、「使う人のライフスタイルや性格との相性」が重要です。
向いているのはこんな人
- 数字や記録を見ると安心する
- 毎日の体調変化を言語化したい
- 小さな変化に気づけるようになりたい
- 自分で整える感覚を身につけたい
こういう方は、トラッキングアプリや体温デバイス、睡眠計測ツールなどと相性がいいです。
向かないかもしれない人
- 数字を見るとプレッシャーを感じてしまう
- 忙しすぎて、記録を習慣にする余裕がない
- デバイスに依存したくない
この場合は、温活グッズや香り、マッサージツールなど“今ここで整える”タイプのケアから始めるのがおすすめです。
✅ 大切なのは、「どれが優れているか」ではなく「自分に合った方法を見つけること」。
続けられることが、一番のフェムケアです。
まとめ
フェムテックグッズは、あくまで「選べるケアのひとつ」であって、誰にとっても万能なわけではありません。
だからこそ、“なぜ使いたいのか”を自分で決めてから選ぶことが、後悔しない第一歩です。
この記事のポイントは以下の通りです。
- 目的別マトリクスで「記録/把握/体感」のどれを重視したいかを整理する
- 機能だけでなく、通知の内容やプライバシーへの配慮、価格も比較する
- 自分の性格や生活リズムに「合う・合わない」を見極めて、無理なく続けられるものを選ぶ
フェムケアは、「自分を知って、自分を労わること」。
グッズ選びも、その一部であるべきだと思います。
参考情報・出典
本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。
日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」
https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4
厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html
順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html
関連記事:PMDDセルフチェックと診断基準
✅ 「フェムケアの部屋」では、LINEで月経・セルフケア・食事管理に役立つ情報をお届けしています。
あなたの“自分にやさしい選択”をサポートするヒントを、ぜひ受け取ってください。
公式LINEはこちらから登録
使い方の型(今日からできるステップ)
フェムケアって、情報を集めるだけで終わってしまいがち。
「知識はあるけど、行動に移せてない」そんな状態、私自身もずっと悩んできました。
だからこそこの章では、“今日からできる”ことに絞って、3つの具体的ステップをご紹介します。
すべて難しいことではありません。
ルールよりも“感覚を育てる”ことを大切にしたセルフケアの「型」、ぜひ試してみてください。
1週間の食事記録テンプレートとタグ付け
「食事を整えたい」と思っても、何をどう整えればいいか分からない——
そんなときに役立つのが“記録するだけ”の食事ログ習慣です。
テンプレート(手帳でもスマホでもOK)
| 日付 | 時間帯 | 食べたもの | 気分 | メモ(PMS期?) |
|---|---|---|---|---|
| 9/26 | 朝 | 雑穀ごはん・味噌汁・焼き魚 | すっきり | – |
| 9/26 | 昼 | パスタ・パン・カフェラテ | 眠い・イライラ | ○(PMS中) |
| 9/26 | 夜 | 野菜スープ・ナッツ | 少し落ち着いた | – |
タグ付けで「気づき」を可視化する
- #満足感あり → 栄養バランスが良かった証拠
- #過食衝動 → PMS期や睡眠不足との関連性あり
- #リズム乱れ →外食・お酒・夜更かしとの関係を確認
✅ 目的は、「反省」じゃなく「パターンに気づくこと」。
数値や厳密な栄養管理ではなく、感情とのリンクを記録していく感覚でOKです。
PMS期の買い置きリストと置換ルール(甘いもの→果物+ナッツ等)
PMSがつらくなる前にやっておくと本当にラクになるのが、「食べても安心」なものの買い置きです。
ポイントは、“がまんしない”ために“選べるものを用意しておく”こと。
おすすめ買い置きリスト
| カテゴリ | 食材例 | 効果のポイント |
|---|---|---|
| フルーツ | バナナ・りんご・冷凍ブルーベリー | ビタミン・食物繊維・満足感あり |
| ナッツ類 | くるみ・アーモンド(素焼き) | マグネシウム・オメガ3・腹持ち◎ |
| 発酵食品 | 無糖ヨーグルト・甘酒・味噌 | 腸内環境を整える・気分の安定 |
| 主食系 | オートミール・玄米パック・雑穀ごはん | 血糖コントロール・腹持ち◎ |
| 飲み物 | ノンカフェイン茶(ルイボス・麦茶)・豆乳 | 冷え対策・ホルモンバランスケア |
置換ルール:欲しいもの→代わりになるもの
- ケーキ・チョコ → 冷凍ブルーベリー+ヨーグルト+はちみつ少量
- スナック菓子 → ナッツ+干し芋 or 雑穀せんべい
- 甘いドリンク → 豆乳+きなこ or シナモン
- こってりご飯系 → 雑穀おにぎり+味噌汁
✅ ここでも「完璧主義」はいりません。
「どうせ食べるなら、体がラクになるほうを選ぼう」くらいのやわらかい視点で十分です。
就寝前ルーティン(温活+ノンカフェイン+軽ストレッチ)
PMS期に過食が起きやすいのは、「寝る前の不安感や満たされなさ」からくるケースが多いんです。
だからこそ、寝る前の“整える習慣”が、日中の食欲安定にもつながるというのが私の実感です。
夜ルーティンの3ステップ(15〜30分で完結)
- 温活(10分)
- 湯たんぽ or お腹に貼るカイロ
- 足湯・温かいタオルで首元を温める
- 「あったかい」を感じることで副交感神経がONに
- ノンカフェイン飲料(5分)
- ルイボスティー・カモミール・甘酒(少量・温める)
- 寝る前に“何か口にする”安心感は、過食予防にも効果的
- 軽ストレッチ(5分)
- 足を伸ばして深呼吸+骨盤まわりをゆらす
- 体がゆるむと、「食べたい」より「休みたい」が自然と出てくる
✅ 就寝前は、「満たすために食べる」から「休むことで満たされる」へとシフトする時間。
意識的なケアはもちろん、“心地いい習慣”を作ること自体がフェムケアだと思います。
まとめ
PMSや食欲のコントロールって、気合いとか根性ではどうにもならないものです。
だからこそ、「うまくいかない」のはあなただけじゃないし、それは失敗でもありません。
今回紹介した“使い方の型”のポイントを振り返ると…
- 記録は「感情と行動の関係性」を可視化するもの
- 食べたい衝動は「置き換えられる」ように準備しておく
- 寝る前の温活や飲み物で、「食べずに整える習慣」を育てる
✅ フェムケアとは、自分の体を“敵”じゃなく“パートナー”にしていくプロセス。
今日の1つの行動が、来月の“少しラクなわたし”につながります。
参考情報・出典
本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。
日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」
https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4
厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html
順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html
関連記事:PMS症状記録ダイアリーの使い方
✅ 「フェムケアの部屋」では、LINEで日々の体調変化やセルフケアのヒントを配信中。
「わかる、私もそうだった」から始めるケア、一緒に見つけていきましょう。
公式LINEはこちらから登録
比較と事例(フェムテック活用のビフォーアフター)
「PMSがつらい。でも何をどう変えたらいいかわからない」
そんなとき、一番欲しいのは「自分と似た状況の人が、どう改善したのか」というリアルな声ではないでしょうか?
この章では、フェムテックを使ったケアのビフォーアフターを、
- トラッキング中心/温活中心/併用タイプの比較
- ライフスタイル別の3シミュレーション
という2つの視点でまとめています。
自分に合いそうなスタイルを、ぜひ見つけてみてください。
トラッキング中心/温活中心/併用のメリデメ比較
フェムテックの使い方は、人によって合う・合わないがあります。
ここでは、3つの代表的なアプローチを比較してみましょう。
| タイプ | 主な特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ①トラッキング中心 | アプリや体温計を使って、周期や体調を記録・予測 | – 食欲や不調の「傾向」が見える |
- 事前準備・予防がしやすい | – 数字に敏感な人にはプレッシャー
- 習慣化にコツがいる |
| ②温活・リラックス中心 | 温熱グッズや香り、ストレッチなど“感じる”ケアが中心 | – 過食・イライラの緩和 - 体の安心感につながる | – 「なぜ効果があるのか」が見えづらい
- 客観的な把握はしにくい |
| ③トラッキング+温活併用 | 記録と体感ケアを組み合わせ、状態に応じて選択 | – 精神的にも身体的にもバランスが取れる - 自己理解が深まる | – 取り入れる内容が多く、やや手間
- 自分の“軸”を見つけるのに時間が必要 |
✅ 「どれが正解」ではなく、「今の自分に必要なのはどれか?」を見極めるのが鍵です。
たとえば、日々が忙しくてストレスが強い人は温活中心、仕事の予定に合わせて体調を整えたい人はトラッキング重視、というように使い分けてOK。
3パターンのシミュレーション(在宅勤務・外勤・子育て中)
フェムケアはライフスタイルによって“取り入れやすさ”がまったく違います。
ここでは、代表的な3タイプの女性像をもとに、1ヶ月のフェムテック活用事例をシミュレーションしてみましょう。
① 在宅勤務・自営業のAさん(30代後半)
課題:生理前の眠気と集中力の低下、過食癖
選んだケア:スマート体温計+朝の温活+軽いヨガ
- 朝イチで基礎体温を測り、周期をアプリで管理
- 生理前に入ったら、オートミールとナッツを買い置き
- 集中できない日は「今は高温期」と割り切り、作業時間を短縮
- 就寝前に足湯+ハーブティーで過食防止のルーティン化
変化:
✅ 「今日は無理しなくていい日」と判断できることで、食べ過ぎや自己嫌悪が減少
✅ 仕事のパフォーマンスも「波に逆らわない」ことで安定
② 外勤・営業職のBさん(20代後半)
課題:出先での暴食・イライラ・寝つきの悪さ
選んだケア:トラッキングアプリ+コンビニでの食選びリスト+温感シート
- アプリでPMS期を予測→その週はカフェインと甘いものを意識的に控える
- コンビニでは「ナッツ+豆乳」「雑穀おにぎり+味噌汁」など、置換ルールを活用
- 夜は温感シートでお腹と腰を温め、スマホを30分前にOFF
変化:
✅ 「なぜイライラするのか」が見えてくることで、無駄な自己否定が減る
✅ 間食が自然に減って、月1kgペースで体重も落ちた
③ 子育て中のCさん(40代前半)
課題:PMS期の情緒不安定と食欲暴走。自分時間が取れない
選んだケア:簡単な食事記録+貼るカイロ+甘酒の常備
- 手帳に「朝・昼・夜の満足度(○△×)」だけメモ
- 甘いものが欲しくなったら、冷蔵庫の“甘酒ヨーグルト”で置換
- 子どもが寝たあと、カイロを貼って深呼吸だけの“なんちゃって温活”
変化:
✅ 「自分をちゃんと見てる感覚」が持てるように
✅ 夫にPMSのタイミングを説明できるようになり、協力体制が整った
まとめ
PMS対策も、フェムケアも、「これさえやればOK」なんてものは存在しません。
でも、「何に困っていて、何が効いて、どんな変化があるのか」を知ることができれば、ケアはもっと自分ごととして捉えられるようになります。
この記事の要点をまとめると…
- トラッキング/温活/併用にはそれぞれ向き不向きと目的の違いがある
- ライフスタイルに応じた「無理なくできる型」を見つけることが、継続のカギ
- ケアによる変化は、「体調の安定」だけでなく自己理解・人間関係・仕事の質にもつながってくる
✅ 自分の体に合ったケア方法は、「試してみて、やめてみて、また戻ってみる」ことでしか見つかりません。
一歩ずつ、自分だけの“ちょうどいいフェムケア”を見つけていきましょう。
参考情報・出典
本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。
日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」
https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4
厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html
順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html
関連記事:PMSイライラ管理術
✅ LINE公式アカウントでは、PMSやフェムケアの小さなヒントを毎週お届け中。
あなたの毎日にちょっと役立つ「知ってよかった」が見つかります。
公式LINEはこちらから登録
受診の目安とセルフケアの限界(安全性の担保)
「これってPMSかな?」「でも病院に行くほどではないかも…」
そうやって我慢を繰り返している方、本当に多いです。
私自身も、“もうちょっと様子を見よう”を何度もくり返して、結果的に不調を長引かせてしまった経験があります。
この章では、どこまでがセルフケアでOKなのか、どこからは医療の力を借りるべきなのか、その線引きをできるようになることを目的にしています。
体と心の安全を守るために、知っておいてほしい内容を整理しました。
「生活支障度」「期間」「重症度」チェック
「つらい」と感じた時、それが受診に値するものなのか、どう判断すればよいのでしょうか?
厚生労働省や専門学会でも推奨されているのが、以下の3つの視点です。
① 生活支障度(どれくらい日常生活に影響があるか)
- イライラや落ち込みで仕事や家事が手につかない
- 対人関係に支障が出る(家族に当たってしまう、孤立したくなる)
- 甘いものが止まらず自己嫌悪が強くなる
- ベッドから出られない、外出が億劫になる
✅ 「我慢すればなんとかなる」状態を超えていたら、要注意です。
② 症状が出る期間は?(日数と周期性)
- 毎月、生理の3〜10日前に明確に症状が現れ、生理開始とともに改善するか?
- 月の半分以上、気分の浮き沈みが続いているなら、PMDDや他の疾患の可能性もあります。
✅「周期にリンクしているか」を意識することで、受診時にも説明しやすくなります。
③ 重症度(症状の強さと継続性)
- 感情の起伏がコントロールできず、自分が自分でない感覚
- 食欲や睡眠に明らかな異常がある(過食・不眠・寝すぎ)
- 「消えたい」「いなくなりたい」と感じる瞬間がある
✅ このレベルの症状が毎月繰り返されるようなら、自己対処では限界です。
心療内科・婦人科など、女性のメンタルに理解のある医療機関の受診が推奨されます。
薬物療法や専門外来に相談すべきサイン
フェムケアやセルフケアで整う人もいれば、それだけではどうにもならない人もいます。
それは気合いや努力の問題ではなく、ホルモンや脳内物質の仕組みによるもの。
受診をおすすめしたいサイン
- サプリや食事改善を1〜2周期試しても改善が見られない
- 月経周期と関係なく、気分の波が激しくなってきた
- 過食・過眠・無気力が1週間以上続く
- 日常生活に大きな支障がある(遅刻・欠勤・家事放棄など)
このような状態では、漢方薬・低用量ピル・SSRI(抗うつ薬)などの医学的介入が効果的なケースも多くあります。
✅ PMSやPMDDに特化した婦人科・心療内科の「月経関連メンタル外来」なども各地に増えてきています。
「今のつらさが“治療の対象”になることを知らなかった」という声も多いので、一度調べてみるだけでも気持ちがラクになることがあります。
自己判断でやりがちなNG
体調不良に慣れてしまっていると、間違った対処法や放置によって症状がこじれてしまうこともあります。
以下は、PMS対策で陥りやすいNGパターンです。
NG① 気分を上げようと無理に予定を詰め込む
- 外出・飲み会・運動などを増やして気を紛らわせようとする
→ 逆に疲れがたまって悪化。自律神経も乱れやすくなります。
NG② 食べることでメンタルをコントロールしようとする
- 甘いもの・カフェイン・お酒などをその場しのぎで多用する
→ 一時的な高揚感のあとに強い反動(落ち込み・後悔)がきます。
NG③ 「わたしだけが弱い」と思い込む
- 他人と比べて「もっと大変な人もいる」と自己否定
→ 不調を放置して悪循環から抜け出せなくなる要因に。
✅ PMSやPMDDは、性格や精神力の問題ではなく「医学的な状態」。
だからこそ、自分を責める必要はまったくありません。
まとめ
セルフケアはとても大切。でも、それだけで何もかも解決できるわけではないのが現実です。
受診を「最後の手段」ではなく、「ひとつの選択肢」として持っておくこと。それが、自分の心と体を大事にする第一歩になります。
今回のポイントは以下の通りです。
- 「生活への影響」「症状の期間と重さ」で受診の目安をチェックできる
- セルフケアが効かないと感じたら、医療の選択肢を検討する勇気を持ってほしい
- 自己流対処でこじらせないように、「今の自分に本当に必要なケア」を見極めることが大事
✅ フェムケアとは、「我慢する力」ではなく「助けを求める力」でもあります。
今のあなたの状態は、そのまま相談していいレベルかもしれません。まずは、安心できる情報にアクセスすることから始めてみてください。
参考情報・出典
本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。
日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」
https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4
厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html
MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms
日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」
https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/
関連記事:生理不順で病院に行くべき期間
✅「フェムケアの部屋」では、LINEでPMSや体調の不安に寄り添う情報を配信中。
「誰にも相談できない」を、そっと手放す場所にしませんか?
公式LINEはこちらから登録
Q&A(よくある質問)
PMSやフェムケアについて話すと、よく出てくるのが「これってどうなんですか?」という具体的な疑問。
ネットには情報が溢れていますが、正反対のことが書いてあることも多くて、余計に迷ってしまうこともありますよね。
ここでは、私自身がこれまでの活動や発信の中でよく聞かれる質問に、生活者の視点+専門情報に基づいたバランスのある回答でお答えします。
サプリは必要?食事で足りる?
答え:基本は「食事から」。でも、足りないときはサプリを補助的に使うのもアリです。
PMSの改善に役立つとされる、ビタミンB6・マグネシウム・鉄分・カルシウムなどは、普段の食事から意識的に摂ることでかなり補える栄養素です。
たとえば…
- ビタミンB6 → さつまいも、鶏むね肉、バナナ
- マグネシウム → ほうれん草、海藻、ナッツ類
- 鉄分 → あさり、小松菜、納豆、レバー
とはいえ、「毎日完璧に摂れるか?」といわれると、正直ハードルが高い日もあります。
特に、仕事や育児が忙しくて食事バランスが乱れがちな方、ストレスやカフェインで栄養を消耗しやすい方は、サプリが心強い味方になることも。
✅ 選ぶポイントは、「単体で大量摂取するよりも、複数の栄養素をバランスよく含むサプリ」を選ぶこと。
そして、「まずは2周期試してみて、効果を実感できるか」で判断するのがおすすめです。
カフェインはどこまでOK?
答え:PMS期はなるべく減らす。でも「完全にゼロ」にしなくても大丈夫です。
カフェインは、交感神経を刺激して一時的に気分を上げたり集中力を高めたりしてくれる働きがあります。
でも、生理前はすでに自律神経が乱れやすく、カフェインの刺激が逆効果になることも。
具体的には…
- イライラ・緊張感・焦燥感が強くなる
- 眠りが浅くなり、翌日の疲労感が悪化
- マグネシウムや鉄の吸収を妨げてしまうことも
では、全カフェインNGか?というと、そういうわけではありません。
✅ たとえば…
- 午前中の1杯のコーヒーはOK(午後以降はノンカフェインに切り替える)
- 紅茶や緑茶よりも、ルイボスティーやハーブティーに置き換えてみる
- 「飲みたいときは飲む」代わりに、他の栄養バランスを意識する
大事なのは、“減らす”ことより、“コントロールできている”感覚を持つこと。
それだけで、PMS中の不安や焦りもずっと軽くなります。
生理前の強い甘いもの欲はどう抑える?
答え:「抑える」より「選びなおす」。代替え戦略でコントロールしやすくなります。
生理前の強烈な甘いもの欲求。これは意思の弱さではなく、ホルモンバランスによる自然な反応です。
生理前には、以下のような体内の変化が起きています:
- セロトニンが減る → 気分が不安定に
- 血糖値が乱れやすくなる → 脳が糖を欲しがる
- 睡眠の質が下がる → 疲れから過食に
この状態で「我慢する」「甘いものを悪」と捉えると、かえって反動で暴食しやすくなります。
✅ そこで有効なのが、「置き換え戦略」です。
- チョコレート → カカオ70%以上のチョコ+くるみ
- ケーキ → バナナ+無糖ヨーグルト+シナモン
- ドリンク → 豆乳+甘酒 or ノンカフェインラテ
さらに、甘いものを「食べたい」と感じるタイミングが、実は眠気や不安のサインだったというケースも。
- 眠気が強い → 5分の仮眠 or ストレッチ
- イライラしている → 温感パッド or アロマで一息
- 口さみしい → ガムや歯磨きで「食べたい」欲求をリセット
甘いものをゼロにしなくてもいい。
「自分で選びなおせた」という経験が、心の安心感にもつながります。
まとめ
PMSと食事、フェムケアに関する疑問は尽きませんが、どれも“正解”が1つではないというのが本当のところです。
今回のQ&Aでお伝えしたかったのは、「自分の状態に合った選択をしていい」ということ。
- サプリは補助的に。基本は食事でOK。
- カフェインは“ゼロ”より“上手に付き合う”
- 甘いもの欲は我慢より置換で対処できる
✅ 大切なのは、体の声を聞きながら、少しずつ整えていく感覚。
自分に合う方法を探すプロセスも、立派なフェムケアです。
参考情報・出典
本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。
日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」
https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4
厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html
日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」
https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/
関連記事:PMSイライラ解消法完全ガイド
✅ 「フェムケアの部屋」では、LINEでPMS・セルフケア・食生活のヒントを配信中。
1人で抱えないケアの形、見つけてみませんか?
公式LINEはこちらから登録
まとめ(PMS 食べ物とフェムテックの併走で続ける)
PMSの不調をなんとかしたい。
でも、がんばりすぎると続かないし、自分を責めてしまうこともある。
そんな経験を、私も何度もくり返してきました。
だからこそ、PMSケアには「食事の選択肢」と「フェムテックによる見える化」の両方を無理なく取り入れることが、本当に効果的だと感じています。
ここでは、要点の振り返りと、1か月後に自分を見直すための視点をお届けします。
読むだけで終わらせないために、「続けるための地図」として使ってください。
要点の振り返りと次の一歩
これまでの記事で紹介してきた内容を、以下の3つの柱にまとめます。
1. 食べ物で整える:「我慢」より「選択肢を持つ」
- 生理前はホルモンや血糖値の影響で甘いものが欲しくなるのは自然な反応
- 「控える」ではなく、「置き換える」発想でOK
- 食事記録と感情をリンクさせて、自分のパターンを知ることが第一歩
✅ 甘いものをやめるより、「満たされる食べ方を知る」ことが、整える近道
2. フェムテックで可視化する:「つらい」を“予測可能”に変える
- トラッキングアプリやスマート体温計で、PMSのタイミングを“見える化”
- 温活やリラクゼーショングッズで、衝動的な食欲を落ち着かせる
- 睡眠・体温・気分など、“数字と感覚”の両方で把握できるようにする
✅ 記録ができると、「また来たな」と受け入れられる余裕が生まれる
3. 自分軸で選ぶ:フェムケア=“わたしのケア”を見つけること
- トラッキング重視、温活中心、併用型…ライフスタイルに合わせて選んでいい
- 合わなかったらやめてもいい。変えてもいい。戻ってもいい
- 大切なのは、「やらなきゃ」より「やりたい」に近づくこと
✅ フェムケアは、自分の暮らしに“ちょうどよく寄り添う存在”であってほしい
1か月後に見直す評価指標
「結局、やってみてどうだった?」を振り返る時間を1か月後に必ずとることで、フェムケアは“習慣”に変わっていきます。
以下の5つの視点を、スマホのメモや手帳に残しておくのもおすすめです。
| 指標 | チェックポイント |
|---|---|
| ① 食欲の波 | 甘いもの・暴食への衝動が減った?リズムが分かるようになった? |
| ② 気分の波 | イライラ・落ち込みを事前に予測・対策できた? |
| ③ 睡眠と疲労感 | 寝つきやすさ・朝の目覚めは変わった? |
| ④ 選べた感覚 | ケアを「やらされている」→「自分で選んだ」に変わった? |
| ⑤ 続けられたこと | 1つでも続けられたことがある?それをどう感じた? |
✅ 「続けられなかったこと」ではなく、「できたことが1つでもあったか」を振り返ってみてください。
ケアとは、自分を肯定していくプロセスそのものです。
最後に:フェムケアは、“がんばり”ではなく“選びなおし”の連続
PMSも、感情の波も、毎月やってくるもの。
だからこそ、毎月ちょっとずつ“選びなおす”ことが、最大のケアだと思うんです。
- 今日の私は、どんな状態だろう?
- 今月は、何がちょっとラクだった?
- 来月は、どんなふうに整えてみよう?
そんなふうに、自分に問いかけられる感覚を育てていけたら、
フェムケアは“義務”から“相棒”に変わっていきます。
あなたの体にとって、「ちょうどいいケア」が、これからも見つかっていきますように。
参考情報・出典
本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。
日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」
https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4
厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html
MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms
順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html
関連記事:生理前不調を食事で改善する方法
✅ 「フェムケアの部屋」では、LINEでPMS・フェムテック・食事習慣にまつわるセルフケアのヒントをお届け中。
あなたの1歩が、誰かのケアのきっかけになるかもしれません。
公式LINEはこちらから登録