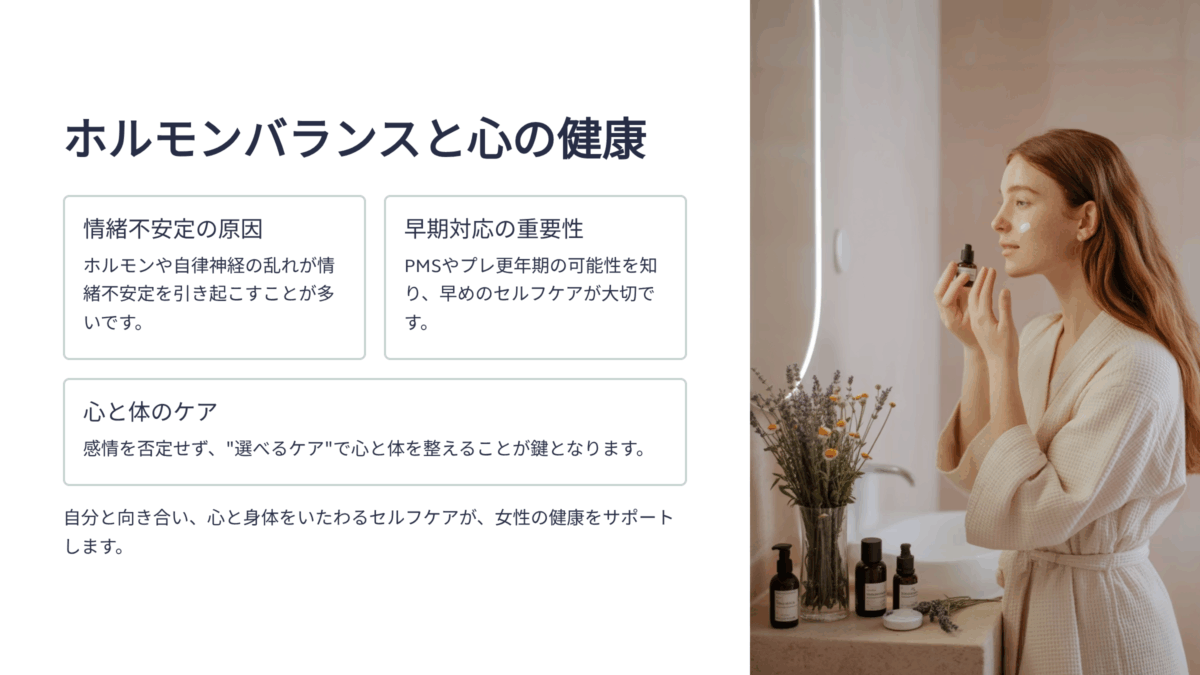なんだか涙が止まらない。気分が上がらない。そんな「情緒不安定」に悩むあなたへ。ホルモンの影響や心のサインを、等身大の体験から解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
情緒不安定ってどんな状態?【わかりやすく解説】
気づいたら急に涙が出てきたり、些細なことでイライラしたり。「私、どうしちゃったんだろう?」と戸惑ったことはありませんか?それはもしかしたら情緒不安定のサインかもしれません。この章では、「情緒不安定」とはそもそも何か、一時的な気分の落ち込みとどう違うのか、そして背景にある原因を女性の心と体のゆらぎという視点から解説します。
「情緒不安定」とは何か?医療用語との違い
まず押さえておきたいのが、「情緒不安定」は正式な医療用語ではないということです。精神科や心療内科では、症状に応じて「気分変調症」「不安障害」「境界性パーソナリティ障害」などの診断名がつくことがあります。でも、私たちが日常で使う「情緒不安定」は、もう少し広い意味を含んでいます。
たとえば、以下のような状態が該当します。
✅ ささいなことで涙が出る、怒りっぽくなる
✅ 気分の波が激しく、自分でもついていけない
✅ 理由もなく落ち込む・不安になる
✅ コントロールできない感情に振り回される
つまり、日常生活に支障が出るほど感情の波が大きくなる状態を、私たちは「情緒不安定」と感じているんです。
一時的な落ち込みと慢性的な不安定さの違い
誰にでも「なんとなく気分が落ちる日」はありますよね。疲れていたり、生理前だったり、原因がはっきりしていれば自然なもの。でも、それが長く続く・繰り返す・日常に影響するようなら、見過ごしていいサインではありません。
以下の表に、違いをまとめてみました。
| 分類 | 一時的な落ち込み | 慢性的な情緒不安定 |
|---|---|---|
| 継続期間 | 数時間〜数日 | 数週間〜数ヶ月以上 |
| 原因の明確さ | あり(例:失恋・疲労) | はっきりしないことが多い |
| コントロール可能性 | 時間とともに回復 | 自力で立て直しにくい |
| 生活への影響 | ほぼなし | 仕事・人間関係に支障 |
どちらが「良い・悪い」ではありません。ただ、慢性的な不安定さは“自分のせい”ではなく、体の仕組みや環境が関係していることも多いんです。
情緒不安定の背景にある主な原因とは?
実は、情緒不安定の背景には複数の要因が絡んでいることがほとんどです。
✅ ホルモンバランスの乱れ(特に月経前・排卵期・産後・更年期)
✅ 自律神経の乱れ(寝不足、ストレス、気温差など)
✅ 心の負荷(人間関係、将来への不安、自分を責めるクセ)
✅ 過去のトラウマや未解決の感情
特に女性は、ホルモンと自律神経の影響を受けやすい体のつくりをしています。PMS(月経前症候群)やPMDD(月経前不快気分障害)なども、情緒のゆらぎと深く関係しています。
だからこそ、「メンタルが弱いから」とか「自分の性格のせい」ではなく、体の声を見つめ直すことが何より大切なんです。
そしてこれは、私自身が遠回りしながらたどりついた実感でもあります。
つづく章では、私が24歳のときに実際に感じた“情緒不安定のリアル”を、体験ベースでお話ししていきます。きっと、あなたの気づきにつながるはずです。
24歳で感じた「情緒不安定」のリアル【体験談ベース】
「なんかうまくいかない」。それが続いたのは、社会人2年目、24歳のときでした。仕事は順調に見えて、見た目は元気。でも、心の中はずっと曇り空のようでした。この章では、そんな当時の私の実体験をもとに、情緒不安定が生活や人間関係にどう影響していたのか、リアルな視点でお伝えします。
感情がコントロールできなくなった日常
正直に言うと、ちょっとしたことで泣いてしまったり、誰かの一言に過剰に反応してしまう日が増えていきました。「自分でも訳がわからないけど、イライラする」「朝起きるとすでにしんどい」。そんな状態が続くと、自分の感情を自分で持て余すようになっていきます。
✅ 楽しみにしていた予定が、当日になると億劫になる
✅ 上司や友人の言葉に敏感に反応してしまう
✅ 反省しても、同じことでまた落ち込む
「もっとポジティブでいなきゃ」「迷惑かけちゃだめ」と思えば思うほど、自分を責めてしまっていました。
一見元気そうなのに、内側はぐちゃぐちゃだった
表面的には笑っていたし、SNSではキラキラした投稿もしていました。でも実際は、帰宅後に泣いていたり、週末はベッドから出られなかったり。“元気そうに見えるからこそ、誰にも相談できなかった”というのが一番つらかったです。
特に、周囲が結婚・転職・起業と人生のステップを踏んでいるように見えたあの頃、自分だけ取り残されているような焦りも感じていました。
あのときの私は、自分の感情に名前がつけられず、「全部自分の問題」と思い込んでいました。今振り返ると、それが一番危うかったなと思います。
周囲との関係に影響…自己嫌悪と孤立感
情緒が不安定になると、人との関係にも影響が出てきます。友達の誘いを断ることが増えたり、職場でのちょっとしたやりとりで落ち込んだり。何より、家族や恋人など、一番近い人にほどイライラをぶつけてしまうんですよね。
そのたびに「また嫌なこと言っちゃった」「どうしてあんな態度を取ったんだろう」と、自己嫌悪が積み重なっていく。そして、ますます人と距離を取るようになって、孤独感だけが深まっていきました。
心が不安定なときって、「誰かにそばにいてほしい」と思う反面、「これ以上人を傷つけたくない」という気持ちもあって。“誰にも頼れない自分”に気づいてしまう瞬間が、一番しんどかった記憶があります。
この頃の私に今声をかけられるなら、「それ、あなただけじゃないよ」って言いたいです。情緒不安定は、あなたが壊れている証拠ではなく、ケアが必要なサイン。そう思えるようになるまでに少し時間はかかりましたが、だからこそ、次の章では私がどうやってその状態から抜け出すヒントを見つけたのかをお話ししていきます。
自分の情緒不安定に気づくサイン【早めの対処が鍵】
「私、最近ずっと気分が不安定かも」と思ったとき、それが一時的なものなのか、もっと深いところで起きている変化なのかを見極めるのはとても大切です。特に女性の体はホルモンの影響を受けやすく、心と体が連動してゆらぎやすいもの。ここでは、私自身の体験からわかった“気づきのサイン”を紹介します。これを知っておくことで、セルフケアの一歩が早く踏み出せるはずです。
生理周期との関係を記録してみてわかったこと
まずやってみてほしいのが、生理周期と気分の変化を記録することです。私も最初はアプリにぽちぽち入力するくらいでしたが、思いがけない発見がありました。
✅ 生理前になると、イライラや落ち込みが強くなる
✅ 排卵期に不安感やソワソワ感が出る
✅ 生理後はスッと気持ちが軽くなる
これを記録し続けていたら、「この気持ちは私のせいじゃない。ホルモンの変化によるものかもしれない」と気づけたんです。これはすごく大きな転換点でした。
PMSやPMDDの可能性もあるので、周期的な感情のゆらぎにはしっかり目を向けてみてください。
身体症状(頭痛・だるさ・眠気)にも注目
情緒の乱れって、実は体のサインとセットで出ることが多いです。私の場合、こんな感じでした。
✅ 眠っても寝足りないほどの眠気
✅ 脳がモヤモヤするような頭痛
✅ 朝からずっとだるくて、何もしたくない
これらは単なる疲れではなく、自律神経の乱れが関係している可能性があります。特に、生理前やストレスが重なっているときに出やすいです。
自分の体調に敏感になることで、「今日はちょっと無理しないでおこう」という判断がしやすくなります。これも立派なフェムケアの一環なんです。
「なんでもないのに涙が出る」状態に要注意
私が本格的に「これは放っておけない」と思ったのは、特に理由もなく涙が出るようになったときでした。感情がふくらみすぎて、自分で抑えられなくなる。こんなときって、「甘えだ」「わがままだ」と思われたくなくて、誰にも言えないんですよね。
でも、これは体と心が出しているはっきりとしたSOS。
「泣くほどのことじゃない」なんて思わなくていいんです。
むしろ、感情が外に出せているだけで、まだ健全。
でもそのままにしておくと、無気力やうつっぽさに進行してしまうリスクもあるからこそ、早めに気づいて、対処できる選択肢を知っておくことが大事です。
心のサインは、放っておくとどんどん鈍くなっていきます。だからこそ、「あれ、なんかおかしいな」と思った時点で立ち止まることが、自分を守る第一歩になる。
次の章では、私が実際に試して効果を感じたセルフケアの方法を、具体的にお伝えしていきますね。
私が実践した情緒不安定の対処法【すぐできるセルフケア】
「情緒不安定かもしれない」と気づいたあとの行動って、とても大事です。でも、いきなり病院に行くのはハードルが高いし、誰かに打ち明けるのも勇気がいる。だから私は、まず“自分でできる小さなケア”から始めました。この章では、実際に私が試してきた中で「これは助けられた」と思えた3つのセルフケアをご紹介します。
書き出す習慣:感情を「見える化」する方法
まず私が始めたのが、感情をノートに書き出すことでした。毎日じゃなくても大丈夫。モヤっとしたとき、イライラしたとき、ただ頭の中でぐるぐるしている感情を言葉にして外に出すだけで、かなりスッキリします。
ポイントは以下の通りです。
✅「正しい文章」で書こうとしない
✅ 頭に浮かんだことを、そのまま書く(例:「なんか泣きたい」でもOK)
✅ 最後にひとこと、「今日もよくがんばったね」と自分に声をかける
感情が可視化されることで、「こんな気持ちがあったんだ」と自分に気づけるようになります。これだけでも、自分を客観視する力が少しずつ育っていくんです。
呼吸・瞑想・アロマなど、自律神経を整える習慣
情緒不安定の大きな要因のひとつが自律神経の乱れ。私は特に夜になると不安感が増すタイプだったので、副交感神経を優位にする“整える時間”を意識して取り入れてみました。
試してよかったのがこちら。
✅ 4秒吸って8秒吐く深呼吸(横になってやると◎)
✅ アプリを使ったガイド付き瞑想(5分でも効果あり)
✅ ラベンダーやベルガモットのアロマを寝室に香らせる
「呼吸なんて地味すぎる」と思うかもしれませんが、実はこれがかなり効きます。体がゆるめば、心も自然とゆるむ。フェムケアも、こういう“地味に見えるケア”の積み重ねなんですよね。
人と話すタイミングと、ひとりになる勇気のバランス
情緒が不安定なとき、誰かに話すことが救いになる場合もあれば、ひとりで静かに過ごすほうが安心できることもある。私はその時々で、意識的に“どちらを選ぶか”を考えるようにしていました。
たとえば、
✅ 「ただ話を聞いてもらいたい」と思える友達に連絡する
✅ 自分にとって安全な人以外とは距離を置く
✅ あえてスマホをオフにして、感情の波が落ち着くまでひとりで過ごす
ひとりになること=孤独ではなく、「今の私に必要なスペースを与えること」だと考えるようにしたら、すごく楽になりました。
セルフケアは、特別な道具もスキルもいりません。“いまの自分”に気づいて、そっと整えることができれば、それだけで十分です。
次の章では、「これって病院に行くレベル?」と迷ったとき、どうやって判断し、実際に医療機関を頼ったかについてお話ししますね。ハードルが下がるきっかけになれば嬉しいです。
医療機関を頼ったときのこと【受診ハードルを下げるために】
「病院に行くほどじゃない気がする」「どう説明すればいいか分からない」――そう思って、受診をためらう方はとても多いです。私もそうでした。でもある日、「このままでは自分を嫌いになりそう」と感じた瞬間があって、勇気を出して一歩踏み出すことにしました。この章では、情緒不安定な状態で医療機関を頼った私の実体験を通じて、迷っている方の背中をそっと押せたらと思います。
婦人科・心療内科どちらを選べばいい?
情緒の不安定さを感じたとき、最初に迷ったのが「何科に行けばいいの?」ということ。
実はこれ、多くの方がつまずくポイントです。
生理周期やPMSとの関連が疑われる場合は、まずは婦人科がおすすめ。
私も最初は「ホルモンの乱れがあるかも」と思い、婦人科で相談しました。
一方で、気分の落ち込みが続いて生活に支障が出ている場合は、心療内科やメンタルクリニックが適切です。
迷ったときは、
✅ 女性専門のクリニック(婦人科+心療内科)
✅ かかりつけ医や地域の相談窓口でのヒアリング
こういった窓口を活用するのもひとつの方法です。
「ここで合ってるかな?」より、「話してみよう」の気持ちを優先して大丈夫です。
カウンセリングで得られた気づきと安心感
私は心療内科の紹介で、臨床心理士さんによるカウンセリングも受けました。正直、最初は「人に話して何か変わるのかな?」と思っていました。でも、実際に話してみると、それだけで心がふっと軽くなる瞬間があったんです。
カウンセリングのなかで教えてもらったのは、
✅ 感情は“良い・悪い”でジャッジしなくていいこと
✅ 自分の思考のクセ(たとえば完璧主義)に気づくこと
✅ 「頑張らない日」をつくってもいいという許し
誰かに受け止めてもらえるだけで、自分を責めるスピードがゆっくりになる。
それは、言葉にしないと得られなかった感覚でした。
薬に頼る?頼らない?選択肢を知ることの大切さ
受診するときに心配なのが、「薬を出されるのかな?」という点ですよね。
私自身も、「飲み始めたらやめられないんじゃないか」と不安でした。
でも実際は、無理に薬をすすめられることは一切なく、症状に応じて「どうしたいか」を丁寧に聞いてもらえました。
もし薬を使うとしても、
✅ 自律神経を整える漢方
✅ 一時的な睡眠補助
✅ 不安感を和らげる低用量の抗不安薬
など、必要最低限で、段階的な選択肢があることを知れたのも安心材料になりました。
重要なのは、「薬=最後の手段」ではなく、「今の自分をサポートしてくれる選択肢のひとつ」として捉えること。
“頼る”ことと“依存する”ことは違うんです。
「病院に行く」って、何か重いことのように感じるけれど、
本当に大変になる前に“今の自分を知るために行く”と思えば、ぐっと気持ちが楽になります。
次の章では、情緒不安定とホルモンの関係について、PMSやプレ更年期とのつながりも含めて詳しく見ていきましょう。
自分の体の仕組みを知ることは、安心感にもつながりますよ。
情緒不安定とPMS・プレ更年期の関係【女性ホルモンとの向き合い方】
情緒不安定な状態が続くと、「私ってメンタルが弱いのかな」と思ってしまいがちですが、それはホルモンバランスの変化が影響している可能性も。特に女性は、月経・妊娠・出産・更年期と、一生を通じてホルモンの波にさらされているんです。この章では、PMSやプレ更年期と情緒のゆらぎの関係を、わかりやすく解説します。まずは、「心の波」が体の仕組みと深くつながっていることを知ることから始めてみませんか?
PMS・PMDDとの違いと見極め方
生理前になると気分が落ち込む、イライラが止まらない、涙が止まらない――
そんなとき、真っ先に疑うべきなのがPMS(月経前症候群)。
さらに、感情の波が強く日常生活に支障をきたすレベルになると、PMDD(月経前不快気分障害)の可能性もあります。
| 症状 | PMS | PMDD |
|---|---|---|
| 主な症状 | イライラ、不安、疲労感、眠気など | 強い怒り、絶望感、自己否定、涙が止まらないなど |
| 日常生活への影響 | 軽度〜中等度 | 重度(仕事・人間関係に支障が出る) |
| 対処方法 | 生活習慣の見直し、漢方など | 医療機関での相談・治療が推奨される |
ポイントは、「生理が始まると症状が軽くなるかどうか」。
私はこれに気づくまでかなり時間がかかりました。
周期的に心がしんどくなる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。
20代後半から増える「ゆらぎ」のサインとは?
「更年期って、40代以降の話でしょ?」と思っていませんか?
実は、プレ更年期(更年期の準備段階)と呼ばれる体の変化は、早い人で20代後半から始まることもあるんです。
たとえば、
✅ 生理周期が乱れがちになる
✅ 月経の量や日数に変化がある
✅ 気分の落ち込み・焦燥感・不眠が強くなる
などのサインが見られます。
私も28歳のとき、「なんか今までと違うな」と感じるタイミングがありました。
病気ではなくても、ホルモンのゆらぎは確実に訪れる。それを知っているかどうかで、対応の仕方が変わります。
食事・睡眠・運動の整え方がカギになる
情緒の安定には、ホルモンと自律神経を整える生活習慣が欠かせません。
ここでは、私が実際に取り入れてよかった基本のセルフケアを紹介します。
✅ 食事:鉄分・ビタミンB群・マグネシウムを意識(豆類、魚、ナッツ類など)
✅ 睡眠:夜22時以降のスマホは手放し、眠る前にアロマや深呼吸でクールダウン
✅ 運動:週に2〜3回、20分程度のウォーキングやストレッチから始める
派手なケアよりも、日々の積み重ねがホルモンを安定させる土台になります。
「これくらいで変わるのかな?」と思っても、続けることで確実に変化は見えてきます。
ホルモンと情緒の関係は、自分を責めないための“根拠”をくれるもの。
女性としての体の仕組みを知ることは、よりよく生きるための前向きな知識です。
次の章では、このゆらぎの時期とどう向き合っていくか――。自分を責めないためのマインドセットや“これから”の選択肢についてお話しします。
自分の「情緒」とうまく付き合うために【これからの選択肢】
情緒不安定は「治すべきもの」ではなく、付き合い方を知ることが大切なサインだと私は思っています。心の波は誰にでもあるし、女性であればホルモンによってそのリズムはもっと複雑になります。でも、それを知り、理解し、選べるようになることが、これからのフェムケアの本質ではないでしょうか。この章では、感情と付き合いながら心地よく生きるための考え方と習慣のヒントをお届けします。
感情に振り回されないためのマインドセット
私がいちばん変わったのは、「感情をコントロールしなきゃ」と思うのをやめたことでした。
感情って、本当は“感じていいもの”なんですよね。
それを無理に押さえ込もうとすると、心にも体にも無理がかかる。
大切なのは、
✅ 感情をジャッジしない(怒っても、泣いてもOK)
✅ 「なんでこうなるの?」ではなく「どうしたい?」に切り替える
✅ 完璧じゃなくて“だいたいOK”でいいと思うこと
このマインドにシフトしてから、気持ちの波が来ても「今はそういう時期なんだ」と余白を持って受け止められるようになりました。
頑張りすぎず、自分にOKを出す習慣
情緒が不安定なときほど、「もっと頑張らなきゃ」「迷惑かけちゃダメ」と自分を追い込んでしまいがち。でも、私が実感したのは、頑張らないことこそ、回復の入り口になるということ。
✅ 洗濯を1日サボってもいい
✅ 仕事を少しセーブしてもいい
✅ 友達の誘いを断っても、罪悪感を感じなくていい
自分に小さな「OK」を出せるようになると、心の中に安心できる“自分の居場所”ができるんです。
「人にどう見られるか」ではなく、「自分がどう感じているか」を軸にしていい。
それが、フェムケアの第一歩だと私は思っています。
情緒ケア=ライフケア。ケアは“選べる”時代へ
フェムケアという言葉が広がってきた今、ようやく「心と体に向き合うことは当たり前」という空気ができつつあります。
でも本当は、もっとシンプルでいいんです。
情緒ケア=その日を気持ちよく過ごすための工夫。
それは、体調管理と同じくらい日常にあっていい。
今は、セルフケアアイテムも情報もたくさんあります。
でも大事なのは、「何を使うか」よりも「どんな自分でいたいか」を選べること。
✅ 今日は泣いてもいい
✅ 今日は香りに頼ってもいい
✅ 今日は誰かに頼ってもいい
そうやって、自分のために“選ぶ”ことができる人が、これからのフェムケアを支えていくんだと思います。
情緒不安定は、弱さではなく、感受性の高さ。
そして、もっと丁寧に生きたいというあなたからのサインです。
「なんでこんなにしんどいんだろう」と思ったら、それは変化のはじまりかもしれません。
あなたの1日が、すこしだけでも穏やかになりますように。
それが、フェムケアを届ける私たちの願いです。