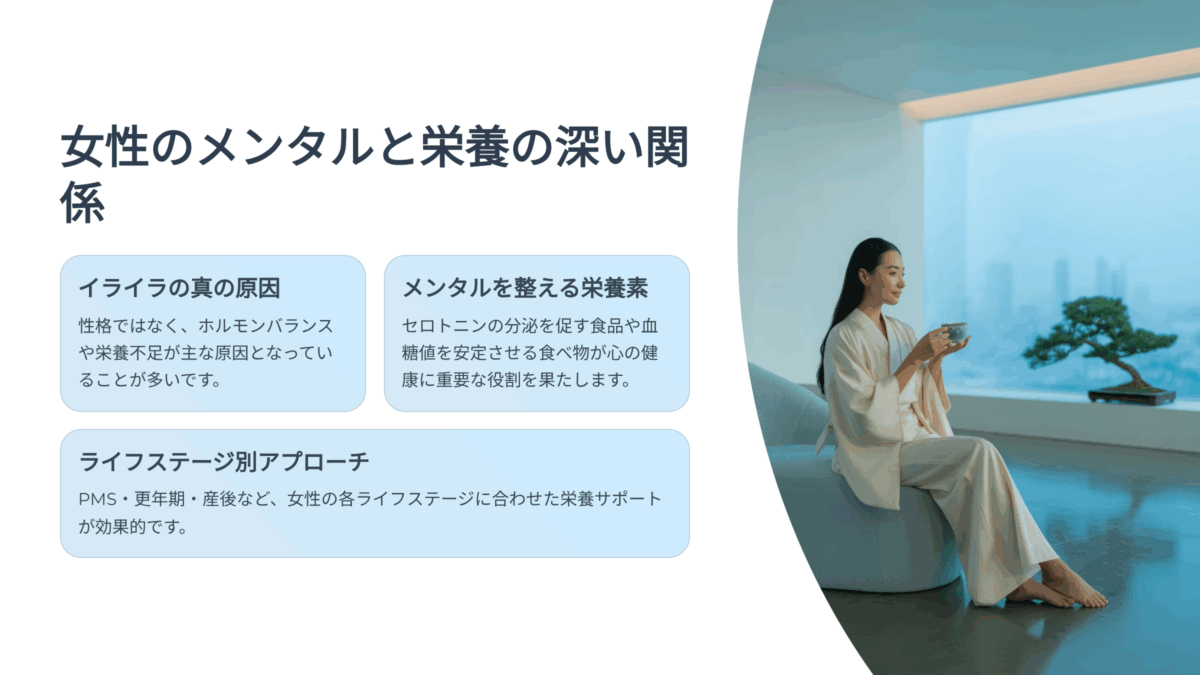なんだか最近イライラしやすい…それ、性格じゃなくて「食べもの」が関係しているかもしれません。ホルモンや栄養との意外なつながり、実体験をもとにわかりやすく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
「イライラしがちな私」とやさしく向き合うための第一歩
忙しい日々の中で、ふとしたことでイライラしてしまう。そんな自分に「なんでこんなことで…」と落ち込んだ経験、ありませんか?
私もずっとその繰り返しでした。でも、その感情の背景に“体”からのサインが隠れていると気づいてから、少しずつ自分へのまなざしが変わっていったんです。
この章では、ホルモンや食事とメンタルの関係をやさしく紐解きながら、イライラする自分を責めるのではなく、「理解する」ための視点をお届けします。
感情の波に飲まれやすい時期って?ホルモンとの関係
「生理前になると、人が変わったみたいに怒りっぽくなる」
これは気の持ちようでも性格のせいでもなく、ホルモンバランスの変化が原因です。特に黄体期(排卵後〜生理前)は、エストロゲンが急激に減少し、心の安定に必要なセロトニンも低下します。
この時期は、心も体も“揺らぎやすい”。
だからこそ、無理や我慢で乗り切ろうとせず、「あ、今ゆらいでる時期だな」って気づくだけでも、心の構え方が変わってくるんです。
✅ホルモンバランスが感情に与える影響
| ホルモンの状態 | 影響する感情 | 体の反応例 |
|---|---|---|
| エストロゲン低下 | 不安・落ち込み | 頭痛・むくみ・眠気 |
| プロゲステロン上昇 | イライラ・緊張 | 乳房の張り・食欲増加 |
「自分をコントロールできない…」って感じるときほど、体のリズムを見直すサインかもしれません。
「私だけじゃなかった」——女性の7割が感じるイライラの正体
ある調査では、7割以上の女性が「生理前にイライラする」と感じていると答えています。
それなのに、私たちは「我慢しなきゃ」「そんなことで怒っちゃだめ」と、自分にブレーキをかけ続けている。これってすごく不自然なことだと思いませんか?
私自身も、家族や仕事に八つ当たりしてしまっては自己嫌悪…という日々が続いていました。
でも、同じように悩んでいる人がたくさんいると知ったとき、少しだけ心が軽くなったんです。
イライラの背景には、以下のような要因が複雑に絡み合っています。
- ホルモンバランスの変動(特にPMS)
- 栄養不足や食習慣の乱れ
- 睡眠の質・量の低下
- 自律神経の乱れ(ストレス)
- 無意識の自己否定感や焦り
この中でも、“食べるもの”は私たちの感情に意外と大きな影響を与えているんです。
食事がメンタルに影響するって本当?
「なんか最近イライラするなあ」と思ったとき、つい甘いものやパンに手が伸びていませんか?
私もそうでした。疲れているときほど、ジャンクなものが欲しくなって、そして食べた後に罪悪感…。
でも実は、食事はメンタルケアの“入り口”になり得るんです。
感情を整えるホルモンや神経伝達物質は、食事から摂れる栄養素を材料にしています。
✅感情と深く関わる栄養素と働き
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材 |
|---|---|---|
| トリプトファン | セロトニンの材料 | 納豆・豆腐・バナナ・卵 |
| ビタミンB6 | 神経伝達をサポート | 鶏むね肉・まぐろ・ピスタチオ |
| マグネシウム | 自律神経を整える | ほうれん草・玄米・ナッツ類 |
| 鉄分 | 脳への酸素供給 | レバー・赤身肉・ひじき |
私もまずは、「朝食に卵を加える」ことから始めました。
たったそれだけの変化でも、「あれ?いつもより気持ちが穏やかかも」と感じる日が増えていったんです。
食事は、気合いも根性もいらない“やさしいケア”のひとつ。
だからこそ、自分を責める前に「何を食べてるか」を見直すことが、すごく本質的なアプローチになると私は思っています。
次の章では、具体的にどんな食材がイライラ軽減につながるかを詳しく紹介していきますね。
私が試して「これは効果あった」と感じたものも、体験ベースでシェアしていきます。
イライラしにくい体をつくる栄養素と食材【一覧で解説】
イライラしやすくなる原因にはさまざまありますが、そのひとつが「脳内ホルモンの材料不足」や「血糖値の乱高下」など、体の内側からのSOSです。
この章では、メンタルを穏やかに保つために意識したい栄養素や食材について、一覧でわかりやすく解説していきます。
「なんとなく不機嫌」「ちょっとしたことで爆発しそう」――そんな自分に悩んでいた私が、食事から変えてみて実感した変化も交えながらお届けしますね。
セロトニンを増やす!トリプトファンを含む食べ物
感情の安定に深く関わる“幸せホルモン”と呼ばれるセロトニン。
このセロトニンは、トリプトファンというアミノ酸から体内でつくられます。
でもここで大切なのが、「トリプトファンは体の中ではつくれない」ということ。
つまり、毎日の食事から意識して摂る必要があるんです。
✅トリプトファンを多く含む代表的な食材
| 食材 | 手軽さ | ひと言メモ |
|---|---|---|
| 納豆 | ◎ | 発酵食品で腸内環境にも◎ |
| バナナ | ◎ | 小腹がすいたときのおやつに |
| 牛乳・チーズ | ◯ | 朝食やおやつに取り入れやすい |
| 豆腐・味噌汁 | ◎ | 和食に自然になじむ |
| 鶏むね肉 | △ | ビタミンB6も豊富で効率的 |
特に私のおすすめは、「朝にバナナ+豆乳」。
忙しい朝でも、これだけでセロトニンの材料がしっかり摂れるので、気持ちのスタートがまるで違ってきます。
血糖値の急上昇を防ぐ、低GI食品のすすめ
「急にイライラして、急に落ち込む」――そんな情緒の乱れがあるとき、実は血糖値のジェットコースターが起きている可能性があります。
甘いものや精製された炭水化物(白米・白パンなど)は、血糖値を一気に上げたあと、急降下させることが。その落差が、心の不安定さにつながっているんです。
だからこそ、ポイントは「ゆるやかに上がって、ゆるやかに下がる食事」。
✅低GI食品の一例
| カテゴリー | 食材例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 主食 | 玄米・オートミール・全粒粉パン | 食物繊維が多く腹持ちも良い |
| 野菜 | ブロッコリー・にんじん・ほうれん草 | 血糖値を緩やかにする食物繊維が豊富 |
| タンパク質 | 卵・大豆製品・ナッツ類 | 糖質の吸収をゆるやかにする |
ちなみに私は、おにぎりを玄米に変えただけで、午後の眠気やイライラが減りました。
小さな選択の積み重ねで、こんなにも体は変わるんだなと実感しています。
鉄分・マグネシウム不足が情緒不安定を引き起こす?
「なんとなくやる気が出ない」「すぐ涙が出る」――これ、もしかしたら鉄分やマグネシウムが不足しているサインかもしれません。
特に鉄分は、脳に酸素を運ぶ働きがある栄養素。
不足すると、集中力や判断力、感情のコントロール力も低下すると言われています。
マグネシウムも同様に、自律神経の安定に欠かせないミネラル。
でも現代女性は、どちらも圧倒的に不足しがちなんです。
✅不足しやすい栄養素と補給しやすい食材
| 栄養素 | 不足のサイン | 食材例 |
|---|---|---|
| 鉄分 | めまい・疲れやすい・集中できない | レバー・ひじき・あさり・赤身肉 |
| マグネシウム | イライラ・筋肉のピクピク・不眠 | ほうれん草・アーモンド・玄米 |
私も鉄分不足でふらつくことが多く、週に1〜2回、あさりのお味噌汁を意識的に取り入れました。
それだけでも「今日、気分がどっしりしてるな」と感じられるようになってきたんです。
コンビニでも買える「メンタルにやさしい食べ物」リスト
「わかってはいるけど、忙しくてちゃんと作れない…」
そんな方も安心してください。コンビニでも買える選択肢って、意外と多いんです。
✅迷ったらコレ!コンビニで手に入る“心を整える食べ物”
- ゆで卵(タンパク質&ビタミンB群)
- サラダチキン(トリプトファン)
- 素焼きナッツ(マグネシウム)
- 納豆巻き or 玄米おにぎり(食物繊維+鉄分)
- 豆乳・ヨーグルト(セロトニンの材料)
- バナナ(トリプトファン+糖の吸収もゆるやか)
「お昼ごはんをサラダチキン+バナナ+玄米おにぎりに変えてみる」
そんな小さな選択からでも、メンタルの安定を感じられる人は多いんです。
イライラしやすい日があるのは、ダメなことじゃありません。
でも、食べるものを変えることで、イライラしにくい“土台の体”を育てていくことはできる。
それを知ったとき、私は初めて「自分を責める必要なんてなかった」と思えました。
次の章では、実際に食事を見直してどう変わったのか、私自身のビフォーアフターをリアルにお伝えします。続けやすいヒントもたっぷり詰め込みますね。
実録:食べ物を変えて感じた“心の変化”と体のサイン
食べ物でイライラが変わるって、本当なの?って思いますよね。
私もそうでした。だけど、ほんの少しの“置き換え”や“減らす工夫”だけで、自分の心にゆとりが生まれていったんです。
この章では、私自身が日々の中で感じたリアルな変化をお話しします。
専門知識よりも体感ベースで伝えるからこそ届くことがあると信じて。
「どうせ私なんて変わらない」と感じている方にこそ、読んでほしいです。
朝食を変えたら、朝のイライラが激減した話
以前の私は、朝がとにかく苦手でした。
バタバタしてるのに頭は働かず、家族の些細な言動にもピリピリ…。
でもある日、読んだ本に「朝食でセロトニンの材料を摂ると、感情の安定につながる」と書かれていたのをきっかけに、食べるものを変えてみたんです。
✅Before:パンとコーヒーだけ
✅After:バナナ+豆乳+ゆで卵 or 味噌汁+納豆ごはん
この朝ごはんに変えただけで、ほんの数日で「あれ?なんか朝イライラしない」という変化が。
セロトニンの材料であるトリプトファンやビタミンB群を朝にしっかり摂ることで、日中の気分が安定しやすくなったのを実感しました。
何より、「これを食べている私ってちょっといい感じ」って思えるだけでも、朝の空気がまるで違ってきます。
甘いものの摂りすぎをやめたら、自分を責めなくなった
気分が沈んでいるときって、どうしても甘いものに手が伸びがちですよね。
私もチョコやクッキーが“心の支え”のようになっていました。
でも、食べたあとに必ずやってくる罪悪感。
「また食べすぎちゃった…」「なんで我慢できないの?」って、自分を責めるループにどっぷり。
そんなとき、ある管理栄養士の方に言われた一言が響きました。
「食べすぎるのは、体がエネルギー不足のサインかもしれませんよ」って。
たしかに、食事のバランスが悪い日ほど、甘いものがやめられなかったんです。
そこで私は、おやつにナッツや甘酒、ドライフルーツを取り入れたり、夕方前にたんぱく質の多い間食(チーズやサラダチキン)を挟むようにしました。
すると、自然とチョコに手が伸びる頻度が減り、「今日、甘いものなくても平気だったな」って思える日が増えたんです。
自分を責めることが少なくなった分、心にも余白が生まれました。
やめたもの/取り入れたもの一覧【ビフォーアフター表付き】
「何から始めたらいいかわからない」という声もよく聞きます。
そこで、私が実際にやめたこと・取り入れたことをまとめたビフォーアフター表をご紹介します。
✅ 谷澤まさみの“食べ方ビフォーアフター”
| Before(やめたこと) | After(取り入れたこと) | 実感した変化 |
|---|---|---|
| 菓子パン中心の朝ごはん | バナナ+豆乳+卵などのたんぱく質 | 朝のイライラが激減 |
| イライラ時のチョコ爆食い | ナッツやチーズ、おにぎりに置き換え | 罪悪感が減り、心が穏やかに |
| 「お腹すいたらすぐ甘い物」 | こまめなたんぱく質補給 | 血糖値の波が穏やかになった |
| 食べないダイエット | 栄養を“足す”意識 | 自分にやさしくなれた |
| 水分をあまり摂らない | 常温の麦茶や白湯を常備 | 頭痛・不快感が軽減 |
全部一気にやる必要はありません。
私は「まずは朝食から」「おやつを変えてみる」そんな一歩一歩の積み重ねでした。
体はちゃんと、食べたものでできている。
だからこそ、自分の感情を“体から支える”って、すごく現実的で効果的な方法だと思うんです。
イライラしたっていい。疲れていてもいい。
でも、そんなときに「どうせ私なんて」じゃなく、「ちょっと整えてみようかな」って思えるようになるだけで、毎日は変わっていきます。
次の章では、PMSや更年期、産後など女性のライフステージごとにゆらぎやすい時期に合わせた食のヒントをまとめていきますね。
「自分は今、どの時期?」と照らし合わせながら読んでみてください。
PMS・更年期・産後…“時期別のイライラ”と食生活のヒント
「自分ってこんなに感情的だったっけ…?」そう感じるときって、じつは“ホルモンの揺らぎ”が関係していることがほとんどなんです。
でも、それをただの「気のせい」や「性格の問題」として片付けてしまうと、自分を必要以上に責めることになってしまう。
この章では、PMS・更年期・産後といったホルモン変化が大きい時期に感じやすいイライラにフォーカスし、それぞれに合った栄養サポートを紹介します。
どれも難しいことではなく、「知ってるだけで、自分をラクにできる選択肢」です。
PMS期のおすすめ栄養素と控えたい食べ物
PMS(月経前症候群)は、生理の約1週間前から起こる心と体の不調の総称。
イライラ、気分の落ち込み、甘いものへの欲求――これらの裏には、エストロゲンとプロゲステロンの急激な変化が関係しています。
特にイライラ感や気分の落ち込みが強いときは、脳内のセロトニン不足や血糖値の不安定さが起きていることが多いです。
✅PMS期に意識したい栄養素とおすすめ食材
| 栄養素 | 主な働き | 食材例 |
|---|---|---|
| ビタミンB6 | セロトニン合成を助ける | 鶏むね肉・鮭・バナナ |
| カルシウム | 神経の興奮を抑える | 小魚・ヨーグルト・豆乳 |
| マグネシウム | 自律神経を整える | ナッツ・ほうれん草・玄米 |
✅控えたい食べ物
- カフェイン(神経過敏を悪化させる)
- 白砂糖・甘いお菓子(血糖値の乱高下を招く)
- 添加物の多い加工食品(ホルモンバランスに影響)
私の場合、「生理前は甘いものはダメ」と制限するのではなく、甘酒やドライフルーツで“質のいい甘さ”に置き換えることで、ストレスが軽くなりました。
更年期のイライラに効くと言われる栄養とは
40代〜50代にかけて訪れる更年期。
女性ホルモン(エストロゲン)が大きく減少することで、感情の浮き沈み・疲れやすさ・不安感などが起こりやすくなります。
でも、これは“老化”ではなく「次のステージに向かう体の変化」。
だからこそ、自分の体と仲良くなるための食事がとても大切なんです。
✅更年期の心と体を支える栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 食材例 |
|---|---|---|
| イソフラボン | エストロゲンに似た作用 | 豆腐・納豆・豆乳などの大豆製品 |
| ビタミンE | ホルモン分泌のサポート | アボカド・ナッツ・かぼちゃ |
| 食物繊維 | 腸内環境を整え、感情も安定 | 雑穀・根菜・海藻類 |
私が更年期を意識し始めたとき、まず取り入れたのが「毎朝、味噌汁と納豆」。
「これが私の調子を守ってくれてる」と思える食習慣があると、揺らぎが来てもブレにくくなります。
産後ママの栄養不足とメンタルのゆらぎ
出産後は、睡眠不足・授乳・ホルモンの大変動などが重なり、まるでジェットコースターのように心が揺れる時期です。
そんな中で「ちゃんとしなきゃ」「育児を楽しめてない自分は母親失格」と感じてしまうママも少なくありません。
でも、その不安やイライラの背景には“栄養不足”があることも。
✅産後の女性が不足しやすい栄養とケアのポイント
| 不足しがちな栄養素 | 役割 | 補える食材 |
|---|---|---|
| 鉄分 | 疲労回復・思考の安定 | 赤身肉・ひじき・あさり |
| DHA/EPA | 脳の働きを助ける | 青魚(さば・いわし・鮭) |
| たんぱく質 | ホルモン・免疫の材料 | 卵・豆腐・鶏むね肉 |
私自身、産後にひどい疲れと情緒不安定を感じていた時期がありました。
「気合いで乗り切る」ではなく、まずは1日1回、具だくさんのお味噌汁を作って食べることから始めたんです。
すると少しずつ、「あ、私いまちょっと元気だな」と思える瞬間が増えていきました。
育児のために、ではなく“自分の土台をつくるために食べる”という視点は、ものすごく大切です。
どの時期にも共通して言えるのは、体と心はひとつながりだということ。
イライラや落ち込みを感じたとき、それはあなたが「ダメだから」ではなく、“栄養のサイン”として出てきている可能性があるのです。
だからこそ、「我慢しよう」「気合いで乗り切ろう」ではなく、“食べて整える”というやさしい選択肢を、これからのケアの中に取り入れてみてください。
次の章では、忙しい日常の中でも無理なく続けられる「やさしい食習慣」のコツをご紹介しますね。
「続けられないから意味がない」ではなく、“続けたくなる工夫”を一緒に見つけていきましょう。
無理なく続く「やさしい食習慣」のつくり方
「体にいいのはわかってる。でも、毎日はムリ」――そんな声、本当に多いんです。
私も、フェムケアに取り組みはじめた当初は、完璧を目指しては挫折して…の繰り返しでした。
でもある日ふと、“続けられる”ことが、いちばんのケアかもしれないって気づいたんです。
この章では、忙しくても、ゆるくても、心と体が整っていく食習慣のつくり方をお伝えします。
がんばりすぎずに、自分らしく。「ちゃんとしなきゃ」から「心地よく続けたい」へ視点を変えてみましょう。
忙しくてもできる!週1の“リセットごはん”
1日3食、完璧な栄養バランスなんて、現実にはムリ。
だから私は、週に1回だけ「心と体をリセットするごはん」を用意する日をつくっています。
✅私が実践している“リセットごはん”の基本セット
- 具だくさんの味噌汁(きのこ・豆腐・わかめなど)
- 雑穀ごはん or 玄米のおにぎり
- 納豆 or 焼き魚 or 卵焼き(たんぱく質をプラス)
- 小鉢の野菜(ぬか漬け・おひたしなど)
これは「◯◯を食べなきゃ」じゃなくて、「私をいたわるためのごはん」という位置づけです。
週1回でも、自分にとっての“整う味”があると、ちょっとした不調にもブレにくくなるんです。
そして何より、「今日もちゃんと食べられた」っていう自己肯定感が、心の土台になります。
気分に合わせて選ぶ、私の“お守り食材”
日によって、気分も体調もバラバラ。
だからこそ、「今日はこれを食べよう」と選べるように、自分だけの“お守り食材”を持っておくことが、セルフケアの大きな武器になります。
✅私が気分別によく選ぶ“お守り食材”
| 気分・体調 | 食材 | 理由 |
|---|---|---|
| イライラしてるとき | バナナ+ナッツ | 血糖値を安定させ、セロトニンを補う組み合わせ |
| 疲れすぎてるとき | 卵かけごはん+味噌汁 | 消化がよく、たんぱく質・ビタミンも摂れる |
| なんだか不安なとき | あたたかい豆乳+甘酒 | 腸が落ち着くと、気持ちも安定しやすい |
| 食欲がないとき | おかゆ+梅干し+蒸し野菜 | やさしい味と香りで胃腸をサポート |
「効く食材」は人によって違うけど、「自分の心がふっと緩む組み合わせ」を知っておくと、毎日がグッとラクになります。
私にとってのそれは、“バナナとナッツ”と“豆腐とごま油”。
どちらも忙しいときでもすぐ取り入れられて、「ああ、今日も大丈夫」って思わせてくれる味です。
食事だけに頼らない、私を整える習慣のヒント
食事はもちろん大切。だけど、食べ物だけではどうにもならない日もありますよね。
そんなとき、私が支えにしているのは“食以外の整える習慣”です。
✅まさみ流・無理なくできるセルフケア習慣
- 朝、3分だけ太陽を浴びる(セロトニンの活性化)
- 夜はスマホを30分早く手放す(自律神経をクールダウン)
- 気持ちを書き出す1行日記(感情を外に出す)
- 「ま、いっか」を口に出して言う(自分へのやさしさを言葉に)
これらは全部、すぐできて、無料で、誰にもバレないセルフケア。
そして不思議と、こうした習慣が“食べ方”にも影響してくるんです。
「今日はジャンクなものばっかりだったな」っていう日も、
「でも、お味噌汁だけは飲めた」とか「湯船には入った」って思えるだけで、
“ちゃんとケアできてる自分”を認めてあげられるようになります。
“ケア”って、がんばることじゃなくて、“自分に戻ること”だと思います。
そして、それはいつも、食べることから始められる。
毎日じゃなくても、週1でも、思い出したときでも大丈夫。
「私は、私を整える方法を知っている」って思えた瞬間から、フェムケアは始まっています。
この記事が、あなたの「やさしい食習慣」へのきっかけになりますように。