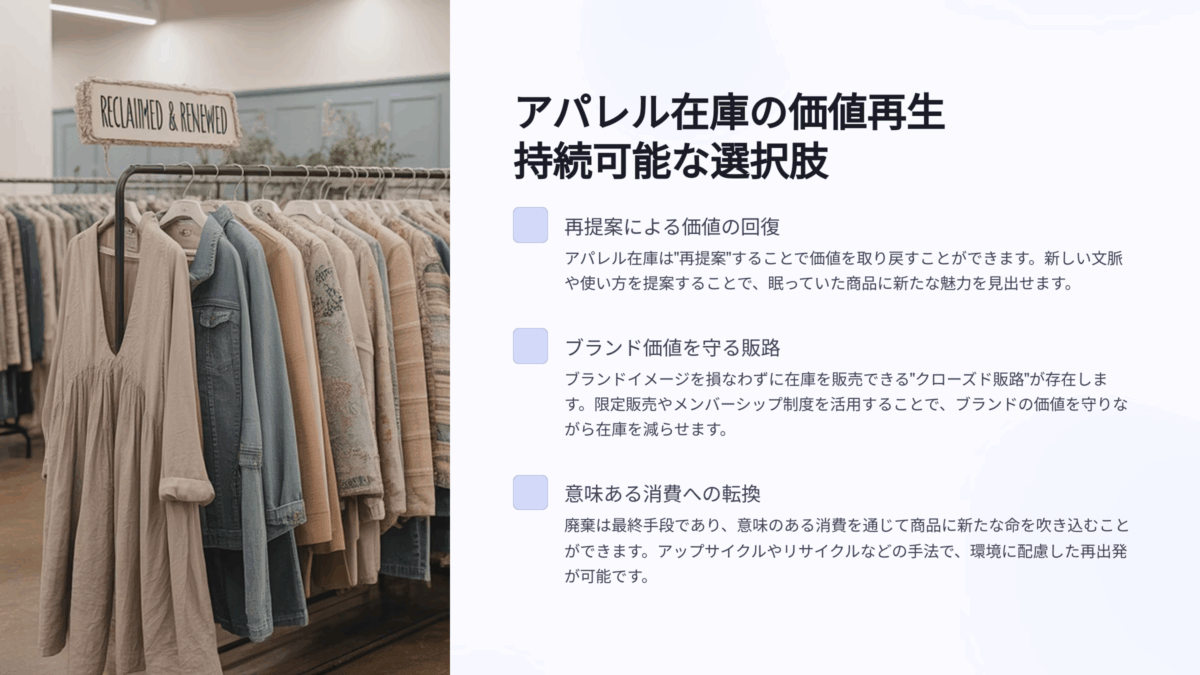夏フェス中止で売り場を失ったアロハシャツ。在庫のまま眠らせておくか、捨てるしかないのか…。そんな行き場を失ったアパレル在庫に、新しい選択肢があることをご存じですか?目次を見て必要なところから読んでみてください。
売れるはずだったアロハシャツが動かない——夏フェス中止の余波
アロハシャツの出番が、一度も来ないまま終わってしまう夏——そんなことが本当に起きてしまうとは、誰が想像したでしょうか。フェスやイベントの中止が続いた夏、在庫として残された大量のアロハシャツは、“売れ残り”という言葉の重さをひしひしと感じさせます。季節商品が動かない現実と向き合うのは、思った以上に苦しくて、決断を迫られる場面も少なくありません。
季節商品は「旬」を逃すと一気に重荷になる
夏フェスのために仕入れた商品やオリジナルで作ったアイテムって、ふだんの販売とちがって「イベントありき」で動くことが多いですよね。アロハシャツのような季節性が高いアイテムは、旬を過ぎると需要が一気にしぼんでしまう。それはもう、あっけないくらいに。
たとえば、デザインもカラーも“今年の流行”に合わせて作った商品であればあるほど、翌年には持ち越しにくくなってしまいます。たとえ新品でも、「今年のムードじゃない」と見られるだけで、お客様の手は伸びません。「まだ使える」ではなく「もう古い」になってしまうこのギャップが、アパレル在庫の厳しさですよね。
特にローカルイベントや期間限定のコラボ商品なんかは、売り切れる前提でつくっている分、余ったときの打撃が大きい。それが数十枚、数百枚ともなれば、もう倉庫スペースを圧迫してくるし、気持ちの焦りもどんどん大きくなってしまいます。
廃棄か、値下げか。それ以外の選択肢が見えない現実
そんなとき、多くの事業者さんがまず考えるのは「値下げ」ではないでしょうか。あるいは、それでも動かなければ「廃棄」もやむを得ない…と。でも、ここが本当に苦しい判断なんです。
✅ 値下げすれば売れるかもしれない
✅ 廃棄すればコストはかかるけどスッキリはする
どちらにもメリット・デメリットがあります。ただ、どちらにも共通しているのは、商品本来の価値が失われてしまうことだと私は思います。
在庫が動かないからといって、そこに込めた想いや、素材の良さ、丁寧な縫製が否定されたわけじゃないんですよね。それでも、販路がなければただの“重荷”として扱われてしまう。その現実に、何度もくやしさを感じてきた方は多いのではないでしょうか。
実は、私自身もそうでした。フェス用につくった夏アイテムが全部ストップになり、動かなくなった経験があります。そのとき、「このまま処分するしかないの?」と問い続けながら、新しい道を探し続けました。
廃棄か、値崩れか。どちらも選びたくないなら、“別の第三の道”が必要なんですよね。
そして、それはちゃんとあります。
次の章では、そのヒントを探っていきましょう。
アパレル在庫の「捨てない」活かし方とは?
アロハシャツのような季節限定のアイテムでも、誰かにとっては「今ちょうど欲しかった」と思えるタイミングがあります。問題は、それを必要としている人とどうつなげるか。“売れない”のではなく、“届いていない”だけかもしれない。そんな視点から、在庫の可能性を見直してみることが、これからの時代にはとても大切です。
値崩れせずに在庫を動かす“販路”が必要
在庫を捨てないためには、もちろん“売る”必要があります。でも、「値下げして大量に出せば売れる」という時代でもなくなりました。お客様も敏感で、「なんでこんなに安いの?」と理由を気にするようになっています。そこにちゃんと納得感がないと、かえって不信感を持たれてしまうことも。
つまり、ただ安く売るだけでは、長く続く販路にはならないんですよね。
求められるのは、「安くする理由が納得できる」「共感できる背景がある」そんな販路です。
たとえば、
✅ 賞味期限が近いから、ではなく「食品ロスを減らすために」
✅ 季節がずれたから、ではなく「在庫を救うために」
という価値のある理由があると、お客様の心の中で「応援したい」という気持ちが芽生えます。ただ“安い”のではなく、“買うことに意味がある”販路。そういう場所にこそ、アパレル在庫はちゃんと居場所を見つけられるのです。
フリマ・アウトレットに出しても、ブランドが傷つくジレンマ
もちろん、フリマアプリや大手アウトレットモールでの販売も手段のひとつです。ただ、ここで多くの事業者さんがぶつかるのが「ブランド価値との両立」という壁。
フリマや安売りサイトに商品を出すと、
✅ 「このブランド、いつも安売りしてるよね」
✅ 「正規価格で買った人が損した気分になる」
といった声が出てきてしまうことがあります。特に、自社ブランドを大切に育ててきた人にとっては、このリスクは見逃せません。
「在庫を売りたい、でも安く見られたくない」
これは、私も何度も葛藤してきた本音です。
だからこそ、ブランドを守りながら在庫を動かせる“クローズドな販路”が求められています。誰でも買える場所に出すのではなく、価値を理解してくれる人にだけ届ける。その「選ばれた場」にこそ、在庫の再出発のチャンスがあると私は信じています。
「捨てたくない」「でも、ブランドは崩せない」
その両方をかなえる道が、ちゃんとあるんです。次は、その具体的なヒントについてお話します。
「誰かにとって価値ある在庫」へ再発想する視点
アロハシャツが売れなかった理由は、本当に「需要がないから」だったのでしょうか。そう考えると、ちょっと違う気がします。その在庫が“今必要な誰か”の目に届いていなかっただけ。私たちが“売れ残り”と思っていた商品も、見せ方や届け方が変われば、まったく別の価値として受け取られることがあるのです。
在庫という言葉の裏にあるのは、「まだ誰にも見つけられていない可能性」かもしれません。
季節・イベントに左右されない“再提案”型の販路とは?
たとえば、「夏フェスで着るつもりだったアロハシャツ」。フェスがなくなれば、当然その需要は消えます。でも、それを“リゾート気分を味わいたい人の部屋着”として提案するとどうでしょう。あるいは、「オンライン会議で映える、気分の上がる一枚」として紹介したら?
実は私たちが“使い道がない”と思っていた在庫も、別の文脈にのせて再提案するだけで、まったく新しい需要とつながるんです。
このような「使い方の再編集」ができる販路は、これからの時代にこそ必要だと思います。
✅ 季節を問わないテーマ別企画
✅ 利用シーンに合わせた提案型の販売
✅ 「応援したくなる」理由づけのあるプラットフォーム
こういった販路が整えば、在庫は“売れ残り”ではなく、“これから出番を待つ商品”に変わっていきます。
エシカル消費という選択肢が広がる背景
もうひとつ、心強い追い風があります。それが、「エシカル消費」の広がりです。最近では、環境に配慮した買い物をしたい、社会にとってやさしい選択をしたいという声が、若い世代を中心にどんどん増えてきました。
エシカル消費とは、“安いから買う”のではなく、“共感できる理由があるから買う”という選び方。その考え方が、在庫活用にもぴったりなんです。
たとえば、
- 「イベントがなくなって行き場を失ったアロハシャツを、捨てずに届けたい」
- 「新品だけど廃棄寸前の商品を、応援購入で救いたい」
そんなストーリーがあると、ただのセール品じゃなく、“買うことで参加できる取り組み”に変わります。
そしてこのエシカルな視点は、モノの価値を「価格」だけでなく「意味」でも測るという、新しい消費のかたちです。
在庫にも“誰かにとっての意味”があるなら、捨てずに届けるべき理由が、ちゃんとあります。
次は、そんなエシカルな販路として、在庫に「もう一度チャンス」を与えている場所をご紹介します。
廃棄しない未来へ。アロハシャツがたどった意外な再出発
捨てるしかないと思っていた在庫が、思いがけない形で必要とされたとき――それは、“商品”が“物語”になる瞬間です。アロハシャツが再び動き出したその背景には、「買ってもらう」ではなく「共感してもらう」という、これからの時代に必要な視点がありました。
実際に売れたのは「夏フェス用」ではなかった
あるアパレル事業者さんが、夏フェス向けに作ったカラフルなアロハシャツ。イベント中止により、大量の在庫が手元に残ってしまいました。「このままでは、処分するしかないかもしれない」と諦めかけたそのとき、あるエシカル系ECサイトに出品してみることに。
そして思いもよらぬことが起きました。
購入者の多くは、「夏フェス用」としてではなく、
✅ 暑い日の家着に
✅ 旅行に行けない夏を、気分だけでも楽しむために
✅ プレゼントや父の日ギフトとして
といった、まったく別の視点でこのアロハシャツを手に取ってくれたのです。
理由を尋ねると、「商品の背景に共感した」「廃棄になるのはもったいないと思った」との声が多く、値段よりも“意味”を重視して選ばれていることがわかりました。
この出来事は、在庫は捨てられるものではなく、活かされるべき資源であると気づかせてくれるものでした。
共感ストーリーで価値が再定義される瞬間
私たちが在庫を「売れ残り」と感じるのは、そこに物語がないからかもしれません。でも、「なぜ売れなかったのか」「どうして残ってしまったのか」まで語ることで、そこに人の気持ちやストーリーが宿るようになります。
商品そのもののスペックではなく、
- 誰かが困っていたこと
- 捨てずに届けようとした想い
- 応援したくなる背景
こうしたストーリーが加わることで、価値がまったく別のものとして再定義されていくのです。
買う人も、それを「安いから」ではなく「意味があるから」選んでくれるようになります。そうなると、もう値下げや大量販売に頼らなくても、“共感”という付加価値で動いていく販路が可能になるのです。
そしてその先にあるのは、廃棄ゼロの未来だけでなく、気持ちよく循環していく社会のかたち。
次の章では、そんな「意味で選ばれる販路」を実現している新しい仕組みをご紹介します。アロハシャツのように、“もう一度チャンスを与えられた在庫”が活躍できる場所です。
OEFという選択肢:アパレル在庫を“価値転換”する販路
「廃棄せず、でもブランド価値も守りたい」――そんな矛盾するように思える願いを、無理に思わずに済む販路があります。それがOEF(Outlet, Ecology, Foodloss)という、エシカル消費のプラットフォームです。ここには、“捨てるしかなかった在庫”を、“応援したくなる商品”へと変えていくための仕組みがあります。
商品情報は公開、でも買えるのは会員だけ=ブランドも守れる
OEFの特徴は、とてもユニークです。
✅ 商品情報は誰でも見られます
✅ でも、実際に購入できるのはサブスク会員だけ
つまり、「オープンだけどクローズド」という絶妙な仕組み。これが、アパレルブランドにとっても大きな安心材料になるんです。
たとえば、
- 通常の販売価格との乖離を表に出しすぎずに済む
- 一般消費者には“安売り感”を与えない
- 値崩れによるブランドイメージの毀損を避けられる
この「クローズド・バイイングモデル」があるからこそ、在庫を動かしながらも、価格競争に巻き込まれずに済むのです。
それに、OEFの会員層は“お得さ”だけでなく“意味のある買い物”を求める人たち。だからこそ、ただの値引きではなく、「捨てるのはもったいないから」というストーリーをちゃんと受け取ってくれます。
廃棄ゼロと収益化を両立する“クローズド・バイイングモデル”とは?
在庫を廃棄するコストも馬鹿になりません。それだけでなく、廃棄には環境負荷もつきまといます。でも、無理に売り切ろうとすると、ブランドを崩してしまう…。
OEFは、その両方の悩みに対して「新しい出口」をつくるプラットフォームです。
この「クローズド・バイイングモデル」は、こういった構造で成り立っています:
| 仕組み | メリット |
|---|---|
| 商品情報は公開されている | SEOやSNSで広く認知が取れる |
| 購入は会員限定 | 値崩れ防止、ブランド保護 |
| サブスク制の会員モデル | ファン層に届ける設計 |
| EPポイントや限定企画あり | 継続的な購入意欲を維持 |
※ このモデルにより、“見せても、売る相手は選べる”という自由度の高い販売が可能になります。
また、OEFでは「在庫が売れる」だけでなく、共感されるストーリーを通じてブランドの認知が広がる効果もあります。「こんな背景があったんだ」「この取り組み、応援したい」といった声が、商品そのものを超えた価値を生み出すのです。
アロハシャツが“夏フェスの売れ残り”ではなく、“共感と循環のアイコン”に変わったように、
在庫はいつでも再出発できます。
捨てるか、活かすか。
選択のその先に、OEFのような“第三の道”があることを、もっと多くの人に届けていきたいと思っています。