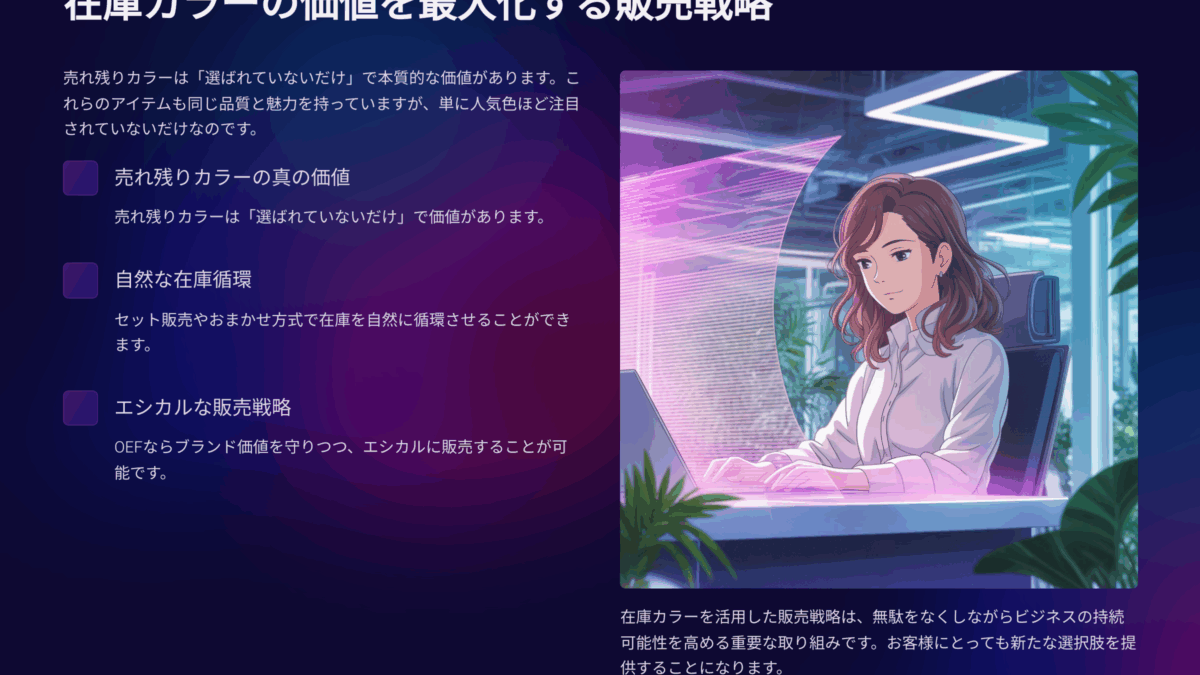人気カラーだけが売れて、他の色違い在庫が残ってしまう…。アパレルや雑貨でよくある悩みに、やさしく現実的な解決策をまとめました。目次を見て必要なところから読んでみてください。
売れ残りニットの“あるある”在庫偏り問題
色違いで展開した新作ニット。ひとつの人気カラーだけがどんどん売れて、他の色が在庫として残ってしまう——そんな経験、アパレル業界では本当によくあることです。誰のせいでもなく、ただちょっとした「タイミング」や「流れ」で起きる現象なんですよね。ここでは、その“在庫の偏り”がなぜ起こるのか、そしてどう向き合えばいいのかを、やさしく整理してみたいと思います。
人気カラーだけが売れて、他が残る理由
まず知っておきたいのは、色の売れ行きに差が出るのはごく自然なことだということです。オンラインでも店頭でも、「一番最初に手に取られる色」が強く引っ張ってしまう傾向があります。
たとえばこんなこと、ありませんか?
✅ SNSの1枚目の投稿写真がたまたま“くすみピンク”だった
✅ モデルが着ていたのが“チャコールグレー”だった
✅ スタイリストさんが“生成り”を推してくれた
これだけで、「売れる色」が決まってしまうことがあります。
特に最初の1週間で売れ筋が偏ると、それが“人気カラー”として一気に定着して、他の色には手が伸びづらくなるんです。
つまり、最初の印象がすべてを左右することがあるということ。
でもそれって、裏を返せば「売れ残った色が劣っている」という話ではないんですよね。
「不人気」ではなく「選ばれなかっただけ」な事実
売れなかった色を「人気がない」と断定してしまうのは、ちょっと早すぎるかもしれません。実際には、その色の良さにまだ気づかれていないだけというケースがとても多いです。
たとえば、後から見直してみると「こっちのほうが着回しやすい」「肌なじみがいい」なんて声が上がることも。選ばれなかった理由は、“その時の文脈に合っていなかっただけ”ということもあるんです。
こんな風に言い換えると、少し気持ちが楽になりませんか?
✅ 「売れ残り」ではなく、「これから選ばれるチャンスがある在庫」
✅ 「人気がなかった」ではなく、「まだその良さが伝わっていない」
実際、私はある冬のニットで、最初はまったく動かなかったマスタード色が、スタイリング提案を変えた途端に完売したという経験があります。「不人気」なんて、誰が決めたの?と思う瞬間でした。
だからこそ、色に“ラベル”を貼ってしまわずに、もう一度その子たちを見つめなおしてみることが大切なのかもしれません。
ニットのように「触れたくなる温もり」を持った商品なら、ちょっとした見せ方の工夫で、新しいストーリーが始まるかもしれません。
色違い在庫の賢い活かし方とは?
在庫が偏ってしまった時、「この色が残っちゃった…どうしよう」と落ち込んでしまう気持ち、とてもよくわかります。でも、ちょっと見方を変えると、それらの在庫は“まだ旅立ちのタイミングを待っているだけ”なのかもしれません。ここでは、そんな“選ばれ待ち”のニットたちを、無理なく・自然に・楽しく届けていくための工夫をご紹介します。
セット販売で“選ばれし1色”を軸に提案する
もし「この色だけは絶対売れる!」というカラーがあるなら、それをあえて“セットの主役”に据えるという方法があります。
たとえば…
✅ 人気カラー1枚+もう1色おまかせで2枚セット
✅ 好評カラー+隠れた名カラーのバランスセット
✅ トレンドカラー+ベーシックカラーのMIX提案
といったように、「この1枚が欲しかったから買ったのに、もう1枚も良かった!」という嬉しい発見を届けられるセットをつくるのです。
これは単に在庫をさばくだけではなく、色の魅力を“並べて伝える”ことができるチャンスでもあります。スタイリング提案や、色の組み合わせを見せながら「こっちの色も実は使えるんですよ」と寄り添うだけで、セット販売の価値はぐんと高まります。
おまかせカラー方式で販売ハードルを下げる
最近よく見かける「カラーおまかせ」の販売方法。これ、“選ぶのが大変”と感じる人にとっては、とてもありがたい仕組みなんです。
たとえば…
| 商品名 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| ニットお楽しみパック | カラーはスタッフおまかせ(1枚) | 特別価格で提供 |
このように「お得に買えるけれど、何色が届くかはお楽しみ」という形式にするだけで、価格以上の体験価値が生まれます。
また、おまかせとはいえ「ベーシック系」「やや冒険カラー」などざっくり系統を選べるようにすると満足度がUPします。「自分で選ばなかった色だからこそ、新しいコーデが生まれた」という声も少なくありません。
「推しカラー診断」など参加型企画で売る
もうひとつのアプローチが、色選びを“遊び”に変えてしまうということ。たとえばSNSや特設ページで「推しカラー診断」企画を展開するのはいかがでしょうか?
✅ 簡単な質問に答えると、あなたの“似合う色”が診断される
✅ 診断結果と一緒に、そのカラーのおすすめコーデも紹介
✅ 診断で出たカラーがそのまま購入できるリンク付き
このような参加型企画にすることで、「残り物」だった在庫が、“あなただけに選ばれた色”に変わるんです。
選ばれて嬉しい、届いてワクワクする、着てみて新しい発見がある——そんな体験の積み重ねが、モノとの出会いを特別なものにしてくれます。
ちょっとした仕掛けで、売れ残りだったはずのカラーが“もう一度選ばれる”チャンスを得る。その可能性を、私たちの手で育てていけたら嬉しいです。
アウトレット・サステナブル文脈での価値変換
「売れ残ったから値下げする」だけでは、在庫には“もったいない”という烙印が押されてしまいます。でももし、それが「廃棄を減らすための、やさしい選択」だったら?見方を変えることで、在庫は“負債”ではなく、“エシカルな価値”として再び注目されます。この章では、サステナブルな文脈を活かして在庫に光をあてる考え方をご紹介します。
「廃棄回避=エシカル」の共感マーケが効く理由
まだ着られるのに処分される洋服。実はアパレル業界では、毎年大量の在庫が廃棄されているという現実があります。ですが近年、「廃棄される前に、自分の手に迎え入れたい」という共感の輪が、少しずつ広がっています。
この共感の火を灯すのが、「エシカルな買い物」という考え方。
✅ 価格だけでなく、「その背景」にも関心を持つ人が増えている
✅ 「廃棄予定の在庫を救う」という選択に共鳴してくれる
✅ SNSでも“エシカルな選択”はシェアされやすい
つまり、「なぜこの商品が今ここにあるのか?」をきちんと伝えることで、単なるアウトレット販売ではなく、“意味のある消費”に変えることができるのです。
「この色のニット、実は少し売れ残っていて…」と正直に伝えたうえで、「でもまだ着てもらえる。廃棄するには、あまりに惜しいんです」と語りかければ、そこに人の想いが乗ります。“共感”は、最大のマーケティング資源になるのです。
ブランド価値を守りながら販売する方法
とはいえ、値下げやアウトレット販売には「ブランド価値が落ちるのでは?」という心配もありますよね。とてもわかります。でも、売り方に“配慮”があれば、むしろブランドの信頼感を高めることも可能です。
たとえば、次のような工夫があります。
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| クローズド販売 | 一般公開はするけれど、購入は会員のみに限定することで市場価格を保護できる |
| ストーリー付きの商品説明 | 単なる“売れ残り”ではなく「選ばれ待ちのカラー」として紹介する |
| 時期をずらした販売 | セール期をずらし、鮮度や安売り感を避ける |
このように、“売る相手”と“売り方”を慎重に設計することで、価格ではなく価値で信頼をつなぐことができるんです。
ブランドは“売らない”ことで守られるのではなく、“どう売るか”で育っていくもの。そんなふうに私は感じています。
サブスク限定・会員限定販売でプレミア感を演出
最後にご紹介したいのが、「クローズド・バイイングモデル」と呼ばれる販売スタイル。これは、価格は見えても、実際に買えるのは選ばれた人だけという仕組みです。
この方法には、いくつかの大きなメリットがあります。
✅ 値下げ商品でもブランドイメージを損なわない
✅ 会員向けの“特別感”をつくることができる
✅ 安さ以上に「買い方の価値」を感じてもらえる
たとえばOEFでは、価格はオープンですが、購入は会員限定。つまり、誰でも商品を見ることはできるけれど、「手にするには選ばれた会員になる必要がある」というプレミア感があります。
これは単なる購買行動ではなく、「共感への参加」なんです。
エシカルな想いに共感してくれた人が、サブスク会員になる。そんな小さなつながりの積み重ねが、在庫にもブランドにも、やさしい循環を生んでいくのではないでしょうか。
残されたニットたちにも、まだまだ旅のつづきがあるはず。
その一歩を、あたたかな“選ばれ方”でつくっていけたら嬉しいです。
売れ残りカラーが“レスキュー商品”に変わる場所
在庫として残ってしまった色違いの商品。見方によっては「売れ残り」と捉えられがちですが、今、そのようなアイテムにもう一度光をあてる販路が少しずつ広がってきています。誰にも選ばれなかったのではなく、“まだ選ばれていないだけ”の在庫が、社会にとっても意味ある形で再流通する。そんなやさしい循環がはじまっています。
エシカルに売れる販路が広がっている
近年、「エシカルな選択肢を持ちたい」と願う消費者が増えたことで、これまで埋もれていた在庫にも、新しい販路や出番が生まれています。
たとえば…
✅ 通常販売ルートでは扱いづらい「余剰在庫」「色の偏り」が専門のマーケット
✅ フードロスや日用品のアウトレットだけでなく、アパレル在庫の“サステナブルな橋渡し”を行うECサイト
✅ 「訳ありだけど、品質に問題のない商品」を選んで買える仕組み
このように、「売れ残り=価値がない」ではなく、「売り方が違えば価値が伝わる」という視点が、少しずつ浸透してきています。
そしてこうした販路の多くは、単に安く売るのではなく、「なぜこの商品がここにあるのか?」という背景ごと、やさしく伝える場でもあるのです。
だからこそ、企業としても「在庫処分」ではなく、「価値転換」という言葉で商品を送り出せる。これはブランドにとっても、購入者にとっても気持ちのいい選択ではないでしょうか。
【OEF】なら色違い在庫も価値として活かせる理由
そんな“価値転換の場”として、【OEF】はとてもユニークな販路です。OEFでは、アウトレット商品やレスキュー在庫を取り扱いながらも、安売り感やイメージの低下を避ける工夫が随所にちりばめられています。
✅ 誰でも商品情報は見られるけれど、購入できるのは会員限定というクローズド・バイイングモデル
✅ 「この商品には、こんな事情がありました」という背景を、やわらかく丁寧に伝える商品説明
✅ 価格よりも「エシカルに救えること」に価値を置く仕組み
✅ SNSやブログなどを通じて、「選ぶことが社会貢献になる」というストーリーの発信
たとえば、色違いで残ったニットを「もったいないおまかせBOX」として提案すれば、“色は選べないけれど、あなたに届くのはまだ選ばれ待ちだった1着”というストーリーになります。
また、人気カラーと一緒に“第二の主役”として他の色を紹介すれば、「この色、意外と使いやすい!」という再発見も生まれます。
OEFはそんなふうに、在庫の再活用を“押しつけ”ではなく、“共感”で届ける場なのです。
「残った商品を売り切る」ではなく、「まだ旅立てていない価値を誰かの手に届ける」。そんな考え方が、少しずつ広まっていくことを、私は心から願っています。
色が違うだけで、価値が失われるなんて、なんだかもったいない。
その“ちょっとした違い”に、やさしい選び方を添えて。
レスキューされる商品たちの次の物語が、OEFで始まっています。