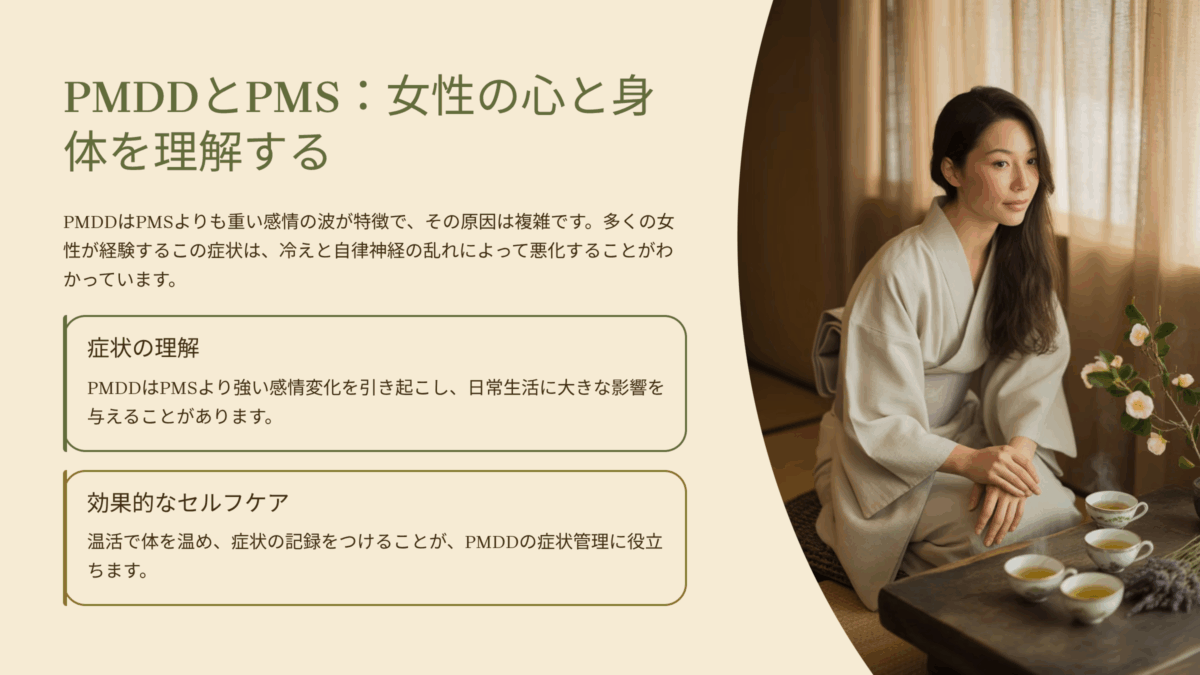毎月、生理前になると気分が落ち込み、理由もなくイライラしてしまう…それ、PMDDかもしれません。筆者の実体験をもとに、原因やセルフケアをやさしく解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
PMDDとは何か?原因に振り回される日々の始まり
PMDD(※月経前不快気分障害)は、PMSよりも重く深刻なメンタルの波を引き起こす症状です。私自身、まさかこれがPMDDだとは気づかず、ただ「感情に振り回されている自分が悪い」と思い込んでいました。でも実際には、それはホルモンの波と、冷えやストレスなど複雑に絡んだ体調要因が影響していたんです。今回は、私の実体験をもとに、PMDDに向き合うプロセスと出会った温活アイテムについてお話しします。
PMSとPMDDの違いとは
最初に感じた違和感は、生理の数日前になると急に感情が不安定になることでした。何もないのに涙が止まらなかったり、家族に強く当たってしまったり。
PMS(月経前症候群)との違いは、感情の深さと制御できなさ。
PMDDでは、特に以下の特徴が強く出ます。
- 突然のイライラや怒りが抑えられない
- 自己否定感が強く、何もかもが嫌になる
- 人間関係に深刻な影響を及ぼす
- 生理が始まると症状が一気に消える
これ、まさに私の状態でした。でも最初は、ただの性格の問題か、ストレスのせいだと思い込んでいたんです。
ネットで検索して「PMDD」という言葉に出会ったとき、やっと腑に落ちた感覚がありました。「これは私のせいじゃない」という気づきが、第一歩でした。
私が感じたPMDDの具体的な症状
私の場合、PMDDの症状は排卵後から生理が始まる直前までの2週間ほど続きました。以下は、当時の私の日記から抜粋した内容です。
- ✅ 朝起きた瞬間から「もう無理」と思う
- ✅ 仕事中、些細な言葉で涙が出そうになる
- ✅ SNSを見ると誰かと比べて落ち込む
- ✅ パートナーに意味もなく冷たくしてしまう
- ✅ 自己嫌悪でさらに落ち込む…の無限ループ
これらの症状は、生理が始まるとスッと消えていきます。でも、それまでの時間が長くてしんどい。
私のPMDDとの戦いは、まずこの「揺れ動く自分」に名前をつけてあげるところから始まりました。
「こんなに情緒不安定になるのは、意志が弱いからじゃない」
そう自分に言い聞かせながら、少しずつセルフケアを探し始めました。
※次の章では、PMDDの原因がなぜわかりにくいのか、生活者視点で掘り下げていきます。引き続きご覧ください。
✅ 次章:「なぜPMDDの原因がわかりにくいのか」では、ホルモンだけに注目しがちな罠と、冷えや自律神経との関係をひもときます。
なぜPMDDの原因がわかりにくいのか
PMDDのつらさを感じていても、多くの人が「もしかして私だけ?」と悩み続けてしまうのは、原因がひとつに絞れないからだと思います。私自身も、体調なのかメンタルなのか、人間関係が関係してるのか――何に悩んでいるのかすらわからなくなっていました。
でも調べるうちに、「ホルモン」「冷え」「自律神経」「ストレス」「性格傾向」…どれも複雑に絡んでいることに気づいたんです。
ホルモンバランスとの関係
まずは、よく聞く「ホルモンのせい」という言葉。正直、それだけで済まされるのはモヤモヤしますよね。でも実際、排卵から月経前にかけて、女性ホルモンは大きく変動します。
とくに関係しているのが、「プロゲステロン(黄体ホルモン)」の増加。これは、妊娠に備えるために必要なホルモンですが、メンタルに対しては沈静作用・不安感の増加といった影響もあります。
そしてこの時期、セロトニン(幸せホルモン)の分泌も減る傾向にあると言われています。つまり、脳内のバランスも崩れやすい。
でもここで厄介なのが、「じゃあホルモン検査しても、はっきりした異常が出ないことが多い」という点。私も婦人科で相談しましたが、血液検査は正常。
「でも、毎月同じタイミングで情緒が崩れる」。この“自覚”こそが、PMDDに気づくサインだったんです。
ストレスや体調の影響も無視できない
PMDDの症状は、ホルモン変化だけでは説明できないほど個人差が大きいと感じています。実際、私がいちばん症状が重くなったのは、職場で人間関係がギスギスしていた時期。つまり、外的ストレスが上乗せされることで、PMDDが悪化していたんです。
また、食生活の乱れや睡眠不足、体の冷えも大敵でした。特に、私は夏でも足先が冷たくなるタイプで、自律神経が乱れやすい体質。そんなときは、
- ✅ 感情がコントロールしづらくなる
- ✅ 無気力状態が続く
- ✅ 体がだるくて起きられない
といった、心と体の両面で不調が現れていました。
「ホルモンのせいだから仕方ない」だけでは済まされない。“生活全体のコンディション”が、PMDDの出方を大きく左右する。このことに気づいてから、ようやく“改善できる部分”にも目が向けられるようになったんです。
次章では、そうして始めたセルフケアの試行錯誤と、実際に効果を感じた「温活」について紹介します。
「何から始めていいかわからない」そんな方にこそ、読んでいただきたいです。
✅ 次章:「試行錯誤のセルフケア:何が効いて何が効かなかったか」
試行錯誤のセルフケア:何が効いて何が効かなかったか
PMDDに気づいたあと、私が最初に思ったのは「何かを変えないと、このままじゃ壊れてしまう」ということでした。でも、何をどう変えたらいいのかはわからない。そこで私は、生活のなかで変えられる小さなことから試していくことにしました。
「これが効いた!」というものもあれば、「これは私には合わなかったな…」というものも。
今日はその両方を、正直にお伝えしたいと思います。
メンタルケアや生活習慣の見直し
まず取り組んだのは、自分の状態を“記録”することでした。毎日の気分、体調、睡眠、食事などをノートに簡単に書いていく。これが意外と効きました。
というのも、「あれ?今週やたら気持ちが沈むな」と思っても、記録を振り返るとちょうど排卵後だとわかる。
この「見える化」によって、無自覚な自己否定を減らすことができました。
また、試したケアはこんな感じです:
- ✅ 朝起きたら5分だけ窓辺で日光を浴びる
- ✅ カフェインを減らし、代わりに白湯やハーブティーを飲む
- ✅ 寝る前はスマホを手放し、ゆっくり入浴する
- ✅ 気分が落ちてきたら“誰かに会う予定”は入れない
正直、すべてが完璧にできたわけじゃありません。でも、この「自分を追い詰めない」工夫が、PMDDの重さを和らげてくれた気がします。
一方で、「ポジティブな言葉を書き出す」「無理に笑顔を作る」といった“ポジティブ思考押し”のメソッドは、逆効果でした。
気持ちが沈んでいるときにそれをやると、「できない自分」を責めてしまうんです。
だからこそ、私にとっての正解は“自然に戻す”ケアだったんだと思います。
体を温めることの意外な効果
そして、ある日ふと試してみたのが「温活」でした。
冷えは昔からの悩みで、「とりあえず体を温めてみよう」と思ったのがきっかけ。最初はお腹と足元に貼るカイロから始めました。
すると驚いたのが、
体を温めると、心が少しほぐれるという感覚。
特に生理前は、お腹のあたりがガチガチに緊張していたことに気づきました。湯たんぽや温熱シートを使うと、その緊張が緩んで「まあ、今日はゆっくりしよう」と思える。
これ、私にとっては大きな一歩でした。
ほかにもこんな温活を取り入れています:
- ✅ 毎晩の入浴(38〜40度で15分)
- ✅ 足首と仙骨まわりを意識的に温める
- ✅ 朝は白湯からスタート
- ✅ 就寝前は湯たんぽを布団に入れる
「気分の落ち込みに、温めるって効くの?」と思うかもしれません。でも、温かさは“安全”のサインでもあるんです。
自律神経が乱れがちなPMDDにとって、「体から整える」ことが心にも作用するというのは、まさに発見でした。
次章では、そんな温活アイテムとの出会いがどんなふうに私の生活を変えてくれたのかを、もっと詳しくお話しします。
✅ 次章:「私を救ってくれた温活アイテムとの出会い」では、冷えの正体と、心まで温めてくれるケア習慣について紹介します。
私を救ってくれた温活アイテムとの出会い
「PMDDって、結局どうすればいいの?」。たくさん調べて、いろいろ試して、でも決定打が見つからない…そんな時期が長く続いていました。
正直、心が折れそうになったこともあります。
そんなとき、ふと手に取ったのが温活グッズでした。
正確には「これでPMDDが治る」なんて思っていなかったけれど、“体にやさしくする”ってことから始めようと思えたんです。結果的に、それが私にとって大きな転機になりました。
「冷え」が心と体に与えていた影響
私は昔から、冬だけでなく夏も足元が冷えるタイプでした。エアコンが効いたオフィスでは靴下が欠かせなかったし、お腹まわりを触ると常にひんやり。
でも、正直なところ「冷え」がメンタルに関係するなんて、当時は全く気づいていませんでした。
ところが調べてみると、冷えが自律神経の乱れを引き起こし、気分の落ち込みやイライラと関係していることがあると知ってびっくり。
実際、私がPMDDで一番しんどかった時期は、真夏の冷房による冷えと重なっていたことにあとから気づいたんです。
特に、以下の部分が冷えると、影響が出やすいと感じました。
- ✅ 足首(全身の血流に関係)
- ✅ 仙骨(腰の中央。自律神経が集中)
- ✅ お腹(内臓の冷えがメンタルに直結)
冷えは「ただ寒い」だけじゃなく、“体がずっと緊張している状態”なんですね。
私の場合、それがイライラや不安感を引き起こす引き金になっていたようです。
実際に使ってみて変わったこと
本格的に温活を始めたのは、PMDDの重さに限界を感じたときでした。最初に取り入れたのは、市販の貼るカイロと湯たんぽ。
特に効果を感じたのは、お腹と仙骨(背中側)に同時に温熱をあてるケアでした。
それから試したのが以下のアイテムです:
- ✅ 電気毛布(タイマー付きで安心)
- ✅ おまたカイロ(布ナプキンに挟んで使えるタイプ)
- ✅ 絹素材のレッグウォーマー
- ✅ 生姜やよもぎを使った温浴アイテム
どれも高価なものではありませんが、「自分を大切にしている」感覚が私の心に変化をくれました。
中でも印象的だったのは、夜寝る前に湯たんぽでお腹を温めながら深呼吸する時間。
この時間が、私の「今日もよくがんばったね」と自分に声をかけられる、かけがえのない習慣になりました。
変化はすぐには出ません。でも、3ヶ月続けたころ、PMDDの揺れが“波打つような感覚”から“緩やかなうねり”に変わったのを感じたんです。
「これは効く!」と確信をもてたわけではないけれど、
“冷えない体”を意識することで、感情に飲み込まれる回数が確実に減ったのは事実です。
次の章では、そんな温活とPMDDとの付き合いの中で、私が今も大切にしている“前向きな距離感”についてまとめます。
完璧じゃなくてもいい。「私はこれでいい」と思える日を、少しずつ増やしていく。そのヒントを共有できればうれしいです。
✅ 次章:「PMDDとうまく付き合うために大切なこと」
PMDDとうまく付き合うために大切なこと
PMDDと向き合っていく中で、私が何度も悩み、転びながら気づいたのは、「治す」ことよりも、どう付き合っていくかを考えるほうが、私には合っていたということでした。
もちろん、治療や薬が必要な方もいますし、それは正しい選択です。でも私の場合、「波のある自分」を受け入れることが、何よりの救いになりました。
この章では、そんな私の視点から、PMDDと長く付き合っていくために意識している2つのことをご紹介します。
自分のリズムを知るための工夫
まず大事なのは、自分のリズムを“知る”こと。これがあるだけで、焦りや自己嫌悪がだいぶ減りました。
私が実践しているのは、ごくシンプルな「感情+体調メモ」を続けること。
アプリでもノートでもいいので、毎日ほんのひとことだけ書き残します。
たとえば:
- 「なんだか無気力」→排卵期だった
- 「怒りっぽい」→生理3日前
- 「やたら元気」→生理直後
こうやって見返すと、“この感情はホルモンの影響かもしれない”と気づけるんです。
この視点があると、「なんで私はこんなに落ち込むの?」という自己否定から、
「今はそういう時期か。じゃあ無理しないでおこう」という受容モードに切り替えられるようになりました。
完璧に管理しようとしないでいいんです。
“ゆるくでも記録する”ことが、PMDDとの対話の第一歩になると思います。
ひとりで抱えない、相談のすすめ
もうひとつ大事なのが、「相談できる相手をひとり持つこと」です。
私も最初は、家族や友人に言えませんでした。だって、「なんか情緒不安定な人って思われそう」とか、「甘えてるって思われないかな」って、不安になりますよね。
でもある日、勇気を出して友人に話してみたら、思いがけず返ってきた言葉がありました。
「え、それ私もかも」
…このとき、私は本当に救われたんです。
PMDDって、見えないからこそ“ひとりで抱えがち”。でも実は、同じように苦しんでいる人はたくさんいる。
話せる人がいなければ、婦人科や心療内科に相談するのも立派な選択肢です。
医療機関に行くのはハードルが高いかもしれませんが、「今の私はプロの手を借りていい」と、自分に許可を出してあげてほしい。
誰かに話すことで、症状がすぐに治るわけではないけれど、「自分はちゃんとケアするに値する存在なんだ」と気づけること。
それが、PMDDとの長い付き合いのなかで、最も大きな支えになります。
ここまで読んでくださったあなたへ。
PMDDは、見えないけれど確かにある不調です。でも、それに名前をつけて向き合おうとしているあなたの姿勢は、もう立派なセルフケアの第一歩です。
少しでも気持ちが軽くなるヒントがあれば、私の体験も無駄じゃなかったと感じられます。
✅ 自分のリズムを“記録”してみる
✅ 体を温める習慣を1つ取り入れてみる
✅ 「誰かに話す」を、少しだけ考えてみる
その小さな一歩が、やがて大きな安定につながりますように。
参考情報・出典
本記事は筆者の体験と生活者視点をもとに構成していますが、医学的な理解を深めるために以下の公的情報を参考にしています。体調に不安がある場合は、必ず医療機関にご相談ください。
日本産科婦人科学会「月経前症候群と月経前不快気分障害」
https://www.jsog.or.jp/modules/diseases/index.php?content_id=4
厚生労働省 e-ヘルスネット「月経前症候群(PMS)」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/woman/w-03-007.html
MSDマニュアル家庭版「月経前症候群(PMS)」
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/女性の健康問題/月経障害/月経前症候群-pms
日本女性医学学会「PMSとPMDDについて」
https://www.jaog.or.jp/public/health/pms_pmdd/
順天堂大学「女性ホルモンと心の健康」
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/nc/premenstrual.html
関連記事:PMSイライラ薬物治療選択肢
✅ LINEでフェムケア情報を受け取るにはこちらから
最新記事・セルフチェック・講座案内など、あなたに合ったケアを一緒に考えていけます。
友だち追加はこちら